東方project[16件]
熱いものにはご注意を【咲霊】
熱いものにはご注意を【咲霊】
キスの日にリハビリにと書こうとして放置してた咲霊仕上げた。
二人でのんびりお茶飲んでるだけの話。
キス要素? そんなものほとんどないよ?
湯を注ぐとふわりと白い湯気と香りが宙を漂う。その瞬間は心地よいものだ。咲夜は小さく笑みを浮かべ、ティーポットの蓋を閉じた。白い指が陶器を撫でる様を霊夢はじぃと見つめていた。どうやら霊夢は自分の指にご執心らしい。貴方の指も綺麗よ、と以前言ったのだが、咲夜のじゃなきゃいや、と返された。可愛らしいものだ。
頃合いをみて、用意したカップの上にポットを傾ける。透き通った明るい琥珀色が白い陶器を満たしていく。色も香りも十分だ。ソーサーに乗せたそれを、隣でもそもそとマフィンを頬張る霊夢の前に差し出す。口の中のそれを飲み込み、彼女は礼を言ってカップに手を付けた。小さく息を吹きかけて冷ます様子はいつ見ても愛らしい。本当ならば飲みやすい温度まで冷ました状態で出したいのだが、やはりお茶はどの種類に置いても熱い方が美味しい。何より温ければ温いで彼女は怒るのだ。自分でちょうどいい温度にするのがいいらしい。難儀なものだ。
こくりと透き通ったそれを飲み、霊夢は満足気に小さく溜め息を吐いた。どうやらお気に召したらしい。
「紅茶、美味しいわね」
「あら、緑茶派ではないの?」
「緑茶派だけど過激派ではないもの。美味しいものにはちゃんと美味しいっていうべきよ」
すました顔でそう言って、霊夢はまた一口紅茶を飲む。緑茶のようにすすらずに飲むようになったのは何時頃だっただろうか。諦めずに注意し続けてよかった、と咲夜は小さく笑みを浮かべる。悪いことではないのだが、少し行儀が悪い。できれば両手でカップを持つ癖も直してほしいのだけれど、これはこれで可愛らしいので強く注意するつもりは今のところない。
そんな彼女の様子を眺め、咲夜も紅茶を飲む。色も香りもちょうどよいが、今日は少しばかり熱く感じる。どうやら湯の温度管理を少しばかり間違えたようだ。自分もまだまだだ、気を付けなければ、と考えてマフィンを口にする。こちらは問題ない甘さと焼き加減だ。
「あっ、つぅ……」
突然、驚いたように霊夢が小さく声を上げた。どうしたのだろうと彼女を見ると、先程の上機嫌な表情はどこへやら、どこぞの雨傘のように舌をべろりと出して顔をしかめていた。
「あら、火傷?」
「みたい」
うぅ、と霊夢は恨めしそうな声を上げる。両手で抱えてたカップを覗き込むと、少なくなっていたはずの中身は九分目あたりまで増えていた。どうやら自分で注いだらしい。時間も経ち既に程よく冷めていると思いそのまま飲んだ結果、うっかり火傷を負ったのだろう。
「貴方、いつも熱いお茶飲んでるのに火傷することなんてあるのねぇ」
「油断してたのよ」
「ごめんなさいね」
「……咲夜が悪いって言ってるわけじゃないわ」
それでも痛いものは痛いのか、霊夢はうーうーと不機嫌そうに呻く。自身の些細なミスへの怒りも含まれているのか、その表情は少し悔しそうにも見えた。
「口の中は治りが早いっていうし、少しの我慢よ」
「そんなこと言ったって痛いものは痛いのよ」
宥める咲夜を霊夢は恨めしそうに見る。べろりと外に出された舌は赤々としており健康的だ。火傷を負うと大抵その部位は赤くなるのだが、これでは分からないな、などと考えじぃとそれを見るめる。
「なによ」
見つめる視線に不機嫌な声が投げかけられる。自身の過失をじっと見られるのがお気に召さないらしい。痛みで動かし辛いのか、どこか舌足らずで可愛らしい。そんなことを言ったら問答無用で札なりなんなりが飛んでくるだろう。沈黙は金である。
「傷は舐めると治るというけど」
「こんなとこどうやって舐めるのよ」
思わずこぼれた言葉に霊夢はきょとんとした表情をする。反して咲夜はいたずらめいた笑みを浮かべた。すっと立てた指でその赤を指差す。ほんの少し動かせば触れてしまうような距離だ。
「人に舐めてもらえばいいのよ」
「ばっちい」
咲夜の言葉に霊夢は更に顔をしかめた。切り捨てる言葉に、今度は咲夜がきょとんと首を傾げる番だった。
「たまにしてるじゃない」
「あれは別よ」
ふざけてするようなことじゃないわ、と霊夢は言う。その声音は突っぱねるようであるが、しっかりと芯の通った真面目なものだ。
つまり、普段そのようなことをする時はおふざけではなく真面目に対してくれているということか。咲夜は嬉しそうに笑みを浮かべた。その笑みが気に入らないのか、霊夢は更に眉に皺を寄せた。そんなに皺を寄せたら痕が残っちゃうわよ、と眉間をつつく。彼女はむぅ、と不服そうに唸って咲夜を睨むが、飽きたのかぺたりと畳に手をつき追い払うかのように手をひらひらと動かした。
「あーもー、そんなこと言ってないで水持ってきてよ」
「はいはい」
子供らしい姿に咲夜は苦笑し、湯呑に水を汲んで彼女に手渡す。いきなり出てきたそれを気にすることなく、霊夢は湯呑を傾け口に含んだ。ようやく落ち着いたのか、はぁと疲れたように息を吐く。冷たいそれのお陰か、痛みは軽く引いたようだ。
「火傷したんじゃこういうお菓子は食べ辛いわね」
机の上に並べられた菓子はどれも水分が少なくぱさぱさとしている。舌を火傷した状態でも食べやすいとは言えないものばかりだ。咲夜の言葉に霊夢は残念そうに俯く。じっと菓子達を見つめる視線は寂しげだ。
「咲夜のお菓子が食べられないだなんて」
「食べやすいものを作るわ。最近暑くなってきたし、プリンなんてどうかしら」
「プリンって、あの黄色い水羊羹?」
「……まぁ、そんなところね」
洋菓子に疎い彼女の言葉に咲夜は諦めたように返事した。プリンと水羊羹は全く違うものだが、きっと違いを説明しても美味しいならそんなことはどうでもいい、と切り捨てられるだろう。実際、原材料や制作の過程を知らなくても美味しいものは味わえるのだから反論し辛い。
冷たい菓子に思いを馳せる霊夢にすっと片手を伸ばし、撫でるようにその頬に触れる。いきなりの行動に、彼女は驚いたように目を見開きこちらを見た。そんな表情にくすりと笑い、頬を撫でそのまま唇を指で撫でる。
「火傷したんじゃ、キスしにくいわね」
「……唇だけなら、痛くないし……大丈夫」
でしょ、と上目遣いで見つめられる。彼女らしい肯定の示し方にふわりと破顔し、その頬を両手で包む。手つきの柔らかさと優しい温度に霊夢は気持ちよさそうに目を細めた。
優しく触れた柔らかなそれからは、菓子のそれとは違う甘い香りがした。
畳む
閑話、休題【わかさぎ姫+魔理沙】
閑話、休題【わかさぎ姫+魔理沙】
わかさぎ姫云々ってことでわかさぎ姫の話。というより魔理沙とだべってるだけ。
パァン、と何かが破裂したような轟音が霧に満ちた湖に響き渡る。それに混じって何かが水に落ち、沈んでいく音がかすかに聞こえた。それも波立つ音にかき消される。
「所詮は半分魚だ。大したことは無かったな」
音という振動でさざめく水面を眺め、魔理沙は小さく呟いた。退治云々と言っていきなり襲ってきた妖怪を撃破し、ミニ八卦炉を懐に仕舞おうとして慌てて手を止める。長い間愛用しているこれは最近どうも機嫌が悪く、妖気に反応して勝手に火を噴くようになってしまった。そんなものを懐に入れていればどうなるかなどそれこそ火を見るより明らかだ。
ざっと辺りを見回した限り、湖で暴れているという妖怪はこいつだけのようだ。途中妖精がちょっかいをかけてきたがあれは平常運転である、気にする必要などない。
さて次、と姿勢を正すと、眼下に広がる水面に何か白いものが浮かんできた。よく見ると先ほど倒した妖怪が仰向けでぷかぷかと波間を揺蕩っていた。足の代わりについた尾ひれとエプロンの白が死んで浮き上がってきた魚を連想させ、魔理沙は不安に駆られる。確かに時々妖怪を退治しているが、それはスペルカードルールに則ったものであり死に直結するようなものはない。だが、事故が無いとは言いきれない。悪い冗談はやめてくれよ、と魔理沙は彼女の下へと急降下した。
間近で見たそれは静かに浮かんだままで、動く気配はない。まずい、と慌てて呼びかける。
「おい、大丈夫――」
か、と尋ねる声は水が跳ねる大きな音にかき消された。直後、全身に水が勢いよく叩きつけられる。真正面からの強い衝撃と冷たさに思わず小さく叫ぶと、開いた口に生臭い水が一気に入り込んでくる。反射的にゲホゲホと咳き込んだ。
「あぁもう、なんなのよ!」
巫女でもないのになんであんなに強いの、と妖怪が叫ぶ。つい先ほどまで身動き一つせずに浮かんでいたとは思えないほどの元気さだ。単に撃ち落された衝撃で放心していたのだろう。そして意識が戻り身を起き上がらせようとした結果、大きな尾ひれで水面を思い切り叩いてしまい、近くにいた魔理沙はそれをもろに被ることになってしまったのだ。
「……あら?」
気配に気付いたのか、妖怪は魔理沙の方を向いて小首を傾げた。何故彼女がまだここにいるのだろう、そして何故ずぶ濡れになっているのだろう。そんな疑問がその顔に浮かんでいる。
その問いに親切に答えることなどあるはずもなく、魔理沙は手に持ったミニ八卦炉を妖怪の眼前に突きつけた。
「…………よし決めた、今晩は焼き魚だ」
「やめてー!」
霧にけぶる湖に悲鳴が響き渡った。
わかさぎ姫と名乗った妖怪に続き、魔理沙は水面間近を飛んでいた。前を泳ぐ彼女の背にはミニ八卦炉が向けられたままだ。そのままでは風邪を引くから陸地に行こう、と提案され了承したが、また襲ってくる可能性がないわけではない。
「油断したところを不意打ち、とか考えるなよ?」
「しません。焼かれるのはごめんですわ」
少ししてここよ、と到着を示す声に顔を上げる。霧だらけで見通しも日当たりも悪いこの湖だというのに、そこは日の光が柔らかに降り注いでいた。なるほど、これならばこれ以上冷える心配もあるまい。一人納得して魔理沙は箒から降り立った。
「なんで魚なのにこんな場所知ってるんだ?」
「陸地住まいの知り合いと話したりするときに使っているのです。秘密にしてくださいね」
妖精達にたむろされては困るのだろう、わかさぎ姫は真面目な顔で人差し指を立て口に当てた。こんないい場所をわざわざ人に教える道理はないと魔理沙は首肯する。よく見れば隅に清水が湧いているではないか。今度から一休みするときに使わせてもらおう。
水でぐしょぐしょになった上着を脱ぐ。寒いが濡れたものをいつまでも着ていては更に体温を奪われるし、何より肌に張り付く衣服の感覚と生臭い水の匂いが不快だった。箒にぎゅっと絞ったそれらを掛け、日がよく当たる場所に固定する。普段ならばミニ八卦炉で乾かすのだが、今のこいつでは勢い余って服を燃やしかねない。使うとしても最終手段だ。
「本当にごめんなさい」
湧き出る清水で口を入念にゆすいでいると、わかさぎ姫はしゅんと申し訳なさそうに眉を八の字にして謝る。先ほどまで勝気な表情で襲ってきた姿から想像できないものだ。近くにあった石に腰を下ろし、膝の上で頬杖をつき俯いた彼女を見る。
「で、なんでいきなり暴れてたんだ?」
「いえ、特に何もありませんわ?」
わかさぎ姫の言葉に魔理沙は首を傾げた。確かに理由なしに暴れる妖怪はいるが、どうも違和感を覚える。
この湖に足を運んだのは妖怪が暴れているとの噂を小耳に挟んだからだ。以前妖精が騒いでいたことがあったけれど、それ以降ここで騒ぎが起きたということは久しく聞いていない。異変の香りがしたので向かってみれば、いるのはいつもの氷精とこの人魚だけではないか。両者とも元々ここらに根付いている妖怪に見える。頭の悪い妖精はともかく、この理性的に見える妖怪がわざわざ理由もなく自らが暮らす場所を荒らし、退治しにくる人間を呼び寄せようとするだろうか。むむ、と唸るが答えは見つからない。
「大体、あなたは私を退治しにきたのでしょう? 正当防衛です」
「『倒してのし上がる』って言ってたよな?」
「言葉の綾です」
魔理沙の指摘にわかさぎ姫はふいと視線を逸らす。じとりと見つめる魔理沙から顔を逸らしたまま頬に手を当て、気が立っていたのでしょうかと溜め息を吐いた。
「最近ネットワークでも妙な話が流れてくるのですよ」
「ネットワーク?」
「妖怪同士のちょっとした繋がりのことです。普段はあそこの石が良いとかあの辺りに巫女がよく来るから注意とかそんな他愛のない話題ばかりなのですが、最近は妖怪の時代がきたー、今こそのし上がる時だー、などと過激なことを言う者が増えてきていて……」
なんでなのでしょう、と悩ましげに言うわかさぎ姫を眺め、魔理沙は顎に指を当てる。人里の方でも妖怪が騒いでいるという話も聞く。人妖ごちゃ混ぜのお祭り騒ぎも終わり落ち着いてきたと思ったらこれだ。まだまだお祭り気分が抜けていない妖怪どもがいるのか、それとも別の何かが起こっているのか。どちらの可能性も十分にあり得る。
「まぁ、気持ちは分かるのですけれど」
「ん? 退治されたいのか?」
先ほど退治しようとしてきたから正当防衛だと主張していたし、ネットワークとやらで妖怪退治の専門家である巫女を避けるための情報を共有していると零していたではないか。矛盾しているのではないかと指摘すると、彼女は首を横に振った。
「退治されたい、と言うより倒すべき存在として認識してほしいという気持ちが強いですね。侮られ見くびられ相手にされないって想像以上に寂しいのですよ?」
わかさぎ姫は口元を水に沈め、拗ねるようにぶくぶくと泡を立てた。その瞳はどこか寂しそうだ。
「私だって、巫女に退治されるような存在になりたいものです」
「自殺志願か?」
「玉の輿願望ですわ」
意味が全然違うではないか、と魔理沙は呆れたように笑った。馬鹿にされたと受け取ったのか、わかさぎ姫は不満げに頬を膨らませる。悪い悪いと笑う魔理沙を見て彼女はまた嘆息する。
「こうやって平和に暮らすことは幸せですけれど、妖怪としてどうなのかと思うこともあるのです。恐れられてこそ妖怪だというのに、何もせずに暮らすのは正しいのか。妖怪としてあるべき姿ではないのではないか、と」
幻想郷の人間と妖怪は互助関係である、と語ったのはどこの宗教家だったか。妖怪は人間なしでは生きていけない。妖怪は人間を襲い存在を知らしめ、恐怖されることで生きることができるのだ。また、完全に否定されてしまうことが怖いとも語っていたか。妖怪は認識されなければ生きていけないのだ。
では、侮られ見くびられ相手にされない、存在しないも同然に扱われる妖怪は、存在を証明できない妖怪は妖怪として在れるのか。種として忘れられずとも、忘れられた個々はどうなるのか。
いつぞやの宗教家達の対談で、妖怪の主体は肉体でなく精神であるという話を聞いたことを思い出す。精神主体である妖怪がこうやって自身で自己の存在を疑うなど、それこそ自殺である。しかしだからといって、わざわざ退治される対象になるよう暴れるのは本末転倒だ。
「相手にされたいならもっと方法があるだろ? なんか特技とかないのか?」
「うぅん……、特技ではありませんが、綺麗な石を見つけるのと歌うことは好きです」
「それだ」
前者はともかく後者は人から求められる技術だろう。最近では妖怪がバンドを組んでいるという。天上の騒霊もまだまだ活動していると聞くしそれに参加すればよいのではないか。そう提案してみるが返事はつれないものだった。
「音楽性が違います」
「わがままだな」
「それに湖から出れませんもの」
「あー、確かにその足じゃ陸地は歩けないな」
流石に物理的な壁は乗り越えられなかった。
ではあれはどうだ、それならこれはどうだ、そもそもさっきのネットワークってなんだ、ついでに石のコレクションを見ていかないか、などと議論を続けるが進展は全く無く話題が逸れるばかりだ。そうこうしている内に中天にあった日は西の空へとその身を徐々に傾けていた。ここにいる目的を思い出し、急いで立ち上がり乾かしていた上着に触れる。厚く黒い生地はまだじとりと湿っていた。
「こりゃ乾きそうにないな」
「その道具で乾かせないのですか?」
「今火力調整できない状態でな。下手したら服どころかこの一帯が燃える」
「……ごめんなさい」
しゅんとまた表情を曇らせるわかさぎ姫の姿に魔理沙は苦笑する。先ほどからの会話といい、根は真面目で気の弱い妖怪なのだろう。それだけにいきなり襲ってきた理由が全く分からない。本人も特に理由はないと言っていたし、ますます怪しい。やはりこれは異変なのではないか。ならばあの巫女が動き出す前に片付けなければ。
乾かしていた衣服を身に着ける。じっとりとしているが先ほどに比べれば多少はマシだ。飛んでいる内に乾くだろう、と楽観的に考えて魔理沙は箒に跨った。こちらを見上げたわかさぎ姫に一言かける。
「じゃあな」
「大丈夫なのですか?」
「大丈夫だって。そっちも巫女には気を付けとけよ。私だからこれで済んだが、巫女に見つかれば確実に煮魚にジョブチェンジだ」
煮魚という単語にわかさぎ姫の顔から血の気が失せる。退治されるのはいいのに食われるのは嫌なのか。
ひらひらと手を振り青い顔をした彼女に別れを告げ、魔理沙は霧深い空へと飛び立つ。
理由なく暴れる妖怪達。戦闘後のあの変わりよう。そして、皆が口にしているという『のし上がる』という言葉。
いよいよ異変めいてきたな。魔理沙は愉快そうに笑みを浮かべた。
畳む
比重【咲霊】
比重【咲霊】
咲霊書きたくなったので咲霊。重い話。
糖度調節間違った感が多少ある。
さくや、と細い声で呼ぶと、なぁに、と柔らかな声が返ってくる。二人きりの時のいつもの甘ったるい色は欠片もなく、それがなんだか寂しい。それを察したのか、咲夜の白く細い指が霊夢の黒く艶のある長い髪を梳いた。慈しむようなその指は、屋敷全体の仕事を指揮し行っているということなど信じられないほど美しい。自分と違ってしっかり手入れをしているのだろうな、とぼんやり考える。
二人きりで会うと約束した時、咲夜は必ずこちらに訪れる。決して霊夢を屋敷に呼ぶことはしない。こちらから向かおうにも先回りして逃がさないように神社に来るのだ。仕事はいいのかと尋ねると、事前にしっかりと許可と休みを貰っていると言われた。公認よ、と楽しげに笑う彼女の顔をまともに見ることができなかったのは記憶に新しい。
けれど、少し不満だ。
感情が顔に出ていたのか、髪を梳く手が止まる。視線を上げると柔らかに笑んだ彼女と目が合う。
「嫌?」
「ちがう」
むしろ好きな部類だ。咲夜の手つきは優しく丁寧で安心する。それを直接言ったことはないが、彼女も分かっているようでそう、と短く返事して霊夢の頭を撫でた。
「咲夜」
「なぁに」
「……次は、あんたのとこじゃ駄目?」
呟くように尋ね、逃げるように彼女の胸に顔を埋めた。
彼女ばかりこちらに訪れるというのは少し面白くない。己の空間に彼女が様々な跡を残していくのは嫌ではない。でも、彼女が自分に跡を残すように、自分も彼女に跡を残したいのだ。
忘れぬように。
無くさぬように。
逃がさぬように。
彼女に、自分を刻み込みたい。
重いなぁ、と自嘲する。霊夢は物に執着する人間ではないが、どうしても手放したくない物もある。咲夜はそれに該当する。同時に独占したいものにも属する。要は、好きなのだ。お茶やお酒とは別の、代替のきかない離したくない離れたくないものだ。
そんな霊夢の考えを知ってかしらでか、咲夜はどこか困ったように笑った。
「ダメ」
「なんでよ」
思わずふてくされたような声で問うと、小さく唸るような声が聞こえた。いつでも冷静で瀟洒に振る舞う彼女にしては珍しい。上目遣いになるような形で見上げると、ゆらゆらと揺れる赤と目が合う。所在なさ気だったそれは意を決したようにこちらを見据え、困ったように笑った。
「貴方が家に来ると、お嬢様が会いたがるでしょう? 二人きりになろうにも、お嬢様から貴方を引き剥がすわけにもいかないし」
独り占めできないじゃない、と呟く声は拗ねた子供のようで、それでいて強い欲が滲み出ていた。
あぁ、咲夜も同じなんだな。安堵して彼女の胸に額を擦りつける。何も言わず咲夜はその背を撫でる。あやすようなその感覚と触れる温かさにとろりと瞼が落ちてくる。
「寝る?」
「ん」
肯定とも否定とも取れる返答をして霊夢は咲夜に身を寄せる。ふふ、と小さな笑い声が降ってきて、自身の背に彼女の両手が回った。そのままぎゅっと抱きしめられる。溶けて混じりあってしまいそうな温度なのに、安心感で胸がいっぱいになる。
一杯のはずなのに、もっともっと欲しくて自らも彼女の背に手を回した。
畳む
紅模様【さなれいむ】
紅模様【さなれいむ】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:早すぎた妻[1h]
霊夢は縁側に腰掛けて、淹れたばかりのお茶に口をつける。博麗神社でよく見られる光景だが、今日は少し違う。
「やっぱり縁側っていいですねー。こうやってお茶飲むの、憧れてたんですよ」
早苗はのほほんと笑う。霊夢は「そう」と小さく相槌を打って茶をすすった。
今日は霊夢一人でなく、早苗と二人だ。お茶菓子も珍しく二人分ある。「里で新作の和菓子が出ていたから」と早苗が持ってきたのだ。霊夢の好物を把握している彼女が持ってくる菓子はどれも美味しい。霊夢は満足げに笑い、「せっかくだから」と茶を淹れた。そして早苗の希望で縁側に二人で腰かけたのだ。
早苗がわざわざ似たものを探してきたこともあり、二人が手にしている湯呑は実質お揃いだ。そんなことをしなくてもいいのに、と霊夢は考えるが、早苗にとっては重要なことらしい。色合いが異なるため取り間違えるような不便はないので彼女の好きにさせておくことにした。
「あ、そういえば、これおすそわけです」
がさり、と早苗が手にした薄い袋を持ち上げる。上から覗きこむと、中には数種類の野菜が入っていた。どれもとれたばかりのようで、所々土で覆われていた。その黒が野菜の色を引き立て、更に美味しそうに見えさせる。
「豊穣の神様に頂いたのですが、家だけでは食べきれなくて。神様に了承はもらったので、おすそ分けに来ました」
「それなら味は確かね。ありがとう」
礼を言い、袋を部屋に押し入れる。立ち上がらず寝そべってぐいぐいと押しやる霊夢の姿に「行儀が悪いですよ」と早苗は言うが、彼女は聞く耳を持たないようだ。
「なんかもう、通い妻みたいですね」
えへへ、と早苗は嬉しそうに笑う。反面、霊夢は渋そうな顔で「訳分かんないこと言ってんじゃないわよ」と切り捨てた。
「えー。だっていつもこうやってお菓子持ってきてますしー、ご飯も作りますしー、お掃除もしますしー。もう妻同然ですよ」
「お菓子については感謝してるけど、ご飯は二人で作ってるし、掃除も手分けしてるでしょ。ふつーよ、ふつー」
指折り数える早苗の姿に霊夢は呆れたように溜め息を吐いた。「それはそれで夫婦の共同作業って感じでいいですね!」と目を輝かせる早苗の顔にベシリと札を張った。妖怪用のものなので人体に害はない。ただ、張り付いて息が苦しくなるだけだ。
「酷い」
「訳分かんないこと言うからよ」
どうにか顔面から札を剥がしむくれる早苗を無視して、霊夢は残っていた饅頭を齧った。粒あんの甘さが口いっぱいに広がる。そうして甘ったるくなった口に渋いお茶を飲む。あぁ、なんと幸せだろうか。霊夢は顔を綻ばせた。
「関係的には霊夢さんが妻ですけど、行動的には私が妻ですよね?」
「だから妻も夫もないでしょ……」
霊夢と早苗に性差はないのだ。妻や夫といった振り分けなどできないのだ。なのに彼女は何故拘るのだろう。霊夢には理解できそうにない。
「そもそも私達じゃ結婚もなにもないでしょ」
「外には『事実婚』という言葉があるんです」
「外は外、ここはここ」
不満気な声を上げる早苗を、霊夢は膝の上に頬杖をついて見やる。下から覗きこむ形なので、早苗からは上目遣いをしているように見えた。まだ少し幼い霊夢のその姿はどこか妖艶で、早苗の心臓がどきりと跳ねた。
「『結婚』云々の前に、『恋人』らしいことした方がいいんじゃないの?」
にやにやと愉快そうに笑いながら霊夢は言う。彼女らしからぬ言葉に、早苗の顔は驚きと羞恥と幸福感でだんだんと紅葉のように鮮やかな赤色で染まっていった。
「……霊夢さん、顔真っ赤ですよ」
「あんたに言われたくないわよ」
それは霊夢も同じだったようで、彼女は顔を隠すようにうつむく。美しい黒髪から覗く頬は早苗同様鮮やかな赤で染まっていた。よく紅白と表現される彼女だが、今は紅紅といった感じだ。
その顔を覗き込むように早苗は腰をかがめ、霊夢の頬を撫でる。寒さで冷えた手にとって、彼女の熱はとても心地よいものだった。冷たさと羞恥心で逃げるのではないかと思っていたのだが、霊夢はピクリと肩を震わせただけで動く気配はない。
「恋人らしいこと、ですよね?」
ゆっくりと、『恋人』という部分を強調して問うと、霊夢は「ん」と短く返事する。肯定とも否定ともとれる言葉だが、肯定と思っておこうと早苗は彼女のなめらかな黒髪を掬い上げ、唇を寄せた。それが分かったのか、霊夢は小さく身体を震わせた。
「そんなとこにしてどうすんのよ」
霊夢は横目で早苗を見やり、小さく呟く。早苗はその物足りなさそうな声に、わざと「何も分かりません」という風ににっこりと笑いかけた。
「自己満足です」
「へんたい」
霊夢は不満げに呟いて、髪を掬う早苗の手に己の手を重ねる。それが現状の彼女にとっての精いっぱいだと知っている早苗は、にへらと幸せそうに笑った。
「でも、恋人同士でできる事って大抵夫婦でもできますよねー」
「うっさい」
緩みきった顔で言う早苗に、霊夢は小さく返す。その声はいつもの不機嫌なものでなく、どこか嬉しそうなものだった。
畳む
はんぎゃくの竹林【輝夜+永琳】
はんぎゃくの竹林【輝夜+永琳】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:反逆の父[1h]
竹林の奥の奥、ひっそりと佇む家屋の庭はいつもより騒がしい。もこもことした桃色の塊が庭を跳ね回っている姿は普段と変わらないが、彼らは自身の体程ある大きさの看板を持っていた。
そこに書かれたのは『ストライキ』の五文字。兎達の労働放棄を示していた。
「ストライキ……って、前にもあったわね」
そんな兎達の姿を、輝夜は窓から眺めていた。気まぐれな兎達の遊びだろう。前回もすぐに収まった――というよりもそれどころではなくなった――のだから放っておけばいいだろう。きっとイナバが解決してくれる。
目の前を跳ねていく兎達に呼びかけてみるが、皆少し悩んでから首を横に振り「はんぎゃくだー」と言ってどこかに跳んで行ってしまった。悩んでいたとはいえ、兎達が逃げていくほどのことは前回はなかったはずだ。今回の騒動は思ったより厄介なのかしら、と輝夜は外を眺めながら呟いた。
「輝夜」
声のする方へ顔を向けると、いつものように腕を組んだ永琳が立っていた。いつの間に入ったのだろう。襖が開く音は聞こえなかったが、彼女なら音もなく現れることぐらい容易だろう。なにせ、永琳なのだから。
「ストライキ?」
「えぇ」
輝夜の問いに返答し、永琳は座った。こっち、と自分の隣をポンポンと叩くと、すぐに隣に来てくれた。彼女も外を跳ねる兎を見ている。
「呼んでもイナバ達が逃げていくの。ちょっと寂しいわ」
「今回のはちょっと厄介でね」
「何があったの?」
「ウドンゲまでストライキに参加してるの」
永琳の言葉に輝夜は目を丸くした。あのイナバが、真面目で永琳の言うことには必ず従っていたあのイナバが、他のイナバ達と同じく仕事を放棄しているなんて。明日は雪でも降るのではないか。
「なんで?」
「分からない。分からないけど『ごめんなさい』って叫んで兎達の中に飛び込んでいったわ」
はぁ、と永琳は深く溜め息を吐いた。忠実だった彼女の裏切りに参っているのだろうか。どうしたのかしら、と呟いた声は真剣そのものだ。
「でも、楽しそうね。私もストライキしてみようかしら」
「やめてほしいわ」
「はんぎゃくだー」
「もう、どこでそんな言葉を覚えてくるの」
笑顔でイナバの真似をする輝夜を見て、永琳は苦笑した。その様子を見て輝夜もまた笑う。冗談よ、分かってるわ、なんて言葉を交わし、二人で窓の外を眺める。あんなにたくさんいたイナバ達はいつの間にかいなくなっていた。
「私が永琳に本気で逆らえるわけないじゃない」
遠い昔、落とされた自分を救ってくれたのは永琳だ。一人反逆し、一人その身で自身を迎えてくれたのは彼女だ。逆らえるわけがない。逆らおうなんて、考えたことなどない。
「反対じゃなくて?」
「どうかしら」
どこか困った顔で返す永琳の姿に、ふふ、と輝夜は笑う。
世界にとって反逆同然の身体である自分。世界を自らの意志で反逆した彼女。互いを背くことなどない。永い永い今までも。そして、永い永いこれからも。
「さて、イナバ達をどうしようかしら」
「話し合いで解決?」
「できたらいいのだけれど」
そう言う永琳の目には疲れが見えた。助手や家事当番がいないのは負担なのだろう。最近は研究などで部屋にこもりきりだったはずだ、疲れているに決まっている。
よし、と気合を入れて立ち上がる。永琳が不思議そうな顔でこちらを見た。そんな彼女に胸を張って言葉を紡ぐ。
「私が解決するわ」
「……できるの?」
「反逆者同士なら受け入れてくれるわよ」
「反逆者同士って、どういう――」
「反逆者のふりをしてあの子たちの中に入って、そこで反逆するの。反逆者の反逆者よ」
名案だという風に両手を上げ広げると、永琳は困惑した様子で顎に手を当てていた。頭のいい彼女でも、疲れた頭では繰り返される言葉の意味を上手く理解できないようだ。なにより理論自体がめちゃくちゃだった。
「そうと決まればはんぎゃくだー」
輝夜、と声を上げる永琳の隣を駆けていく。
形から入る彼らのことだ、きっと竹林のどこかで会議の真似事をしているだろう。今回はイナバがいるからちょっとは会議らしくなっているかもしれない。その様子も見てみたい、だなんて考えながら庭へ出る。
私もまずは形から。反逆者の真似事から、本当の反逆者へ。
そんなことを考え、輝夜は竹林に向かう。青々と茂る竹は彼女をすぐに包み隠した。
畳む
人工的な雨の跡【咲夜+美鈴】
人工的な雨の跡【咲夜+美鈴】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:斬新な水たまり[30m]
赤い赤い廊下を歩く。大きな仕事は済んだので、あとは優先順位が低いものを順に処理していくだけだ。
庭につながる廊下から外へ目をやると、地面にはいくつもの水たまりができていた。不可解なその状態に眉をひそめる。この場所だ、原因は一つだろう。咲夜はわざとらしく溜め息を吐き庭へと歩みを進めた。
犯人の追跡は簡単だった。なにせ水たまりは点々と続いているのだ。それを追って歩けばすぐにその姿が目に入った。
「何をしているの」
しゃがんで地面を見つめている女の背中に冷たい言葉を浴びせる。ナイフのように鋭く冷たい声に女――美鈴はびくりと身体を震わせた。ぎこちなく振り返った彼女は気まずそうな表情をしていた。
「いえ、蛙がいたものですから……」
「子どもじゃあるまいし」
「でも花壇にいられると作業しにくくて困るんですよ。かといって触るわけにもないがしろにするわけにもいきませんし」
神様は怖いんです、と呟いた。そういえばいつぞや新しくできた神社の神は蛙に関係しているといった話を耳にした覚えがある。しかし彼女がそこまで気にすることなのだろうか。咲夜は首を傾げた。
「で、それがこの水たまりとどう関係があるの?」
「触るわけにもいかないので水をかけて追い払ってたら変な方向に跳んでいっちゃいまして」
「追い掛け回してこうなった、と」
丸っきり子供の行動ではないか。あまりのくだらなさに咲夜はわざとらしく溜め息を吐いた。仕方ないじゃないですか、と美鈴は恨みがまそうに呟く。何がどう仕方ないのだと問い詰めたいが、そんなことをしても意味はない。呆れた顔で腕を組み、しゃがみこんだままの彼女を見下ろす。
「これ、どうやって片付けるの」
「今日は天気がいいのですぐに乾きますよ。庭を歩くのは私と咲夜さんぐらいですし困らないでしょう?」
「私が困るじゃない」
確かに雇っている妖精達は飛んで仕事をするし、仕事のほとんどは館内の雑事であり庭に行く者はほとんどいない。ここを通るのは飛ばずに行動する咲夜と庭を一任されている美鈴ぐらいだ。
「咲夜さんなら器用ですし大丈夫でしょう」
「そういう信頼入らないわ」
はは、と誤魔化すように笑う美鈴を咲夜は睨みつける。彼女はそれから目を逸らすように立ち上がった。彼女よりも少しだけ身長が低い咲夜は、先ほどまでとは逆に自然と見上げる形になる。
「汚れたら私が水場まで運んで洗ってあげますよ」
「いらないわよ」
それこそ子供じゃあるまいし、と咲夜は呆れたように呟いた。何故汚れた程度で彼女の世話にならなければいけないのか。そもそも彼女がこんな水たまりを作るのがすべて悪いのではないか。考える内に苛立ってきた。
「とにかく、早くどうにかしなさい」
「どうにもなりませんよ」
「なにかあるでしょ。全部汲み上げるとか」
「流石に無理ですよ」
無茶振りそのものな提案に美鈴は眉をハの字に下げる。それが気に入らないようで、咲夜は目を細め彼女を見つめる。鋭く痛い視線だった。
「まぁまぁ。たまにはいいじゃないですか。ほら、水たまりに映った空が綺麗ですよ」
美鈴は慌てた様子で近くの水たまりを指さす。確かに庭に点在する水たまりには晴れ渡った空が映し出されていた。
「こういう斬新な空の見方もあるんですよ。そう、そういうことです」
「誤魔化さないで」
子供だましにもならない言い訳に咲夜の声音がだんだんと怒りで染まっていく。ふざけすぎたのは十分分かっているようで、美鈴はすみません、と消え入りそうな声で謝った。
「とにかく、早く何とかしなさい。できなきゃおかずを一品減らすから」
「そういうのはやめてくださいよ!」
美鈴は泣き出しそうな声で叫んだ。肉体労働の多い彼女には堪える罰だ。なにより咲夜の料理はどれをとっても美味しい。たった一つとはいえ美味しいものを味わえなくなるのは辛いことなのだ。
水たまりには困り果てて泣き出しそうな赤色が映っていた。
畳む
信【霊夢】
信【霊夢】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:大きな信仰[30m]
博麗神社の巫女といえば博麗霊夢だが、彼女自身は何故巫女をやっているのか、そもそも何故ここで暮らしているのかは全く知らない。
ずるずると記憶の糸をたぐってみても、思い出せる一番古い記憶は『ここに居た』ということだけだ。生んでくれた両親の顔など思い浮かばないし、こんな辺鄙な神社で暮らすことになった経緯も覚えていない。妖怪やら里の者に世話になった覚えはあるが、何故このような状態にいることは誰も教えてくれなかった。自ら尋ねたことがないのだから当たり前かもしれない。一体何故なのだろうと不思議に思ってはいるが、そんなこと気にしても仕方のないことだと彼女は現状を受け入れていた。諦めていたともいえるかもしれない。
そんな彼女は信仰心なんてものは持ち合わせていない。神がいることは自ら実証し知覚しているが、彼らを強く信じ敬っているわけではない。ただそこにいるということだけを認識し、その事実を否定しないだけだ。無論、ここ博麗神社におわすという神も例外ではない。巫女なんて役割を貰っているが、霊夢には神を信仰するなどという考えはなかった。
信じる者は救われるなんて言うけれども、救われなかった者を霊夢は沢山見てきていた。彼らはその願いが叶えば神に感謝するが、叶わなくとも神を本気で恨んだりしない。『救われる』のは本人の気の持ちようでしかないというのが、この辺鄙な場所で願掛けをしていく者の行く末を見てきた霊夢の考えだ。
そんなことを考え実質上蔑ろにしているのだから、自分は救われることはないだろう。そもそも救ってもらいたいと強く思うほどの状況に陥った覚えがないのだけれど。都合よく祈っても思いなど届かず、ただただ自分の無力さを痛感するばかりに決まっている。人にしろ神にしろ、いざというときだけ頼られても困るのは明白だ。自分だってそんな奴見捨てるに決まっている。
けれど。
けれど、もし本当に神様とやらが人を救う気があるのならば。
「……空っぽよねぇ」
上の木枠を外し中を見る。大きな木の箱の中には枯葉すら入っておらず、すっからかんという表現がとても似合う状態だ。予想通りの光景に霊夢は深く溜め息を吐いた。
神様。やる気があるならこのいっそ清々しいほど中身のない賽銭箱を満たしてください。
畳む
辿る幻【早苗】
辿る幻【早苗】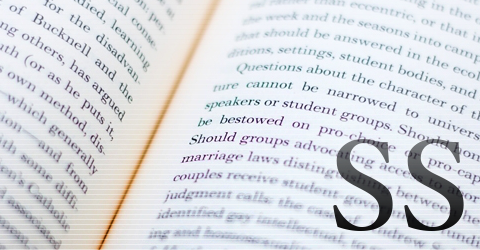
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:100の幻想[30m]
小さい頃は本を読むのが好きだった。
小説はもちろんだが、図鑑を読むのが好きだった。現実でありながら未知の世界が広がっている光景は圧巻で、幼い知識欲が刺激された。動物、花、昆虫、鳥、どんなものでも読んで、それらが存在する世界に思いを馳せた。
図鑑は実在しないものも教えてくれた。妖怪もその一つだ。雪女、のっぺらぼう、小豆研ぎ、猫叉。何百もの幻想の生き物をそこで見ることができた。小説の中で出てきたそれを調べたことも多々ある。
様々な本の中で活躍する彼らは非常に楽しそうだった。人間を驚かせ、時には悪に立ち向かい、何物にも縛られず思うがままに日々を自由に過ごしている。それはルールでガチガチに縛られた人間から見れば羨ましいものだった。
同時に彼らは苦しそうでもあった。人間に存在を否定され、姿を現せば疎まれ退治される。彼らは常に人間とともにあり、人間に虐げられていた。それを可哀想だと零したのは何時だっただろう。
幻想は幻想である。そう簡単に認め受け入れられるものではない。
そんなことを、同じく幻想の存在とされる神は語った。その表情はどこか寂しそうで、幼いながらも胸が苦しくなった。今思えば、彼女らは幼子を宥める為に自身で自身を否定したのだ。幼い子供が感じた程度では済まされないであろう辛さがあったはずだ。
幻想の存在。見たことのない彼らは本当に存在するのだろうか。
図鑑は何も答えてくれない。
パタリ、と床に広げていた本を閉じる。フルカラー印刷に耐えうるしっかりした分厚い紙で作られた本は重く、成長した今でも閉じるのには力が必要だった。これを毎日開いて読んでいたのだから、子供の集中力と探求心は凄い。
固い表紙を撫でる。大きく書かれた『妖怪大図鑑』という文字はどこか色褪せていて、時間の経過を物語っていた。
押し入れの中のダンボールに眠っていたそれらを見つけ黙々と読んでいたが、どれも懐かしいものばかりだ。動物、花、昆虫、鳥、そして妖怪。幻想の存在。見たことのなかった者たち。それらは変わらずそこにいた。
開け放たれた障子の外、鮮やかな青の空を見上げる。遠くにぽつりと浮かぶ黒い点は同じ山に住む天狗だろう。境内で神奈子と話している青い服の少女はおそらく河童だ。最近付き合いができた彼女らは度々ここを訪れ神――神奈子と話していた。
図鑑の中の幻想の存在だった妖怪達。
それが今ここにある。目の前で生きている。
「否定なんて、できませんよね」
だって、この目で見ちゃいましたもの。
そう考えて、くすりと笑みが漏れる。
畳の上では色褪せた図鑑がいくつも寝転んでいた。
畳む
時と夢の比例【魔理沙】
時と夢の比例【魔理沙】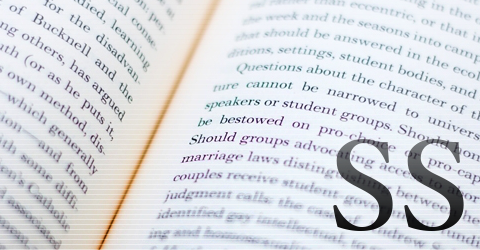
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:大人の夢[15m]
ぐ、と息を詰め足先に力を籠め腕を目一杯伸ばす。そうしても棚の上に積み上げられた本に指先すら届かない。
何故届きもしないこんなところに片づけたのだ、と呆れたように溜め息を吐き、大人しく諦めて椅子を運ぶ。あれほど遠い位置にあったそれはすぐに手の内に収まった。なんだか負けたようで腑に落ちない。
もっと身長が高ければ。そう思うことは多々あるが、身長が伸びる気配はない。徹夜する以外は健康的な生活を送っているというのに何故なのだ、とむくれる。見た目が小さいというのは生きる上で不便なのだ。
もっと成長すればどんなところにも手が届くだろうか。
もっと時が経てば今以上に魔法に近づけるだろうか。
大人になれば。
そう考えることはあるが、結局は机上の空論だ。たらればは物事のきっかけにはなれど、ただ囚われるだけではろくなことにならない。
そもそも、だ。大人になれば身長が高くなるなんて保障はない。大人なんて夢に憧れて悪戯に時を過ごすだけで心身共に成長できるはずがない。大人になるということは、有限である時間が着実に減っていることを意味する。今ですら足りないというのに、これ以上減るなんてごめんだ。
大きな夢を追うために、大人になるのはまだ早い。
抱えた本を机の上に載せる。重いそれは音を立てて着地した。
戻した椅子に座りその内の一冊を開く。遠い昔の大人達が残した知識を、夢を、願いを吸収し、幼い魔法使いは成長を遂げるのだ。
畳む

見上げた先の【咲霊】
見上げた先の【咲霊】リハビリ咲霊。この子らは妙に書きやすい。
TLで見たラブコメチックな膝枕咲霊が可愛くて書き始めたはずなのにどうしてこうなった。
霊夢、と優しげな声が己の名を口にする。声の方へと目をやると、正座をした咲夜が手招きしていた。畳に手を付き、ぺたぺたと這って霊夢は彼女の下へ向かう。何の用だと言いたげに目の前の赤い瞳を見つめると、咲夜は微笑み己の太ももをとんとんと叩いた。誘われるがまま、そこに頭を乗せる。腹に背中を預けるように顔を横に向け頬を付けると、程よい弾力と心地よい熱がほのかに伝わってきた。細い指が頭を撫で、長い髪を優しく梳く。その心地よさに目を伏せた。
「足、痺れないの?」
こてんと仰向けになり、以前から疑問に思っていたことをぶつけた。咲夜の住まう館はテーブルと椅子ばかりで、正座しなければいけないような部屋はなかったはずだ。正座自体あまり慣れていないだろう。それに加え、人の頭を片足に乗せているのだ。足が痺れないわけがない。それでも彼女はいつも涼しげな顔をしているのだから、不思議でならない。
「もう慣れたわ」
こうやって何度もやってるもの、と咲夜は霊夢の前髪をかき上げる。日の当たらない額は僅かな汚れすら見つからないほど白く、黒い髪とは対照的でよく映えた。
「それに練習したのよ。休憩中は正座して過ごしたり、寝る前にベッドの上でやってみたり、すぐに立ち上がれるようにしたり」
「練習してまでやることじゃないでしょ」
指折り数える彼女にそんなに好きなの、と呆れた瞳で問うと、えぇ、と肯定の言葉と柔らかな笑みが返ってきた。物好きなやつだ、と霊夢はその優しい瞳をぼんやり見つめる。赤い目が弧を描き、慈しむような表情がこちらに向けられた。
そんなに楽しいのだろうか、と霊夢は内心首を傾げた。咲夜はよく膝枕をしたがる。彼女はどうも自分の髪を触るのを好むようで、よく自身を引き寄せ長いそれを撫で、時に結ってくれる。それだけなら隣りあって座った方はやりやすいはずだ。だというのに、彼女はこうやって自分を寝転ばせるのだ。一体何が楽しいのだろう。小さな疑問と好奇心が胸の内に湧き出で、どんどんと膨らんでいく。
霊夢が身を起こす。いきなりの行動に、咲夜は不思議そうにその赤い背を見た。そんな彼女を気にすることなく、向き合うように座る。すっと背筋の伸びた美しい姿勢で正座をし、無言で隣に座ったままの彼女を見つめぺしぺしと太ももを叩く。何を意味するのか理解できないのか、咲夜は頬に片手を当て首を傾げた。
「交代」
「え?」
「交代。たまにはやったげるわ」
早く、と急かすように霊夢は目を細める。不機嫌そうなその顔を見て、咲夜は畳に手を付き身を屈め、遠慮がちな様子で示された場所に頭を乗せ横を向いて寝転んだ。白くふわふわとした髪を持つ彼女の頭は存外重く、何故こんな重たいものを率先して乗せろと言ってくるのだろう、とますます疑問が深まる。
邪魔ね、と呟き、霊夢は咲夜のヘッドドレスを外す。動く気配すらなく、されるがままの彼女の頭をそっと撫でる。少し癖のついた髪はふわふわと柔らかな感触がして、触っていて心地よい。三つ編みが解けないように梳いてみる。少し跳ねた銀色は見た目よりずっとさらさらしていた。霊夢は楽しげに銀色の頭を優しく撫でる。咲夜は時折自分の髪を羨ましいというが、彼女の髪も十分に柔らかで滑らかだ。
柔らかな銀色を楽しんでいると、咲夜は仰向けになりこちらを見た。どこかきょとんと呆けたような顔をした彼女は、見上げた先の黒い瞳をじっと見つめた。なんだろう、と不思議に思いつつも、霊夢もじっと見返す。覗き込んだ赤色は井戸水のように澄み切っていた。主人が主人故に『血のようだ』と言われる彼女の瞳だが、どろりとしたあれよりもワインや紅茶といった底の見える透き通る赤だとぼんやり考える。白い髪と肌に浮かぶ赤いガラス玉は、はいつぞや見た赤い月よりも深いそれはとても綺麗で、揺らめいて輝くその色に触れてみたいという衝動に駆られた。
「……される側っていうのも、案外いいものね」
しみじみとした様子でそう呟き、咲夜はふわりと笑った。彼女はそのまま細い腕を伸ばし、霊夢の頬を優しく撫でる。陽の光にも似た柔らかい温かさとほんの少しのくすぐったさに、猫のように目を細めた。
「こうやって貴方を見上げるのも新鮮だわ」
「そういえばそうね」
この膝枕といい抱きかかえた時といい、たしかに彼女はいつも見下ろす側にいた。そう考えるとなんだか気に食わない。不服さが表情に出ていたのか、咲夜は困ったように眉を下げた。そっと頬を撫でる手つきはまるでぐずる子どもをあやすときのそれに似ていて、霊夢は小さくむくれた。
「でも、これだとなんだか遠くに感じるわね」
「そう?」
どこか寂しげな咲夜の声に、霊夢は不思議そうな顔をした。いつもされている時はそう感じない、むしろ近すぎるぐらいに思えた。身長の問題だろうか。いや、咲夜の方がほんの僅かに高いはずだ。何故なのだろう、と更に首を傾げていると、咲夜は苦笑した。
「私にも分からないけれど」
「なにそれ」
変なの、と呟くと、知ってるでしょ、と笑い交じりの声が返ってくる。そのまま、自然な動作で咲夜は立ち上がった。一体なんだ、と己の手から離れた銀色を見つめると、彼女はくるりと綺麗に振り返った。その口元は柔らかく弧を描いており、どこか楽しげだ。
「交代」
「へ?」
「やっぱり、されるよりする方が好きみたい」
さっと手早くスカートをさばき、咲夜は再び正座する。眉を下げ、困ったように笑う銀に誘われるがままに、霊夢も再び彼女に頭を預けた。ほんの少し離れていただけだというのに、布越しの温かさを長らく求めていたように錯覚する。
「……やっぱこっちのがしっくりくるわ」
「でしょ?」
しみじみと、少し悔しげに呟きじぃと天井の方を見る。見上げた先の彼女は楽しげに笑った。普通はされた方が嬉しいだろうに、何故こんなに楽しげなのだろうか。やっぱり変なやつだ、と霊夢は小さく息を吐いた。
「それに、こっちの方が貴方の顔がよく見えるわ」
うんうん、と一人頷いて、咲夜は霊夢の顔を覗き込む。だんだんと近付く赤い月に、霊夢は驚いたように目を見開いた。すぐさま眉間に深く皺を刻み、腕を伸ばし広げた手で彼女の顔を覆うようにしてぐいぐいと押し退けた。
「近い。調子に乗るな」
「あら、残念」
不機嫌そうな声を気にすることなく、咲夜は涼しい顔で姿勢を正す。調子のいいやつめ、と霊夢は目を眇め、ごろりと横を向いた。
「どうする? もうやめる?」
「…………もうちょい」
思案の末のふてくされたような声に、小さな笑い声と温かな手が降ってくる。さらさらと撫でられる感触は温かくて心地よく、安心する。思わず眠ってしまいそうだ。じわじわと姿を現し始めた睡魔に、霊夢は小さく欠伸をした。
「昼寝ばっかりしちゃだめよ」
咎めるような言葉とあやすような手つきは正反対だ。その裏に滲む『寂しい』という感情も、隠すように優しい声音とも正反対で、霊夢は呆れたように溜め息を吐いた。
こてん、と再度転がり、霊夢は咲夜の腹に顔を埋めるように向きを変える。
「寝ないしほっとかないわよ」
安心しなさい、と甘えるように頭を擦り付けると、撫でる手がぴたりと止まった。この体勢では顔を見ることはできないが、きっと彼女はくしゃりといつもの瀟洒な表情を崩し、子どものように笑っているだろう。勝てないわね、と苦笑交じりの声に、当たり前でしょ、と不遜に返した。
柔らかな手と、柔らかな体温と、ほのかに香る彼女の匂い。
やはり、こちらの方が安心できる。ぼんやりと考えて、霊夢は目を伏せた。
畳む
#咲霊 #百合