No.154, No.153, No.152, No.151, No.150, No.149, No.148[7件]
twitter掌編まとめ5【SDVX】
twitter掌編まとめ5【SDVX】
twitterで書き散らしてた大体2000字ぐらいの掌編まとめ。twitter掲載時から修正とか改題とかしてるのは気にするな。
成分表示:奈←恋1/キサ+煉1/つまぶき1/はるグレ+レフ1/嬬武器兄弟1/神十字1/火琉毘煉1/ハレルヤ組1/グレイス+ハレルヤ組1
晴れ舞台が焼き付いて/奈←恋
「今度の文化祭、演劇部の舞台でお姫様役をやることになったの」
そう言ってふわりと笑う親友の横顔は、夕焼けに照らされて色付いていた。夏も終わりに近づいているというのに夕の陽は鮮烈で、白い肌を暖色に染め上げていた。
「……え? お姫様? 奈奈が?」
処理落ちした脳味噌が、インプットされた情報をやっと理解する。アウトプットされたのは、間の抜けた呆けた声だった。
「変、かしら……?」
「ううん! すっごく似合うわ!」
穏やかな弧を描いていた眉があっという間に八の字に下がる。陰った可愛らしい顔を前に、慌てて言葉を続ける。そう、と奈奈は依然不安げに首を傾げる。そんな顔をさせてしまうようなことを漏らした己を内心罵倒しながら、似合うに決まってるじゃない、と恋刃は微笑んだ。
「それで、しばらくは練習で遅くなるの。本番まで、一緒に帰れなくなっちゃうと思う」
寂しげに告げる七色の少女の手を、紅色の少女はきゅっと握る。少し曇った虹の瞳がぱちりと瞬いた。
「待つから一緒に帰りましょ。奈奈一人で夜遅くに出歩かせるのは危ないわ」
文化祭での公演である、大がかりな物になるだろう。それだけ練習量も多く、日が暮れるまで稽古を重ねるのは容易に想像できた。秋に近づき夜がすぐさま降りてくるようになった今、その程度の理由で親友一人で夜道を歩かせるなど言語道断だ。
「いいの?」
「もちろん。あ、ついでに練習見学できない? 劇の内容気になる」
明日聞いてみるわね、と七色は笑う。お願い、と紅色も笑った。
見学許可は簡単に下りた。毎日練習に励む親友を舞台袖から眺め、時には差し入れを持ち込み、時には初めての演技に不安がる様を励まし、時には過度に卑下する姿に檄を飛ばし。練習の日々は過ぎていく。
文化祭当日は盛況だった。大きな体育館に用意された座席の八割は埋まり、多くの人が舞台の幕開けを待っていた。
大丈夫かしら。普段とは正反対の黒いドレスに身を包み、カタカタと震えながら奈奈は漏らす。大丈夫よ。すっかりと冷たくなった美しい手を握り、恋刃は自信たっぷりに言う。演劇部の、七色の彼女の努力をずっと見てきた己には、この舞台の失敗など全く考えられなかった。大成功に決まってるわ、と冷えた手を包んで温める。そうだよ、大丈夫、と舞台衣装に着替えた部員たちも口々に言った。
頑張ってくるわね、と最後には笑顔で手を振った親友は、今は堂々とした姿で舞台に立っていた。初めは緊張でわずかに震えていた声も、今では普段通りの澄んだ、それでいて稽古によって鍛えられたよく通る声をしていた。動きもなめらかで、初心者には見えないものだ。ここしばらくの彼女の努力が結晶となり、ここで輝いていた。
主人公役である演劇部員の少年も、小さな身体をめいっぱい動かし舞台を盛り上げる。勇者である主人公は、ヒロインであるお姫様を追いかけて国中を旅する。たった一人の険しい旅路の様子を、幼い少年は懸命に演じてみせた。
物語は佳境に入り、とうとう勇者と姫は出会う。救うべき存在との邂逅だけでは、ハッピーエンドには至らなかった。ナイフを持った勇者は慟哭する。姫の悲痛な悲鳴が会場中に響き渡った。少女の手からリンゴが転がり落ちる。凶器を握ったまま蹲り嗚咽を漏らす少年の手に、たおやかな手が重ねられた。
どくん、と心臓が大きく脈打つ。え、と思わず漏らした声は、最大の山場を演出する音楽に掻き消された。
どくん、どくん、と心臓がうるさく跳ねる。気持ちが悪くなるぐらい鼓動が早くなる。背筋を冷たい何かが撫ぜる。嫌な汗が頬を伝う。
どうして、と少女は一人混乱に陥る。このシーンは練習でも特に見たものだ。主人公の台詞を覚え、帰り道に二人で練習したほどの場面である。なのに、何故か嫌なものが身体中を這って回る。細い身を雁字搦めにして、どこかへ連れて行こうとする。
精神は暗く揺れ動いているというのに、紅い目は舞台上に釘付けになっていた。細い手を振り払おうとする勇者に、姫は――親友は必死に言葉を振り絞る。序盤か弱く演出されたヒロインの隠された強さが発揮されるシーンだ。大好きな親友の最大の見せ場、最高に格好良い素敵なシーンだ。目が離せるわけがない。なのに、心は目を力いっぱい閉じてしまいたくてたまらなくなる。
何で。どうして。こんなに素敵な舞台なのに。こんなに素敵な演技なのに。こんなに素敵な奈奈なのに。
嗚咽を堪えることなく泣く勇者の背に、姫はそっと腕を回す。小さな身体を包み込むように、細い身いっぱい使って抱き締めた。
奈奈が、誰かを抱き締めている。
胸がカァと熱を持つ。心臓がギュウと締め付けられる。顔からサァと血の気が引いていく。末端がどんどんと冷えていくのが分かった。
情動に震える少女は、ずっと舞台を見つめる。見たくもない、と心は意味が分からないことを叫ぶ。見なければならない、と頭は当然のことを語った。
主人公が、ヒロインが舞台中央で抱き締め合う。金が、赤が、黒が、スポットライトを浴びて鮮烈にきらめいていた。
輝かしい舞台を見つめる紅は、光など失っていた。焦点の合わないガーネットが、結末で結ばれる二人をただ見つめていた。
口止め料八十円/キサ+煉
オレンジ色のスニーカーに包まれた小さな足が一生懸命動く。バッジで飾った帽子を揺らし、着崩したモスグリーンのジャケットをはためかせながらキサは廊下を駆けた。
夏休みの間にたくさんのスクープを撮ることができた。あとはこれを報道するだけだ。あぁ、早くたくさんの大事件を伝えたい。もちろん、起こったのは楽しいことばかりではない。しかし、そこには読み取るべき真実が眠っているのだ。これを広めないで何が報道か。
走る小柄な身体を、高い影が遮る。ぶつからないように急いでブレーキを掛けた。キュッと靴の底面と廊下が擦れる音があがる。
塞がる者から何かが飛んでくる。いつも通り、放り投げられた物を両手でキャッチする。学園内の購買で売られているあんぱんだ。大好きなそれに、思わず頬が緩む。それもすぐに戻り、少女は不可思議そうな表情を浮かべた。
「次郎くん、いつもあんパンくれるけど何で?」
「火琉毘煉だ」
疑問を投げかける少女に、煉はすぐさま訂正を入れる。『火琉毘煉』はあくまで彼が名乗っているだけで、本名は『鈴木次郎』である。真実を伝えるべき存在でありたいのだ、人のことはきちんと本名で呼びたい。
「いつも勝手に人のことを面白おかしく喧伝するからだ」
今だってそうだろう、と少年はすぐ隣、彼女のクラスのドアを指差す。たしかに、今まさに集めた大スクープを学級中に披露するところだった。読まれてるなぁ、と鞄にそっと手をやる。早朝にようやくできあがった、彼が載った新聞をそっと奥に隠した。
「この退治屋である火琉毘煉の活躍を記事にすればいいものの、何でやれ熱中症になったやら服が乾かないやらそういうことばかり言いふらすんだ」
「熱中症の危険性は報道すべきでしょ? 服のも梅雨の酷さを表すにはちょうどいい写真だったし」
指を立ててキサは言う。納得してしまったのだろう、うぐ、と悔しげな声が漏れた。
「あと毎回もらってもちょっと困るなぁ」
いつだって愉快な事件の中心にある彼は、キサが記事にすることの多い人物の一人だ。それを報道しようとする度、すぐさまあんパンが投げて寄越されるのだ。それも、毎回。一体、どこで情報を仕入れているのだろう。そこばかりが気になって仕方が無い。聞いても答えてくれないのだけれど。
「抜かりない。いつでも美味に舌鼓を打てるよう、保存期間が長いものを選んでいる」
顎に指を当て、煉はふっと格好付けたように笑う。論じているのはそこではないが、賞味期限が長いのはありがたい。
それにしても、毎回これでは財布が痛むだろうによくやることだ。大変だねぇ、と漏らしそうになった言葉をそっと飲み込む。もらう側が言う言葉ではない。
「だから言うなよ」
眼鏡で飾られた幼げな顔をビシリと指差し、白髪の少年は言う。人を指差すんじゃないわよ、と足下から窘める声があがった。
「分かったよー」
少女はひらひらと手を振って応える。ネタが一つ減ってしまうのは残念なことだ。しかし、きちんと対価としてあんパンを受け取っているのだから口は閉じねばならない。真実の報道は大切ではあるが、そこを反故してしまうのは良くない。そのあたりは弁えていた。
言葉を信じたのだろう――今まで何度も同じことをして口止めしたのだから信じて当たり前だ――煉は、では、と身を翻す。そのまま大仰な動きで廊下を歩き、自身の教室へと入っていった。足下を歩く式神が振り返り、小さく礼をする。ごめんなさいね、と大人びた声が聞こえた気がした。真っ白な毛が美しい狐は、すっと音も無く消えた。
黒い背を見送り、キサは乱れた頭を掻く。落ちてきそうになったキャスケットを慌てて受け止め、しっかりと被り直した。
新聞は作り直しかなぁ。
心の中で苦く呟いて、報道少女は軽い足取りで教室へと入る。ホームルームが始まりを告げるチャイムが、人がいなくなった廊下に響いた。
救う旅路と深い夢路/つまぶき
すぅすぅと穏やかな寝息が眼下からあがる。ソファに横たわった可愛らしい寝顔を前に、つまぶきはあー、と何とも言えない声を漏らした。
オンラインアリーナのバージョンアップ、それに伴う楽曲とエフェクトの追加、プレー性向上を目的とした機能アップデート、外部世界の大会運営に関する相談、プロリーグ開催に向けての準備。加えて通常アップーデトを行うだけでも重労働だというのに、そこにヘキサダイバーの調査にバトル大会も加わったのだからそれはもう大変だ。世界に一番近い位置にいる頑張り屋さんな少女は、起こる何もかもに全力で打ち込んだ。
そんな大仕事をいくつも終え、ようやく業務に凪が訪れた。ここ数ヶ月世界の代表として様々なことを行っていたレイシスを慮り、少しの間ナビゲートの仕事はグレイスが一任してくれている。おかげで、少女は久しぶりに穏やかな日々を過ごす時間を手に入れることができた。
そんな中で彼女がまず選んだのは、ゲームだった。新シーズン以降と同時のアップデートで追加される楽曲、そのジャケット撮影で久方ぶりに会話した少年からゲームの楽しさを説かれたのだ。彼女がやるゲームといえば、自分が暮らす世界の音楽ゲームが主だ。家庭用ゲーム機は持っているものの、随分と長いこと触っていない。オンラインサービスに入れば自由にできるよ、という少年の言葉に、便利デスネ、とキラキラと瞳を輝かせて言っていたことは記憶に新しい。
少女の手には大きなゲーム機を充電し、四苦八苦しながらオンラインサービスに加入し、専用のゲームをダウンロードし。そうして、彼女は世界を救う旅へと繰り出した。
荒廃した世界を旅するだけでなく、強い味方キャラを作り出すシステムに自身で歩いてマップを作るシステムと、勧められたゲームにはたくさんの要素が詰まっていた。やりこみ要素も兼ねているものだ。うんうんと唸りながら味方を作り出す横顔は真剣で、それでいて好奇心に輝いていた。二人で相談しながら合成を進め、マップを歩き、物語を歩んでいく。今日はようやく物語の終点に近い中ボスを倒したところだ。
点けっぱなしになっているゲーム機に近づく。画面はボス戦とその後の会話イベントが終わったところで止まっていた。念のためセーブをして、ゲーム機をスリープ状態にする。己の小さな身体では骨が折れる作業だが、あれほど頑張ってクリアしたのが水泡に帰しては一大事だ。しょんぼりとした少女の顔など見たくない。
落ちないようにゲーム機をソファの奥に追いやり、小さな妖精は部屋を飛び回る。隅に畳まれしまってあったブランケットを一生懸命引きずり、彼女の寝る場所へと帰る。なんとか広げ、よく眠る柔らかな身体を布で包み込んだ。一仕事終え、ふぅと息を漏らす。これで風邪を引くことはあるまい。
すやすやと眠る桃を眺める。ゲームはもう佳境だ。この進み具合ならば、数日後には最終ボスを撃破し物語を終えることができるだろう。そんな盛り上がるストーリーが気になって仕方無いのか、彼女は日に日に夜更かしをしていた。遅いから寝ようぜ、と誘っても、もう少しダケ、と懇願してゲームを続けるのだ。おかげで最近は寝不足のようで、授業中うとうととすることがあると聞いている。毎日同じだけ夜更かしして物語を横で見つめる己も日夜眠気と戦っているのだけれど。
身を丸め、穏やかに眠るレイシスを見下ろす。真っ黒で大きな目がふと細まった。
己がヒトと同じほどだったなら、彼女をベッドまで運んでいけるのだろう。少女の手のひらに収まってしまうほど小さな己では、そんなことは到底できない。潰されるのがオチである。結局、できるのは起こすか毛布を掛けてやるかの二択だ。この可愛らしい寝顔を歪めることなどできるはずがないから、毎回後者を選ぶこととなっている。
「風邪引くナヨナー」
長い髪を座面に広げ、白い瞼を下ろし、桜色の唇から寝息を漏らす少女に語りかける。深い眠りの海に身を沈めている彼女には届くはずがないと分かっている。それでも、一言ぐらいこぼしたくなる。心配なのだ、これでも。
三角形の口が大きく開く。くぁ、とあくびが漏れた。
己もいい加減寝なければいけない。きっと明日も起きる時間ギリギリまで眠っているであろう少女を起こしてやらねばならないのだ。いつまで経っても手が掛かる。ふ、と穏やかな吐息が弧を描く口元から漏れた。
ふよふよと飛び、ソファの縁に近い場所に身体を落ち着ける。ここならばレイシスに潰されることもないだろう。余った毛布の端に潜り込み、妖精は薄い身体を柔らかなクッション生地に預けた。
おやすみー、と眠たげな声。そのまま、桃の少女と銀の妖精は暖かな眠りに身を委ねた。
緑の壁/はるグレ+レフ
小さく息を吐き、烈風刀は立ち上がる。パッパと手を叩き、付いた微細な土を落とした。手を洗わねばならない。しかし、ここに水場らしい水場は無い。布で拭っているが、衛生上限界もあるだろう。どうしたものかな、と考えていると、烈風刀、と名を呼ばれた。
払う手をそのまま、少年は振り返る。黒い世界を背景に、躑躅の髪がふわりと揺れるのが見えた。トン、とヒールが地面を打つ。自分の庭のように暗い海を跳び回る少女が目の前に降り立つ。髪と同じ色をした目が、まっすぐに己を射抜いた。
「昨日の続きなんだけど」
「あぁ、あれですか」
様々な事象が重なり、しばらくの間彼女の下に身を寄せることになった。ネメシスを侵攻する彼女は、度々立案した作戦の相談をしてくる。つい先日までネメシスに住まっていた己は土地勘がある。効率的な進軍方法を相談されることが多々あった。
「ルートは十分だと思います。強いて言えば、特別教室棟側からも送り込めば挟み撃ちにしやすいでしょうか」
「あぁ、そっちは考えてなかったわ」
宙空に紫の電子モニタが現れる。ネメシスでも度々見るそれと全く同じのデバイスは、バグを使って作ったものらしい。器用なものだ、と感心したのを覚えている。
「ねぇ、この地形ならここの庭みたいなところからも――」
かざすグレイスの手にあわせ、モニタが動く。そのまま、こちらへと向けられた。電子の地図を指差そうと、細い身が近づく。瞬間、強い風が間を二人の通り抜けた。
風圧に細めた目を開ける。向いた隣、風が吹き込んできた場所には忍装束に身を包んだ少年がいた。夜闇に浮かぶ満月のような瞳がこちらを睨めつける。緑衣に包まれた手が、そっと広げられた。まるで後ろにいる少女を守るように。
「はーるーかー!」
少年の後ろから声があがる。明らかに苛立った、強い調子のものだ。目的を果たすべく大切な作戦を練っていたところを邪魔されたのだ、感情的なところがある彼女が怒りを覚えるのは当然である。
「邪魔するなって言ってるでしょ! 何回言ったら分かるのよ!」
それも、もう片手ではとうに足りないほど邪魔されているのならば。
グレイスと烈風刀は二人で相談することがよくある。会話の最中、特にふとした瞬間距離が近づくと、必ず始果は現れるのだ。忍である彼の動きなど、速度と手数を重視して戦う烈風刀ですら捉えられない。いつも間に入られ、警戒した目でじぃと睨まれてしまう。
子猫を守る親猫のような姿に、少年は苦い笑みをこぼす。彼の行動は、躑躅の少女にとっては不可解に映るだろう。しかし、碧い少年にとってはこの上なく分かる行動原理だ。だって、想いを寄せる少女が知らない男と二人で話している状況など、許せるはずがない。
「すみません」
「謝るならやるなって言ってるじゃない! 何で覚えない――」
警戒をあらわにした声音で忍の少年は謝罪の言葉を紡ぐ。毎度のことだ。学習しないそれが気に食わないのだろう、少女は声を荒げるばかりだ。それも何故か途中でふつりと途絶えてしまう。
「……いいからどきなさいよ。話の途中なんだから」
「…………はい」
少し低くなった声に従い、少年は二人の間から一歩横にずれる。碧と躑躅を阻んだ緑の障壁は失われた。しかし、その姿はスッと消える。気付けば、彼はグレイスの後ろにいた。長い袖に包まれた手が、黒で彩られた白い腹に回される。そのまま、ぎゅっと抱き締め後ろに寄せた。会議中の二人の身体が遠ざかる。
「…………で、ここのスペースなんだけど」
「はい」
身体を包まれることに一切言及せず、少女は話を続ける。小さな唇が紡ぐ声は、もう諦めきった響きをしていた。これも毎度のことなのだから仕方が無い。画面を見る邪魔にならないなら、と受け入れているようだ。ある種合理的な判断である。
躑躅と若草の様子を気にせず、否、気にしない風を装って烈風刀は話を続ける。グレイスもどんどんとアイディアを出していった。
ちらりと横目で少女を、その背を、腹を、身体を強固に守る少年を見る。依然、彼は険しい顔をしていた。やはり、己とグレイスが話すことをよく思っていないらしい。それでもこれ以上手を出してこないのは、『邪魔するな』という愛しい少女の命令を受けてのことだろう。今回のようなことはあれど、彼は忠臣と表現するのがこれ以上にないくらい相応しい人物なのだ。
ふ、と烈風刀は息をこぼす。微笑ましさのような、諦めのような、羨望のような、複雑な音色をしていた。
これぐらいできれば良かったのに。
あり得もしないことを頭の隅に追いやり、少年は発光するモニタに視線を戻す。黒衣で飾られた白い指が、電子画面を何度も辿った。
機能/性能/君の色 /嬬武器兄弟
青い布地を頭から被る。輪に腕を通し、太い肩紐をしっかりと肩に掛けた。生地の中程に付いた長い紐を後ろに回す。どうにか後ろ手で蝶々結びにした。うっかり踏んで躓かないように、ぎゅっと引いて端の部分を短くする。腰に当たる少しねじれた感覚から美しい形になっていないことは分かるが、怪我を引き起こさないことの方が重要だ。見目を気にするのは慣れてからだ。
買ったばかりのエプロンを見下ろし、雷刀は満足げに笑みを浮かべる。何故そんなものをわざわざ着けるのだろう、と料理する弟の背を見て疑問に思っていたが、実際に着けてみるとなかなかに良いものだ。気分が切り替わる感覚がした。
まな板の前に立ち、包丁を握る。白いそれに載った野菜をリズミカルに切っていく。途中、勢い余って跳ねた具材がエプロンに守られた腹に当たった。少し厚い布地に阻まれているため、服が汚れることはない。こういうところが便利なのだな、と新たな発見に少年は目を輝かせた。
「案外似合ってますね」
後ろから声が飛んでくる。包丁を置いて振り返ると、マグカップを手にした弟の姿があった。碧い視線は己の身体を守る青い生地に注がれている。彼と一緒に買いに行ったものだが、着ける姿を見せるのは初めてだ。
「だろー? 料理もできるオニイチャンって感じでいいだろー?」
ニコニコと笑みを浮かべ、朱い少年はくるりと回る。長い腰紐がふわりと舞って身体とともに円を描いた。台所でふざけない、と叱責の言葉がすぐに飛んでくる。
「後ろ、縦結びになってますよ」
じっとしててください、と冷静な言葉に、大人しく動きを止める。キッチンに入ってきた烈風刀は、青い腰紐をするりと解いて手早く結び直していく。綺麗な青く細い蝶々が引き締まった腰に止まった。あんがと、と生地の持ち主は振り向いて礼を言う。
「後ろ手だと結びにくいんだよなー」
「いつか慣れますよ」
そう言う弟はいつだって後ろ手でも綺麗な蝶々結びを作っていた。長い間赤いエプロンを身に着け、キッチンに立っていただけある。それでも何だか悔しい。不器用な自覚はあるが、蝶々結びなんて基礎的なことぐらいは早くできるようになりたい。
「そーいやさ、何で烈風刀のエプロンって赤なんだ? いっつも青選ぶだろ?」
ふと浮かんだ疑問をそのまま投げかける。碧い髪に碧い目。碧は弟を象徴する色だ。だからか、彼は碧いものを好んで買うことが多い。それが、エプロンだけは正反対の赤いものなのである。珍しいことだ。
冷蔵庫に手を掛けた碧い少年は、白い戸を開けるのを止め顎に手を当てた。翡翠が宙を漂う。
「……たぶん安かったからですね。生地が丈夫で安いとなると、色を選ぶ余裕なんてありませんから」
なるほど、と雷刀は頷く。弟は好みより機能を優先する節がある。毎日着けるものなのだから、機能を優先するのは当然ではあるのだけれど。
買う前はたかが布、と思っていたが、実際に買いに出てみるとかなり違いがあることを知った。布地の厚さ、身長に合った丈、ポケットの有無、適度な腰紐の長さ、その他諸々。選択すべきこと、重要視するべき点はたくさんあった。片割れのアドバイスと己の好みを擦り合わせた結果、今身に着けた厚めの青いエプロンを買ったのだ。悩んで選び抜いただけあって、身に着けたこれは心を弾ませる代物だった。
「貴方こそ、何で青にしたのですか? いつもは赤を選ぶでしょうに」
朱い髪に朱い目と、弟と正反対の朱に縁がある己は、何を買うにもその色を選ぶことが多かった。今回のように青を選ぶのはほとんど無いことだ。彼が疑問に思うのも無理は無いだろう。
「烈風刀が赤ならオレは青かなーって思って」
店頭には同じ型の赤色もあった。けれども、手を伸ばしたのは片割れを想起する青だった。別にお揃いの色でも良かったのだが、なんだか彼の色を選びたかったのだ。今思えば、洗濯する時取り違えることがなくなるので合理的な判断だ。
「いつもは逆ですのにね」
何だか不思議です、と烈風刀は笑う。確かになー、と青い裾をつまんで雷刀も笑った。
「晩飯、楽しみにしとけよ」
「期待してますよ」
ニカリと笑う兄に、弟はふわりと口元を綻ばせる。おう、と元気な声がキッチンに響いた。
朱い唇降りしきり/神十字
ちゅ、と可愛らしい音が若草芽吹く草はらに落ちる。くすぐったいよぉ、ときゃらきゃらとした可愛らしい笑い声があがった。
硬い輪郭をした手が少し短い前髪をそっと上げる。赤い唇が、さらけ出された白く柔らかな額に落とされる。おにいちゃんキスばっかしてるー。鈴のような笑い声が蒼天に昇った。
「だってお前らのこと大好きだしー?」
「わたしもおにいちゃんのこと好きだよー!」
紅葉手がシャープな線を描く頬に伸ばされる。潤った小さな唇が、春の日差しを浴びて色付き始めた肌に触れる。幼子の可愛らしい口付けに、紅い男はニカリと笑みを浮かべた。オレも好きー、と黒衣に包まれた腕が彼の半分にも満たない小さな身体を抱き締める。可愛らしい笑声が、明るい笑声が、昼空に響いていく。
和やかな風景に、青年は頬を緩める――はずだった。けれども、最近の有様を見ては苦い表情ばかりが浮かんでしまう。子どもにこんな顔を見せてはいけないのに、と表情筋を律しようとするが、意識に反して強張っていくばかりだ。
なぁ、あれって何?
住宅が並ぶ街並み、玄関で頬に口付け合う家族を見て紅は疑問の声をあげる。えっ、と思わず同じ音を返してしまった。だって、数え切れない時を生きている『神』である彼が口付けを知らないなど考えるはずがないではないか。
大切な人への親愛表現ですよ、と優しく笑って教えた。翌週、今度は唇と唇を合わせる男女の姿を見て、あれもそうなのか、と指差された時は頭を抱えたが。
新たな感情の表現方法を覚えた彼は、施設の子どもたちに口付けを降らせるようになった。曰く、皆好きだから。曰く、全員大切だから。子どもたちと同じ時を過ごすようになって随分と経つ。愛情も湧くだろう。庇護欲を刺激する幼子ならば尚更だ。己だってあの子たちが愛しくて仕方が無い。
けれども、その表現を一律に『口付け』でやってしまうのは良くないに決まっている。口には絶対にするな、と言い聞かせているが、何かあっては大変だ。大切なファーストキスを覚えたての表現方法を使いたがる存在に奪われてしまっては、可哀想なんて言葉では済まない。
「なんかすげー顔してるけど」
地を映し始めていた蒼の中に、紅が宿る。目の前には、少し屈んでこちらを覗き込む神の姿があった。いつの間にか子どもたちと別れてこちらに来たらしい。
「……いい加減キスするのやめたらどうですか」
「何で? 好きなんだからいいじゃん」
「色々と問題があるのですよ」
あっけらかんとした様子の神に、人間は渋い顔をする。事故が起こってからでは遅いのだ。それに、あんな微笑ましい風景を見ているというのに何故だか胸が薄ら暗くなるのだ。長く暮らしているはずの己以上に懐いている姿を見ているからだろうか。嫉妬としても幼すぎる。はぁ、と溜め息をこぼす。そーなのか、と紅は納得半分疑問半分の声を漏らした。
「でも大切な人にやるもんなんだろ? 皆大切なんだしいいじゃん」
「『大切』の中でも特に大切な人にするものなのです。そう簡単にするものではありません」
へぇ、と赤い口から間の抜けた声が漏れる。そうは言ったものの、彼の中で『大切』の分類がきちんとされているか怪しい。不安は尽きない。
「それに、子どもたちの教育にあまり良くありません」
所構わず口付けを降らせる神の姿に影響され、子どもたちの間では口付け合うのが流行し始めている。こちらも『口』への事故が不安だ。言い聞かせ、早く廃れさせなければいけない。そのためには、まず元凶を止めなければならないのだ。
ふんふんと目の前の紅い頭が上下し頷く。今度は肩を寄せるようにことりと傾く。戻ってまた頷き。なるほどな、と会得のいった声が聞こえた。
どうやら理解してくれたらしい。よかった、と胸を撫で下ろす。あとは子どもたちの方をどうにかせねば。考える頭に何かが触れる。温かなものがそっと頭を撫ぜ、こめかみを伝い、頬へと添えられる。
「じゃあクロワにはしてもいいんだよな?」
だってクロワは一番『大切』なんだし。
そう言って神は笑う。頭上におわす太陽のような眩しい笑みが向けられる。きゅうと何かに締め付けられるような感覚に陥った。思わず一歩退く。固さが目立つ手が自然と離れていった。
「……まぁ、僕になら」
日々振り回されているものの、己ならば彼にきちんとストップを掛けられるはずだ。『事故』があっても子どもたちほどダメージは受けない。それに、『神』の求めるものを捧げる信者の役目である。頬や額を差し出すぐらい安いものだ。
草が踏みしめられる音。目の前の紅が視界を埋める。また頬に温度。紅玉がふっと細まり、赤い口が開く。クロワ、といっとう甘い声が己の名をなぞった。
紅が近づく。風に揺られる紅が、真ん丸な紅が、八重歯で彩られた紅が近づく。視界を埋めていく。鮮やかな、眩しいほど鮮やかな色に反射的に目を閉じた。
柔らかな温もりが頬に触れる。ちゅ、と可愛らしい音が耳元で聞こえた。
熱は一瞬で離れて消えていく。消えていくはずなのに、頬が熱くて仕方無い。触れた場所から伝播していくような心地だ。情けない、と思わず目を伏せる。たかが頬へと口付け程度で赤くなるなど、初心にも程がある。
「そういや何で口はダメなんだ?」
「…………色々と複雑なのです。帰ったら説明しますから」
この場で唇に唇に触れる意味など教えられるはずがない。彼を納得させる簡潔な言葉は持っていないのだ。それに、子どもたちに聞かれては一大事である。彼と二人暮らしをしているのだから、帰ってから本で例でも出しながら説明した方が早い。
なぁ、と呼ぶ声。視線をやると、輝く炎瑪瑙と視線が合った。
「帰ってからもやってもいい?」
「ダメです」
すぐさま切り捨てると、不満げな声があがる。頬を膨らませる姿は幼げで可愛らしいが、絆され許してしまうべきことではない。それを含めて、帰ってからみっちり教えねば。
一人決心し、蒼は子どもたちへと歩みを進める。そろそろ戻りますよ、と屈んで視線を合わせながら告げる。はーい、と元気な声と、早くも草を踏みしめ駆けていく音が聞こえた。
風が子の、人の、神の背を押す。若い緑で染まった庭から影が消え、建物の中からはしゃいだ声が聞こえ始めた。
業焔宿りし瞳/火琉毘煉
幕が垂らされたブースに入る。敷かれた布に皺が寄らないよう、慎重に足を運んだ。
空間の真ん中に音も無くしゃがみこむ。少し斜めを向き、少年は片膝を床につけた。右半身に温度。視線をやれば、珍しくこちらに寄り添う式神の姿があった。あまり接触を好まない彼女だが、指定されたポーズなのだから仕方無い。早くしなさいよ、と言いたげな菫がこちらに向けられた。
懐から取り出した愛用の札を、いつものように両手の指に挟んで構える。そのまま、真正面を向いた。まばゆいほどの照明が、数え切れないほどの撮影機材が、脚立に設置されたカメラが見返してくる。透明なレンズと視線がぶつかる。遠くまで引かれ小さくなった円の中に、黒が、白が、赤が見えた。
深い赤の目がすぅと眇められる。よく舌が回る大きな口が閉じられ、口角が上げられる。普段は見せることのない不敵な笑みを作りだし、退治屋はまっすぐにレンズを見つめた。
「よく撮れてるじゃないか」
液晶画面を横から覗き込み、煉は満足げに言う。撮影の興奮冷めやらぬのか、どこか上擦った調子をしていた。親指と人差し指を顎に当て、ふふふ、と漏らす笑声もどこか浮ついている。前足を机に掛けて一緒に覗き込んでいた鈴音が呆れを多分に含んだ息を漏らした。
いつもの調子の少年に構うこと無く、撮影班は淡々と撮った写真を比較していく。これでいいかな、と一枚の写真がノートパソコンの画面いっぱいに表示される。いいじゃないか、と依然浮かれた声が飛んできた。
「俺の業火より燃え血よりも深い瞳が鮮明に刻まれているな。この漆黒の闇と紅蓮の焔差す純白の髪も綺麗に映って――」
「じゃあこれで決まりだねー。お疲れ様」
流れるように言葉を並べ立てる少年に、撮影を担当していた識苑は手を振る。よく回る舌が止まり、世話になった、と礼の言葉がなめらかに告げられた。礼節はきちんと弁えていた。
黒いブーツが踵を返す。一歩進んだところで、それはまたくるりと回った。赤い瞳が次の撮影の準備をしようとパソコンを操作する背を眺める。しばしして、なぁ、と煉は口を開いた。
「先の写真なんだが」
「あれ? 別のが良かった?」
「いや、違う」
慌てて先ほど決定したばかりの写真を開く教師に、退治屋は否定の言葉を返す。夕陽色の目がぱちりと瞬いた。相対する茜空の目が宙を泳ぐ。しばしして、長い指が液晶に映る自身の顔を差した。
「……左目にエフェクトを付けることってできるか?」
「ちょっと」
煉の提案に、足下に付いていた鈴音が抗議の声をあげる。黒衣に包まれた足を白い前足がぺしんと叩く。わがままを言うな、手を掛けさせるな、と鋭い紫苑の瞳が頭上の主を見上げた。
「いや、もちろん現時点でも素晴らしい写真ではあるのだが、この彼岸花のように鮮烈で紅玉のように濃く深い左目に焔のように輝きたなびく光のエフェクトを付けることで写真の更なる魅力が引き出され――」
「いいねぇ! かっこいいと思うよ!」
言い訳をするように早い調子の長口上を遮り、月色の目がぱぁと輝く。骨張った手がマウスを操り、画像編集ソフトを立ち上がる。左目に風になびくような赤の線を引き、腕を組んで依然迂遠な言葉を連ねる少年に画面を向けた。
「こんな感じ?」
「そう!」
簡素に加工された写真を指差し、白髪の少年は大声をあげる。理想通りだったらしい。
「そういえば持ってきた宣材写真もこういう風に加工されてたしねー。君っぽくて良いと思うよ」
「そうだろう? 俺の代償背負いたる左目にはこういうのが――」
「いい加減にしなさい」
また口を開く煉の頬に肉球が押しつけられる。見かねて立ち上がった鈴音の手だ。まだ丸みを残した頬がぐにりと歪んだ。口に近い部分を押さえられてか、長々とした言葉が止む。そんな二人を気にすること無く、識苑はマウスを操作した。
「うん、じゃあエフェクト入れとくね。今度こそお疲れ様」
「よろしく頼む」
では、と手を振って身を翻し、少年は大仰な足取りで扉へと歩いていった。戸を開け、廊下に出て一礼し、彼は撮影室を出た。
特別教室棟の廊下に、ふふふ、と浮かれた調子の笑い声と、はぁ、と呆れた調子の深い溜め息が響いた。
月より団子/ハレルヤ組
窓越し、星が輝く夜を背に白が並ぶ。綺麗に揃えられた真ん丸は三方の上に積み上げられ、美しい三角山を作り出していた。つるりとした丸だというのに転がり落ちる気配すらないところから、作った人間の几帳面さがよく窺える。
薔薇輝石の瞳が、柘榴石の瞳が真っ白ですべすべとした表面を見つめる。二色の瞳は山を成す団子に釘付けになっていた。こくりと白く喉が上下する。真っ白なお団子。美しいお団子。美味しそうなお団子。丁寧に作られた月見団子は、少年少女の食欲をこれでもかと刺激した。夕飯を食べたばかりだというのに腹が鳴ってしまいそうなほどだ。
「……一個ぐらいならバレなくね?」
「形崩れちゃうからバレちゃいマスヨ」
「食べる用は別で作ってありますから勝手に食べない」
月見団子の山に熱烈な視線を送る二人の背に、ほのかに棘が見える声が掛けられる。身体が二つビクンと震え、鏡合わせのような動きでおそるおそる振り向く。食欲に輝く紅葉と桃に、盆を持った浅葱の姿が映った。
「タッ、食べマセンヨ?」
「まだ何にもやってねぇよ?」
きょろきょろと視線を泳がせる二人に、烈風刀は小さく息を漏らす。呆れと少しの愛しさがにじんでいた。薄く険しさが浮かぶ表情が解け、小さな笑みを浮かべた。
「それに、そちらは作ってから時間が経って固くなっています。あんまり美味しくありませんよ」
こっちを食べてください、と少年は手にした盆を机の上に置く。両手でなければ持てない大きさのそれには、朱と桃が今の今まで見つめていた白があった。それも、三つ。
碧は手慣れた様子でテーブルに皿を並べていく。各々の前に置かれた小皿の上には、一口サイズに整えられた団子が小さな山の形に盛られていた。脇にある小さな鉢には、黒と茶と橙がスプーンとともに入っている。二色の瞳が不思議そうな様子で三色を覗き込む。少し節が目立つ指が器を順々に指差した。
「これがあんこで、こっちがみたらし餡、そっちがかぼちゃ餡です。好きなものを掛けて食べてください」
わぁ、と感嘆の声が二つあがる。誤魔化すように宙をうろうろと漂っていた紅水晶と紅玉が皿に一心に向けられる。見つめる瞳は夜空に浮かぶ星と同じほど輝いていた。関心は台の上に成された大きな三角山でなく、目の前の小さな山にすっかりと移ってしまったようだ。
並べられた団子の前に、三人一緒に手を合わせる。いただきます、と元気な合唱が夜の部屋に響いた。
「あんこ美味しいデス~!」
「かぼちゃんめぇ! 甘い!」
好きな餡を掛けた団子が赤い口の中に消え、柔らかな頬がもぐもぐと動く。感動に満ちた声が二つあがった。それはよかった、と烈風刀もみたらし餡をひとすくい掛けて団子を口に運ぶ。出来が良かったのだろう、花緑青の目元がふわりと解けた。
赤い口の中にどんどんと白が消えていく。団子も餡もあっという間に無くなってしまった。ごちそうさまでした、とまた合唱。美味しかった、と元気いっぱいの二重奏が続いた。
ルビーレッドが、チェリーピンクがそろりと動く。同じ方向へと向けられた視線二つは、まだ山を成す大きな月見団子に吸い込まれた。輝く二色は、まだ食べ足りないと語っていた。夕飯をめいっぱい食べて尚、ほの甘いであろうそれに目を奪われてしまう。『甘い物は別腹』とはよく言ったものだ。
「そのまま食べるのには向いていませんよ」
「じゃあどうすんだ? 捨てるわけにはいかないだろ?」
「調べたのですけど、おしるこにするのがいいそうで。水分を吸って柔らかくなり食べやすくなるみたいです」
おしるこ、と二つの声が重なる。同時にバッと振り返り、白い山に向けられていた視線が若草色に注ぎ込まれる。見つめる二色の瞳には、食欲の光が煌々と輝いていた。小さく開いた口から涎が垂れてしまいそうなほどの輝かしさだ。
「……明日にする予定だったんですけどね」
半分諦めた調子の声に、少年と少女の目が丸くなる。まっすぐに見つめる瞳には、期待がたっぷりと乗っていた。
困ったように、呆れたように眉を八の字にした碧は、手早く盆に皿を載せる。秋服に包まれた腕が、三方へと伸ばされる。そのまま、器を重ねて空けたスペースにそれを載せた。
「今から作ってきます。ちょっと待っててください」
「ハイ!」
「おう!」
やったー、と顔を向き合わせ手を上げ喜ぶ二人の姿に、烈風刀はそっと口元を綻ばせる。先の団子も、飾っていた月見団子も、彼が自作したものだ。自分が作った料理を楽しみにしてくれている。美味しく食べてくれている。作り手冥利に尽きる光景だ。
再びキッチンに立った少年は、ふとリビングへと視線を戻す。ローテーブルの前に腰を下ろした二人は、窓の外には一切目もくれず楽しげに話していた。おしるこ、とはしゃぐ声が耳をなぞる。
お月見なんですけどね、と笑みを含んで呟く声は、少し冷えた台所に落ちて消えた。
「今日の卵焼きしょっぱかったですね」「たまにはこういうのもいいでしょ?」/グレイス+ハレルヤ組
いただきます。四重奏が昼休みの賑やかな教室に響く。合わせた手を解くと、各々箸や弁当箱の蓋に手を掛けた。
薄紫の蓋を両手で開けて取り、グレイスは箸を握る。弁当箱の半分には、朝作って詰め込んだおかずたちが並んでいた。一部冷凍食品を詰め込んだものの、どれもなかなかの出来だ。一人で料理するようになってしばらく経つが、ようやく見目を意識して作ることができるようになってきた。それでもまだ姉や仲間の碧には敵わないのだけど。
んめー、と向かいから声。頬いっぱいに弁当を頬張る雷刀の姿が見えた。深紅の箸には黄色い卵焼きがあった。少し大ぶりなそれが、めいっぱいに開いた赤い口に吸い込まれる。頬をもぐもぐと動かしながら、またんめぇ、と感嘆の声をあげた。飲み込んでから喋りなさい、と諫める声が朱い頭にぶつけられた。
「なんかさー、たまにしょっぱい卵焼き食べたくなるよな」
なんでだろな、と彼は白米に箸を伸ばす。わしりと掴み、口に放り込んでいく。すっとした輪郭をした頬が丸く膨らむ。
え、と躑躅は思わず声を漏らす。白身フライを口に運ぶ手が止まった。
「卵焼きって甘いんじゃないの?」
「しょっぱいのもあるだろ?」
きょとりとした顔をする躑躅の少女に、朱い少年もきょとりとした顔を返す。アァ、と隣から納得したような声。
「ワタシは甘いのしか作りマセンカラ、グレイスはしょっぱい卵焼き食べたことないンデス」
ネメシスに来たばかりの頃は、レイシスが昼ご飯に弁当を作ってくれていた。その中に入っている鮮やかに黄色くてかっちりと巻かれた卵焼きはいつだって甘かった。卵焼きとはこういう味なのか、甘い食べ物なのか、と今の今までずっと思っていたが、それは彼女の嗜好の結果だったらしい。
「オレらも基本甘いのだけど、しょっぱいのも作るぜ?」
な、と雷刀は隣に顔を向ける。そうですね、と烈風刀は箸を置いて応えた。へぇ、とグレイスは漏らす。甘いのとしょっぱいのがあるなら、辛いのや苦いのもあるのだろうか。今度聞いてみようか、と掴んだままだったフライを口に入れる。魚の香りと塩気が舌の上に広がった。
「食べてみますか?」
筋の浮かぶ手が深い青の二段式弁当箱を掴む。少年はおかずが入った段を少女の目の前に差し出した。ブロッコリーの緑、プチトマトの赤、カップグラタンの白、ウィンナーの茶色。様々な色の中に少し焦げ目の付いた黄色があった。
いいの、と尋ねると、えぇ、と穏やかな声が返ってくる。いただきます、と一言断って、グレイスはよく焼かれた卵焼きへと箸を伸ばした。一口で食べるには少し大きなそれを半分かじる。口内に広がったのは普段のほの甘い優しい味ではない。しょっぱさの中に不思議な風味が広がるものだった。
「ほんとだ。しょっぱい」
こくりと飲み込み、少女はこぼす。美味いか、と正面から問いが飛んでくる。美味しいわ、と素直に答えると、目の前の顔がパァと明るくなった。どうやら今日の弁当を作ったのは兄の方のようだ。
「……ねぇ、これって砂糖の代わりに塩入れればいいの?」
「そだな。今日は白だしも入れたけど」
初めて聞く名だ。しろだし、と思わず復唱する。スーパーに売ってますよ、と優しい声がかけられた。ふぅん、とどこか心ここにあらずといった調子で声を漏らしてしまう。
「美味しいわ。ありがとう」
礼を言って、グレイスは残りの卵焼きを食べる。またふわりと風味が香る。これが『しろだし』とやらによるものなのだろうか。塩のしょっぱさだけでも十二分に美味しいだろうが、こうやって風味があると更に美味しく感じる。料理って不思議、と心の中でこぼした。
躑躅の目が弁当箱からあがる。しばしの逡巡、ねぇ、と健康的に色付いた唇が控えめな声を発した。
「しょっぱい卵焼きって、塩としろだしってやつどれぐらい入れればいいの?」
「……えーっと…………、塩はこんくらい? で、白だしはなんかちょっとどばってならないぐらい」
少女の問いに、制作者である朱は悩んだ末身振り手振りで示す。正確な分量を知りたいのだが、どうやら感覚で作っているようだ。いつも直感で行動する彼らしい。
「こればかりは感覚と経験ですね」
苦笑を漏らしながら烈風刀が言う。レシピを厳守し、きちんと量って料理をする彼らしくもない言葉だった。経験ねぇ、とどうにもならない解答をぼやくように繰り返した。
「……うん。分かったわ。ありがと」
今一度礼を紡ぎ、グレイスは白米に箸を伸ばす。舌の上にほのかに残った塩気に、米の甘みが加わった。なるほど、しょっぱい卵焼きはご飯に合うのか。甘い卵焼きも合わないわけではないが、白米に合わせるならこちらの方が良いように思えた。
今日は帰りにスーパーに寄ろう。そして卵と『しろだし』とやらを買おう。帰ったら試作だ。ぶっつけ本番ではまずいものができあがってしまうかもしれない。そんなもの、自分で食べるのはもちろん人に食べさせるわけにもいかない。
考え、少女は食事を続ける。鼻の奥にはまだあの風味が残っている気がした。
畳む
twitterすけべまとめ2【ライレフ/R-18】
twitterすけべまとめ2【ライレフ/R-18】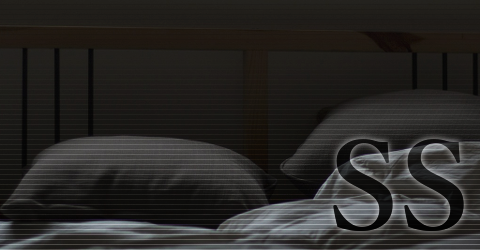
twitterで書き散らしてた大体2000字ぐらいのすけべまとめその2。twitter掲載時から修正とか改題とかしてるのは気にするな。
足りない熱
低いモーター音が薄暗い部屋に響く。微細な音であるが、深夜の静まりかえった部屋では酷く大きく聞こえた。機械的なそれの中に、荒い呼吸が混ざる。あまりにも浅く乱れたそれは酷く辛そうに聞こえるが、確かな熱と甘さを帯びていた。
激しい振動が、肚の中を直接刺激する。電動する機械が力強くうねり、繊細な粘膜を擦り上げる。球体が連なったような胴体が蠢き、うちがわを擦り、抉り、引っ掻き回す。その度に、莫大な快楽が脳味噌に叩き込まれた。
「ッ、あ、ァ……ぅ、ん……」
細い声が塞いだ口から漏れ出る。艶めいたそれは、性的興奮を、快感を覚えていることがありありと分かるものだ。
バスタオルを何枚も敷いたベッドに横たわった烈風刀の身体は、下半身だけ生まれたままの姿だった。薄闇の中肌を晒す下肢は、股ぐらを中心に濡れている。特に酷いのは臀部だ。薄く肉が乗ったそれは、ぬめったものにまみれていた。双丘の間、秘めたる場所は粘液が滴るほどぐっしょりとしていた。
濡れそぼつそこには、明らかな異物が鎮座していた。バイブレーターだ。雄の器官を形取った機械が、常は閉ざされるべき蕾を大きく割り開き、内部へと侵入していた。黒い器具は、ヴィンヴィンと音をたて円を描く。その度に、熱っぽい吐息や高い嬌声が部屋に響いた。
この偽物とは――兄に片恋していた頃、『抱かれたい』という欲望を満たしてくれたこの機械とは縁を切ったはずだった。だって、自分にはもう恋人がいる。嬬武器雷刀という、ずっと想いを寄せてようやく結ばれた恋人がいる。こんな紛い物に頼ることなどあってはならなかった。
だが、実際はどうだ。片想い時代より欲望を溜め込み、多忙が故に愛する人と身体を繋げることもできない日々。どうにか一人慰めようにも雄の部位だけではもう満足できない。受け入れる部分を指で刺激しても、物足りなさを覚えてしまう。クローゼットの奥底にしまいこんだこれに再び手を伸ばしてしまったのは、必然でありながらも愚かとしか言い様がなかった。
電動モーターが、あらかじめプログラムされた通りに動く。内壁を擦り、性的快楽を欲求を発散しきれない身にもたらす。雄を欲し泣き喚く肚を慰める。効果は絶大だった。指なんかでは届かない部分を直接刺激する。指では加減してしまうような場所を容赦なく抉る。指では再現できない動きで内部を蹂躙する。凄まじい肛悦を与えられ、少年はただただ法悦を謳い上げた。
口を押さえていた手が片方離される。そろそろと動き、音をたてて内部を荒らし回る器具に触れた。快感に震える手が、限界まで潜り込みはみ出た柄を捕らえる。そのまま、そいつを引き抜いた。ずるるる、と抜き、ぶちゅんと濡れた音をたてて押し込む。抜いて挿入れてを繰り返す。律動の真似事だ。兄との性行為を再現しようとしているのだ。
「あっ、ァッ……ん、ぅう……ンッ」
ぐちゅぐちゅとローションが泡立ち音をたてる。肚の内が掻き回される。性交を思わせる音色と刺激だった。快楽に支配され処理能力が落ち込んだ脳味噌は、一人寂しい遊戯を愛しい人とのまぐわいと錯覚した。
目の前に放り出した携帯端末を手に取る。震える手でスリープを解除すると、液晶画面いっぱいに兄の笑顔が映し出された。いつぞや畑仕事の合間に取ったその写真は、性など欠片も感じさせない。けれども、今の烈風刀にとってはこれ以上無く興奮をもたらすものだった。何と言ったって、身体がずっと求めているつがいの姿なのだから。
「ぁ、らいと……らいとぉ……」
口を塞ぐことなどもう忘れていた。とろけきった瞳で画面いっぱいに映し出された朱を見つめ、甘ったるい声で愛し人の名を紡ぐ。吐息と嬌声混じりのそれは、卑猥としか言い様がないものだ。一心不乱にバイブレーターを動かす様も、またいやらしさに拍車を掛けていた。
半ばまで抜いた偽物を、一気に挿入する。シリコン製の硬いモノが、イイ部分をごりごりと刺激する。視界に数え切れないほどの白が散った。アッ、と一際高い音が夜闇に響いた。
じゅくじゅくと潤滑油と腸液をかき混ぜ、自らの手で肚を蹂躙していく。脳髄に快楽を叩き込み、理性を壊れさせていく。常は隅に押しやっている本能を剥き出しにさせていく。きもちいいことしか考えられなくしていく。
ァ、と艶やかな声が、ヴィン、と低い機械音が、じゅくり、と淫らな水音が、深夜の私室を満たしていく。よく整頓された清潔な部屋は、淫猥極まりない性の匂いで満ちていた。
目の前で白い光が弾けて消える。機能が破壊されるのではないかというほど頭の奥が痺れる。紛い物の雄を迎え入れた腹が疼く。絶頂が近いのだ。高みを求め、碧は注挿する手を早めていく。前立腺を潰すように浅く抜き差しし、限界まで届くように強く突き入れる。ただでさえ容赦ない手つきだというのに、自動で蠢き震える機械が更にそれを酷くした。
ごりゅ、と先端がいっとう好む部分を抉る。パチン、と目の前で何かが弾けた気がした。
「ッ――――アっ!」
びくん、と横たわった身体が跳ね、弓なりにしなる。盛大な嬌声が部屋に響き渡る。勃ち上がりとめどなく雫を漏らしていた屹立から白が吐き出される。雄を模した機械を咥え込んだ場所がきゅうぅと強く締まった。
全力疾走したかのような荒い息がシーツの上に落ちていく。頂点に至ったというのに、ひ、ぁ、ととろけきった声がどんどんとこぼれる。電源を切っていない機械が内部で蠢いているからだ。力の入りづらい手で、運動を続けるそいつをどうにか引き抜く。ずる、と肉の孔からぬらぬらと輝く黒いシリコン器具が抜け落ちた。
喘鳴に似た呼吸が部屋に落ちては積もっていく。快楽漬けになった脳味噌が落ち着いていく。薄れ行く本能が喚き立てる。これじゃあ足りない、と。
「らいと」
愛しい人の名を呼ぶ。物足りなさと切なさと寂しさとが混じった、暗い色をしていた。
こんなもの、あの人との触れ合いには及ばない。少し硬い手でなぞられ、潤いが少し足りない唇で触れられ、熱の塊のような逞しい雄で肚を穿たれる。偽物を用いた慰めなど、幸福に満ちた性行為には似ても似つかなかった。
愛しい人に触れられたい。愛する雄に食われたい。己だけの捕食者に蹂躙されたい。まぐわいを重ねた身体は、満たされることなく大好きな人を求めた。
はぁ、と重い息を吐く。モーターが仕事をする音が、渇求の悲鳴あげる脳味噌の片隅に響いた。
悦び求めて
節の目立ち始めた指が、柔らかな洞に潜っていく。今まで触れてきた何よりも熱く柔らかく思えた。
第一関節まで埋め、指の腹で内壁を撫でながらゆっくりと戻る。頃合いを見計らい、第二関節まで潜り込ませ、鉤状にした指先で熟れた肉を引っ掻く。根元まで這入り込み、好む部分をとんとんとあやすように押してやる。侵入者がうちがわを荒らす度、高い艶声が部屋に響いた。
腹を擦りつけながら、埋めていた指をゆっくりと引き抜く。解れ始めた孔に、潤滑油で濡れきった人差し指とまだ乾いた中指を添える。飢えを訴えるようにひくつくそこに、二本同時に侵入していく。わずかに増えた圧迫感にか、う、と苦しげな声が漏れるのが聞こえた。安心させるように、苦しさなど忘れさせるように、ぷっくり膨れた一部分を揃えた指でぐっと押した。瞬間、目の前の体躯がびくんと大きく跳ねる。アッ、と鋭い嬌声付きだ。雄を誘う響きが薄闇に広がった。
指を動かす度、ぐちゅ、ぐちゃ、と淫らな音があがる。たっぷりと注入したローションが捏ねられる音であり、柔らかな媚肉が蹂躙される音であり、官能を誘う音だ。腹に灯る焔に、薪をくべていく。情火は燃え盛るばかりだ。
指二本が勝手気ままに動くことほどになったのを見計らい、雷刀は侵入者たる二匹をゆっくりと引き抜く。あまり強い刺激を与えないようにしたが、解せども未だ狭い肉の道には侵入者は太すぎた。結果、熟れきった粘膜は擦られ、快楽を発生させる。あ、ぁ、と溺れきった細い声が雄の欲望を刺激した。
長い時間をかけ、ようやく指が肉洞から去っていく。注ぎ込まれ、塗り込められたローションが糸を引き、指先と後孔を繋ぐ。あまりにも淫靡な風景だ。思わず、ゴクリと唾を飲む。ぷつりと粘液の架け橋が切れて尚、ぬらぬらと光る指先を魅入られたように見つめた。
ぬとつく指先から視線を上げる。そこにあったのは、シングルベッドに寝転がった弟の身体だ。
清潔な白い枕の上には、汗ばみ少し束になった浅葱の髪が散っている。浅海色の瞳には涙が膜張り、本物の海のような様相になっていた。完璧な日焼け対策を行っている白い身体は、うっすらと紅潮している――明らかな性的興奮によって。筋肉で薄く盛り上がった胸の頂には、ツンと上を向き主張を存在する赤の姿があった――これもまた、性的興奮を覚えている証左である。薄く割れた腹筋は、粘ついた液体で濡れていた。カウパーだ。中心部で勃ち上がり大きく主張する弟自身から、絶えず透明な雫がこぼれていた。筋肉が発達し肉の薄い足は、だらしなくシーツの上に放り出されている。絶え間なく与えられ続けた快楽で――この先たっぷり与えられるであろう肉の悦びを期待して、動くことができないのだ。
総じて、卑猥以外に表現することができない様相だった。腹の奥底を、雄の本能をこれでもかと刺激する姿に、朱は今一度唾を飲み込む。最上級の馳走を前に、今から味わう快感への多大なる期待に、じゅわりと唾液が湧き出た。
「エッロ……」
思わず漏らした言葉は、無意識のものだった。それ以外に形容することができない、それほど言葉を漏らしてしまう姿であった。
「な、にが、えろいですか。へんたい」
ぜぇはぁと荒い呼吸の合間に、罵声が飛んでくる。快楽漬けにされたはずの怜悧な脳味噌は、まだ思考力と会話能力を失っていないらしい。涙を湛えた孔雀石が、こちらを睨みつける。それもすぐ発言者の顔から移ってしまう。濡れた翡翠が向けられたのは、呆けたように掲げられた手――今さっきまで己の中身をぐちゃぐちゃに荒らし回った指だった。明らかに更なる刺激を欲している目だ。内部への侵入者を欲する目だ。雄にめちゃくちゃにされることを期待する目だ。
あまりにも情熱的な視線に、隠し持つ淫乱な性質を露わにした様子に、雷刀は苦笑を漏らす。どれだけ熱心に見つめられようとも、こいつにもう用は無い。バトンタッチする時間だ。
「だって、エロいもんはエロいじゃん」
心の底からの言葉に、赤い頬が更に熟れていく。指に固定されていた視線が動き、己が身体を見下ろす炎瑪瑙を強く睨めつけた。法悦の涙を流しながらそんなことをされても、こちらの情欲を、征服欲を刺激するだけだ。そんなこと、今までの行為から分かりきっているだろうに。
放り出された足、膝裏に手を潜り込ませ、持ち上げる。腰が持ち上がり、解しに解されぷくりと膨らんだ秘蕾が眼下に晒された。縁が赤らんだそこは、雄を誘うようにはくはくとひっきりなしにひくついている。早く挿入れてくれ、と本能が強く訴えていることが丸わかりだ。
浅く開けては閉めてを繰り返す狭穴に、雄の象徴を擦り付ける。己のそれも、既に先走りでドロドロに濡れていた。ここまで我慢できたことを褒められたいほどの状態である。それほど、愛する人の肚の内を求めていた。
ちゅくり、と秘部と秘部が触れ合い、小さな音があがる。口付けにも似た音だ。それ以上に艶然で、妖艶で、欲望を刺激する音色をしていた。
ほんの小さな接触と音に、組み敷いた身体がびくんと跳ねる。ぁ、とあがった声は、快楽に溺れ、期待がたっぷりと詰め込まれたものだった。雄を欲し、雄に食われ、種を植え付けられることを夢想した、淫奔極まりない響きだった。
足を掴んだ手に力を込める。そのまま、膝をシーツの上に押さえつけた。眼前に、はくりはくりと口を開ける淫穴がはっきりと映る。ローションをたっぷり注がれ艶めく隘路の中までつぶさに見えるほどだ。
ず、ず、と勃ち上がりきった己自身を、ひっきりなしに蠢く窄まりに擦り付ける。特に敏感になった部分を熱で弄ばれてか、唾液で潤った唇から物欲しげな嬌声がぽろぽろとこぼれるのが見えた。押さえつけたはずの腰が揺らめき、自ら怒張に肚への入り口を擦り付ける。あまりにも浅ましく、あまりにも蠱惑的な動きだった。
焦らすそれをやめ――我慢が限界を超え、雷刀は切っ先をぴったりと蕾に宛がう。途端に、揺らめく腰の動きが止まった。今から待望の存在が己のうちがわに這入ってくるのを理解してのものだ。
えっろ、とまた無意識にこぼす。今度は罵声は飛んでこなかった。代わりに、熱烈な視線が向けられる。快楽と期待にとろけきった瞳が、つがいをじぃと見つめていた。
これほどまで期待されたのなら、応えなければならない――何より、己が弟を欲してやまないのだ。
これ以上の我慢などできるはずがない。これ以上理性が保つはずがない。むしろ、あの瞳を見た瞬間に、理性は消し飛んでいた。剥き出しになった本能が叫ぶ。早く食らえ、と。
喚き立てる本能に従い、宛がった欲望の塊を一気に粘膜の中に突き入れる。一際高い声が、待望の悦びを謳い上げる声が、捕食者の心を強く刺激した。
奥の奥まで
肉と肉がぶつかる音が室内に響き渡る。音があがる度、凄まじい快楽が怜悧なる頭を焼いていった。
腰が打ち付けられる強さは尋常ではない。常はこちらの身体を慮る恋人は、今日ばかりは理性を完全に失っていた。獣の本能を剥き出しにしたつがいは、暴かれざる孔にひたすら猛った楔を突き立てる。こじ開けもう二度と使い物にならなくさせるような勢いだった。
ばちゅん、と湿りを帯びた打撃音があがる。痛覚信号が刺激を伝達し、これは痛みであると訴えた。しかし、快感に浸されて馬鹿になった脳味噌は甘美なる感覚であると誤認した。打ち付けられる度、穿たれる度、痛覚が反応する。きもちがいいことをされている、と。
ふー、ふー、と烈風刀は獣じみた呼吸を漏らす。最初はシーツに突いていた手は既に崩れ、だらしなく放り出している状態だった。掴まれた腰だけ高く上げ、顔を白い布に埋め、ひたすらに甘やかな息を吐き出す。もう嬌声をあげる余裕など無かった。与えられ続ける法悦は凄まじく、思考能力を奪っていく。理性など全てぶち壊して、本能を剥き出しにしていく。孕みたい、なんて馬鹿げたことを真剣に求めてしまう。
ごりゅ、ごちゅ、と腹の奥底を穿たれる。高く上げられた尻、侵入を果たした肉洞、その行き止まりを突き破らんと硬い先端が幾度も突き立てられる。最奥を守りし襞を越えるのは容易なことではない。だから、雄は試行を重ねる。素早く重い動きで狭穴に剛直を突き入れ、奥の奥を力強くノックする。抉るように奥を突かれる度、多大な快感が脳味噌に注がれる。許容量なんて知らないとばかりに、きもちいいことだけをどぱどぱと注ぎ込む。本能だけになったつがいは、幸福に熱い吐息を漏らした。
ぼちゅん。一際強く、奥底を突かれる。瞬間、砦たる襞が掻き分けられ、更なる奥へと侵入を許した。
ァ、と思わず声が漏れる。腹の奥底に這入られた苦痛や恐怖によるものではない。悦びだ。吐息に分類されるような細いそれは、ひたすらに幸せ色に染まった響きをしていた。
暴かれざる場所への到達を確信したのだろう、雷刀は注挿を更に早く、重くする。当たり前だ、そこは一番きもちよくなれる場所なのだ。快楽を追い求める獣が食い散らかそうとするのは必然である。
役目を奪われた襞は、這入り込む先端を押し返そうと絡みつく。それが多大なる悦楽を生むのだろう、動きは細やかになる。襞に扱かれることを求めての動きだ。そして、秘められたる場所へと種を吐き出そうとする動きだ。
種を植え付けられる。孕まされる。
あり得ない予感に、涙膜張る碧い瞳がとろりととろけた。雄を抱きとめた腹がきゅんきゅんと疼く。強く締め付け、早くちょうだいとねだってしまう。
どちゅ、と一際大きく突かれ、抉られ、穿たれる。守りし襞を何枚も破った先、侵入など許してはならぬ場所に先端が這入り込む。快楽信号が全身を走り、頭に凄まじい量の孔悦をぶち込んだ。目の前が白む。脳味噌が白む。思考ができなくなる。身体が大きく痙攣をする。支配者の蹂躙により、絶頂を迎えたのだ。ぁ、あ、と痙攣の度に吐息と同義の声が漏れる。歓喜を表すように、媚肉は受け止めた屹立をぎゅうぎゅうと熱烈に抱き締めた。
どくん、と受け入れた怒張が脈を打つ。それを合図に、腹の奥の奥が焼かれるような感覚に陥った。快楽の頂点に至ったつがいが、この腹に種を吐き出しているのだ。
びゅーびゅーと音をたてて、獣の濁流が腹を白く染め上げていく。身体を守る襞を破られ、異物に荒らし回され、腹を膨らませんばかりに体液を注ぎ込まれる。悲惨な状況だ。だというのに、被食者たる烈風刀は口元を綻ばせた。普段の整い澄んだ表情など影すらない、だらしないと評されても仕方の無いゆるみきった顔で熱を受け止めていた。
孕まされる快楽が脳味噌に押し寄せる。受容できない量を叩き込まれる。きもちいい。きもちいい。
聡明たる脳味噌は姿を消していた。あるのは、つがいを求め、種を求め、快楽を求める本能剥き出しの脳味噌だ。きもちいいことだけを求めて、きもちいいことだけを認識する都合の良い脳味噌だ。
雄茎が脈打ち、白濁液を吐き出す。決壊した川の様子に似たそれも、だんだんと勢いを失っていく。それでも、最後のひとしずくまで注ぎ込まんと、決して漏らすまいと朱は強く腰を押しつけていた。抱えて腰だけ高く上げさせたつがいに覆い被さり、限界まで押しつけ侵入し、生殖液を吐き出す。孕ませんとする動きだった。それがまた、きもちよくて仕方が無い。肉体の快楽だけでなく、精神まで快楽に満たされていく。幸福に染まりきった身体がびくびくと跳ねる。達しているのだ。それも全て、支配者たる雄によって押さえつけられた。
腹の中の脈動が失われていく。それでも、雄根はナカを満たしたままだ。注ぎ入れた子種を欠片でも漏らさせまいと栓をしているのだ。
背中に温かいものがのしかかってくる。雷刀だ。あれだけ激しい律動をした彼も相応に疲れているのだろう、あー、と肺の空気を全て吐き出すような息とともに、体重を預けられる。体格が同じ人間の体重を受け止めるのは苦しい。揺さぶられ突き立てられたこちらも疲弊しているのだから尚更だ。それでも、苦しさ以上の幸福が胸を埋める。きゅう、と隘路が更に狭くなった。
は、と漏らした息は、薄い疲労と明確なる幸福、貪欲なる熱で染まっていた。
本能声あげ
荒い息が重なり合う。瑞々しい肌が触れ合う。熟れきった粘膜が絡み合う。狭い部屋には濃厚な性の匂いが立ちこめていた。
ぁ、ぁ、と細い声が眼下からあがる。整った眉を悩ましげに寄せ、涙湛えた碧い目を細め、唾液の満ちた赤い口を開け、烈風刀は嬌声を漏らす。高い音が鼓膜を震わせる。欲望を煽る音が頭に満ちていく。愛する者の痴態に心も身体も昂っていくばかりだ。あまりの興奮にめまいがしそうだった。
足を押さえつける手に力がこもる。波打つシーツに鍛えられた足を縫い付け、雷刀は組み敷いたつがいの腰を高く上げさせる。ずるりと抜いた楔を、すっかり綻んだ狭穴に突き立てる。ばちゅん、と湿り気を帯びた打撃音が部屋に響き渡った。全体重をかけた腰使いに、碧は一際高い声をあげた。
杭を打ち込むような注挿をひたすらに繰り返し、奥の奥まで隘路を切り開く。突き当たりの場所を突く、否、叩き続ける。いっとう好む場所を何度も強く刺激され、片割れはただただ喘ぐ。意味の無い単音ばかりをこぼす姿は、普段の頭脳明晰な彼からは想像できないものだった。
「ぁ、アッ……らいと、イく、イッちゃ、ぁッ」
涙をこぼし、烈風刀はイく、と繰り返す。縋るように首に回された腕に力がこもる。必死のあまりか、切りそろえられた爪が背中に突き立てられた。昂った脳味噌は、そのわずかな痛みすらきもちがいいと認識した。
弟はどこか潔癖なところがある。同時に、変な部分で恥ずかしがり屋なところがあった。そんなものだから、日常生活で性に関する単語を口にすることはない。乳の俗称を聞いただけで顔を赤らめる始末である。俗称ですらこれなのだから、誘うために性交を示す単語をストレートにぶつけようものならば顔を真っ赤にして怒るのだ。やることは全部やっているくせに、と考えるが口には出さない。
そんな片割れが、絶頂を示す語を何度も口にする。性的快楽の頂点に至ることを自ら甘い声で報告してくる。あまりにも淫らな姿だ。雄を興奮させる姿だ。単純な己にはてきめんだった。
どちゅ、と体重をかけて奥底を突いてやる。昂ぶり上擦った声が断続的にあがった。背中に立てられた爪が、更に深く皮膚に埋まっていく。普段の彼ならば、傷を付けることがないよう力を緩めるだろう。だが、情欲に溺れ高みに至りつつある現状ではそんなことに気が回るはずがない。赤い線がいくつも背中に描かれていく現状に、は、と熱い息を漏らした。
いっぱいイきな?
首元に顔を埋める恋人、その耳元で囁いてやる。びくん、と組み敷いた身体が跳ねる。埋めた肉槍がぎゅうと抱き締められた。搾り取るような締め付けに、思わず喉が苦しげな音をこぼす。絡みつく襞を振りほどくように、何度も腰を引いては打ち付ける。解すように、荒らすように、何度も何度も肉鞘に剣を突き込んでいく。あがる声はどんどんと細く、高くなっていった。
「ァッ、イっ、イっちゃ……イく、…………あッ!」
背中に一際強く爪を立て、唯一自由なつま先をピンと伸ばし、押さえつけられた身体を弓なりにしならせ、烈風刀は叫声のような嬌声をあげる。きゅうぅ、と内部が強く締まった。気をやったのだ。ナカが侵入者をぎゅうぎゅうと締め付ける。襞が蠢き、根元から扱きあげる。種をねだるような動きだった。
逃がさんとばかりに抱き締めてくる洞から雄を引き抜き、肉の道を割り開いていく。肉傘が絡みつく襞をゴリゴリと擦る。引き締まった身体がビクビクと跳ねた。
「……ぁ!? ァッ、やだっ! やっ、あ……! イッた! イッたからぁ!」
「ごめん!」
どうにか謝罪の言葉を絞り出し、雷刀は腰を打ち付ける。達して敏感になっていることは分かる。もっと労ってやるべきなのは分かる。けれども、淫猥極まりない乱れた姿を見せられては我慢できるはずがなかった。もっと欲しい。もっときもちよくなりたい。欲求ばかりが脳味噌を占めていく。本能に抗うことなど不可能だ。
絶頂を求め、一心不乱に腰を動かす。更に敏感になった粘膜は痙攣し、ひたすらに肉茎に絡みつく。縋るように締め付ける。凄まじい快楽が獣の欲望に染まった頭に注ぎ込まれた。
雄を刺突される度、甘い涙声があがる。過度な快感をぶち込まれ続ける彼は、意味のある言葉など発せられなくなってしまっていた。聡明な彼が、あー、あー、と譫言のような声しか漏らさなくなっている。普段と全く違う、己にしか見せない姿にまた獣の本能が煽られる。繰り出す一撃は重くなっていくばかりだ。
ァ、と小さな声。瞬間、ビクンとまた身体が跳ねた。内部が一際強く締まる。潤んだ肉が肉に絡みつく。再び気をやったのだと頭の片隅で理解した。
とどめの一撃だった。ぁ、と掠れた声が漏れる。ほぼ同時に、腹の奥で燃え盛っていた炎が天を衝いた。脳味噌全部が痺れて世界が認識できなくなる。碧が影差す視界が白んだ。
熱い肉に、熱い液が注ぎ込まれる。どくどくと脈打つ己自身が、つがいの腹に子種を注いでいく。生殖本能が、独占欲が、支配欲が満たされていく。きもちいい。その五文字だけで脳味噌が埋め尽くされた。
濁液が粘膜を焼いていく感覚にか、烈風刀はあ、ぁ、と声をあげる。細いそれは幸福に染まりきったものだった。
何事にも終わりは来る。腹を膨らまさんばかりの射精も、どんどんと勢いを失っていく。永遠に続くような心地がしていた快楽もゆっくりと凪いでいった。
はー、はー、と息が重なる。全力疾走をした後のような荒く酷いものだった。当たり前だ、身体全てを使って、全ての力を振り絞って激しくまぐわったのだから。
背中に走る痛みが消える。首にしがみついていた腕が解けていく。首筋に埋められていた碧い頭が、とさりとシーツが敷かれたマットレスに預けられた。
常は手入れされた美しい顔は酷い有様になっていた。翡翠の瞳は涙で潤み、どこかぼやけている。目尻は赤く染まり、涙が線を引いていた。紅潮した頬は同じく涙で濡れている。浅く開けられた口の端からは、だらしなく唾液がしたたっていた。
憐憫を誘うような姿に、心臓がドクリと跳ねる。これだけ荒らし回った罪悪感ではない。興奮にだ。哀れさすら感じさせる酷い顔は、雄の欲望を煽った。
「……たっしたといったじゃないですか」
「だってオレはイッてねーし」
それはそうですけど、と紡ぐ唇は唾液にまみれてつやめいている。浅い息をこぼす口からは、赤い舌が覗いていた。熟れきった果実のようなそれに、思わずかぶりつきたくなる。ようやく理性を取り戻した脳味噌は、衝動をどうにか抑え込んだ。
「きもちよかった?」
「……い、わなくて、わかるでしょう」
もごもごと口を動かし、弟は視線を逸らす。二度も気をやった事実から目を逸らしているようにも見えた。可愛らしい姿に思わず口元が緩む。なにわらってるんですか、とまだとろけた声が不満を訴えた。ごめん、と返すも、やはり笑みが漏れてしまう。だって、こんなに愛らしい恋人を前にしているのだから仕方が無いではないか。
潤んだ目でこちらを睨む碧の頬を撫ぜる。もう一度謝り、熟れきった柔らかな肌に口付けを落とした。
いたくてきもちくてたまらない
粘ついた水音が聴覚を犯す。果実が潰れるような音がなる度、神経を焼くような肛悦が頭に叩き込まれた。発生源が己である事実を突きつけられ、烈風刀はぶるりと震える。ぅあ、と漏れた声は、はしたない音を漏らし続ける羞恥よりも音とともに湧き上がる快楽が勝った音色をしていた。
堪えるようにシーツを握り締める。ベッドに突いていた手はとうに崩れ、前腕で身体を支えている状態だ。頭はうつ伏せで寝るように下がっているというのに、腰は高く持ち上げられている。尻を高くあげ雄に秘めたる場所を晒す姿は、交尾をねだる獣に似ていた。人間という理性的な枠組みから外れた、本能だけがあるまぐわいの形をしている現状を改めて認識し、背筋を鋭いものが走っていく。マゾヒスティックな悦びが、光速もかくやという速度で脊髄を駆け上がる。きもちいいことだけを脳味噌にぶち込まれる。快楽漬けにされた頭は、元来の理知的な動きなどできなくなってしまっていた。暴かれた本能がひたすらに叫ぶ。もっと欲しい、と。
ぱちゅん。ぬちゅん。尻を下腹部が叩く度、狭穴に剛直が突き立てられる度、思考する機能が削れていく。聡明なる脳味噌は快楽だけを認識する器官になりつつあった。
ずるぅ、と肉太刀が鞘から抜けていく。張り出た部分でうちがわ全体を擦られ、ぁっ、と細い嬌声が漏れる。切ない響きをしていた。当たり前だ、大好きな人の熱が去って行くのだから。きもちいいことが奪われるのだから。
全ては杞憂だった。ゆっくりと後退していった屹立は、先端を埋めた状態で止まった。赤く熟れきった縁に引っかけるような状態だ。お腹の中がさみしくて、きもちいいのが無くなったのがかなしくて、碧は無意識に腰を揺らめかせる。勝手に動いて勝手にきもちよくなろうとしているのだ。痴態を見せつけて雄を誘っているのだ。
は、と溜め息にも似た音が後ろから聞こえる。炎で焼かれたような酷い熱を孕んだものだった。掴まれた腰に切りそろえられた爪が食い込む。粘膜を傷つけまいと深く切っているのに、それでも刺さってしまうほどの力の入れ方だ。ほの甘い痛みに、肚がじくじくと疼く。淫らなる肚はつがいを待ちわびていた。
ふっ、と鋭く息を吐く音。同時に、ばちゅん、と湿った打撃音があがった。痛覚信号が送られる。それ以上に、快楽信号が脳味噌にめいっぱい叩き込まれた。
「――アッ!」
喉をそらせ、烈風刀は叫ぶ。この上なく甘ったるい響きをしていた。この上なく悦びを謳っていた。
腸粘膜を肉槍が一気に擦りあげていく。閉ざされた肉の道を無理矢理割り開いて、己の形に変えていく。すぐに戻り、また突き刺し、抜いて、捩じ込んで。激しい動きは身体を内部から破壊せんとようにすら見えた。壊しに壊して、自分だけのものにしようとするような動きだ。
毎回好き放題に荒らされ、好き放題に暴かれ、好き放題に躾けられ、被虐趣味に目覚めつつある身体が悦ばないわけがない。待望の熱を与えられて、待望の快感を叩きつけられて、碧はひたすらに喘ぐ。浅海色の瞳からは法悦の涙がぼろぼろと流れ、シーツを濡らしていた。
凄まじい肉悦は最高としか言い様がなかった。けれども、同時に恐怖が湧き上がってくる。きもちがよすぎて怖いのだ。このままずっときもちよかったら、きもちよすぎてしんでしまうかもしれない。快楽に浸りきって溶けた頭は、普段ならば欠片も考えないような馬鹿な恐怖を覚えた。
頭の下敷きになっていた腕を伸ばす。震えるそれが前に伸び、放り出された枕を望む。何かに縋っていなければ怖くてたまらなかった。常ならば抱き縋る朱い頭は、今は後ろにいる。きっと雄の象徴が解れきった蕾に突き立てられる姿をじぃと見ているのだろう。はしたない姿を見られている。また被虐的な快感が背をなぞった。
もう少し、というところで、腕が止まった。否、止められた。広げた手の上に、熱いものが乗る。そのまま、マットレスに沈み込むほど押しつけられた。縫い付けると表現してもいい。法悦で支配されろくに力が入らない腕は、簡単に動きを止められてしまった。
首筋に熱いものがかかる。吐息だ、と理解するより先に、鋭い痛みが走った。尖ったものが皮膚に、肉に突き立てられる。絞るように寄せられる。噛まれたのだ。めいっぱいに歯を突き立て肉を食いちぎらんばかりに噛みつかれたのだ。
引きつった音が喉から漏れる。全力の力が込められたそれは、快楽を吹き飛ばすような痛みだ。同時に、思考全てを吹っ飛ばすような快楽だ。マゾヒスティックな身体は、痛みはきもちいいことであると学習済みだった。鋭い痛みが、鋭い快感が、噛まれた肩から全身に広がっていく。びくん、と組み敷かれた身体が跳ねた。きゅうぅ、と悦びに震える肉が収縮し、隘路が更に狭くなる。お返しと言わんばかりに這入り込んだつがいをめいっぱいに抱き締めた。粘膜と粘膜、熱と熱が密着する感覚に、また震える。浮かぶ血管の形まで分かりそうなほどだ。あっ、ぁっ、と喘ぐ姿は喜悦に満ちていた。
手を縫い付けられ肩を噛まれたまま、肉茎が突き立てられる。腹の奥底を叩き、肉の悦びをめいっぱいに与えていく。腰を高く上げたつがいを噛みついて押さえつけ、一心不乱に腰を振る姿は猫の交尾に似ていた。もはや人間らしさなど欠片も残っていなかった。
性的快楽が利巧な頭を焼いて、馬鹿にしていく。きもちいいことしか考えられない、動物の姿に変えていく。人間たらしめる理性を捨て去って、獣としての本能だけにしていく。
普段はなめらかに言葉を紡ぐ口は、閉じる機能を忘れたかのように開け放たれていた。理性的に話す声は、上擦ってとろけたものとなってしまっていた。学園で見る『嬬武器烈風刀』の姿からは想像もできない、かけ離れたなんて言葉では済まないほどの様相だ。兄にしか見せない姿だ。愛する恋人に食われる時だけ見せる姿だ。互いに生殖本能だけになった時にだけ見せる姿だ。この上なく卑猥で、この上なく淫乱だ。
こちゅこちゅと浅い部分を突かれる。ごちゅごちゅと奥底を叩かれる。どちらも大好きで、どちらもきもちよくてたまらない場所だ。イイところをめいっぱいに刺激され、少年は法悦を叫ぶ。甘い響きで雄を悦ばせていく。
ごちゅん、と腹を破らんばかりに肉槌が行き止まりを叩く。それがトドメだった。
縫い付けられた手が映る視界が白くなっていく。薄闇の中、小さな光が瞬く。バチン、と何かが弾けたような音が聞こえた気がした。
「――――ッ!!」
覆い被さられ、噛みつかれ、押さえつけられた身体が一際大きく跳ねる。だらだらとしずくを漏らしていた中心部が白濁を吐き出す。雄を咥え込んだ後孔が締まる。暴かれ荒らされる肚が痙攣し、受け入れたつがいを力いっぱい抱き締めた。
食いちぎらんばかりの刺激に、抱きとめた雄がビクビクと震える。ぁ、と少し上擦った声。瞬間、肚の中が一気に熱を持った。
突き当たりに熱いものが叩きつけられる。精液だ。絶頂を迎えた雄は、つがいを孕ませようと種を奥底に注ぎ込んだ。凄まじい勢いで吐き出されるそれが、粘膜を焼いていく。内部を焼き尽くされる感覚に、引き締まった身体が痙攣する。痛いほど勃ち上がった烈風刀自身がぴゅくりと勢い無く濁液を漏らした。
内部で脈打つ雄が動きを止めた頃、やっと凄まじい快楽の波が引いていく。身体を、脳味噌を浸していたきもちよさがだんだんと落ち着いていく。残るのは激しい運動による疲れと、この上ない幸福だった。愛し合って繋がった喜びが胸を満たす。ぅあ、とこぼした声は幸せ色に染まりきっていた。
「……ご、めん。噛んじまった」
肩を食う牙が外される。酷く申し訳なさそうな声が後ろから聞こえた。そこにはもう獣らしさなどない。ちゃんと人間の形をしていた。
じくじくと疼く傷口に思いを馳せる。これだけ深く噛まれれば、酷い痕が残るだろう。下手をすれば血を流すほどの傷になっているかもしれない。当分の間、襟ぐりが広い服を着るのは控えるべきだろう。
怒るべきだ。叱るべきだ。分かっているのに、まだきもちいいことで満たされた頭は、被虐趣味に耽った頭は、そんな言葉を紡ぐ気など欠片も起こさせなかった。
鏡を使わねば見えない傷口を、雄に所有されている事実を明確に示す痕を夢想して、涙膜張るとろけきった瞳が幸せそうに細まった。
畳む
邂逅:御伽噺の紅【神+十字】
邂逅:御伽噺の紅【神+十字】
九月六日はcroiXの日!
ということで神様と十字さんの馴れ初め話。捏造しかないよ。俺設定の塊だよ。ご理解。
昔から本が好きだった。
紙とペンを介して知らない世界を、見たこともない世界を、見ることなんてできない世界を知ることができるなんて、この上なく面白い。この世にはまだまだ見たこと、聞いたことがないものが満ち満ちている。加えて幻想から生まれた物語までたくさんあるのだ。まだ何も知らない子どもが引き込まれるのは必然であった。
幼いながらも、きっと己が今いる小さな世界を出て行くことは難しいと察していたのも一因だろう。これ以上『外』を知ることはない。無意識が囁く度、少年はページをめくる。なめらかな指先が、抵抗するように紙を辿る。
様々な物語の世界の中でも、海を舞台にした冒険譚が特に好きだった。己が見ることのない世界を欠片だけでも理解できた気がして、どこか空虚な心が満たされるのだ。
そうして今日も、蒼い少年は書庫を訪れる。
カツンカツンと靴底に打たれる石床が音をたてる。昼下がりの施設内部は静かだった。今日は気持ちが良いほどの晴れ空だ。子どもたちのほとんどは外で遊んでいるのだろう。庭に近い本館に戻れば、その賑やかな声も聞こえてくるはずだ。
カツン。音が止む。青年はある扉の前で足を止めた。ところどころ塗装の剥げた古めかしいそれの上部、旗のように飛び出て掲げられた札には『書庫』と記されていた。
大して厚くもない扉をそっと開くと、埃の匂いが出迎える。ここに訪れるのは己ばかりだ。最近はその己すらも来る頻度が減っている。手入れするものがいない部屋に埃が住み着くのは必然だ。
ちらはらと舞う粒子を軽く手で払いながら、青年は奥へと歩みを進める。さほど広くない部屋の中ほど、子どもの背丈ほどしかない小さな書棚の前で止まる。薄く積もる灰色で汚れることも厭わず膝をつき、彼は手にした本を元の順番通りの位置に戻していった。ぎゅうぎゅう詰めに近い本棚は、持ってきたもの全てを戻し終えてもいくらか大きな隙間が残っている。誰かが本を借りていった証拠だ。子ども達が書物に触れているという事実に、心がふわりと満たされる。物語を愛する者が少しでも増えるのは嬉しいことだ。
膝を軽く叩きながら立ち上がり、今度は壁際に取り付けられた背の高い本棚に向かう。天井まであるそれは、大人でないと掃除の手が届かない代物なだけあって埃が積もりっぱなしだ。軽く払ってやりつつ、残った本を戻していく。胸に抱えられていた本は、どんどんと元の居場所へと帰っていった。
さて、と青年は室内を見渡す。今日は何を借りていこうか。とはいっても、子どもの頃から通い詰めていたこともあり、ここにある本はジャンル問わず大方読んでしまった。最近は昔読んだものの内容を忘れてしまったものを読み返すことが多くなっている。
とりあえず、と目の前の棚の中身をざっと見る。冒険譚、英雄譚、恋愛譚、詩集、郷土資料、図鑑、辞書。大人の背丈に合わせた書棚だけあって、子どもにはいささか難解なラインナップだ。どれも大人になる少し前には読んでしまったのだけれど。
喉が悩ましげな唸りを漏らす。幾許かの空白の後、骨張った指は郷土史を扱った書物へと伸ばされた。空想世界の物語を読みたいという欲求は、前回の貸し出しである程度満たされている。しばらく触れていないジャンルに手を出したい気分だった。それに、改めてこの土地を知るのは良いことだ。子どもたちに語り聞かせるためにも知識をつけておくに越したことは無い。
本と本の間から抜き取ったそれを適当に開く。埃とインクと古い紙の独特な匂いが混ざって香り立つ。嫌いなものではないが、少し鼻がくすぐったい。くしゅん、と小さなくしゃみが一つこぼれ落ちる。開いた蒼い目が、すっかりと変色してしまったページに向けられた。
Gott。
章題なのか、ページの上部を書き殴ったような筆跡でその四文字が占めている。大きな文字の下に書かれた文章を読み解くに、どうやらこの土地の紙に関する章のようだ。瞬き、細かな文を更に追っていく。
曰く、遠い昔にこの地を襲った災厄を払った神。村を救った神。語り継いで崇めるべき神。
そういえば、昔そんな話を大人から聞かされた覚えがある。随分と昔のことで、今ようやく思い出した程度のものだ。土地にまつわる御伽噺に食いつかないはずがない自分が忘れてしまっていたほどだ、よっぽど簡単に話されたのだろう。おそらく食い下がっただろうが、それでも何も覚えが無いあたり本当にただの短い言い伝えのようだ。
――紅い髪と目。真紅の外套と剣。その鮮烈な色は、血を思い起こさせた。
神が起こした奇跡とやらが書き連なる中、そんな一文が記されていた。歴史を記す書にあるまじき、あまりにも詩的な表現に思わず眉根を寄せる。そも、『血』など救ってもらった神に対して使うような形容ではなかろうに。昔の本にケチをつけても仕方が無いのだけれど。
他のページもぱらりとめくってみる。昔、大人から聞かされた話がいくらか見受けられた。わざわざ本に記そうとされたものだけあってか、昔口伝えで聞いたそれよりもずっと詳しい。中には初めて聞く逸話もあった。
ほんの少し読んだだけでも好奇心を刺激される、面白いと思えるものだった。今日はこれを借りていこう。きっとこの厚みでは数日足らずで読み終わってしまうが、他にめぼしいものもない。今回はこの一冊だけだ。
古い装丁がほつれてしまわないようにそっと脇に抱き、蒼は書庫を出る。家に帰る前に、書を借りた旨を台帳に記さねばならない。元々は書庫に備え付けてあったそれは、利用者の減少に伴い職員のいる部屋に移されていた。
そう広くない施設である、目的の場所に着くのはすぐだった。ノック三回、扉を開ける。中には、カップを手にした女性職員が椅子に座っていた。
「あら? 今日お休みでしょう?」
「はい。でも、借りていた本全て読んでしまったので返してしまおうかと」
突然の出現にかぱちりと瞬く彼女を尻目に、青年は台帳に書名を記す。掠れた表紙と背表紙からかろうじて読み取れるのは、村の名前と『記録』の文字ぐらいだ。少し悩んだ末、『郷土資料』とペンで書く。曖昧なものだが、正しい名前が分からないのだから仕方が無い。
「明日にすればよかったのに」
「散歩のついでですよ。それに、返せるものは先に返した方がいいですから」
真面目ねぇ、と笑顔でこぼす彼女に苦い笑いを返す。真面目も何も無い。ただ、済ませられるものを済ませていないと自分が落ち着かないだけなのだ。それを『真面目』と評価されるような性格と行動をしているのは、己でも理解している。
「で? 今日は何を借りるの?」
「今日はこれ一冊にしようと思いまして」
胸の前に本を掲げて答える。古い表紙に目を移した女性は、細目で厚いそれを見る。ようやく文字が読み取れたのか、あら、と小さな声を漏らした。
「郷土史の本? 随分と渋いわね」
「中身を見たら面白そうだったので。それに、己の住む土地を知るのは重要です」
「相変わらずえらいわねぇ」
そう言って彼女はニコニコと朗らかな笑みを浮かべる。温かな表情には、微笑ましさがにじみ出ていた。完全に子ども扱いをしている時の顔と声だ。幼い頃から世話してきた彼女らにとって、己はいつまで経っても『子ども』なのだろう。けれども、もう一人で暮らし彼女らと共に働く程度には自立しているのだ。この歳にもなって子ども扱いなど少々居心地が悪い。思わず、慈愛に満ちた目からふぃと視線を逸らした。
「……興味深い本です。じっくりと読みたいと思います」
「そうね、ゆっくり読んで。お休み、楽しんでね」
ではまた明日、と一礼し、青年は出入り口へと向かう。またねぇ、と柔らかな声に再び軽く礼をし、廊下へと出た。
カツンカツン。石床が音をたてる。遠くから子どもの声が聞こえる。元気に遊ぶ姿を眺めたい気持ちはあるが、今日は裏口から出て行くのが得策だろう。本を借り手にした今、元気いっぱいの彼らに遊びをねだられても付き合うことができない。悲しい顔をさせるわけにも、本を野外に置くわけにもいかなかった。
施設の裏側、林に向いた面に取り付けられた扉をくぐる。瞬間、飛び込んできた昼空の眩しさに思わず目を細める。雲一つ無い、太陽だけが存在する青い空。洗濯物がよく乾きそうな良い天気だった。
早く帰ろう。お茶でも淹れて、ゆっくりと読もう。それが最高の贅沢だ。
脇に抱えた知識の塊に思いを馳せながら、青年は自宅へと歩みを進めた。
パタン、と音をたてて厚い本が閉じられる。背もたれに体重を預け、青年は天を仰ぐ。ずっと文字を追っていた目を閉じ、外部刺激から逃げた。かすかに走る痛みを誤魔化そうと、目頭を軽く揉む。心地良さに、あー、と情けない声が漏れた。
目を開き、姿勢を正して時計に視線を移す。短針と長針の兄弟は、日付がもう少しで変わる頃合いだと告げてきた。思っていたよりも長く読んでいた、否、引き込まれてしまったらしい。はぁ、と重い溜め息を吐き出す。長い間同じ姿勢で目を酷使した疲労感よりも、知らない世界をめいっぱい楽しんだ充足感が強くにじんでいた。
今日借りた郷土資料は、端的に言うならば『当たり』だった。古い蔵書だけあってか、昔口頭で軽く聞かされた程度の話など比ではなく詳しく記されている。どれも言葉短ながら的確で、けれども読者を釘付けにするような文章だ。解説を主としているのにこれだけ読み手を文字の世界に引き込んでいくのだから、書き手は相当な手練れなのだろう。どこにも著者が書かれていないのが惜しいところだ。
相当数あるページと項目の中、特に力を入れて書かれていたのは『神』についてだ。昼に見た部分はほんの触りだったらしく、ページを追えば追うほど彼について深く掘り下げられていく。記された文は他の章とはまるで別人が書いたような熱量と表現力で、この項目だけ他と力の入れようが違うということがありありと分かる。それほど、著者はこの『神』に心酔していたようだ。
記された『神』については、幼い頃いくらか聞かされていた。村を襲った災厄を払ってくださった神様。村を助けてくれた神様。この書を読むまで忘れていたようなものだが、こんな熱の入ったものをぶつけられては俄然興味が湧いてくる。他の資料を読み漁りたいと思わせるほどだ。
気になったのは、『教会に祀られた』という一文だった。そういえば、そんな話を聞かされた覚えがある。けれども、村の外れにある教会は既に管理する者はおらず廃れた状態だったはずだ。あそこは古くて危ないから入ってはいけません、と子どもの頃に何度も言い聞かされたのを覚えている。大人の忠告は素直に受け入れる性質だったのもあり、今の今まで近づくという発想すら出てこなかった場所だ。大人になった今でも、森の奥にあるらしいそれを目にしたことは無い。そもそも、そこに至る道すら放置されているのだ。わざわざ草むらを掻き分けて廃教会を訪れようなんて考える人間はそういない。己も然りである。
神。救世主。伝説の存在。物語の主役。
そんな、己にとんと縁が無い非日常があそこにあるかもしれない。そう考えると好奇心をそわりと撫でられる心地がするのは、己がまだまだ子どもだろうか。否、こんなに熱のこもった文章を読んで興味を持たない人間の方がおかしい。当然だ。仕方の無いことだ。それらしい言葉を並べ立てる。こういうところがまだまだ子どもなのであることぐらい、自覚はあるのだけれど。
今日はもう遅い。明日に備えて寝るべきだ。閉じた本をそっとテーブルに置き、青年は身なりを整えランプの灯を落とす。暖色に包まれていた部屋は、一瞬で黒に包まれた。慣れた闇の中を進み、ベッドに入る。薄い布団を被ると、布地と綿の柔らかさとほのかな温かさが薄着の身を包んだ。
次の休みにあの教会に行ってみよう。大人になった今ならば、誰にも咎められないはずだ。
そんなことを考え、青年は目を閉じる。柔らかな寝具に包まれた身体は、眠りの海にゆっくりと浸っていった。
ザ、ザ、と草を掻き分ける音が薄ら暗い空間に響く。真昼間だというのに、木々が陽光を遮る雑木林は夕暮れのようなほの暗さだった。道なき道を進む不安もあってか、不気味さすら感じられる。幽霊の一人や二人出てきてもおかしくないのではないかなんてふざけたことを考えた。
長袖を着てきて正解だった。季節にそぐわない黒い生地は暑さと汗による不快感を覚えさせるが、こんな草むらを肌を出して進んでいくより何百倍もマシだ。そもそも、後者が愚かなだけである。草で肌を切ったり虫に刺される危険性はいくらかの我慢を重ねてでも排除すべきだ、と教えられていた。
ザ、ザ。同じ音が森の中に響いては消えていく。もう少しのはずだが、と辺りを見回す。のびのびと茂る木と我が物顔で地を埋め尽くす草に包まれた空間は、緑で染め上げられている。だが、その一色の中に濃い灰が点々と見えた。石畳だ。至るべき道を確信し、そちらへと足を伸ばす。隙間から草が生い茂り、埋まって土に同化しつつあるそれを辿っていく。カツン、と靴底が石を打つ音が葉擦れの中に落ちた。
カツン、カツン。石畳の上を靴音が歩いていく。跳ねていく。駆けていく。しばしして、目的の場所に辿り着いた。
そこは、聞いていたよりもずっと形を残していた。壁はもうほとんど塗装が剥げているが崩壊はしておらず、少しのひび割れを覗かせながらもきちんと役割を果たしている。ドアも木の地が見えきっているが、扉としての形を成して正面を向いていた。古ぼけた屋根のてっぺんに立つ十字架は輝きを失っているが、ここが『教会』という場所であることを雄弁に語っていた。
村外れの廃教会。幼い頃から行ってはいけないと言われ続けていた場所――あの本曰く、『神』が祀られている場所。
とくりとくりと胸が高鳴る。生まれもあって、『神』という存在を強く信じて生きてきたわけではない。信仰心なんてものもない。久しぶりの冒険と初めての場所に興奮しているのだ。この歳で、と呆れる己がいる。けれども、昔から冒険譚を読み漁っていた青年にとっては心震える風景だ。なんたって、物語に出てくるような『神が祀られた廃教会』が現実の存在として目の前にある。
石や段差で転ばないよう、しっかりと地を踏みしめて進んでいく。ザリ、と細かい土と石のかけらが踏まれる音が硬質な足音を彩った。
廃れた場所らしくもない、しっかりと存在と役割を主張する扉に手をかける。力を込めて押すと、ギィ、と蝶番が擦れる嫌な音が木々に包まれた世界に落ちた。歪むことなく簡単に開いてしまうなんて、これまた廃れた場所らしくもない。不躾な不満が心に湧いて出た。幻想に小さなヒビが入っていくような心地だ。
両開きの扉を完全に開く。古ぼけた厚い戸の向こうには、寂れた風景が広がっていた。左右に五列ずつ並ぶ長椅子は、埃を被って白んでいる。薄灰のなかに小さく散らばる茶は木のクズの色か、それとも壁の塗料か、破片か。どれにせよ、人が長らく訪れていないことは明らかだった。
埃くずたちが敷かれた空間、通路に当たる真ん中部分は強い色で彩られていた。ステンドグラスだ。これまた古ぼけているが、割れたり砕けた様子は無い。作られた時そのものと同じであろう姿で講堂を照らしていた。色とりどりの硝子は、木々の隙間から差し込む光を通して狭い聖域を彩る。本当に放置された場所なのか、と疑ってしまうほどの美しさだった。
その中に、紅があった。
色鮮やかな紅。よく晴れた夕焼け空のような紅。血のような紅。
目に焼き付くような紅で染められたヒトが、そこにはいた。
紅い影が、硝子の極彩色を背負った影が振り向く。布が重たげにひらめくのが見えた。
そこにあったのも、また紅だった。
磨かれたルビーのようにつややかな紅。熟れきったいちごのような深く鮮やかな紅。したたり落ちる鮮血のように澄んだ紅。
ひたすらに美しい紅と、視線がかちあった。
「――え? 人?」
声が重なる。紅い人影も、立ち尽くす己も、深い森での邂逅に驚愕していた。当たり前だ、こんな森の奥、それも村の子ならば『近寄るな』と言い聞かされてきた廃教会に自分以外の人間が来るとは思うまい。
「え? 何でニンゲンがここに?」
先に口を開いたのは紅だった。柘榴石の瞳も血の色をした口も丸く開いて、呆然としたように言葉を紡ぐ。自分が言った言葉ですら信じられないと言いたげな表情と声音をしていた。へ、とあがった音は疑問に満ち満ちていた。
「何で、って……」
好奇心、と正直に答えるのは抵抗があった。己も大概いい歳である。『本を読んで気になったから来た』だなんて幼稚な事実を口にすることなんてできない。それぐらいは弁えていた。
「貴方こそ、何故こんなところにいるのですか?」
場をやり過ごそうと、問いに問いで答える。普段子どもたちにはするな、と言い聞かせていることだ。破ってしまった罪悪感が胸を苛む。けれども、初対面の人間に幼稚な理由を馬鹿正直に話す勇気も、驚愕に溺れる中上手くはぐらかす方法も持ち合わせていなかった。こんな場所なのだから誤魔化しようが無いのだ。
そうだ、森の奥の廃教会に何故人がいるのだ。
紅い姿をじぃと見る。村では見たことがない顔と服装だ。焚き火のように真っ赤な髪の持ち主なんて村にはいないし、季節外れにも程があるロングコートとロングブーツをまとう人間も見たことがない。街の人だろうか。否、街の人間が少し外れにある村、その中でも外れにある廃教会に来るなんてことはまず無いだろう。では、旅人か。そうだとしても、こんな森の奥底を滞在場所に選ぶなど怪しい。あんなにも目を惹かれた色が、だんだんと怪しいものに思えてくる。
ただ、何か引っかかるような。
「何でって、だってオレ――」
当然だろうという調子で語り出した口がはたりと止まる。へ、とまた間の抜けた音。赤い口の中に尖った八重歯が覗いた。紅玉の瞳が、更に紅玉らしく丸くなる。え、え、と漏らす声はどんどんと上擦り大きくなっていった。
「ていうかオレのこと見えてる!?」
素っ頓狂な声で叫び、目の前の紅い男が駆け寄ってくる。バタバタと騒がしい足音が寂れた空間に響く。何だ、と一歩退くが、それも瞬時に詰められた。コートに包まれた腕が上がり、がっしりと力強く肩を掴まれる。鼻先がくっ付きそうなほど顔が近づく。紅が視界いっぱいに広がった。
「え!? マジで!? オレのこと見えてる!? 話せてる!?」
鮮烈な紅い瞳がまっすぐに蒼を射抜く。キラキラと輝くそれは可愛らしいさを思わせるものだ。同時に、吸い込まれて引き返せなくなるような魔力を感じさせた。とくりと心臓が音をたてる。何故だか分からないが、息を呑んだ。
「み、『見える』って何ですか。当たり前でしょう」
意味の分からぬことを矢継ぎ早にまくし立てる男に、青年は眉根を強く寄せる。目を細め、少しでも紅から逃げようとする。無意味だった。紅い紅い目が、己を見つめる。
人間を見ることを、人間と話すことをこれほどまでに騒ぎ立てるなど、怪しいにも程というものがある。もしや、気でも狂っているのだろうか。明らかな危険性にまた一歩退こうとするが、鷲掴むと表現するのが正しいほど力強く捕らえる手が許してくれなかった。紅い紅い目が、己を映す。
いや、だって、えぇと、と怪しさと危うさをまとった男は言葉をボロボロとこぼれさせる。何らかの説明はできるようだが、思考と言語化が追いついていないようだ。うぇ、とパニックに陥った子どものような声が聞こえた。紅い紅い目が、縋るように己を射抜く。
紅い髪。紅いコート。紅い瞳。廃教会。あからさまにおかしい、ヒトから外れた言動。
「――Gott?」
頭の中に浮かぶ点が、線で結ばれていく。形を持ったそれは、あり得ない事象を思い浮かばせた。馬鹿げたことを、と脳味噌は嘲笑う。けれど、単純な部分が声として吐き出し、空気を振動させ相手に伝達した。古い空間に、疑念と驚愕に満ちた声が落ちる。
姿形が似ているだけではないか。『神様』なんて馬鹿げている。だって、あれは昔話で。御伽噺で。ただの言い伝えで。『神』なんてものが目の前に存在するはずなどあり得ない。
けれども、目の前の紅はあの文献が記すそのままの色をしていて。
「――そう! そう!!」
己の馬鹿げた言葉に、目の前の男は顔をパァと輝かせる。そう、と肯定を意味する語を繰り返す声は上擦っており、興奮をよく表していた。声だけでは感情の発露が追いつかないのか、掴まれた肩を揺さぶられる。ぐらんぐらんと視界がぶれる。
「オレのこと信じてるやつ、まだいたんだな!」
感動すら感じさせる声をあげ、紅い男は掴んだ肩から手を離した。分厚い生地に包まれた腕が広げられ、目の前の黒い胸に飛び込む。そのまま、ぎゅっと抱き締められた。拘束する力は凄まじい。このままでは骨の一つや二つ折れてもおかしくないような力加減だ。ぅ、と苦しげな声が漏れる。押し退かそうとするが、どういう理屈がびくともしない。その間にも、込められる力は強まるばかりである。ミシ、と嫌な音が聞こえた気がした。
「ちょ、と、く、くるし、い……」
せめてもの抵抗で、脇をバンバンと叩く。込めることができた力は普段の半分にも満たないものだ。それほどまでに、拘束する腕力は恐ろしい強さだった。ごめん、と慌てた声。背に回された腕が離され、温度が離れていく。タン、と足音を立て、紅は飛び退いた。つい嬉しくてさ、と漏らす声はしょげたものだ。まだどこか浮かれた調子も見える。高揚感が隠せていない。
「ニンゲンに会うの、えっと…………かなり久しぶりだからさ。身体使うのも久しぶりだったし。ごめん」
もそもそと言葉を紡ぐ男の顔はどんどんと俯き、ついには地を見つめる。叱られた子どもの姿そのものだ。姿形はどう見ても大人のそれなのに、言動が完全に子どもである。そのちぐはぐさが、どこか不気味にも思えた。やはり怪しい。危険だ、と脳味噌が叫ぶ。けれど、足は動かなかった――ここから離れる気など欠片も湧いてこなかった。
「……本当に神なのですか?」
発してから、何と間抜けなことを、と己が罵倒する。そんな問い、肯定されても否定されても信用などできるはずがない。だって、『神』は御伽噺の世界の存在なのだ。この世にいるはずがない。そして、騙っていいものでもない。どう答えられようと、目の前の男を信用する要素など無い。
「おう!」
返ってきたのは、自信に満ち満ちた肯定の語だった。地を見つめていた顔がぱっと上がり、満面の笑みを咲かせる。腰に手を当て胸を張る姿は堂々としたものだ。神を騙るにしてはいささか児戯めいた行動だが。
でも、こんなにはっきりと肯定されて、当たり前のように言われては、何だか信じてしまいそうになる。姿形が本の通りだから。相手が肯定してるから。嘘なんて言っているように見えないから。たかがそんな要素だけで初対面の人間を、否、『神』を信じてしまいそうになるなんて、単純にも程がある。己はこんなにも馬鹿だったのか、と呆れを覚える始末だ。
けれど、目の前の紅は何よりも鮮明に語っていて。
「いやー、オレのこと信じてくれるニンゲンがまだいたなんてなー」
「……まだ信じてはいませんよ」
へにゃりと笑う紅に、蒼は警戒心をこれでもかとあらわにした声で返す。どんな感情で塗りたくろうと、移り変わる心からすれば言い訳でしかない言葉だった。
「ウソ」
そんな青年の様子を気にすることなく、男は短く告げる。ニィ、と真っ赤な口が意地悪げに弧を描いた。紅い紅い目が、己だけを一心に見つめる。
「だって、信じてるやつがいねーとオレ動物にすら見えねーもん。触れんのも無理」
そう言って、男は踏み出し再び距離を詰めてくる。今度は離れる余裕が無かった。呆然と垂れた手に、硬い手が重ねられる。手のひらと手のひらを合わせ、指と指を絡め、きゅっと握られ掲げられる。肌から伝わってくる感触は、温度は、確かに生き物のそれだった。
見える。話している。触れている。
男が言うことが正しいのならば、目の前の紅は『神』で、この現象は己が『神』なんて存在を信じている証左らしい。そんな馬鹿な、と心が呆れきった声をあげる。文献一つ読んだだけで『神』なんてものを信じるのか、己は。幼子よりも純粋で、単純で、思わず頭が痛くなる。
だが、あの本から言い知れぬ何かを感じ取ったのは本当だ。こうやって、休み一日潰して廃教会を訪れるほどには惹かれていた――御伽噺の『神』を求めていた。
「じゃ、今後ともよろしく」
「は?」
絡めた手をぱっと離し、紅い神は笑う。訝しげな声を漏らす青年に、何を言っているのだと言わんばかりに首を傾げた。紅い紅い目が、きゅるりと輝く。
「だって信じてくれてんだろ? 信仰してくれるんだろ?」
見つめる瞳は、こちらを信じ切ったものだった。初めて会った人間を心から信用し、確信し、当然のように語る。幼い子どもの行動だ。堂々としすぎて、当たり前のように振る舞われて、うっかり信用してしまいそうになる。
「い、や、信仰なんて……」
信仰などしていない。それどころか、未だに目の前の存在を『神』だと信じ切れてすらいないのだ。なのに、何故こうもはっきりと、常識のように言ってくるのか――存在しているのか。
目の前の紅が、己の心を明確に表していた。
えー、と男は不満げに唇を尖らせる。それもすぐに、まぁいいや、と切り替わった。表情がコロコロ変わるところまで子どもある。『神』はおろか、本当に大人なのかと疑ってしまう。
「信じてくれるやつがいるだけでじゅーぶんか」
ふっと目を細め、紅は、『神』は呟く。あれだけ狂喜し上擦っていた声は、平常らしい見た目相応に低いものになっていた。それが、どこか寂しさを誘う。輝き光る炎瑪瑙の中に、うっすらと影が差したように見えた。
「……存在できるようになってどうするのですか」
目の前の存在は『神』で、この世に確かに存在する。それはもう認めてしまおう。目の前の男が『神』を語る狂人であったとて、もう心は信じることに自然と傾いていた。
「正しくは顕現な。存在自体はずっとしてた。誰にも見えねーってだけで」
人差し指を立て、『神』は訂正する。彼にとっては重要な事柄らしい。それもそうか、『存在』を否定されてはいい気はしないだろう。
でも、見えないのに『存在』するんだなんて。それは本当に『存在』と言えるものなのだろうか。誰にも見えない。誰とも話せない。何にも触れられない。それは、『在る』と言っていいものなのだろうか。
「まぁ、どうもしねーよ。いつも通りここにいるだけ。変わんね」
ここがオレの居場所だからさ。『神』は語る。そういえば、彼はここに祀られているのだった。唯一の存在場所なのだろうか。いや、でも元は村を救ったという存在なのだ。村にいてもおかしくないのではないか。何故、人など来ないここにずっと『存在』するのだ。
「こんなに長く人がこね―ってことは、今村でオレのこと知ってるやつなんていないんだろ? ここから出てっても怪しまれるだけだって」
へらりと笑う男に、青年は唇を引き結ぶ。告げられた言葉は残酷ながら全くの真実だ。『村を救った神』の存在など、子どもが寝る前に軽く語り聞かされる程度のものである。純粋な幼子ならまだしも、現実を知ってしまった大人が信じているはずがない。それどころか忘れているだろう。あの書の存在を知るまで、そんな御伽噺を忘れていた己のように。
だからさ、と『神』は頬を掻く。眉尻を下げてはにかむ。紅い紅い目が、寂しげな色を見せる。
「たまに来て、村の話聞かせてくれね? 今どうなってるか全然分かんねーから気になるんだよな」
平和なままか、と『神』は問う。一応助けたもんは助けたもんだしさー、とまるで世間話をするかのように語る。内容はどう考えても狂人のそれだ。『神』と認めてしまった今は、信じる他ないが。
「……いいですよ」
「ほんと!?」
ずぃ、と目の前の身体が近づく。また鼻先が触れそうなほど距離が縮まった。相変わらずおかしな距離感に、青年は怖じ気づいたかのように一歩引く。『神』の距離感覚は人間とは違うらしい。
「あまり頻繁には来れませんけれど。話をするぐらいなら、いくらでも」
どうせ休みの日はまとめて家事をするか、本を読むかぐらいだ。訪れるのにいささか時間は掛かるものの、話をすることぐらい造作も無い。毎日子どもたちを相手にしているだけあって、何かを語るのは得意な方だ。
それに、もしかしたら昔のことを教えてもらえるかもしれない。文献にも書かれていないような、昔の話。神話の世界。未知の世界。想像するだけで知識欲が刺激される。利用するようで悪いが、それぐらいは許されるだろう。一応、己の『信仰』により『神』は顕現できているようなのだから。
「じゃ、約束な!」
紅い目が喜ばしげにきゅうと細まり、大きく弧を描き、笑顔を咲かせる。季節外れの向日葵のような、満開で、鮮やかで、存在感のある笑みだった。それもすぐに萎み、えっと、と彼は口ごもる。無骨な手が少し丸い頬を掻いた。
「……名前、なんてーの?」
「croiXです」
手短に名乗る。いつだったか与えられた己の名前は、長年名乗ってきたというのに未だにどこか違和感を覚える。そんな青年の様子など気にすること無く、男はくろわ、と復唱する。くろわ、くろわ、と紅は噛み締めるように何度も口にする。夕焼け色の頭が大きく縦に動いた。
「じゃ、よろしくな! クロワ!」
ずぃと大きく広げられた手が差し出される。あまりにも自然な姿に、思わず不用心に手を重ねてしまった。触れた瞬間、逃がさんとばかりにぐっと握られぶんぶんと振られる。随分と激しい握手だ。加減というものを知らないらしい。
「貴方は何と呼べばよいのでしょうか?」
「Gottでいいよ。名前ねーし」
「名前が無い……?」
当たり前のように告げられた言葉に、青年はゆるりと首を傾げる。名前が無い、だなんてどういうことだろう。何者にも名前は与えられるはずだ。『神』なんて崇め奉られる存在ならば尚更である。崇拝するものに名前が無くては困ってしまうではないか。
「明確な神格があるわけでもないしな。ただの神」
「そう、ですか」
「気にすんなって。神様なんてそんなもんだぜ?」
他にも名前ねーやつなんていっぱいいたし適当に呼んでたしな、と男は語る。歌うようなそれは、明るい響きに反して何とも寂しい現実である。かといって、自分一人ではどうすることもできない。目の前の『神』は『神』でしかないのだ。
「じゃ、またな。話、楽しみにしてるから」
男はひらひらと手を振る。紅い紅い目が己だけを見つめる。瞬間、鮮烈な紅は視界から消え去った。
え、と青年は声を漏らす。急いで辺りを見回しても、椅子の影を確認しても、扉の後ろを確認しても、あるのは古ぼけたそいつらとボロボロの壁ぐらいだ。手の甲で目を擦ってみる。けれど、晴れた視界は変わらない。あの紅がいない。
夢だったのだろうか。幻覚だったのだろうか。そうに決まっている。だって、『神』なんているわけがない。
けれども、この背には、この手には、あの温かな温度と確かなる感触がはっきりと残っていた。
呆然と正面を見やる。夕焼けに近い色をした陽光を受けるステンドグラスは、物言わず地面を鮮やかに染めていた。
畳む
屋台明かりと紅い花【福→紅】
屋台明かりと紅い花【福→紅】
ボルテ軒とか椿ちゃんちとかの地元の店屋さんってお祭りとかに出店出してるのかなーとか考えた結果。機会逃しまくって六年近く温めてたなど。
福紅増えろ……増えろ……。
ガヤガヤと騒がしい人の声が、屋台から漂う香ばしい匂いが、生ぬるい夏の夜風が肌を撫ぜる。湿度と気温に伴うほのかな息苦しさに、福龍は襟を緩めようと首元に手をやる。触れる前に腕を下ろし、長机の端に置いた小型扇風機へとほんの少しだけ身体を寄せた。店の名前を掲げた場所を任されているのだ、どれだけ暑くともだらしない格好をしてはならない。こんなことで店の評判が落ちては大問題だ。
実家の飲茶店は、今年も地元の祭に屋台を出店することに決めた。夏場、それも屋外で飲茶なんて、と初めの頃は考えていたが、意外と客足は良い。ごま団子や桃まんといった甘味を買っていく浴衣姿の女性客もいれば、ちまきやしゅうまいといった塩辛いものを買っていく赤ら顔の男性客もいる。そこそこの山を成していた料理の詰まったパックは、祭はまだ中頃だというのに三分の一ほどまで減っていた。
はぁ、と息を吐く。じっと立っているだけだというのにうんざりするほど暑い。夜とはいえ、今の時期は夏の盛りである。その上、焼け付く鉄板を扱う屋台たちからは多大なる熱が発生し場を満たしている。対策に持ってきた小型扇風機などほとんど役に立たないほど、会場は昼と変わらぬ空気をしていた。
椿がいないのは幸いだな、と少年は熱気でほんのりとぼやけた頭で考える。彼女がここにいれば、暑い暑いとひたすら文句を言っていただろう。暑さにやかましさまで加わっては堪ったものではない。
本当ならば毎年兄妹で店番をする手はずなのだが、妹は『友達と約束している』と言って遊びに行ってしまった。両親は出店を子ども二人に任せ、変わらず店を切り盛りしている。今は一人で店番をしている状態だ。家族全員人使いが荒いったらない。
屋台の裏側、足下に置いた鞄からペットボトルを取り出す。水分補給はしっかりしろ、と師範である父から毎年言われていた。事前に凍らせたそれは、もうほとんど溶けて緩く熱を孕みだしている。それでも、熱気に晒された常温のものを飲むよりずっとマシだ。キャップを開け、細いボトルを傾ける。ほんのりとした冷たさが喉を潤した。
「こんばんは」
夏の空気にそぐわぬ涼しげな声が耳を撫ぜる。客か、と福龍は急いでボトルから口を離し鞄に放り込んだ。はい、と接客用の声で応えて振り返る。金の目に映ったのは、つややかな黒い髪と夜闇でも鮮やかな紅の瞳だった。見覚えのある、否、見知った姿にドクリと心臓が大きく跳ねた。
「く、れは、さん……?」
食品を並べた机を挟んで向こう側、屋台の真ん前にいたのはクラスメイトであり想い人である紅刃だった。常は無彩色のセーラー服を纏う細い身は、大輪の赤い花が咲いて舞う白い浴衣に包まれている。腰まである長い髪は高い位置でまとめられ、大きな純白のコサージュが付けられたかんざしで彩られていた。
一体どうして、と漏らしそうになるのを必死で堪える。客に対して『どうして』なんて問いかけるのは失礼にも程がある。しかし、疑問を覚えるのは当然だ。椿が言う『友達』は高確率で紅刃を指す。妹と一緒にいると思い込んでいた級友が一人で目の前に現れたのだ。何故、と熱を持ち始めた脳味噌がもう一度声をあげた。
「椿と一緒じゃないんですか」
「そのはずだったんだけど、待ち合わせの場所に来ないのよね」
だからこっちに来てみたのだけれど、と少女はきょろきょろと辺りを見回す。妹の宣伝により、己ら兄妹の家が屋台を出しているのはクラス中に知れ渡っていた。現れぬ友人がいるかもしれない唯一の心当たりをたどってここに来たのだろう。
「あいつなら結構前に出てったんですけど」
「あら、そうなの」
店番よろしくネ、と片割れが元気に手を振って店を出て行ったのは、もう少し机上に商品が積み重なっていた頃だ。客足を考えると、ある程度時間が経っていることが予測される。なのに合流できていないというのはどういうことだろうか。
青い少年の言葉に、紅い少女は口元に手を添え大きな目を瞬かせた。提げた桃色の巾着に手を入れ、彼女は携帯端末を取り出す。液晶画面を見つめる瞳は、どこか曇って見えた。おそらく、椿に連絡を取ってみたものの返信が無いのだろう。あいつ、とここにいない兄妹に悪態を吐いた。
うぅん、と晒された細く白い喉から悩ましげな音が落ちる。決心するように丸く整った頭が小さく上下し頷く。紅い目がまっすぐにこちらを射抜いた。
「申し訳ないのだけれど、少しここで待たせてもらえないかしら? たぶん、待ち合わせ場所よりこっちに来る可能性の方が高いと思うの」
形の良い眉がわずかに下がり、八の字を描く。いつだってきりりとした美しい紅玉は、申し訳なさそうにほのかに細まっていた。人のことをよく考える優しい彼女のことだ、きっと無理を言っていると思っているのだろう。
少女の言うことは一理ある。待ち合わせ場所がどこかは知らないが、目の前の通路の様子を見るに会場内はどこも人が多いだろう。あのいつだって元気の有り余る妹は、その場をくまなく探すよりも会場内を駆けずり回って友人を探すに決まっている。ここにも来るはずだ。屋台の店先に立っていた方が目立って見つけやすいだろう。
それぐらい安いものである。けれども、少年の心は悲鳴をあげた。当たり前だ、突然『好きな女の子と二人きり』なんて状態に放り込まれるのだ。初心な心が耐えられるはずがない。
合理的な彼女の願いを取るか、無理だと叫ぶ己の心を取るか。
「……どうぞ」
天秤は前者に傾いた。沈黙の末に告げられた了承が渋々といったものに映ったのだろう、無理言ってごめんなさいね、と紅刃は依然眉尻を下げた表情で謝罪を紡いだ。全部椿のせいですから、とどうにかフォローを入れる。実際、全てはあの妹が悪いのだ。彼女が謝る必要など欠片も無い。罪悪感を覚えないでほしいが、あまり言葉を生み出すのが得意ではない己には上手く伝える術は無かった。
「ただ待たせてもらうのも悪いわね。ごま団子一ついただけるかしら?」
こぶりな巾着から財布を取り出し、紅は机上に並べられたパックを一つ指差す。五個入りのそれは、店で提供している物よりも少し小さい。会場内で食べ歩くことを考えてのサイズだ。
「いや、気を遣わなくてもいいですよ」
「待ってる間にお腹が空いちゃったの」
はい、と少女は硬貨を取り出しこちらに差し出す。ぐ、と喉が詰まったような音が思わず漏れた。言い訳までさせて気を遣わせているという事実に、心が苛まれる。本当にあいつ、と依然音沙汰が無い妹を恨みがましく思い浮かべた。
表示価格ぴったりの代金を受け取り、ありがとうございます、と平積みになったパックを一つ差し出す。ありがとう、と穏やかな微笑みと共に、紅い少女はフードパックを受け取った。ころりと中身の団子が薄っぺらい容器の中転がる。
カランコロンと赤い鼻緒の下駄が軽やかな音を奏でる。屋台と屋台の間、人が通ることのほとんどない薄暗がりに紅刃は移動する。手首に巾着を提げた手が、透明なパックを開ける。中に放り込まれたプラスチック製の楊枝を持ち、白ごまを纏った団子に刺した。紅で薄く彩られた健康的な色をした唇に、小さな甘味が吸い込まれていく。一口サイズのそれが可愛らしい口の中に消えていく。まろい輪郭を描く頬が上品に動いた。
「いつ食べても美味しいわね」
「……伝えておきます」
甘い飲茶に頬を緩める紅に、青は反射的に視線を逸らして返す。妹のせいで余計な気と金銭を使わせたという罪悪感はもちろん、想い人が己に向けて愛らしい笑みを浮かべている事実を受け止める度胸が無かった。化粧で更に美しく仕上げられたかんばせは、恋心を抱える少年にはあまりにも刺激が強い。既にキャパオーバーになりそうなほどである。
もぐもぐと紅い少女は団子を味わう。黙々と青い少年は屋台内を無意味に整理する。元々口数が多い方ではない己には、好きな女の子を会話で楽しませる自信など無かった。作業を言い訳に現実から逃げているのだ。何とも情けないことである。かろうじて出たのは、ゴミもらいます、の一言だけだった。
ガヤガヤと人が行き交う。風に吹かれて声が、匂いが、熱が少年少女を包む。賑やかな祭の場だというのに、二人の間には沈黙が流れていた。どうしよう、と伏した目をうろうろと泳がせる。月色の目に映ったのは、放置しっぱなしの銀色だった。
「……あの、座ってください」
屋台の屋根の下、荷物や道具を置く奥の机に立てかけてあったパイプ椅子を少女に差し出す。貸し出し時に用意されたものの、使っていない一脚だ。相手は慣れていないであろう下駄を履いた少女である、いつまでも立って待たせるわけにはいかない。かといって、飲食物を扱う屋台に部外者を入れるのは少しばかり気が引ける。己にできることは、椅子の提供が精一杯だ。
えっ、と少女は振り向く。こちらを見る柘榴石が、驚いたようにぱちりと瞬いた。
「悪いわ。大丈夫よ」
「下駄で立ちっぱなしは疲れるでしょう。使ってください」
「でも、こんなところで椅子に座るのはさすがに邪魔になっちゃうわ」
手を振って断る少女の言葉は正論であった。やはり、座ってもらうなら中に引き入れるべきだろうか。けれど。しかし。頭の中で問答を繰り返すも、答えは出ない。結局、そうですか、と手にしたそれを引き下げることしかできなかった。元の位置に銀の椅子を戻す。暖色の明かりに照らされる鉄素材は鈍く光っていた。
「……椿から連絡返ってきましたか?」
「まだね」
いつものことだから、と笑う紅刃に、福龍は苦い顔をする。普段からどれだけ迷惑を掛けているのだ、あの妹は。呆れと申し訳なさが恋心に揺れる胸を満たしていく。
「ちょっと電話してみます」
そうだ、最初からそうすればよかったのだ。何故思いつかなかったのだ。己を罵倒しつつ、急いで携帯端末を操り妹へと電話を掛ける。耳元でコール音が奏でられるが、十数回繰り返されてもあの無駄に元気な声がスピーカーから聞こえてくることはなかった。暇な時は端末をいじって遊んでいる彼女がこれほどまで出ないということは、現在手に持っていない疑いがある。もしくは、兄からの電話など対して重要ではないと無視しているのか。前者であってほしい。否、前者であっても困るのだけれど。
「出ないみたいね」
「……すみません」
そういう時もあるわ、と少女はひらひらと手を振る。頼りない姿を晒してしまった。内心顔を覆って蹲ってしまいたい気分だ。そんな情けない様など絶対に見せないが。
「そういえば毎年店番してるみたいだけど、大変じゃない?」
「家での店番とあまり変わらないので、特には」
妹に比べ営業トークが苦手な己が接客をするのと、小さな金庫一つで金銭を管理するのはいささか不安である。しかし、それをわざわざ言う必要など無い。この歳でその程度のことを懸念する様子など他人に見せたくなかった。相手が恋心を寄せる相手ならば尚更である。
「実家がお店って大変ね」
「紅刃さんも神社の手伝いが大変でしょう」
「そうでもないわよ? 忙しいのは七五三の時期と年末年始ぐらいだもの」
毎日手伝ってるあなたの方がすごいわ。
尊敬の念がにじむ声で、穏やかながらも儚げな笑顔で、紅刃はこちらを覗き込むようにそっと首を傾ける。提灯の明るくもどこか淡い光に照らされたかんばせは、美しい以外に表現する言葉が無かった。
心臓が大きく音をたてる。脈が早くなる。口内が渇きを覚える。顔に熱が集中していく。特に、頬が熱くなるのが嫌でも分かった。
いえ、と短く返し、福龍はふぃと視線を逸らす。今の己は大層情けない顔をしているだろう。こんな赤い顔を、緩んだ顔を見せるわけにはいかなかった。
また沈黙が二人を包む。相手はどうか分からないが、己にとっては気まずくて仕方が無い。せめて客が来れば接客を言い訳に逃げることができるのだが、生憎客足は途絶えて久しい。暑いのだから当たり前だ。分かっているものの、何故こんな時ばかり、と心の中で頭を抱えた。
「紅刃ー!」
騒がしいほどの雑踏の中、聞き慣れた声がまっすぐに飛んでくる。人混みを器用に縫って現れたのは、己と同じ青い髪を振り乱して駆ける少女、双子の妹の椿だ。
「紅刃ー! 待たせてごめんアル!」
「お前、今までどこに行ってたんだ」
「父上に呼ばれてたアル。友達と遊ぶならこれ持ってけって」
申し訳なさそうに謝る妹に、兄は刺々しい声を飛ばす。瞬時にけろりとした顔をした彼女は、手に持ったビニール袋を掲げた。乳白色のそれの中身を三人で覗き込む。薄い袋の中には、プラスチックパックに詰められたごま団子と桃まん、大福に杏仁豆腐のカップまで入っていた。気前が良いことだが、女子高生二人で食べきるには無茶な量だ。友達をどれだけ大人数と想定して持たせたのだろうか。
「あら、いいのかしら」
「いいに決まってるネ。父上、紅刃に食べてもらうの楽しみにしてたみたいアルヨ」
あの子は美味しそうに食べるからって張り切ってたアル、と椿はニコニコと笑みを浮かべる。呼ばれた少女は、恥ずかしげに口元を隠した。白い頬にほのかに色が浮かぶ。
たしかに、彼女はいつも涼やかな顔を柔らかに綻ばせ美味しそうに食べてくれる。師範が張り切るのも納得だ。ただ、その言葉を食い意地が張っている、と捉えてしまったのだろうか。そうかしら、とこぼす声は少し揺れていた。
「先に食べてから行くネ。福龍、詰めるアル」
「いや、お前、屋台内にはさすがに――」
「商品には触れない隅っこにいるから大丈夫ネ! ほら、椅子貸すアル」
止める福龍など気に掛けず、椿は紅刃の背を押す。狭い屋台の中に高校生の少女が二人入ってくる。浴衣姿の想い人が近づいてくる。人が三人並ぶのがやっとのスペースだ、距離は触れてしまいそうなほど近くなってしまった。心拍数が上昇する。唇が緊張で引き結ばれる。口の中から水分が失われていく。一歩下がろうとしたところで、妹が間に割って入った。ほら貸すアル、とたおやかながらもしっかりとした手が後ろにあるパイプ椅子を取った。安堵とかすかな口惜しさが胸に広がっていく。馬鹿らしいそれを消し飛ばすように、濃い青の頭がぶんぶんと振られた。
「福龍ー、杏仁豆腐食べるアルカー?」
「足りるのか?」
「多いくらいネ。というかこれ、絶対福龍の分も入ってるアル。食べなきゃダメアルヨ」
ほら、と椅子に座った妹は白で満たされたプラスチックカップを差し出してくる。分かった、と兄は大人しく受け取った。妹も想い人もよく食べる方だが、それでも二人で食べきるには難しい量に見える。最初から合流することを見越して己の分も入れて寄越したのだろうか。それとも、単に娘の友人のために張り切りすぎたのか。妹に少し甘い師範のことを考えると、どちらかといえば後者のようにも思える。
美味しーアル。美味しい。腰を落ち着けた少女らから高い声があがる。可愛らしい光景に頬を緩めながら、少年もスプーンを取った。プラスチックの小さなそれが、白い個体をすくい上げる。口に運ぶと、何とも言えない生ぬるさと確かなる甘みが口内に広がった。美味しいが、暑い夏の夜にはなんとも言い難い感覚である。それを見越して彼女は押しつけてきたのだろうか。
軽快に会話を交わしながら、少女らは飲茶に舌鼓を打つ。その間にも、客はちらほらと現れる。忙しく一人対応に追われながらも、少年は内心安堵の溜め息を吐いた。ただ立っているだけでは、どうにも想いを抱えた少女へと意識が向いてしまう。作業をしていた方が気が紛れてよかった。
食べた食べた、と椿は声をあげる。ごちそうさまでした、と紅刃は礼儀正しく言う。青髪の少女は立ち上がり、中身がまだ少し入った袋を奥の机に置いた。ぽん、と肩を叩かれる。ちらりと視線を向けると、ニコリと笑んだ妹の姿があった。
「じゃ、店番よろしくネ」
「終わるまでには帰ってこいよ」
「分かってるアル」
当たり前だというように言うが、毎年彼女は忘れて遊び、両親が店を終えるまで己一人で後始末をするのだ。おそらく今年もそうだろう。もう諦めていた。
「ちゃんと帰すから安心して」
「……すみません」
いたずらげに微笑む紅刃に、福龍は申し訳なさそうに返す。子どもじゃないアルヨ、とむくれた声が飛んできた。忘れて遊ぶのは子どもだろ、と返すと、膨れた頬から呻り声が漏れた。
よろしくアルー。待たせてくれてありがとう。元気な声と温かな声を残し、赤い背と白い背が雑踏へと混じっていく。視界からその二色が消えたのを確認したところで、はぁ、と酷く大きく重い溜め息を吐いた。頼りない足取りで隅に向かい、パイプ椅子に腰を下ろす。ガシャン、と耳障りな音が祭の片隅に響いた。
顔を片手で覆う。触れた頬はまだ熱を持っていた。あまりにも幼稚な己の反応に、少年はもう一度溜息を漏らした。現実から逃げるようにぎゅっと目を閉じる。瞼の裏に、浴衣姿の少女が浮かんだ。慌てて目を見開く。強く頭を振ってあの美しい姿を消し飛ばそうとした。
道具が雑多に並ぶ机の隅に置いた時計を見やる。二本の針は、祭の終わりまでまだまだ時間があることを語っていた。
遊びに行ったのだ、また彼女が姿を現すことはない。落ち着いて、ゆっくり店番をしよう。茹だる頭でどうにか考え、少年は椅子から立ち上がった。
提灯の暖色の明かりが、机上の透明なパックと飲茶たちを照らしていた。
畳む
twitter掌編まとめ4【SDVX】
twitter掌編まとめ4【SDVX】
twitterで書き散らしてた大体2000字ぐらいの掌編まとめ。twitter掲載時から修正とか改題とかしてるのは気にするな。
成分表示:ライレフ2/嬬武器兄弟2/レイ+グレ1/魂+冷音1/ハレルヤ組1/ユーシャ+千影+チョコプラちゃん1/ハレルヤ組+グレイス1/識苑+かなで1
夏空と傷痕/ライレフ
痛いほどの陽光が世界を照らし出す。波の音が眩しいぐらいの夏空の下響き渡る。バシャバシャと水が跳ねる音。子どもたちのはしゃぎ声が蒼天に昇った。
浮き輪をつけ、子猫たちは波打ち際に足を浸してはしゃぐ。『自分たちだけで深いところに行かないように』という言いつけをしっかりと守り、足先が浸る程度の浅い場所で遊んでいた。
元気な様子に、烈風刀は頬を緩める。猫は水が苦手と聞き少し心配していたが、彼女らはそうでもないようだ。怯える様子など全く無く、積極的に海を楽しんでいた。
ビーチパラソルの下、少年は傍らのクーラーボックスを開く。凍らせておいた飲み物は、順調に溶けていた。これなら冷たい状態でいつでも水分補給できるだろう。弁当の類もきちんと保冷剤に囲まれている。しばらくは平気だろうが、あまり時間をおいては不安だ。頃合いを見て食事を摂ることを促さねば。きっと、あれだけはしゃいでいれば声を掛けるより先に『お腹が空いた』と寄ってくるだろうけど。
「れふとー!」
「らいとー」
後ろから呼ばれ、パラソルの下兄弟二人は振り向く。視線の先には、浮き輪を抱えたニアとノアの姿があった。細い足が砂浜を蹴って走る度、まとめて結った蒼髪とサンバイザーに付いた長い耳が揺れる。
「見て! でっかい浮き輪!」
「おっ、借りてきたんだ?」
「そうだよー。これなら海の上でぷかぷか浮けるかも」
身の丈半分ほどもある大きな浮き輪を抱え、少女らは目を輝かせる。いいなー、と雷刀は羨むように青い浮き輪を眺める。いいでしょー、とニアは自慢げに笑った。
「らいとたちは海入らないの?」
ニアの問いに、兄弟の動きが止まる。青兎たちをまっすぐに見つめていた二色二対の瞳は、反対方向に逸らされた。
「あー……えっと……」
「僕たちは荷物の管理をしなければいけませんから。後で入りますよ」
目を泳がせ言葉を濁す朱に反し、碧はにこやかな笑みを浮かべて返す。荷物の管理をしなければいけないのは事実だ。万が一盗難被害に遭って楽しい時間を台無しにしてしまうなどあってはならない。
「……いいの?」
「えぇ」
不安そうに今一度尋ねる妹兎に、弟は笑みを崩さず首肯する。その笑顔は普段通りのようで、少しだけ固い。それが伝わったのだろう、姉妹は不思議そうな表情で互いの顔を見た。
「あとで交代するね!」
「もうちょっとだけよろしくね!」
そう言って、兎たちは海へと駆けていく。浮き輪持ってきたよー、とはしゃぐ子猫たちの声によく通る声が混ざった。
「……もっと上手く誤魔化せないのですか」
「できたら苦労しねぇよ……」
はぁ、と双子は嘆息する。晴れ渡る夏の青空に相応しくない、重く暗いものだった。
「誰のせいでしょうね」
呟くようにこぼし、烈風刀は羽織ったパーカーの裾を握る。溶けてしまいそうなほど気温が高いというのに、まるで閉じこもるように前を合わせた。鍛えられた腹が、緑の布地の奥に消える。
「さぁな。誰のせいだろうな」
投げやりに返し、雷刀もパーカーの襟元を握る。凍える身を守るように引っぱり、赤い生地で首を隠した。早くも日に焼け薄く色付いた肌が赤い生地に埋もれる。
本当なら、こんな暑い中パーカーなど着ていたくない。海にだって入りたい。めいっぱい泳ぎたい。そう思えど、行動できぬ色が二人の肌に刻まれていた。主に、背中と腰に。
海に行く、つまりは人前で肌を晒す予定があるのは分かっていた。分かっていて、二人でベッドに雪崩れ込んだ。全てが終わった後に傷が残る懸念が浮かび上がったが、まぁ大丈夫だろうと兄は笑い飛ばした。弟も、早く治るようにと薬を塗った。それでも、深く刻まれた爪の痕はうっすらと残ってしまったのだ。あまりにも無計画で、あまりにも浅はかとしか言いようがなかった。
こんなもの、子どもたちに見せるわけがいかない。純粋な桃たちはきっと心配するだろうし、知識がついていてもおかしくない年頃のニアたちには勘ぐられてしまう可能性がある。そんなことはあってはならない。その結果がこれである。
「海、入りてーなー……」
「行ってくればいいのではないですか。背中は見えにくいですし」
「烈風刀だけ入れねぇのはやだ」
どんなわがままですか、と碧は嘆息する。だってずるいだろ、と朱は唇を尖らせた。そんな配慮をするぐらいなら、最初から誘うなという話である。乗った己も同罪なのだから、口に出すことはしないけれど。
ザザン、と波の音が鼓膜を揺らす。光を受け輝く海面を、浅瀬ではしゃいで遊ぶ兎と子猫を、兄弟は眺める。熱い海風が二色の髪とパーカーを揺らした。
「先に言い出したのそっちだかんな!」「意味が分からないのですけど!」/ライレフ
一日紙の上を走り回っていた重たい腕を持ち上げ、雷刀は鞄から鍵を取り出す。揃いのキーホルダーを付けたそれは、銀のシリンダーを回し錠を開けた。鍵を握りこんだまま、ノブを回す。住まいと廊下を分かつ扉が開き、暖色灯の明かりが己を迎え入れた。
「ただいまー……」
力の無い声で帰宅を告げる。言ったものの、リビングにいるであろう弟には聞こえないだろう。分かっていても口にしてしまうのは癖なのだから仕方無い。
「あ、おかえりなさい」
靴を脱ぐために座り込んだ己の頭に、耳慣れた声が降ってくる。手を止めて振り返ると、そこにはエプロンを着けた烈風刀の姿があった。胸にはタオルの束が抱えられている。洗濯物をしまっていたところなのだろうか。朱い目が白くふわふわとしたそれをぼんやりと眺めた。
「ただいま」
「ちょうどいいところに帰ってきましたね。ご飯にしますか? それとも先にお風呂にしますか?」
今一度帰宅の言葉を口にする。返ってきたのは、穏やかな笑みと問いだった。今週の食事当番は烈風刀だ。晩ご飯を作っておいてくれたのだろう。風呂の用意ができているのは単純にタイミングの問題だろうか。彼のことだから、自分が入ろうとしていたところを譲ってくれるのかもしれない。
飯、と声帯が震える直前で、動きが止まる。あれ、と脳内で疑問の声があがる。疲れ切った脳味噌の端に、投げかけられた言葉が引っかかったのだ。毎日聞く文句ではある。けれども、この二つを並べるのは何か意味があったはずだ。なんだっけ、ととっちらかった記憶の引き出しを片っ端から開けていく。それはすぐに見つかった。
ご飯にする? お風呂にする? それとも――
定番の誘い文句だ。恋愛に疎い自分でも知っているほど使い古された、けれども確かな意味を持つ言い回しだ。それを、今恋人が口にした。己に向かって発した。その事実が、停滞していた思考に染み渡っていく。
最後の提案は無かったではないか、偶然だろう。疲れ切った脳味噌に一欠片残った冷静な部分が告げる。恥じらいがちな彼のことだ、言おうとして押し込めてしまったのかもしれない。疲弊した脳味噌の茹だった部分がでたらめを言う。否、きっとそうだ。そうに決まっている。補習で丸一日勉強漬けにされ疲労困憊の脳味噌は、間違った方向へと舵を切った。
脱げかけの靴のまま立ち上がり、こちらを見つめる愛しい人へと一歩踏み出す。エプロンの肩紐が通る確かな肩を、両の手で捕らえた。ぱちりと瞬く孔雀石を、柘榴石がまっすぐに見据える。
「れっ、烈風刀がいい!」
発した声は少しばかり裏返っていた。なんとも格好が付かない。けれども、奥手で恥ずかしがり屋な恋人がこんな風に誘ってきたのだ、興奮し上擦ってしまうのも仕方が無いことである。バクバクと心臓が脈打つ。夜風に晒された頬は、高揚で薄ら赤く染まっていた。
「は?」
返ってきたのは、酷く冷えた声だった。全てを凍りつかせるような、切り捨てるような、鋭く冷たい音だ。あれ、と疲労で溶けた脳味噌が疑問符を浮かべる。
「馬鹿なこと言ってないで選んでくれませんか。こっちにも段取りがあるんですから」
見つめ返す、否、睨む浅葱は冷たい色をしていた。先ほどまでの温かさなど欠片も無い。手入れされた唇から紡がれる言葉も、酷く面倒臭そうな音色をしていた。
「あ? え? あれ? え、だって――」
「決められないのなら先にご飯食べててください」
肩を掴む手を振りほどき、烈風刀は呆れきった調子で言う。お風呂先にいただきますね、と残し、彼は洗面脱衣所へと消えた。
パタン、とドアが閉まる音。扉にはめられたガラスから光が漏れ、廊下に伸びるのが見えた。
「…………………………えー」
長い長い沈黙の末、雷刀は吐き出すように声を落とす。あまりにも間の抜けた音をしていた。
どうやら先の言葉は単なる偶然で、己の解釈と返答は誤答だったらしい。そんな馬鹿な、と茹だりきった脳味噌が泣き声をあげる。それみたことか、と小指の先ほど残っていた冷静な脳味噌が真っ当な声をあげた。
はぁ、と重苦しい溜め息をこぼす。勘違いとはいえ、期待したのに冷たくあしらわれたのは心にくるものがある。それも疲れ切ったところをとびきり酷く扱われたのだ、痛みはひとしおだ。
はぁ、ともう一つ溜め息。とにかく、手を洗おう。ご飯を食べよう。それから、風呂に入って、部屋に突撃してやろう。偶然とはいえ欲望を焚きつけたのはあちらなのだ。それぐらいしたって罰は当たらないはずだ。
今一度座り、脱ぎかけだった靴を脱ぐ。紐がぐちゃぐちゃになったそれを、踵を揃えて置く。鞄を引っ掴み、朱は洗面所へと足を向けた。
狭い玄関ホールの明かりが、少し萎れた白い背を照らした。
甘味と塩気と即席劇場/嬬武器兄弟
「映画見ようぜ!」
リビングに元気な声とナイロン生地が擦れる音が飛び込んでくる。突然のそれに、烈風刀は手元の携帯端末から視線を上げた。そこにはナイロンバッグを高く掲げた雷刀の姿があった。
「いいですけど……何ですか、それ」
「ポップコーンとコーラ」
大股でキッチンに向かう兄の背を追う。食器棚に手を伸ばしていた彼はくるりと振り返り、ほら、とエコバッグを手渡してくる。ずしりと重いそれの中には、市販のポップコーンの袋とコーラのペットボトルがあった。どれも大容量だ。二人で食べるにしても、いささか多いように思える。
「やっぱ映画っつったらポップコーンとコーラだろ?」
「そうですけど……、もしかしてこのためだけに買ってきたんですか?」
「俺の奢りだからいいじゃん」
棚の奥からプラスチックカップを取り出し、朱は冷凍庫を開ける。製氷皿を取り出し、乱雑に氷をカップに入れていく。ガラガラとしっかりと凍ったそれが硬い音をたてた。
「烈風刀はポップコーン持ってっといて」
ナイロンバッグからペットボトルを抜き出し、雷刀はひらひらと手を振る。分かりました、と短く告げて、キッチンを後にした。
リビング、壁際のテレビの真ん前に置かれたローテーブルに鞄の中身を並べる。白いポップコーンが爆発するように飾られたパッケージは、片手で持つには少しばかり苦労する大きさだ。それが二つ。つまり、一人一袋の計算である。さすがに多くないか、と碧は顔をしかめる。大方、値段の安さに反する大きさに惹かれて選んだのだろう。
「烈風刀ー、カーテン閉めといてー」
「もう閉めてますよ」
「いや、どっちも閉めといて」
キッチンから飛んできた声に、烈風刀は首を傾げながらも窓際に向かう。ベランダに続くガラス戸には、光を通す薄手のカーテンが引かれている。昼下がりの今は、遮光仕様の厚手のものを閉めるには早い時間だ。不可思議に思いながらも、少年は薄青色のカーテンを閉めた。陽の光が消え、リビングが暗くなる。
あんがと、と後ろから声。視線をやると、薄闇の中にストローの刺さったプラスチックカップを二つ持った片割れがいた。透明なそれの中身は黒に近い茶で染まっている。コーラを注ぎ入れたのだろう。カラン、と少し溶けて小さくなった氷が軽やかな音をたてた。
手にした飲み物をテーブルに置き、雷刀は机上のリモコンを手に取る。丸い電源ボタンを押すと、画面がパッと光を取り戻した。闇の中、大きな液晶が存在を主張するように眩しく輝く。
「目が悪くなりますよ」
「一時間ちょっとぐらいならだいじょぶだろ」
ソファに座った兄は、その隣のスペースをぽんぽんと叩く。眉間にかすかな皺を寄せつつ、弟は手が指し示す場所に座った。ほい、とポップコーンの袋が飛んでくる。
「何見る?」
「見たいものがあるのではないのですか?」
「別に。何か映画見たいなー、って思っただけだし」
問いかけるも、返ってきたのはぼんやりとした答えだった。確かに唐突だとは思ったが、本当にただの思いつきだったとは。彼らしいといえば彼らしい。自分だけ、でなく、二人で、と当然のように己を巻き込んでくるのはやめてほしいのだけれど。
「……この間レイシスが面白いと言っていた映画、たしか今月から配信していたはずです。それを見ましょう」
まぁ、でもたまにはこんな非日常もいいかもしれない。
珍しく悠長なことを考えながら、烈風刀は背もたれに沈み込む。膝に抱えたポップコーンの袋がガサリと音をたてた。
分かった、と弾んだ声。液晶画面内をカーソルが動き回る。話題作としてピックアップされていたおかげで、目当ての映画はすぐに見つかった。
再生ボタンが押される。画面が暗転し、しばらくして映像配信会社のロゴが大きく表示された。ドサ、と重い音。兄もまた背もたれに身を預けたようだ。
スピーカーから流れる鳥の鳴き声に、ビニールパッケージを開ける音が二つ重なった。
夏色スイーツ旅/レイ+グレ
燦々と陽が降り注ぐ窓の外を眺めながら、グレイスは水が入ったグラスを傾ける。カラン、とガラスと氷がぶつかり軽やかな音を奏でた。
「お待たせしました。レモンのレアチーズケーキ、ブドウのタルト、わらび餅パフェ、トロピカルスイカ杏仁クリームソーダ、アイスハニーミルクティーです」
銀の盆を両手に一枚ずつ持ったウェイトレスは、すらすらと唱えながらテーブル上に皿とグラスを並べていく。ケーキとドリンクを目の前にし、対面に座った姉は感動の声をあげた。
背の高いグラスを引き寄せる。まろやかな茶色と細かな氷で満たされ真っ白なストローが刺さったそれは、見るだけでも涼やかだ。炎天下の中歩き回った熱が薄れていくような心地がした。
「いただきマス!」
長いスプーンを手に、レイシスは手を合わせる。元気な声がテーブルに響いた。おあがりなさい、と妹は小さな声で返し、ストローに口を付けた。一口吸い上げると、香り高い紅茶の中にはちみつの風味と独特の甘さが広がった。ここのカフェラテは美味しいと聞いていたが、紅茶もこれほど美味しいとは。疲労がまとわりつく身体を、冷たさと甘さが癒やしていく。
口を離し、ちらりと視線を上げる。躑躅の瞳に、パフェスプーンでわらび餅パフェをめいっぱいにすくう桃が映った。バニラアイスと黒蜜、きなこが小さなスプーンの上で山を成す。溶けて落ちてしまいそうな白と黒は、真っ赤な口に吸い込まれた。こくりと細い喉が上下する。途端、きらめく薔薇輝石が大きな虹を描いた。
「美味しいデスー!」
「良かったわね」
感嘆する姉に、妹は緩く笑んで返す。一口、もう一口とレイシスはスプーンを運ぶ。頬張る度に、可愛らしい顔がとろけていく。幸せとはこのような表情を言うのだろう。
スイーツ食べに行きマショウ!
そう言って彼女が寄宿舎の部屋に突撃してきたのが今日の午前のこと。あれよあれよと着替えさせられ、手を取り外へと出かけたのだ。飲茶店のごま団子にかき氷、鯛焼き屋の夏限定カスタードアイス鯛焼き、喫茶店のソーダゼリーにクリームソーダ、そしてカフェのケーキにパフェ。様々な店をはしごし、夏を満喫するようなスイーツを楽しんでいく――といっても、それはほとんどレイシスの話だ。あまり量が食べられない己は、かき氷と鯛焼き、小さめのクリームソーダで胃が限界を迎えた。本当ならば『お腹がいっぱいだ』と言って帰宅を促すべきなのだろう。それでも、幸せ満開な笑顔で甘い物を食べる姉の姿を見ているだけでも十分に楽しくて、ついつい付き合ってしまう。腹もいっぱいになるのだけど。
アイスティーを飲みながら、もぐもぐとスイーツを満喫する姉の姿を密かに眺める。パフェのバニラアイスとわらび餅を食べ終えた彼女は、そっとフォークに持ち替えた。銀色のカトラリーが、つやつやと輝くぶどう、それを支えるタルト生地に突き立てられる。大きく切り取られたそれが、リップで彩られた口に吸い込まれていく。美しい曲線を描く頬が動く。んー、とたまらないと言わんばかりの高い声がケーキを頬張る口から漏れた。
「アッ、グレイスも一口食べマスカ? とっても美味しいデスヨ!」
視線に気付いたのだろう、鮮やかなピンクの瞳がぱちりと瞬く。細い指がフォークを操り、ケーキを一口分すくい上げた。あーん、と弾んだ声とともに、紫で彩られた銀がこちらに迫った。
「お腹いっぱいだからいいわ」
少しばかり身を引き、グレイスは差し出されたケーキから距離を取る。最後に食べてからいくらか歩いたものの、アイスティーを数口飲んだだけで再び胃は容量限界を訴えた。たった一口といえども、ケーキが入る余地は残っていない。『甘い物は別腹』とよく言うが、己には当てはまらないようだ。
そうデスカ、と姉は手を引っ込めしゅんとした様子で視線を下げる。美味しいものは分かち合いたいのだろう。そうでなければ、わざわざ己を誘ったりはしないはずだ。
「貴方が食べたくて頼んだんでしょう? 貴方が全部食べるべきだわ。いっぱい食べる方が幸せなんだから」
柔らかな微笑みを浮かべ、妹は言う。いいのか、と問うように、紅水晶がこちらを見やる。応えるように、尖晶石がふわりと細められた。フォークの上に鎮座していたぶどうが、もぐりと食べられた。
「また今度来た時、一緒に食べマショウネ」
ケーキという幸せを飲み込んだ彼女は、まっすぐにこちらを見つめて言う。アッ、次は秋の方がいいデショウカ、とはわはわと少女は口にする。同じラインナップになるのを避けるためだろう。そういう細かな気を遣ってくれるのだ、この優しい薔薇色は。
「そうね。また秋に誘って」
マゼンタの目がふわりと細められる。柔らかな視線を受けたピンクは、表情を輝かせた。ハイ、と元気な声が甘味が並ぶテーブルに落ちた。
秋といったらモンブランだろうか。カボチャとサツマイモもある。抹茶の旬は秋だと聞いたことがある。楽しみはいっぱいだ。
気持ちが良い様で食べる姉を眺め、妹はアイスティーに口を付ける。柔らかな甘みと豊かな香りが口の中を楽しませた。
冷たさ半分こ/嬬武器兄弟
カサリと小さな音が店内音楽に混じって聞こえた気がした。嫌な予感に、烈風刀は手に提げた買い物かごに目をやる。店内専用のプラスチックかごの隅に、入れた覚えのないアイスのパッケージが居心地悪そうに佇んでいた。
「雷刀」
眉間に皺を寄せ、隣に並んでいた兄を見る。鋭い視線を避けるように、ふいと顔が逸らされた。やはり彼の仕業のようだ。
「家計簿つける時にややこしくなるでしょう。自分で買ってください」
「えー」
唇を尖らせる朱に、碧はかごから取り出したアイスを突きつける。まっすぐになった口が何か言いたげにもごりと動く。しばしして、日に焼けた手が渋々といった様子で青と白で飾られたそれを受け取った。そのまま黙って列を離れていく。最後尾に並んだのだろう。
夕方の人が多いスーパー、セルフレジに向かう列はじりじりと進んでいく。ようやく己の番が訪れ、烈風刀は重いかごをレジ台に乗せた。手慣れた様子でナイロンバッグを広げ、電子パネルを操作しながらかごの中身をスキャンしていく。最後に電子マネーカードをかざし、会計を済ませた。
通学鞄を肩に、二つになった買い物袋を両手に携え、レジの群れから出る。出口には、アイスのパッケージを剥き身で持った兄がいた。黙って近づいてきた彼が、右手に握った薄手の鞄を自然に取る。行こーぜ、と歩き出した朱の後ろに続いた。
自動ドアをくぐる。途端、熱された湿った空気が身体にまとわりついた。まだ高い位置にいる太陽の光が剥き出しになった肌を刺す。不快指数を上げるばかりのそれらに、思わず眉を寄せた。店内の心地良い空調にしばらく浸った身体には少しばかり厳しい環境だ。夏とはいえ、夕方になったならば少しぐらい涼しくなってもいいだろうに。そんな無意味な愚痴が頭をよぎる。
「ほい」
隣から声。視線をやると、そこには半透明のプラスチックパッケージを差し出す雷刀の姿があった。バッグを肘にかけた右手には、同じものと薄いビニールパッケージがある。そういえば、先ほどかごに勝手に入れられたアイスは二つ一セットのものだったはずだ。
「貴方が食べたくて買ったんでしょう」
「あちぃだろ? 素直に食えって」
ほら、と空いた左手に細いそれを押しつけられる。食品を落としてはたまらない、と反射的に受け取ってしまった。つめてーだろ、と夕焼け空の目がにこりと弧を描いた。事実、既に熱を持ち始めた身体には心地の良い温度をしていた。
ありがとうございます、と返す声ははっきりとしない響きとなってしまった。純然たる好意なのだから素直に受け取るべきだとは分かっているものの、どうにも慣れない。弟の様子を気にすることなく、兄はビニールパッケージの頭部分をパキリと折って開けた。真っ赤な口に柔らかなそれの先端が含まれる。ちゅう、と可愛らしい音が聞こえた。
「んめー!」
アイスから口を離した途端、朱い少年は声をあげる。つい先ほどまで冷凍庫で入念に冷やされていた氷菓は彼を満足させたようだ。倣うようにパッケージの頭を折る。いただきます、と呟いて、碧い少年も冷たいそれを含む。吸い上げると、冷たさと甘さが口の中に広がった。
「美味しいですね」
「だろ? 久しぶりに食ったけどやっぱいいよな」
穏やかな声をこぼす烈風刀に、雷刀は上機嫌な様子でアイスを振った。言われてみれば、久しぶりに食べた気がする。幼い頃は、買い物ついでに一つ買って二人で分けて食べたものだ。今では、兄一人で全部食べてしまうことの方が多いのだけれど。
今日の晩飯なんだっけ。夏野菜カレーですよ。やった。
和やかに言葉を交わしながら、兄弟連れ立って歩いて帰る。制服に包まれた背を夕陽が照らした。
翌日、元気な青い背を思いっきり叩いてやった/冷音+魂
ケホ、と乾いた音と息が漏れる。小さな音だというのに、枕元の青は怒鳴られたように身を竦ませた。
「魂、これ、お母さんが持っていきなさいって……」
差し出されたのは白いビニール袋だ。薄い生地の向こう側に、うっすらと緑とオレンジが見える。市販のフルーツゼリーか何かだろう。後で食べる、と返した声の後ろにまた咳が付く。今度はゲホゲホと量が多かった。
「だっ、大丈夫?」
「大丈夫なわけねぇだろ……」
狼狽える冷音に、魂は低い声で返す。喉がいがらっぽくてどうにも低くなってしまうのだ。何より、根底に怒りがある。ごめんね、と萎れた謝罪の声に、少年は咳をこぼした。
「秋だぞ……考えろよ……」
秋も深まってきた先日、台風がやってきた。珍しく規模が大きなそれは、街を暴風雨で掻き乱した。一部地域では避難警告が出たほどである。幸い、己たちの暮らす地区はただただ雨風が酷いだけで済んだのだけれど。
そうだ。警報も何もなく、ただ雨が強いだけ。これでもかというくらい強いだけ。今までの人生で一番ではないかというぐらい強いだけ。
そんな天気の中、この雨に狂う腐れ縁が浮かれないはずがないのだ。
被害を警戒した学校は授業を切り上げ、皆早くに家に帰ることとなった。教師から特に念を押して注意されたというのに、冷音は家から正反対の、台風に近づく方角へと走っていったのだ。慌てたのは魂だ。正直なところ、止める義務などないのだからこのまま放って帰ってしまいたい。だが、ここであいつを野放しにしては彼の母親が心配するのだ。いつも世話になっている、美味しいお菓子を食べさせてくれる素敵な人。少しでも恩は返したかった。
そうして頭一つ分は上の首根っこを引っ掴んでどうにか家に帰ったのが一昨日のこと。熱が出たのが昨日のこと。学校を休んだのが今日のこと。休みの連絡を知り――正しくは『お前のせいで風邪引いたんだけど』と恨みがましいメッセージを受け、冷音が見舞いに来たのが今だ。
「何でお前はピンピンしてんだよ」
「さぁ……?」
慣れてるからかなぁ、と呑気な言葉が返ってくる。ふざけんなよ、とまた低い声が落ちた。咳二つ。
「ゼリー食べる?」
「食べる……」
ガサガサとビニール袋を漁る音を横に、ゆっくりと身を起こす。熱はだいぶ引いているものの、一日以上横になっていたからか妙に気怠く感じた。
はい、と蓋を外されたゼリーとプラスチックスプーンが手渡される。何も言わず受け取った。熱が出るほど風邪を引いた原因はこいつなのだ、礼を言う義理などない。
スプーンですくい、透明なゼリーと剥かれたみかんを口に含む。程よい甘さと冷たさが渇いた口を、妙に詰まる喉を、空っぽに近い胃を癒やした。思わず声を漏らす。袋の持ち主がほっと息を吐くのが横目に見えた。
黙々とゼリー菓子を食べていく。心地良い甘さとたっぷりの潤いを残し、カップの中身は空になった。無言でクッションに座る腐れ縁に突き出す。はいはい、と呆れた調子で食器は回収された。
「残り、おばさんに渡しとくね」
そう言って、青い少年は立ち上がる。ある程度無事な様子を確認し、謝罪も済ませ、菓子も渡したのだ。もう帰るのだろう。黙ってひょろ長い背を見やった。冷音、と咳交じりの声で名前を呼んだ。
「今日はもう外出んなよ。まっすぐ帰れよ」
「心配しなくてもちゃんと帰るよ」
魂こそちゃんと寝なよ。そう残して、扉は閉まった。廊下を歩く音。遠くで人が話す声。また足音。そして、静寂が訪れる。
枕元の携帯端末を操り、天気を確認する。今日の天気予報は晴れのち曇り。夜の降水確率は三〇パーセントだった。つまり、降る可能性はある。
風邪引いても知らねーかんな。口の中で呟いて、少年は二色の目を閉じた。
氷と染め色/ハレルヤ組
シロップディスペンサーから液体が流れ出る。鮮やかな赤のそれは、真下のカップに降り注ぎ白い山を染めていった。レバーが元の位置に戻る頃には、白は鮮烈なる赤に様変わりしていた。ぬるいシロップをめいっぱい注がれた削り氷は、溶けて一回り小さくなってしまった。
「掛けすぎではありませんか」
「掛け放題なんだからいっぱい掛けた方がいいじゃん」
呆れた声に、弾んだ声が返される。そうだぜにいちゃん、と屋台主の笑い声も飛んできた。随分と気前が良いことである。
「レイシスは何味にしたんだ?」
「いちごデス!」
シロップをかけ終わった雷刀は隣へと視線を向ける。呼ばれた少女は、満面の笑みで『氷』の文字が大きく描かれた発泡スチロールカップを掲げて見せた。藍の生地に白の花散る浴衣姿にいちごの赤いかき氷はよく映えた。
「オレもいちご!」
「僕は……メロンにしましょうか」
お揃いであることに喜びはしゃぐ兄を退け、弟は緑の液体が詰まったディスペンサーからシロップを掛ける。白い氷はあっという間に緑に染まった。濃く鮮やかなそれは、提灯の温かな光に照らされる闇の中でもはっきりと存在を主張していた。
ありがとうございマシタ、と礼を言うレイシスに続き、兄弟二人も礼を言う。お祭り楽しんどいで、と主人は手を振り少年少女を見送った。
屋台の群れから少し離れた場所、開けた広場へと移動する。設置された椅子と机は既に埋まっており、ほとんどの者が立って談笑している。壁際の少し空いたスペースに三人は身を滑り込ませた。
「いただきマス!」
「いただきまーす!」
「いただきます」
声を揃え、三人はストローでできたスプーンを構える。ストライプで彩られたそれが、サクリと軽い音をたててかき氷に差し込まれる。小さくすくう者もいれば、こぼれそうなほど多くすくう者もいる。三者三様にシロップに染められた削り氷を溶ける前に口に運んだ。
「んめー!」
「冷たいデスー!」
レイシスと雷刀は感嘆の声をあげる。美味しいですね、と烈風刀は穏やかな笑みを浮かべ二人を見た。節の目立ち始めた手が、透き通るなめらかで美しい手が、一口、また一口とかき氷を運んでいく。いてぇ、と時折頭を押さえる朱に、桃は慌てすぎデスヨ、可愛らしい笑顔を浮かべた。そういう彼女も、痛いデス、と頭を押さえる。もっとゆっくり食べましょう、と苦笑混じりの声が窘めた。
暑い夏の夜の中、冷たくて甘い氷菓子はどんどんとすくわれ形を崩していく。あっという間に色とりどりの氷は姿を消してしまった。朱はカップを傾け、底に残ったシロップを飲み込む。意地汚い、と顔をしかめる碧に、もったいないじゃん、と彼は唇を舐めながら返した。
「なーなー、レイシス。べーってして」
「何を言っているのですか」
手本を示すように舌を出す兄を、弟は鋭く切り捨てる。垂らした舌をそのまま、雷刀はストローを振って器用に言葉を紡ぎ出す。
「ほら、かき氷食べたらシロップで舌の色変わるって言うじゃん? 変わってんのかなーって」
「赤いシロップなのですから変わるわけがないでしょう」
「雷刀は変わってマセンネ」
しかめ面で正論を吐く碧と垂れた舌を眺める桃を前に、朱は不満げに目を細める。烈風刀の指摘通り、だらしなく垂れた舌は元の健康的な赤色のままだった。残念デス、とレイシスは眉を八の字に下げて厚いそれを眺めた。
「あっ、そだ。烈風刀はメロンだったじゃん? 緑になってんじゃね?」
「そうかもしれマセンネ!」
しょんぼりとした少女の様子に、朱い少年は舌をしまい慌てて声をあげる。赤い線で彩られたプラスチックストローが碧い少年を指した。行儀が悪い、と指摘するより先に、え、と驚愕の浮かぶ声があがる。
「烈風刀、べーってしてくだサイ!」
べー、と薔薇色の少女は舌を出して実演する。可愛らしい小さな舌は、やはり元気な血の赤をしていた。突然矛先を向けられ、弟はえ、と再びこぼして身を固くする。舌を出すなどはしたない。けれども、愛しい少女がそれを望んでいる。守るべきマナーと少女への忠誠心が天秤に掛けられる。もちろん、一瞬で後者に傾いた。
浅葱の瞳がうろうろと泳ぐ。しばしして、べー、と控えめな声とともに薄く開いた口から小さく舌が覗いた。中ほどまで出されたそれは、すっかりと着色料の緑色に染まっていた。
「本当に緑デス!」
「こんなにはっきり変わるんだなー」
手を合わせて喜ぶ桃と、感心した声をあげる朱。薔薇輝石の瞳と炎瑪瑙の瞳が、緑に染まった小さな舌に一心に向けられる。じぃと見つめられている事実に、子どものような行動をしている事実に、まだ丸さが残る頬が舌と反対の紅で薄く色付いた。すぐさま緑で染め上げられた赤は引っ込められ、姿を消した。
「もういいでしょう。屋台を回る時間がなくなりますよ」
誤魔化すように言って、碧は二人の手からカップとスプーンを回収する。真っ当な指摘に、ハワ、と少女は声をあげた。
近くに設置されたゴミ箱に分別して捨て、少年は行きますよ、と手を差し出す。ハイ、と元気に応えた少女が手を伸ばす。大きな手に載せられたのは、横から伸ばされた同じほどの大きさの手だ。行こーぜ、と兄は不自然なまでにニコリと笑いかける。弟は一瞬眉を寄せる。すぐさま解き、そうですね、とこれまた不自然な笑みを浮かべた。
たこ焼きと焼きそばと、あと何でしたっけ。ベビーカステラ食べたいデス。オレから揚げ食べたい。ゆるゆると会話を交わし、三人は広場を歩いていく。藍の浴衣と黒の浴衣二つが屋台街へと歩いて消えていった。
×4/ユーシャ+千影+チョコプラちゃん
サクン、とよく焼けた生地が軽やかな音をたてる。歯応えは固いそれは、口の中ですぐに解けた。素朴な甘さが舌の上に広がる。もう一口。チョコレートがかかった部分は更に甘く、けれども心を癒やすかのような優しさをしていた。
「もうちょっとなのになー……」
クッキーをかじりつつ、ユーシャは携帯ゲーム機を操る。画面下に表示されている残機数は、いつの間にか一桁まで減っている。ゲームオーバーまですぐそこだ。呻り声をあげながら、少年はもう一枚クッキーに手を伸ばす。個包装のそれが音も無く破かれる。
「そろそろアイテム使ってみたら?」
隣で焼き菓子を頬張る千影がボタンを押す。ピロン、と電子音とともに、アイテム欄が表示された。一面から触っていないそこは、もう全ての欄が埋められている。これ以上獲得できない状態だ。
「使ったら卑怯じゃない?」
「あー……。分かるけど、ずっと使わんかったらもったいないやろ?」
少女の言い分もっともだ。攻略が有利になるアイテムがあるのならば、積極的に使うべきである。ずっと詰まっている今なら尚更だ。けれども、アイテムを使い強い状態で敵に勝つというのはなんだか気が引ける。否、悔しいのだ。道具などに頼らずに勝利を掴み取りたい。ゲーマーとしての意地とでもいうのだろうか。
「使えるもの全部使ってこその勝利だよ~?」
液晶画面を見つめる二人、その脇に置かれたカップの中から声がする。露草と竜胆が両手で抱えるサイズのそれへと向かう。マグカップの縁に腕を乗せた妖精は、眼鏡の奥に柔らかな笑みを浮かべていた。
彼女の言葉に、青い目が悩ましげに細まる。引き結ばれた口から、また呻り声が漏れた。彼女の言も正論である。こうなってはもう意地との闘いだ。
「一回使ってクリアできたら普通の状態でもっかいクリアすればええやろ。実質ノーアイテムクリアや」
「それは何か違わない?」
「違わんやろ。アイテム使わずにクリアしたことには変わりないんやから」
ほらほら、と少し濃い色をした指がボタンを押す。既に載せられた少年の指を避けながら十字キーを操り、一番入手しやすく強化効果も薄いアイテムにカーソルを合わせた。
「じゃ、ウチそろそろ撮影の時間やから」
がんばりやー、とクッキーを口に放り込み、少女は去っていく。残ったのは一人の人間と一人の妖精、陽気な電子音を奏でる携帯ゲーム機だけだ。
ねぇねぇ。依然悩ましげに液晶画面を眺めるユーシャに、どこか弾んだ声がかけられる。
「気合い入れるために、大人でビターな味試してみる?」
そう言って、妖精はにまりと笑う。とぷん、と軽い音と同時に彼女の姿がマグから消える。すぐさま、隣に置かれたプラスチックカップから顔を出した。チョコレート色の小さな指が、すぐ隣、今の今まで彼女がいたマグカップを指した。
コクリと息を呑む。苦い味は得意ではない。今だって、コーヒークッキーを避け、プレーンやチョコレートといった甘いフレーバーばかり食べていた。今彼女が入っている己が使っていたカップだって、中身は甘い清涼飲料水だ。妖精のために用意されたマグ、その中身のコーヒーはまだ自分には早い味である。
けれど。
携帯ゲーム機を机に置き、白くて大きなマグカップに手を伸ばす。ほんのりと温かなそれを前に、もう一度息を呑む。気合いを入れるのだ。苦みで目を覚まし、百パーセントの力を発揮するのだ。持てる全てを以て、勝利をもぎ取るのだ。
コーヒー独特の香りが鼻をくすぐる。苦みの象徴のようなそれに眉をしかめながらも、少年はひと思いにカップの中身を口に運んだ。
あっま、という声が、溜まり場と化しつつある控え室に響いた。
川の字+1/ハレルヤ組+グレイス
ソファとローテーブルを部屋の隅へと押しのける。あらわになったフローリングをさっと拭き、押し入れから運んできた敷き布団を三枚敷く。数枚のシーツで覆い、枕と掛け布団を置く。賑やかな団欒の場は、夜を穏やかに過ごす場へと変わった。
「……来客用の布団、もう一つ買わなければいけませんね」
敷き詰められた広い布団を眺め、烈風刀は小さく笑う。だなぁ、と自分の枕を抱えた雷刀が返した。
「グレイスはワタシと一緒のお布団で寝るから大丈夫デスヨ~!」
置きっぱなしにしてあった寝間着に着替えたレイシスは、姉の部屋着を借りて着るグレイスに抱きつく。ぴゃわ、と小さな悲鳴があがった。
「狭いでしょ!」
「前に一緒に寝た時は余裕デシタヨ? 大丈夫デス!」
「あれはこっちに来たばっかで小さくなってた時の話でしょ! 今はあなたとほとんど身長変わらないんだから狭いわよ!」
かしましい姉妹の様子を、兄弟は微笑ましそうに眺める。何笑ってんのよ、と鋭い視線と声が飛ばされる。べつにー、と朱は浮かぶ笑みを隠すことなくはぐらかすように返した。八重歯覗く桜色の唇が悔しげに結ばれる。
立て続けに行っていた機能アップデートが落ち着いた今日、久しぶりに四人で夕食を食べようという話になった。広く時間の融通も利くから、という理由で嬬武器の兄弟の住まう部屋に集まり、料理し、心ゆくまで会話と食事を楽しんだ。テレビのクイズ番組で競い、テーブルゲームに興じ。賑やかな時を過ごしていく内に、夜はすっかり更けていた。こんな夜更けに女性二人で帰らせるのも悪い、いつも通り泊まっていくといい、という話になったのはすぐだった――レイシスが度々兄弟のところに泊まっていることを知らなかったグレイスは非常に驚いていたけれど。
全員シャワーを浴び、寝間着に着替え、各々寝る準備を済ませる。慣れた手つきで三人で布団を敷き、今に至る。
三枚分の敷き布団は広いが、高校生四人で寝るにはいささか手狭にも見えた。かといって、今から布団一式を手に入れるなど不可能だ。今日のところはこれで凌ぐしかない。
姉妹――というよりほとんどグレイスである――は静かなる夜の中で言葉を交わし合う。攻防は続くばかりだ。さてどうしようか、と朱と碧の兄弟は互いに目配せをした。
兄弟二人で一つの敷き布団を使い、残りの二つをレイシスたちに譲るという手もある。しかし、おそらく彼女はそれを由としないだろう。泊まらせてもらっているのに布団まで譲ってもらうのは申し訳ない、と。普段は尊大にも見える姿勢を取るグレイスもそう言うだろう。人をよく見て気遣う子なのだ。
「…………あぁもう、しょうがないわね」
折れたのは躑躅の少女だ。この少女はつっけんどんにするものの、最終的には姉に甘いのだ。ヤッター、と薔薇色の少女は万歳をする。すぐさま目の前の細い身をぎゅっと抱き締めた。苦しいって言ってるでしょ、と抗議の声があがる。
「……お布団、別に買わなくてもいいわよ」
マゼンタの瞳が、ターコイズを見やる。薄紅刷かれた頬が、健康的な色をした唇がもごもごと動いた。
「私、そんなに泊まらないし。わざわざ買うなんてもったいないわよ」
「たまには泊まるだろ? それに、布団なんて何組あっても困るもんじゃないし」
「置き場所には困りますよ」
能天気な兄の言葉を弟は素早く切り捨てる。ほら、と妹はすっと目を細めた。けれど、と穏やかな声が続く。
「スペースさえ考えなければ多くて困ることはないのは事実ですしね。何より、グレイスが泊まってくれる度に狭い思いをさせるのも申し訳ありませんし」
烈風刀の言葉に、グレイスはきゅっと唇を引き結ぶ。う、と苦々しげな声が細い喉から漏れた。尖晶石が宙を泳ぐ。うー、と小さな呻り声。しばしして、可憐な唇がもそもそと音を紡ぎ出した。
「……ちょっとぐらいなら狭くても大丈夫よ。気にしないで」
「そうですか」
「グレイスがそう言うならそーすっか」
すっかりと俯いてしまった少女に、兄弟は了承の言葉を返す。両者とも言葉には決してしないが、想定の結末であった。何をどう言っても、この勝ち気で少々意地っ張りな少女は優しくて温かな姉のことが大好きなのだ。もちろん、姉も妹をこれでもかと愛している。そんな二人が一緒に寝るのは最早必然と言ってもいい。それくらい、この姉妹はいつだって一緒なのだ。
では寝ましょうか、と少年の言葉に、残る三人は元気に返事をする。布団の上を足が動き回る。中央の布団にレイシスとグレイス、右の布団に雷刀、左の布団に烈風刀が横たわった。いつもとほとんど変わらない風景である。
碧がリモコンを操作し、部屋の電気を消す。電子音とともに、明るかった室内は闇へと溶け込んでいった。賑やかしさはすっかりと消え、静寂が部屋を包む。
「おやすみなさい」
「おやすみー」
「おやすみなサイ」
「おやすみ」
四人は就寝の挨拶を交わす。四色四対の目が閉じられ、眠りへと沈んでいった。
最後は意地で飲み干した/識苑+かなで
ビニール袋がガサガサと揺れる。暗い夜道では青白いそれはどこか輝いて見えた。
早く帰らねばな、と識苑は足を動かす。意志に反して、速度は遅い。疲労感と空腹が足を引っ張っていた。早く空腹を満たすためならば外食を選ぶべきだろう。けれども、激務続きの胃袋には普段通っている店の味付けは刺激的すぎる。結果、帰り道のコンビニエンスストアでおにぎりを数個買って済ませることとなった。黒い三角形がビニール袋の中を転がる。
角を曲がった瞬間、油の匂いが鼻をくすぐる。う、と思わず苦しげな音が喉から漏れる。普段ならば空腹を誘う芳しいものだが、今の自分にとっては毒となって襲ってくるものだ。早く通り過ぎよう。そう思った瞬間、発生源である店の戸が開いた。
「あっ、識苑先生!」
闇夜なんて感じさせない元気な声が己を呼ぶ。店内の光に背を照らされた少女は、ぱっちりと開いた栗色の瞳をキラキラと輝かせた。
「あー……、こんばんは」
「こんばんは! 今日は何食べてく? おにーちゃん!」
「『おにーちゃん』はやめてほしいんだけどなぁ」
営業スマイル全開のかなでに、青年は苦笑で返す。もう『おにーちゃん』なんて歳ではないし、何より彼女がこのように呼ぶのは営業トークの最中であることがほとんどだ。客にはなれない今日、そう呼ばれるのは少しだけ申し訳ない気持ちになる。そう、と三角巾に飾られた頭が傾いだ。
「良いタイミングだね! 今日は野菜増量キャンペーン中だよ!」
「いや……今日はちょっと無理かなぁ……。もうご飯買っちゃったし」
店の戸にある『野菜増量中』の張り紙を指し、看板娘はにこりと笑う。教師はひらひらと手を横に振って苦い笑みを漏らした。あまりにも輝かしい笑顔に、罪悪感が湧いてくる。けれども、食べきれるはずがないと分かっているものに手を出すのは良くない。『お残し』は何よりもいけないのだ。
「でも野菜足りる? 野菜いっぱい食べなきゃ健康に悪いよ?」
透けて見えるビニール袋の中身を眺めて言う。たしかにおにぎり数個では野菜など摂取できない。だが、『超超超特盛り』で有名なこの店のラーメンを食べるには、今胃の空き容量は完全に不足している。それに、野菜の摂取と同時に過剰な油分と塩分を摂取することとなるのだ。下手をすればこちらの方が健康に悪影響を及ぼす。
「かるーく食べれるミニラーメンもあるよ? お野菜食べてこ!」
さぁさぁ早くと言わんばかりに小さな手が着っぱなしの白衣の裾を引っ張る。あぁ、これはもう完全に逃げられない。常連である己が残すことはないという信頼もあって、彼女は迎え入れようとしているのだ。半ば無理矢理だが。
「……ここって少なめサービスってあったっけ?」
「特盛りサービスならあるよ!」
通い始めてから初めて尋ねる言葉に、正反対の言葉が返される。だよねぇ、と諦めの言葉を漏らしながら、白衣に包まれた痩身が店へと吸い込まれていった。
畳む
書き出しと終わりまとめ16【SDVX】
書き出しと終わりまとめ16【SDVX】
あなたに書いて欲しい物語でだらだら書いていたものまとめその16。相変わらずボ10個。毎度の如く診断する時の名前がちょくちょく違うのは気にしない。
成分表示:プロ氷1/嬬武器兄弟2/ニア+ノア+レフ1/ライレフ2/レイ+グレ1/氷雪ちゃん1/ノア+レフ1/恋刃1
見上げる貴方/プロ氷
葵壱さんには「届きそうで届かない何かがあった」で始まり、「そう思い知らされた」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば8ツイート(1120字)以内でお願いします。
届きそうで届かなくて、ぐっと背伸びをする。つま先に力を入れめいっぱい腕を伸ばしても、目当てのものには指先がわずかに触れるのがやっとだ。もうちょっと、というところで、それは大きな手に掴まれ消えた。振り返ると、そこには今まさに取ろうとしていた保存容器を片手に持った識苑の姿があった。
「これ?」
「ぁ、はい。ありがとうございます」
差し出された容器を受け取り、氷雪は礼を言う。ようやく手にすることができた安堵と、手間を掛けさせてしまった申し訳なさが胸を渦巻いていく。常磐色の目が薄く伏せられた。
「片付ける場所変えなきゃだね」
ごめんね、と言って青年は困ったような笑みを浮かべる。いえ、と慌てて否定の言葉を返すが、変更すべきであるのは事実だ。保存容器を一番利用する自分が手に届かない場所にしまっておくのは非効率的だ。
台所上部に設置された棚の扉を閉じる大きな恋人を見上げる。普段よりも少しだけ首に負担が掛かるのは気のせいではない。常は下駄でいくらかかさ増しした身長は、今はスリッパによって正常な数値になっている。見上げる角度が増すのも自然なことだ。
それが少しばかり悔しい。自分がもっと身長が高ければ、もう少しだけ釣り合いが取れるのに。今のように迷惑を掛けなくても済むのに。隣に並んでいても自然なのに。湧き起こる暗い感情に、少女はきゅっと唇を結んだ。
「どしたの?」
下から愛しい桃色が現れる。いつの間にか俯いてしまっていたらしい。眼鏡の奥の夕陽が、心配げな色を宿してこちらを覗き込んでいた。
「いえ。何でもありません。取ってくださりありがとうございます」
ぱっと顔を上げ、否定と感謝の言葉を吐く。本当に大丈夫だ、と示すように微笑んでみるが、きっとぎこちなく映るだろう。それがまた自己嫌悪を誘う。
腰を屈め目線を合わせたまま、識苑はそっか、と笑った。優しい彼は、自分がまた余計なことを考えているのを理解しているのだろう。その上で触れずにいてくれるのだ。子どもの自分なんかより、ずっとずっと大人な恋人は。
下駄を履いて背伸びをしないと、わざわざ屈んでもらわないと、目すらまっすぐに見られない。身長も、年齢も、全く釣り合わない。そう改めて思い知らされた。
痛いと言っても離してやらない/嬬武器兄弟
AOINOさんには「泣き虫が笑った」で始まり、「もう会えないかもしれないと思った」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば3ツイート(420字)以上でお願いします。
ボロボロと涙をこぼす泣き虫が、ぱぁと表情を輝かせ笑った。れふと、とまだ涙に濡れた声が元気に己の名を呼んだ。
「れふとぉ!」
「ばか!」
ずびずびと鼻を啜りながら駆け寄ってくる兄を、弟は怒鳴りつける。泣き腫らし赤くなった目の端から、ぽろりと涙が一粒落ちた。
「な、んで、一人で走っていくのですか! 『手を繋いでいよう』って、言ったじゃないですか!」
週末のショッピングモールは混んでいた。まだ小学生、しかも何にでも興味を示しすぐにどこかに行ってしまうような兄と二人で出かけるのには向かない場所だ。それでも、買いたいものがあったのだから行くしかない。学校帰りに寄るには難しい距離なのだ。
家を出る前から『二人で手を繋ぐ』『一人で行動しない』『どこかに行きたいなら事前に一声掛ける』と約束していた。事実、途中まではきちんと守っていたのだ。ここに入りたい。あれを買いたい。手を繋いで邪魔にならないように歩きながら、二人で珍しい遠出を楽しんでいたのだ。
気がついた時には、右手の温もりは無くなっていた。辺りを見回しても、大切な朱はどこにもいない。はぐれたのだと理解した瞬間、サァと血の気が引くのが己でも分かった。
公共の場だ、大声で名前を呼んだり駆け回って探すのは良くない。まずは、元の道を戻ってみなければ。そうして一店舗一店舗確認しながら来た道を丁寧に戻るが、最初に来た出入り口に戻ってきても片割れの姿は見つからなかった。鼻がツンと痛くなるのを我慢しながら、念のため持っていたリーフレットを確認する。『迷子センター』と書かれた場所目掛けて、碧は逸る足を押さえながら向かった。
結果、そこに兄はいた。開けたその場所、ボロボロと泣いて店員に縋る朱色の姿を見てどれほど安堵したことか。どれほど怒りを覚えたことか。結果、真っ先に発露したのは罵声二文字だった。
あんなに言ったのに、と弟は漏らす。苦しさと悔しさと怒りが強く滲んだものだった。ごめん、と鼻を啜りながら兄は返す。どちらも涙で潤んだものだった。
力なく垂れ下がった左手に腕を伸ばす。そのまま、紅葉のようなそれをぎゅっと握った。ここで捕まえておかねば、またどこかに行ってしまう。いつでもその場の衝動で動くのだ、この兄は。
見かねたのか、見つかってよかったわねぇ、と店員が優しい声で語りかけてくる。ご迷惑をおかけしました、と烈風刀は深々と頭を下げた。慌てて雷刀も弟を真似る。
「行きますよ」
「うん……」
固い声で言い放ち、弟は握った手を引く。しょぼくれた声が返ってきた。人の少ない場所を選びながら通路を歩いて行く。気を付けてね、と穏やかな声が背中から聞こえた。
「……よかったぁ。もう会えないかと思った」
そう言って、兄は握る手に力を込める。今度こそはぐれまいという意志がひしひしと伝わってきた。
もう会えないかもしれないと思った。それはこちらの台詞だ。まだ少し痛む鼻をすすり、弟は繋いだ手を力いっぱい握った。
日焼け対策は万全に/ニア+ノア+レフ
葵壱さんには「守りたいものはありますか」で始まり、「夏が始まる」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば7ツイート(980字)以内でお願いします。
守らねばならないのだ。今、彼女らを守ることができるのは己しかいないのだから。
「二人とも、ちゃんと日焼け止め塗りましたか?」
「塗ったよー!」
「ちゃんとニアちゃんに背中も塗ってもらったよ」
ビーチパラソルの下、日焼け止めのチューブ片手に烈風刀は頭二つは下の双子兎に問いかける。元気な挙手と声が返ってきた。証拠だと言わんばかりに、ノアはくるりと振り返りロングヘアを手で避けて背中を見せる。色が残らない薬品を塗った証拠というには乏しい光景だが、わざわざさらけ出して見せるほどなのだから信頼すべきだろう。
「それならよかった」
少し険しくなっていた碧の表情が緩む。体質によるものの、日焼けは度が過ぎると翌日以降痛むのがほとんどだ。海の楽しい記憶を日焼けの痛さで上書きしてしまうような事態は避けるべきである。
「約束、覚えてますか?」
「足の付かないところには二人だけで行かない!」
「生き物には触らない!」
もう一度問いを投げかけると、二人は宣誓するように手を上げ返す。どちらも前日から口を酸っぱくして言い聞かせてきた言葉だ。準備運動は、と追加で尋ねると、したよー、と双子はぴょんぴょんと跳びはねた。
よし、と少年は一人頷く。とても素直でもう高学年の彼女らだ、約束をきちんと覚えていると信じていた。それでも、はしゃいだ状態ではそれを完遂できるかは怪しい。テンションが上がった人間が何をするかなど分からないことは、幼い頃から片割れの姿を見てきて痛感していた。きちんと注意を促し、いつでも手助けできるように観察するのは、今この場で保護者的存在である己が果たすべき役割だった。
「れふとは日焼け止め塗った?」
「塗りましたよ」
「……背中は塗ってないでしょー?」
問いを返してきたノアに、烈風刀は優しい笑みで応える。少しの間の後、ニアはにやりと笑って少年の背中に回った。小さな手が、薄緑の上着の裾をぴらりとめくる。
「いえ、でも僕はパーカーを着ていますし大丈夫ですよ」
「後で脱ぐかもでしょ? 塗らなきゃダメだよ!」
「そーだよ!」
いたずらげな手をそっと退けるが、今度は二人で挟むように前後から飛びつかれた。わわ、と揺らめく足に力を入れる。ちゃんと塗ろー、と兎の合唱がパラソルの下に響く。正論であった。
「……そうですね。後で塗っておきます」
「一人じゃ塗り辛いでしょ? ニアが塗ったげる!」
「ノアもー!」
軽い足さばきで跳び上がり、姉兎は碧の手に握られていた日焼け止めチューブを取る。すぐさま後ろに回った妹兎が薄手のパーカーをバッとめくった。
「いえ、一人でも大丈夫ですから――」
「ほらほら、座って!」
「立ったままじゃ塗りにくいよー」
烈風刀の抵抗は、ぴょんと跳んで肩を押さえつけるニアの手によって防がれた。柔らかい砂、その上に敷かれた大判のレジャーシートの上に尻餅をつくように腰を下ろす。ほらほら、とぐいと後ろに引かれ上着を剥ぎ取られる。筋肉の線が見える白い背が生地の下からあらわになった。
パキン、とチューブの蓋が開けられる音。ねちゃ、と薬剤が捏ねられる音。ふんふん、と上機嫌な鼻歌。全てが己を置き去りにして愉快な合奏となって空に昇っていく。
ここまできたら、もう逃げ場などないようだ。塗らねばならないという彼女らの言い分は確かなものであるし、塗ってもらえるならばそうした方がいいのだろう。相手が小学生、それもいたずらっこな女の子たちであるというのがいささか不安を覚えるのだけれど。
塗るよー、と元気な声二つ。よろしくおねがいします、と観念して返すとほぼ同時に、ぬるい何かが背中に当てられた。小さなものが四つ、愉快げな鼻歌とともに背を駆け回っていく。二人がかりとはいえ、少し時間がかかるだろう。現に、背中に文字を書いて遊んでいるのだから。反応すれば長引くので耐えるしかないのだけれど。
海遊びという夏の始まりはもう少し先のようだ。
疲れた身体には温もりが必要なのです/ライレフ
葵壱さんには「世界はいつだってかみ合わない」で始まり、「だから、もう少しだけ」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば5ツイート(700字)以上でお願いします。
世界はいつだって噛み合わない。
テスト期間が始まって、ようやく終わったと思えば週刊アップデートの企画が舞い込んで。ようやく各方面への対応やコンテスト企画の立案を終わらせたと思えば、今度は世界のアップデートが決まって。
忙殺という表現が相応しい日々だった。気を抜けばあまりの忙しさに押し潰されていただろう。最終的には皆ランナーズハイのようなものになっていたのは、きっと気のせいではあるまい。
尻餅をつくようにソファに座り、烈風刀は背もたれに体重を預ける。たとえくつろぐためのソファとはいえども、もたれかかるなど行儀が悪いと分かっている。けれども、きちんと姿勢正しく座る気力などもう欠片も残っていなかった。帰宅し、あり合わせのもので食事を済ませ、シャワーを浴びただけで身体は限界を迎えたのだ。部屋に戻るために足を動かすのすら億劫だ。気が咎めるが、限界を超えて動けるほどのアドレナリンは尽きてしまった。
カチャリと扉が開く音。ぺたりぺたりと力の無い足音がキッチンの方面へと向かうのが聞こえた。しばしして、また足音。重苦しいそれは、己のすぐ隣で止まった。どさ、とつい先ほど聞いたばかりの音とともに、座面が沈み込む感覚が襲う。次いで背もたれが揺れる。隣に座った兄が、己と同じようにソファに身体全てを預けたのだろう。
「れふとぉ」
「なんですか」
力ない声に、力ない声で返す。もはや返事をするのすら面倒臭く感じる。どうやら己は思ったよりも疲れているらしい。相手も同じなのだろう、普段ならばぽんぽんと一方的に投げられる言葉は途絶えてしまった。
こつん、と肩に小さな衝撃。同時に温かな温度と重み。朱がもたれかかってきたのだろう。確認しなくとも分かる。確認するために顔を動かすのも煩わしく思えた。
「……おつかれ」
「……おつかれさまです」
耳に直接、彼らしくもない小さな声で労いの言葉が注がれる。どうにか同じく労う語を返した。長いアップデート企画期間、そしてロケテストに向けた準備のために共闘した相手である。同じほど頑張って、同じほど疲れているのは分かっていた。
温かな呼気が肌を撫ぜる。そのまま眠ってしまいそうなほどの穏やかさだ。疲れ果てた状態で腹も満たされ温かな湯に包まれれば、眠気を覚えるのも仕方が無いだろう。心なしか、横から加えられる体重も増えている気がする。
本当なら『寝るなら部屋で寝ろ』と言うべきなのだろう。そもそも、己も早く部屋に戻って寝るべきなのだ。こんなところでだらだらと座って時間を無為に過ごすのは身体にも良くないと分かっていた。
けれども。
肩に寄せられた朱い頭に、己も少しだけ身を寄せる。まだ濡れた感覚が肌から伝わる。常ならば不快に思うだろう。だが、今ばかりはその奥から伝わる温かなものが心地良くて仕方が無かった。
日数を数えるのも面倒なほど頑張ったのだ。ちょっとぐらいなら、愛しい人とともにいても罰は当たらないはずだ。身体はもちろん、心にも休息は必要なのだから。
だから、もう少しだけ。
いつだって見ていたいもの/ライレフ
葵壱さんには「ぱちりと目が合った」で始まり、「忘れたままでいてください」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば7ツイート(980字程度)でお願いします。
薄くなった碧とぱちりと目が合った。
やべ、と危機を覚えた瞬間、胸をぐいと押される。唇に灯っていた温もりが去っていく。代わりに、鋭い視線が向けられた。
「な、んで、目を開けているのですか!」
先ほどまで触れ合わせていた唇をわなわなと震わせ、烈風刀は叫びに近い声をあげる。興奮のあまり少しひっくり返った音は、怒気と羞恥と混乱がごちゃ混ぜだ。つい先ほどまでの甘やかな雰囲気など消し飛んでしまった。
「いや、なんとなく……?」
視線を逸らし、雷刀は言葉を濁す。真っ赤な嘘である。初心な恋人が期待に頬を染め、睫が震えるほど強く目を閉じ、こちらに身を委ね唇を差し出す様が見たかったのだ。あちらは毎回くっついてしまいそうなほど強く目をつむるので気付かれることはないと思っていたのだが、どうやらそう上手くいかないようだ。
「何となくで人の顔見るのやめてくれませんか」
眇め睨めつける孔雀石は射殺さんばかりの強さを持っていた。恥ずかしさよりも怒りが勝ってきたようだ。奥手な彼の言うところの『顔』がどういうものかを指摘してやりたい気分になるが、怒りを買うだけだということぐらいさすがの己にも分かる。好奇心を無理矢理押さえ込んで殺した。
「は、ずかしいから、今度からはちゃんと閉じてください」
僕にはいつも目をつむれというくせに、と恨めしげ声が飛んでくる。だってそう言わなきゃキスさせてくれねぇじゃん、といじけたように返す。ぐぅ、と喉が鳴る音が聞こえた。
肩に添えていた手を離す。このまま久しぶりに睦まじく過ごす予定だったが、この調子では到底無理だろう。嘆息しそうになるのを堪える。元凶は己なのだから。
ふと疑問がよぎる。目が合った。つまりはあちらも己のことを見た――目を開けたということである。いつもあれだけ強く目を閉じる彼が、だ。慎ましやかな恋人が、理性的な恋人が、無意味に口付けの最中に目を開けるとは思えない。何故なのか。
「烈風刀だって目ぇ開けたじゃん? オレのキス顔見たかったってこと?」
つい先ほど殺したはずの好奇心がするりと言葉となってこぼれ落ちる。やべ、と再び頭が遅すぎる警鐘を鳴らす。感情的ながらも至極正論な鋭利な言葉が飛んでくるか、キャパシティを越えてしまい衝動に任せた拳が飛んでくるか。どちらか分かったものではない。己の浅はかさを嘆く脳味噌が、恐れに身体の動きを制止した。
予想に反して、返ってきたのは真っ赤な顔と沈黙だった。潤った唇の端がひくりと引きつるのが見えた。あれ、と疑問符が浮かぶ。震えが止まり開かれた赤い口から紡がれた言葉は、確信をもたらすものだった。
「そっ、そんなわけないでしょう! 違いますから! ……もう、あんなの忘れてください!」
どうか素敵な休日ヲ!/レイ+グレ
AOINOさんには「恋って偉大だ」で始まり、「優しい風が髪を揺らした」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば10ツイート(1400字程度)でお願いします。
恋って偉大だな。
ハンガーラックを真剣な眼差しで見つめるグレイスの姿に、レイシスは思わず笑みを浮かべる。自分が率先して選び与えていたのもあるのだろうが、彼女はあまり服に頓着がない。人並みに興味はあったようだが、自主的にお洒落をする姿は見たことがなかった。そんな妹が、鋭さすら思わせる眼差しでうんうんと呻り声を上げながら自分が着る服を選んでいるのだ。微笑ましいったらない。
「ね、ねぇ、これ、似合うかしら?」
くるりと振り返った躑躅は、一着の服を身体に当てながら問う。華奢な手が選んだのは、ミントグリーンのトップスだ。爽やかな色合いは、彼女の鮮やかな髪をよく引き立てていた。
「とっても似合いマス! 可愛いデス~!」
「貴方、いつもそう言わない?」
賞賛する桃に、躑躅は訝しげな視線を向ける。そんなことないデスヨ、と頬を膨らませるが、言われてみればそんな気もする。だって、可愛い可愛い妹には何だって似合うのだ。仕方の無いことである。
「本当に似合ってマスヨ。グレイスは黒い衣装を着ることが多いデスケド、こういうパステルカラーもとっても似合ってて可愛いデス!」
思いの丈をそのまま言葉にする。尖晶石の瞳がぱちりと瞬き、頬に淡い朱が広がった。そうかしら、と嬉しげな、それでもまだ不安そうな色が残った声が返ってきた。
「ソレニ、緑は始果サンとお揃いデスシ!」
グレイスの恋人である京終始果は、いつも緑の忍装束を着ていた。『お揃い』なんてことを意識してこれを選んだわけではないだろう。けれども、長く連れ添う彼女にとって彼と緑色はきっと深く結びついているものだ。無意識が選んでもおかしくはない。
先ほどまで眉間に皺を寄せていた可愛らしい顔が、きょとりと幼くなる。数拍、マゼンタの目がこれでもかというほど見開かれた。薄紅色が浮かんでいた頬が紅葉したように真っ赤に染まる。
「そっ、そんなっ、そういうの意識したわけじゃないわよ!」
服屋のど真ん中で少女は叫ぶ。常識ある彼女は、すぐさまハッとし気まずげな表情を浮かべた。めいっぱい開かれていた口が、小さくもごもごと動く。
「大体でっ、デー……休みの日まであの服を着てるわけがな…………いやあるわね……始果だもの……」
どうにか否定しようとするが、逆に彼女の中で確信が生まれてしまったようだ。さすがにそんなことはないだろう、と言いたいところだが、相手はグレイス以外のほとんどに興味を示さない男である。親しいとは言い難い己が言い切るのは難しかった。
「ッ、やめた! 別のにする!」
グレイスは慌てた調子で持っていたハンガーをラックの中に戻す。ミントグリーンが服の森に消えた。
余計なこと言うんじゃなかった、と後悔を覚えながらも、表情に出さぬよう再び唸り始めた妹に少しばかりアドバイスをする。時折携帯端末で調べながら、どうにか『初めてのデート服』というとびきり大切な買い物を終えた。
服屋を出て、二人で並んで歩く。本当ならば頭からつま先までコーディネートしたいが、相談されていない部分は本人に委ねるべきだ。好きな人と過ごすための服を、他人の指図で全て決めるのは良くない。助けを請われたのならば別だが。
「……付き合ってくれてありがと」
ショッパーを両の手で握りながら、グレイスは呟きにも似た声で言う。ほのかに照れが乗ったそれは、とても穏やかな音色をしていた。可愛らしい姿に、姉は思わず頬を緩めた。
「ハイ。ワタシもとっても楽しかったデス」
デート楽しみデスネ、と軽く返してみる。隣に並ぶ細い肩がびくりと震えた。しばしして、そうね、と確かな喜びが滲んだ声が返ってきた。
晴れやかな帰り道、優しい風が桃と躑躅の髪を揺らした。
残りの授業の間眠気はもう訪れなかった/氷雪ちゃん
葵壱さんには「ぱちりと目が合った」で始まり、「そっと目を閉じた」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば6ツイート(840字)以上でお願いします。
ぱちりと目が合った。目が合ってしまった。
午後一番の授業は睡魔が時折やってくる。久しぶりに訪れたそれから逃れようと、氷雪は小さく頭を振る。少しだけ眠気が飛んだ視界の端に、空とは正反対の色が映った気がした。普段ならば授業中に余所見をすることはない。けれども、その珍しい色に視線は窓の外へと吸い寄せられてしまった。
真っ青な空の下そびえる白い校舎、その壁によく跳ねる桃が咲いていた。鮮やかな桃色が、屋上から垂らしたロープに身を預け、白衣を翻し、壁を蹴って移動する。その度に高い位置で結った髪が風に舞った。
識苑先生だ、と心の中で呟く。学園中を駆け回っている、という話は聞いたことがあるが、本当らしい。休み時間や放課後に見かけることはあるが、授業中に出くわしたのは初めてだ。それはそうだ、余所見をすることはいけないことなのだから。
まるで地を駆けるのと同じように、鴇色が壁を移動していく。一歩間違えれば死に直結するような高さにいるというのに、動作には恐怖など全く感じさせない。地を歩くのではなく壁を蹴って生活するのが当然のように校舎の側面を移動していた。
すごいなぁ、と見る度に考える。己は運動神経が良いと言いがたい。五〇メートル走は平均より少しだけ遅いし、球技も積極的に試合に参加できるほどの実力はない。体育の時間は苦手だった。そんな者から見れば、縦横無尽に空間を移動する彼の姿は一種の感動を覚えるものである。
薄紅梅がするするとロープを辿って屋上へと上がっていく。宙を蹴り壁を蹴る安全靴が屋上という地面を踏みしめるのが見えた。休憩だろうか。あんな体勢で長い間動くことなど危ないのだから当然だ。
桃が舞う。くるりと舞う。眼鏡が陽の光を受けて、キラリと光る。レンズの向こうの夕陽色が鮮やかに輝いて見えた。
まくり上げられた白衣から覗く腕が上空へと上がる。大きな手がひらひらとこちらに振られた。
瞬間、熱を持つ。熱いものが頬から広がり、顔を染め上げていく。窓の外を見て陽光を浴び続けていたのが原因でないことは明らかだった。
慌てて外から視線を逸らす。常磐色の瞳が、広げられたノートを一心に見つめた。
気付かれた。授業中、余所見をしているのを見られてしまった。羞恥が、罪悪が、後悔が胸を満たしていく。
いや、勘違いかもしれない。校舎の中から見れば、壁や屋上にいる彼の存在はすぐに目に留まるだろう。しかし逆、無数の窓が存在する校舎の中から一生徒を見つけることなど不可能に決まっているのだ。そもそも、授業中に窓の外を見ている生徒などたくさんいるに決まっている。己に手を振ってくれたなんてことはあり得ないのだ。きっと、勘違いだ。
あぁ、それでも熱は収まらない。優しくしてくれている先生に、こんな不真面目な姿を見られたかもしれないのだ。恥ずかしいったらない。
現実から逃げるように、少女はそっと目を閉じた。
潤す飴玉/ノア+レフ
あおいちさんには「笑ってください」で始まり、「懐かしい味がした」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば3ツイート(420字程度)でお願いします。
「ほら、そんなに泣かないで。笑ってください」
困ったように笑いながら、少年は目の前の頬を拭う。肌に寄せられたハンカチの生地は柔らかで、洗剤の良い匂いが心地良かった。心落ち着くものを与えられているというのに、少女の目からはボロボロと涙がこぼれるばかりだ。
笑ってなんて無理だよ、と返そうにも、喉がつかえて形にできない。う、と嗚咽を漏らすばかりだ。そんな己を見ても、彼は呆れる様子無く流れる雫を拭ってくれた。
「飴でも舐めますか? 少し落ち着くかもしれません」
そう言って烈風刀は衣装のポケットに手を入れる。しばしして出されたのは、手のひらサイズの丸いケースだった。中には外装と同じ色をした小さな丸い飴がたくさん詰まっている。スーパーでよく見る甘いのど飴だ。
食べる、となんとか嗚咽交じりに返す。手を出してください、の言葉に、ノアは長い袖をまくり小さな手を出した。カラカラと音。手の上で振られた丸いプラスチックケースの中から、飴玉が一粒飛び出した。
転がり落ちそうなそれを急いで口の中に放り込む。程よい甘さとフルーツの香りが口の中に広がっていく。コロコロと舌で、頬で転がす。少しだけ涙が引っ込んだ気がした。
「……おいしい」
「それはよかった」
喉はちゃんとケアしないといけませんからね、と少年は笑いかける。喉。歌。ライブ。練習。たった一言から様々な言葉が引きずり出されていく。じわ、とまた涙が湧き出してきた。それもすぐ、少し濡れた布地に吸われて消えた。
「にあ、ちゃんが、わるい、の」
のあだってちゃんとれんしゅうしてるのに、と言い訳めいた、否、言い訳でしかない言葉を吐いてしまう。自己嫌悪に、少女はぎゅっと目を閉じた。雫が珠となって地面へと落ちていく。
元々内気で何事も不安がって自信があまり持てない己にとって、初めてのライブステージは不安でしかなかった。大丈夫かな、失敗しないかな、と弱音ばかり吐いてしまう己に、姉はいつだって大丈夫だと励ましてくれた。
それでも、限界というものはあるらしい。大丈夫だって言ってるでしょ、と今日は強い言葉がぶつけられた。そんなに不安ならもっと練習すればいいじゃん。続けざまにぶつけられた言葉は、小さな心を抉った。
練習ならいつもしている。放課後はもちろん、家に帰ってからも二人で歌詞や振り付けの確認は欠かさずにやっていた。その努力の積み重ねを知っているはずなのに。じわりとまた涙が浮かぶ。
違う。悪いのは己だ。いつも励ましてくれる姉に甘えてばかりだったのが悪いのだ。分かっているのに、飛び出たのは謝罪の言葉ではなく大粒の涙と、ニアちゃんのいじわる、という泣き言だった。
大好きな姉の顔が見たくなくて、走って、走って。気付いた時にはどこかの暗がりにいた。そして、たまたま通りかかった烈風刀に慰められる今に至る。
「二人がちゃんと練習しているのは皆知っていますよ。それこそ、ニアだって」
ニアが一番分かっているはずです、と少年は涙を流す少女の頭を撫でる。優しい手つきに、また透明な雫が溢れる。拭ってくれるハンカチはすっかりとぐしょぐしょになっていた。
これは秘密なんですけどね、と烈風刀は声をひそめる。口元に手を添える姿は内緒話をする時のそれだ。
「ニアもとっても不安みたいなんです。『大丈夫かな』っていつも尋ねてくるんですよ」
少年の言葉に、ノアはぱちりと大きく瞬く。あの姉が、いつだって元気で、自信満々で、己を励ましてくれる姉が不安に思っているだなんて。そんな姿、ちっとも見せなかったというのに。
「『大丈夫』と言っても怖いみたいで。でも、『ノアちゃんとなら大丈夫だよね』って最後には言うんです」
少女は再び瞬く。驚愕をあらわにした青に、碧は優しく笑いかける。大きな手が丸い頭をなぞった。
「ニアも、ノアと一緒で不安なんです。でも、ノアがいるから頑張っていられるのですよ」
何があったかは僕には分かりませんけど、きっと二人なら大丈夫です。
唱えるように言って、少年は可愛らしい頭を撫で続ける。慈愛に満ちた手つきだった。
ボロボロと、涙が次々と溢れ出る。嗚咽が喉を突いて出る。止めなければいけないのに、止まる気がしなかった。ひたすらに幼稚な姿を晒す。それでも、彼は飽きることなく頭を撫で、涙を拭ってくれた。
どれほど経っただろう、やっと嗚咽がおさまってくる。涙も少しずつながら姿を消しつつあった。
「落ち着きました?」
「……うん」
ありがと、れふと、とまだ濡れた声で礼を言う。いえ、とずぶ濡れの顔をハンカチのまだ乾いている部分で拭われた。
「飴、もう一個食べますか?」
泣いている内に飲み込んでしまったらしい。口内の甘い粒はいつの間にか無くなっていた。こくりと頷くと、また手のひらにまあるい飴が出される。すん、と鼻を啜って口に放り込む。食べ慣れた味だ。だって、いつも家で二人で舐めている飴なのだから。
「舐め終わったら戻りましょうか。きっとニアが探していますよ」
「……探してないよ」
「探してますよ。絶対に」
断言する烈風刀に、ノアは懐疑的な目を向ける。瞬間、バイブレーション音が聞こえた。ポケットに手を入れ、少年は携帯端末を確認する。連絡だろうか。そうだ、彼だって練習の最中のはずだ。なのに、こんなところで無駄に時間を使わせてしまった。もう一個湧き出た罪悪感が胸を塗り潰していく。
「……ごめんね、れふと」
「いえいえ。僕も休憩したいところでしたから」
練習続きじゃ気が張ってしまいますから、と少年は笑う。嘘ではないだろうが、本当でもないだろう。靄が晴れることはない。
カラリ。ケースが音をたてる。大きな手に飴玉が転がる。そのまま、大きな口に吸い込まれていった。シャープな輪郭をした頬が動く。美味しいですね、と少年は笑った。うん、と少女も頷いた。
食べ慣れた、姉との思い出が詰まった味が口の中を占めた。
新たな朝を待ちわびて/嬬武器兄弟
あおいちさんには「石段を駆け上がった」で始まり、「ほら、朝が来たよ」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば13ツイート(1820字)以上でお願いします。
参考:2023/1/1 日の出日の入り時間
一段飛ばしで階段を駆け上がる。足が振り上げられる度、手にしたビニール袋がうるさく音をたてた。ダン、と地を蹴る重い足音と、ビニールが擦れる音が暗闇に響く。
ようやく住まう部屋に辿り着き、雷刀はポケットから鍵を取り出す。かじかむ手でキーをさしこみ、錠を開ける。戸を開けると同時に、ただいま、と帰宅を告げた。
靴の踵を踏んで脱ぎ捨て、足早に廊下を進む。足下から這い寄る冷気に、ぶるりと身体を震わす。急いでリビングに繋がる扉を開くと、程よい温かさが迎えてくれた。
「ただいまー」
「おかえりなさい」
今一度帰宅を告げると、柔らな声が返ってくる。こたつに身体を潜らせた烈風刀は、みかんの房を片手にこちらを見ていた。机上には、剥かれて半分に割られたオレンジ色が置かれている。おそらく待っている間に食べていたのだろう。
「肉まん食う腹無くなるぞ」
「みかん半分程度で大袈裟ですよ」
そう言って彼はマグに口を付ける。淹れてから随分と経ったそれからは、柔らかな白い湯気は消え去っていた。もうかなり冷えているだろう。ビニール袋をこたつ机に置き、ちょうど空になったマグカップを二つ回収する。新しく淹れてくる、の言葉に、ありがとうございます、と礼が返された。
電気ケトルに目分量で水を入れ、インスタントコーヒーをこれまた目分量でマグへと放りこむ。しばし待ち、カチンと音をたてたケトルから沸きたての湯を入れる。あっという間に熱いコーヒーの完成だ。肉まんに合うかは微妙なところではあるが、手軽に飲める温かいものといえばこれである。
マグを両手にリビングへと帰る。弟は相変わらずみかんを食べていた。夜中、それも新年明けてばかりのテレビはあまり興味を引くものはやっていなかった。きっと手持ち無沙汰なのだろう。
ほい、と弟の目の前に青いマグカップを差し出す。礼の言葉とともに、彼は湯気があがるそれを両手で受け取った。ぐるりと回り込み、彼の隣の面に腰を下ろす。分厚いこたつ布団の中に足を入れると、心地良い温度が末端を包んだ。ほぅ、と思わず溜め息が漏れ出る。
先ほど置いたばかりの袋を漁る。中から取り出したのは、肉まんの包み二つだ。夜中に無性に食べたくなり、コンビニへと走ったのだ。お蕎麦とみかん食べたばかりでしょう、と小言を言う弟に、別腹とだけ返して外へと出た。瞬間、身を包んだ冷気に後悔を覚えたが、それ以上に食欲が勝った。衝動がままに足を動かし、二つ買ってまた走り、今に至る。
冬真っ只中の空気に晒されていたというのに、丸い中華まんはまだ温かだった。赤で飾られた白いパッケージを一つ、無言で手渡す。ありがとうございます、とまた礼の言葉。柔らかな饅頭はそっと両手で受け取られた。
止めるテープを取り、下に付いた敷き紙を剥がす。いただきます、と二人分の声。同時に大きな口でかぶりつく。温かな温度と皮の甘み、中に詰められた肉の旨味が舌を楽しませた。んめぇ、と思わず声を漏らす。
「やっぱ冬は肉まんだよなー」
「さっきまで『冬はみかんだ』と言ってたではないですか」
「どっちも」
呆れた調子で笑う弟に、兄はケラケラと笑う。言葉を交わすのもそこそこに、互いに黙々と肉まんを食べる。こぶりなそれはあっという間に無くなった。ごちそうさまでした、と重なる声。くしゃりと丸められた紙と、丁寧に畳まれた紙が簡易的なゴミ箱に入れられた。橙が重なった箱の中に、白が咲く。
「今何時ー?」
「もうすぐ六時ですよ」
「初日の出って何時だっけ」
朱の問いに、碧はえっと、とこぼして携帯端末を操る。しばしの沈黙。七時頃のようです、と液晶画面に表示されているのであろう情報が読み上げられた。
「まだまだじゃん」
「起きていられるんですか?」
「らくしょー」
とは言ったものの、本当はもうかなり眠い。夜も遅いことはもちろんだが、肉まんでかなり腹が膨れてしまった。普段ならばこれ程度では腹は満たされないが、生憎昨晩お腹いっぱい蕎麦を食べ、今の今までみかんをだらだらと食べていたのだ。胃はかなり満たされていた。少し遠いコンビニまで走っていった疲れも今更になって襲ってくる。疲労感と満腹感が睡魔を誘う。けれども、せっかくここまで起きたのだ。何としてでも初日の出を拝みたい。
みかんを食べ、携帯端末をいじり、時間が過ぎるのを待つ。睡魔は相変わらず居座り、眠りへと誘ってくる。気付けば、こくりこくりと船を漕いでいた。
寝ないでくださいよ、と肩を叩かれる。寝ねーよ、という返事は思った以上にふにゃりとしていた。もごもごと口を動かす様子に、苦い笑いが返された。
シャ、とカーテンが開けられる音。窓の向こうを見やると、真っ黒だった空はほのかに色を取り戻しているように見えた。
「ほら、もう少しで新年の朝が来ますよ。頑張ってください」
全ては三文字に帰結する/恋刃
葵壱さんには「最初は何とも思っていなかった」で始まり、「そっと笑いかけた」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば5ツイート(700字程度)でお願いします。
最初は何とも思っていなかった。否、多大な喜びすら覚えていた。
だって、大好きな姉と大好きな親友が仲良くなってくれるだなんて、嬉しいに決まっている。好きな人が好きな人のことを好ましく思ってくれるのだ。これほど嬉しいことはない。
と、思っていたのだけれど。
「――それで、ミカエルが走っていっちゃって。慌てて追いかけたんです」
「あら、大変だったのね」
「でも、そのおかげで知らない綺麗な花壇を見つけたんです。満開のお花で埋め尽くされてて、とっても綺麗で。ミカエルが走っていかなかったら絶対に知らなかったから、よかったなぁって」
えへへ、と奈奈はどこか面映ゆそうに笑みを浮かべる。たしかな喜びをにじませたそれに、紅刃は穏やかに素敵ね、と微笑みを浮かべた。
穏やかな光景に反し、恋刃はわずかに目を眇める。平静を取り繕うとするも、整った細い眉はかすかに寄せられ眉間に薄く皺を作っていた。
大好きな姉と大好きな親友が楽しく会話している。仲良くしてくれている。幸せな光景だ。喜ばしい現実だ。だというのに、このところは幸福に満ち満ちたそれを眺めると胸の内を得体の知れない何かが広がっていくのだ。暗いそれは小さな心を覆い影を落とす。胃もたれをしたような不快感が胸のあたりを満たす。解が無い問いを目の前にしたようにもやもやとする。訳の分からない現象だ。だって、好きな人と好きな人が仲良くしているのは幸せなのに。
「恋刃?」
愛しい声が己の名をなぞる。そこでやっと、己が俯いていることに気付いた。
「はっ、はい。何でしょうか、お姉さま」
「奈奈ちゃんが持ってきてくれたチョコ美味しいわよ。食べないの?」
「たっ、食べます!」
姉が差し出した箱から、妹は急いでチョコレートを一つ取ってかじる。チョコレートの豊かな風味と、ラズベリーの爽やかな香り、少しビターな味が口内に広がった。薄く険しさをまとった深緋の目が、ぱぁと輝いた。
「とっても美味しい!」
「よかった。恋刃も気に入ってくれて」
赤い少女の歓喜に満ちた声に、七色の少女はふわりと笑みをこぼした。鮮やかな多色の瞳がふわりと弧を描く姿に、心臓がドキリと音をたてる。美味しい、と誤魔化すように言って、手にしたそれを食べきった。
「な、な。ねぇ、奈奈」
手を拭き、隣に座る少女のワンピースの裾を引く。どうしたの恋刃、と不思議そうな視線と声がこちらに向けられた。
「このチョコ、どこで買ったの?」
「この間ショッピングモールに新しいお店ができたでしょ? そこで買ったの」
ここ、と少女は箱の片隅にある紙片を取る。初めて見る店名だ。本当にオープンしたての店なのだろう。ねぇ、とほのかに揺れた調子の声。裾を握る指に温かなものが触れた。
「今度一緒に買いに行かない? 奈奈もこの味好きだから、もっと食べたいの」
「……もちろん! 連れてって!」
奈奈の誘いに、恋刃は喜色満面の笑みを浮かべる。触れた手を取り、握り返した。目の前の虹色が、穏やかな弧を描いた。
「よかったわね」
ふふ、と呼気のような笑声。姉だ。そうだ、この場には姉もいたのだ。親友との約束に浮かれて忘れていた。恥ずかしい姿を見せてしまった、と少女の頬に髪と同じ色が浮かんだ。
「はい」
こちらに向けられていた虹色が、穏やかに細まった紅色へと向けられる。瞬間、どろりとしたものが胸に湧き上がった。訳の分からない感覚に、思わず身体が強張る。
何故だ。今この瞬間まで幸せに包まれていたのに、何故こんなものが胸を満たすのだ。理由なんて皆目見当が付かない。正体も欠片も分からなかった。
「次のお休みで大丈夫?」
声にはっとする。きゅ、と手を握った親友は、ほのかに頬を染めこちらを窺っていた。ドロドロとした何かが胸を掻き回す。美しいそれが、何故だか直視できない。
「えぇ、そうしましょう」
少女は固さの残る顔でそっと笑いかけた。
畳む

甘い幸せ分けっこ【ハレルヤ組】
甘い幸せ分けっこ【ハレルヤ組】ハレルヤ~~~~~~~~Cafe VOLTEにケーキ食いに行ってくれ~~~~~~~~~(発作)
というわけでハレルヤ組がケーキ食べるだけの話。
ボックス席の広いテーブルの上に音も無く食器が置かれていく。よく磨かれた小ぶりなフォーク、シンプルながらも上品なデザインをした皿、温かさを感じられる白を鮮やかな赤で縁取ったカップ。それぞれが目の前に並べられた。空になった銀の盆を脇に抱えたウェイトレスは、ごゆっくりどうぞ、の一言と伝票を残し美しい足取りで去っていった。
はわぁ、と感動と歓喜に満ち溢れた声が向かい側から聞こえる。並べられた輝くような白い皿、その上に載せられた美しいケーキを前に、少女は真ん丸な可愛らしい目をキラキラと輝かせていた。つやめく薔薇輝石の瞳が、フルーツでカラフルに彩られたケーキを一心に見つめる。たおやかな手は、震える心と湧き上がる喜びを表すように笑みを形作る口に添えられていた。
ぱちん、と小さな音をたてて手が三対合わさる。いただきます、と広い席に元気な三重奏が響いた。
華奢な指がナプキンの上に置かれたフォークを手に取る。銀色が、色彩鮮やかなケーキにそっと差し込まれる。ナパームでつやめく果実とそれらを支えるカスタード、アーモンドクリーム、タルト生地が一口サイズに切り分けられた。ブルーベリーといちごが輝く一欠片を慎重に刺し、桃は小さな口にカトラリーを運んだ。赤い口内に銀の先端とケーキが消える。もぐもぐとまろく柔らかな頬がゆっくりと動く。んー、と喜びで溢れかえった声が閉じた口から漏れ出た。
「美味しいデス~!」
頬に手を添え、レイシスは幸せ色に染まりきった声をあげる。甘い物が大好きな彼女にとって、ケーキは幸せをそのまま形にしたような素敵なものだろう。新鮮なフルーツがたっぷり載った贅沢な代物は、彼女の心を十二分に満たしたようだ。
可愛らしい様子に薄く笑みを浮かべつつ、烈風刀も同じくフォークを手に取りケーキを切り分ける。きめの細かい薄い黄色のスポンジと真っ白なクリーム、その中に覗く赤いいちごに銀が刺される。口に運ぶと、バニラの甘さがふわりと香る。濃厚ながらもしつこさを感じさせないミルクの風味、砂糖の穏やかな甘みが舌に広がった。綿飴のようにすぐに溶けてしまいそうなほどふわふわなスポンジと少し固めに立てられた生クリームのなめらかな舌触りが気持ち良い。己でもケーキを作ることはいくらかあるが、こんなにも軽く、それでいて満足感が得られるような代物を作ることなど不可能だ。学園の女子たちに絶大な支持を得ているのも納得の味であった。
ケーキ食べに行きマセンカ?
控えめで可愛らしい誘いが来たのは三日前のことだ。世界の更新も無事終わり、今はちょうど運営業務が落ち着いてきた頃合いである。ようやく自由な時間を手に入れられてきたからこその言葉だろう。どうデショウカ、と伺う瞳には少しの不安が膜張っていたことを覚えている。
もちろん、兄弟二人で二つ返事をした。好きな女の子と出掛けられる。それも『カフェでケーキを食べる』だなんてデートのようなことを、だ。絶対に逃したくない、人生で一番逃すべきではない機会である。そもそも、この愛する少女の提案を断るなどという選択肢は双子の中に存在していなかった。
そうして足を運んだCafe VOLTE。ショーケースでケーキを選んで食べる今に至る。
ショートケーキをもう一口食べ、少年は続いてカップに手を伸ばす。中で湯気を立てる黒にそっと息を吹きかけ、赤い縁に口を付けた。コーヒー特有の香ばしい匂いが鼻腔をくすぐる。舌の上に深い苦みと少しの酸味が広がっていく。ケーキの甘みが洗い流されていく心地だった。香りも味も、家で飲むものとは段違いだ。さすがカフェラテを名物にしているだけある。
「烈風刀、烈風刀!」
ハイテンションな声が己の名を呼ぶ。カップを置き隣を見ると、そこには少女と同じくらい目を輝かせた兄の姿があった。手に持ったフォークの先には黒いものが刺さっている。彼が頼んだのはガトーショコラだっただろうか。少し遠い位置から、それも一口分しか見えないというのに、生地がみっちりと詰まっているのが分かる。きっととても濃厚な味がするだろう。
「これすっげーんめぇ! 食ってみろよ!」
ほら、あーん。雷刀は手にした食器、突き刺したケーキをこちらへと伸ばしてくる。否、突きつけるといった方が正しい勢いと距離だ。あまりの近さにか、チョコレートの香りが鼻を掠める。誘われるように素直に口を開き、シックな黒を迎え入れた。
瞬間、先ほどの比ではないほどのチョコレートの香りと風味が口内に満ちた。少し固い歯触りながらも、舌に載せればゆっくりと溶けていく。生チョコレートとよく似た食感をしていた。驚くほど濃厚な舌触りと味わいだ。やはりここのケーキは上等だ。それでいて学生でも手が出せるギリギリの値段なのだから恐ろしい。
「美味しいですね」
「だろ? すっげぇうめぇ!」
柔らかに解けるそれを飲み込み、碧は穏やかに声を紡ぐ。味を、感情を共有できたのが嬉しいのか、赤はニッと笑った。マジうめぇ、と彼はまた黒を切り分けて食べる。まだ丸さを残した頬がもごもごと動いた。
「こちらも美味しいですよ。食べますか?」
「食べる!」
弟は兄の方へと皿を差し出す。もらってばかりでは申し訳が無い。それに、彼のことだからいつも通り後々一口ちょうだい、とねだってくるのは分かりきっていた。だったら先に食べさせてしまった方がいい。
問いに元気な声が返される。肯定の語を紡いだ口が、あ、と大きく開かれる。子どもめいた姿にはいはい、と呆れた調子で漏らし、碧い少年はケーキを切り分ける。スポンジと生クリーム、スライスされたいちごがカトラリーに載せられた。隣へと伸ばされた銀食器は、すぐに健康的な口に挟まれた。薄黄色が赤の中に消える。わずかに紅潮した頬が動き、喉が動く。朱い目がぱちりと瞬いた。
「こっちもめっちゃうめぇ! ふわふわ!」
丸い目を更に丸くし、朱い少年は喜び溢るる声をあげる。どうやらかなり気に入ったようだ。味覚の近い己が好ましいと思ったのだ、兄も気に入るのは納得である。それ以上に、彼は何だって美味しく食べるタイプなのだけれど。
はわぁ、と溜め息にも似た可愛らしい声が落ち着いた音楽流れる店内に落ちる。確かに聞こえた愛おしい音に、烈風刀はバッと発生源へと顔を向ける。視界にきょとりと目を瞬かせるレイシスが映った。撫子色の瞳は、向かいの席に座る己たち兄弟をしっかりと見つめていた。
ビクン、と肩が跳ねる。そうだ、今はレイシスも一緒だったのだ。家の中と一切変わらぬ調子の兄につられ、自然に食べさせられてしまった。食べさせてしまった。兄弟で食べさせあうなんて光景を彼女の前で繰り広げてしまった。ただでさえ人に見せるような姿ではないというのに、よりにもよって想いを寄せる女の子の前で家での癖をそのままやってしまった。幼稚な姿を見せてしまった。焦燥と羞恥、多大なる後悔が上等な菓子で潤った心を荒らしていく。食べた物以上の質量が胃の腑に落ちる感覚がした。
「二人だとそういうことできていいデスネ」
表情を強張らせる烈風刀を、気にせずケーキをを食べる雷刀を眺め、レイシスは穏やかに笑む。微笑ましさがよく出たそれの中に、言葉にしがたい寂しさがうっすらと見えた。
世界の誕生と同時に生まれた少女は、長い間一人きりだった。小さな妖精が常に寄り添ってはいたものの、同じヒトの形をした存在と出会うまで随分と時間が掛かってしまったという話は聞いている。二回目のバージョンアップが行われた世界には多くのヒトが増え、彼女にも友人がたくさんできた。けれども、立場上運営業務を優先させねばならない桃は遊びに出掛ける機会もあまり多くはない。世界に一番近い女の子は、世界のためにその身を犠牲にしていた。
そんな彼女には、食べ物を分け与えあう、特に食べさせあうなんて経験はあまり無いのだろう。否、そもそも己たち兄弟がおかしいのだ。皿を交換するだけで済む行為を、わざわざ一口食べさせてやるなんてことは普通無いのだ。長い間一人で暮らし、一人で生きてきたナビゲーターは違和感を覚えていないようだけど。
「ん? レイシスも食う?」
能天気な声が薄く陰った空気を打ち払う。もう三分の一は姿を消したチョコレートケーキに、フォークがガッと勢い良く突き立てられる。大きく切り分けた塊を刺した銀食器が、少女の前に差し出された。
「ほら、あーん」
朱い瞳が桃を見据える。突如突き出されたそれに、レイシスはぱちりと瞬きをした。美しいラズベリルが丸くなり、キラキラとした輝きを取り戻す。はわ、と漏れた声は少しの驚きといっぱいの喜びで彩られていた。
「ハイ! アーン」
意味を理解した桃は大きく口を開く。あーん、と言いながら雷刀はフォークを伸ばす。リップで淑やかに飾られた唇が閉じ、銀の先にあった黒が姿を消した。美しい輪郭をした頬がもごもごと動く。モルガナイトの中に宿る光が更にまばゆく輝きだした。
「美味しいデス!」
「だろ? だろー?」
感動の声を漏らす薔薇色の少女に、朱い少年はフォークを振って返す。満面の笑みを咲かせる少女を眺める笑顔はどこか自慢げだ。
はわぁ、と感嘆の声を漏らす桃が銀を手に取る。瑞々しいフルーツがたっぷり載ったタルトが手早く切り分けられた。一口サイズになったそれを崩れないように器用に載せる。照明を受けたナパームがつやつやと光った。
「ワタシのタルトも美味しいデスヨ」
ハイ、アーン。少年の真似をして、レイシスはフルーツタルトを載せたフォークを差し出す。八重歯で飾られた口の端が嬉しげに上がった。あーん、と復唱し、雷刀は小ぶりなそれを一口で食べる。頬が動き、喉が動く。食物を受け入れた口が笑みを形作った。
「フルーツうめぇな!」
「カスタードとマッチしてるんデスヨネ。甘くて爽やかで美味しいデス!」
朱と桃はきゃっきゃとはしゃぐ。 その様子を横目で眺める碧は、複雑な色を宿していた。
愛する少女が楽しく時を過ごしているのは、この世で何より素晴らしいことだ。けれども、その相手が兄だというのが不服で仕方が無い。片想いする少女と恋敵が仲良くケーキを食べさせあう光景を目の前で繰り広げられて、まだまだ発展途上の心が平常でいられるわけがなかった。幸福を嫉妬が食い荒らしていく。荒ぶ心を落ち着けようとコーヒーを一口。何故だか苦みばかりが舌の上を支配した。
ちらりと兄へと目をやる。少女へと向けられていた目が逸れ、紅玉と蒼玉がかち合う。瞬間、喜びの輝きに溢れた真紅がニマリと細められた。口の片端が吊り上がり、半分笑みを覗かせる。余裕に満ちた笑顔である。何とも腹立たしい笑顔であった。愛おしい少女の前でなければめいっぱいに顔をしかめていただろう。表情を歪めそうになる筋肉を何とかコントロールするも、口の端がひくりと引きつるのだけは抑えられなかった。
「アッ、烈風刀も食べマスカ?」
弾んだ声が己の名をなぞる。どうにか普段通りの表情を作り、少年は顔を上げた。そこには、フォークを片手に笑顔を咲かせるレイシスの姿があった。ケーキのために用意されたカトラリーには、キウイとオレンジがつやめくタルトが載せられている。細い腕がこちらへと伸ばされた。
「ハイ、アーン」
ニコニコと笑みを浮かべ、桃は言う。差し出されたケーキ。『あーん』の声。先ほどの兄に与えていた姿と同じだ。つまり、己にもケーキを食べさせようとしているのだ。
バクン、と心臓が大きく脈打つ。爆発してしまいそうなほどの動きだった。思わず胸を押さえそうになるのを必死に堪える。バクン、バクン、と臓器が騒がしい音をたてて収縮を繰り返す。あまりにうるさいそれを制御しようにも、どうにもできなかった。
食べている物を一口分け与える。そんなの、幼い頃から兄弟でよくやっているのだから慣れっこだ。けれども、相手がレイシスとなれば別である。恋心を募らせる少女に、直々に食べさせてもらえる。そんな夢のようなことが今まさに起こっているのだ。思春期真っ只中、片想い最中の高校生の心臓が耐えられるわけがない。
身体が強張る。目が見開かれる。顔が熱を持つ。反対に、指先は氷水に浸したように温度を失っていく。好きな女の子に『あーん』をしてもらえる。夢のような現実だ。受け入れたい。掴み取りたい。恥ずかしい。あまりにも恐れ多い。欲望と理性がぐちゃりと混ざり合う。常は冷静であろうとする頭はもうぐちゃぐちゃになっていた。
逡巡、烈風刀は小さく口を開ける。ここで断ってしまっては、あの優しい少女は可愛らしいかんばせを曇らせてしまうだろう。判断に時間が掛かっている今ですら、彼女を不安にさせているかもしれない。愛おしい人を悲しませることなどあってはならない。絶対に回避すべきだ。
あーん、と少女と同じ言葉を口に出す。声は少しつかえ、響きも揺れていた。潤った唇もぷるぷると細かに震えている。緊張が如実に表れていた。緊張するなと言う方が無茶な状況なのだから仕方が無い。
ハイ、アーン。開いた口に、フォークが、ケーキがそっと入れられる。すぐさま閉じ、少年は身体を銀食器から、少女から距離を取った。心臓は依然うるさく鼓動する。どうにかケーキを咀嚼するが、生地を噛み締める歯すら震えているような気がしてたまらなかった。
「どうデスカ?」
「お、美味しいですね」
尋ねる桃に、碧はぎこちない声と笑みを返す。こんな凄まじい緊張の中、味なんて分かるわけがない。ケーキを味わう余裕なぞ欠片も残っていなかった。ほとんど塊のまま胃の腑に落ちていったそれに少しの罪悪感を抱く。本来は舌を楽しませる素敵な菓子だというのに、己の心が矮小なせいでただ飲み込むだけになってしまった。きちんと食べたというのに、食べ物を粗末にしてしまった気分だ。
震える手を制御し、コーヒーを飲み下す。苦みが混乱する脳味噌に活を入れた。少しずつ静まっていく心と頭の中、何かがよぎる。何だ、と思わず思考をそちらに向けてしまう。正体は疑問だった。あのフォークはレイシスが使っていたものだよな、という当たり前の事実が疑問として姿を現した。
レイシスが使っていたフォークで食べさせてもらった。レイシスが使っていたフォークに口を付けた。つまり。
身体が固まる。カップを下ろそうとした手が空中で止まる。浅葱の目がこれでもかと見開かれた。心臓がまた騒ぎ立てる。フリーズしたはずの脳味噌は、間接キス、と俗称を叫んだ。
いや、よく考えろ。あのフォークに直前に触れたのは兄では無いか。食べ物を載せた先端部分に口を付けたのは兄だ。つまり、兄との間接キスである。いつも通りだ。変わらぬことではないか。大丈夫、いつも通り、と頭の中で何度も繰り返す。刷り込んで刻みつけて思い込ませる。疑問を抱く余地を丁寧に塗り潰して無くしていく。
不自然な動きながらも、どうにかカップをソーサーに置く。ふぅ、と密かに息を吐いた。少し下がった視界、目の前に食べかけのショートケーキが映る。そういえば、食べさせてもらったのに何も返さないのはいかがなものだろうか。それも、相手はケーキが大好きな女の子である。きっと、選べなかった、自分と違うものも気になっているだろう。色んなものを楽しみたいはずだ。
「こちらも美味しいですよ。一口どうぞ」
「エッ、いいんデスカ?」
剥かれたオレンジを頬張る少女は、ぱぁと顔を輝かせる。えぇ、と柔らかに答え、烈風刀はレイシスの前へと皿を差し出そうとした。
つやつやの唇が開く。血の通った赤い口が眼前に晒される。あ、と可愛らしい声が大きく開かれたそこから聞こえた。
突然のことに、少年はきょとりとした様子でその顔を眺める。何故フォークを握らないのだろう。何故口を開けるのだろう。聡明な頭は答えを弾き出す。意味をはっきりと理解する。穏やかに綻んでいた顔が瞬時に固まった。
口を開けて待つ。つまり、食べさせてもらおうとしている。
ケーキ皿に触れていた指がピクリと震える。そのまま手を引っ込めてしまいそうになるのを何とか耐えた。
彼女には一口なんて言わず好きなだけ食べてほしいのだ、このまま皿を押して全て差し出すのが正解に決まっている。けれども、ここで無視をするような対応をしては彼女は悲しんでしまうのではないだろうか。やってもらえなかった、と寂しがってしまうのではないだろうか。嫌がられた、と勘違いしてしまうのではないだろうか。様々な憂慮の中、本能が囁く。何を御託を並べているのだ、お前がやりたいだけだろう、と。
ギリ、と奥歯を噛み締める。固まった指を動かし、皿の上に載せられたフォークを手に取った。ピースケーキの太い部分、大粒のいちごとたっぷりの生クリームが載った場所を切り分ける。崩れてしまわないように慎重に刺し、持ち上げる。震えをどうにか押さえ込みながら、目の前の少女へと銀色を伸ばした。
「あ、あーん……」
ただ差し出すだけだったはずが、思わず声が漏れてしまう。いや、彼女も兄もこう言って食べさせていたのだ。言う方が自然である。復唱しただけと判断できる程度の響きだ。理性がそれらしい言葉を並べ立てる。本能は意地悪げな表情でその様を眺めていた。
可憐な口に、赤いいちごと白いクリーム、黄色のスポンジが近づく。開いたそこが閉じられ、ぱくりとフォークを口に含んだ。見計らって碧は即座に身体を引く。勢いのあまり背もたれに当たり、ソファが揺れた。
柔らかな曲線を描く頬が動く。白く細い喉が上下し、含んだものを嚥下していく。弧を描いていた目がぱっちりと開かれ、また宝石のようにキラキラと輝きだした。
「いちご美味しいデス! スポンジもふわふわデス~!」
あげる声は今日一番の感動がにじんでいた。どうやら、かなり彼女好みの味だったらしい。可愛らしい姿に、動悸と表現した方が相応しい動きをする心臓が落ち着きを取り戻していった。
「もう少し食べますか?」
わずかに身を乗りだし、今度こそぐっと皿を押し少女の真ん前へと差し出す。もう己には手が、フォークが届かないほどの位置だ。また食べさせるような事態にはならないだろう。
「いいんデスカ? あとちょっとしかありマセンヨ?」
「美味しかったんでしょう? 好きなだけ食べてください」
鴇色の瞳が碧とケーキを行き来する。どうぞ、と背を押してやる。しばしして、いただきマス、と控えめな声とともにフォークが伸ばされた。クリームでコーティングされた生地を小さめに切り分け、少女は口に運ぶ。少しの遠慮と不安がにじんでいた顔は、瞬時に明るいものになった。桃の睫に縁取られた目が閉じ、大きな弧を描く。んー、と漏らす声は幸せをそのまま音にしたような響きをしていた。可愛らしいの一言に尽きる姿に、少年は頬を緩めた。
もう一口控えめに食べ、レイシスはありがとうゴザイマシタ、と皿を持ち主へと返した。どういたしまして、と白い皿を引き寄せ目の前へと帰還させる。柔らかな白と黄にいちごの赤の差し色がよく映えていたケーキは、残り三分の一ほどになっていた。あまり時間を掛けて食べては表面が乾いてしまう。美味しい物は美味しい状態で食べるべきなのだ。フォークを握り、筋の浮かぶ手が口にケーキを運ぶ。閉じようとしたところで、はたと動きが止まった。
先ほどレイシスにケーキを食べさせた。己のフォークで食べさせた。つまり、このフォークはレイシスの口が付いたもので。はっきりと触れたもので。
間接キス。今度こそ、レイシスとの紛うことなき間接キス。
動きが止まる。一気に冷凍されたかのような固まり方だった。翡翠の目がふるふると震える。脳味噌の中で何かがうるさく騒ぎ立てた。
どうしよう。どうするべきなのだ。いつだって即座に最適解を弾き出す利巧な頭は、混乱の渦に陥り機能を停止していた。思春期の男子高校生には刺激が強すぎる事実である。仕方の無いことだ。
間接的なものとはいえ彼女の口と触れ合うなぞ、あってはならないことだ。そういうことは大切に大切にしなければいけないのだ。けれども、このままではケーキが食べられない。皿の上のものは全てレイシスに分け与えるという手があるが、今まさに口に運ぼうとフォークに刺したこの一口は絶対に食べなければいけない。フォークに口を付けなければいけない。レイシスが触れた、このカトラリーに。
機能を再開するも混乱したまま迷走する頭は、フォークを一旦置く、という答えを弾き出した。カチャリと食器と食器が高い音を奏でる。銀色の上には、ケーキの欠片が載せられたままだ。
平常心、平常心。まじないのように繰り返し、烈風刀はコーヒーカップに手を伸ばす。もう冷めつつあるコーヒーは、まだ豊かな香りを漂わせていた。惑いに惑いとっちらかった頭を、心地良い香りが落ち着けていく。少し含み、苦みで思考をリセットしようとした。
あれ、と落ち着きを取り戻し始めた頭が声をあげる。脳内のそれにつられ、碧い目が向かい側に向けられた。
視界に映るレイシスは、楽しげにケーキを頬張っていた。もちろん、フォークで。先ほど己が口を付けたフォークで。
つまり。
ぐ、と思わず喉が狭まる。カップを持ち上げた手がビクンと跳ねる。その拍子に、口内の黒い液体が食道ではない部分へと飛んで入った。迫り上がってくる感覚に、急いで食器を置き口に手を当てる。ゲホ、ゴホ、と湧き上がる咳を手で押し止めた。
「えっ、何? だいじょぶか?」
「大丈夫デスカ?」
「だ、いじょうぶ、です……」
突如むせ返った烈風刀に、レイシスと雷刀は驚きの声をあげる。整理反射をどうにか抑えながら無事を答える。大丈夫なわけがなかった。身体も心ももうぐちゃぐちゃだ。咳き込みながら、少年は自己嫌悪に陥る。たかが間接キス程度でこんなに動揺するなど、どれだけ初心なのだ。本当に高校生か。咳と呆ればかりが湧いて出た。
むせる様子が落ち着いてきた頃合い、桃と朱は心配げな瞳を元に戻し、残ったケーキを食し始める。最後の一口を名残惜しげに味わい、二人はフォークを置いた。ごちそうさまでした、と食事の挨拶が輪唱のように奏でられる。美味かったー。美味しかったデスー。コーヒーとカフェラテを味わう口から、満足げな声があがった。
どうにか常の様子を取り戻しながら、碧はコーヒーをちびちびと飲む。二人が食べ終わったのだから、己も早く食べなければいけない。けれども、未だケーキに、このフォークに手を付ける勇気は無かった。
「…………アノ」
控えめな声が上がる。炎瑪瑙と苔瑪瑙が上がり、正面を見る。目の前の桃は、可愛らしい瞳をうろうろと泳がせていた。頬にはわずかに紅が浮かんでいる。チークの人工色ではない、血の色だ。
「……ショートケーキ、とっても美味しかったノデ……、もう一個食べてもいいデスカ?」
口元に手を当て、少女はことりと頭を傾いだ。ツインテールが揺れる。髪と同じ色をした眉はわずかに下がり、八の字を描いていた。浮かべる笑みは先ほどまでの元気いっぱいのものではなく、少し困ったような、恥ずかしげなものだ。
彼女はよく食べる。それはもうよく食べる。平均よりも食べる量が多い己たちの倍は余裕で食べるほどの健啖家だ。そして、甘い物は彼女の大好物だ。もう一つ求めてしまうのは当然と言ってもいいことである。ここのケーキはあまりにも美味しすぎるのだ。
「オレももう一個食べよっかなー。今度はふわふわなやつ」
ほら、どいてどいて、と窓側に座っている雷刀は烈風刀の身体を横から押す。弟は大人しく退いて、兄を出してやった。肯定を意味する声に、少女は表情を明るくする。一緒に行きマショウ、と彼女もソファから身を下ろし立ち上がった。ロングスカートの裾がふわりと広がる。
行ってきマスネ。待っててなー。言葉を残し、二人は飲食スペースからショーケースへと駆けていく。席にはケーキメニューも備え付けられているのだからそれを見て頼めばいいだろうに。いや、きっとケースの中に整列した数々のケーキを眺めながら選ぶのが良いのだろう。その方が絶対に目も心も楽しいのだから。
カップの中身を飲み干し、烈風刀は息を吐く。碧い瞳は、白い皿へと向けられた。ケーキが五分の一は残った皿に。銀のフォークが横たわる皿に。
きょろきょろと辺りを見回す。もちろん、桃の姿も朱の姿も無い。そんなことは分かりきっているのに、何故だか確認してしまう。やましいことをするように周りを窺ってしまう。怪しいにも程がある姿だ。けれども、小さな心は周りが気になって仕方が無かった。
震える手でフォークを掴む。ふぅ、と息を深く吐く。吸って、吐いてをしばし繰り返す。こくりと息を呑む。意を決し、銀のそれを、ケーキが一口載ったそれを口へと運んだ。
舌の上に優しい甘みが広がった。
畳む
#レイシス #嬬武器雷刀 #嬬武器烈風刀 #ハレルヤ組