No.47, No.46, No.45, No.44, No.43, No.42, No.41[7件]
積み重なる温度【ライレフ】
積み重なる温度【ライレフ】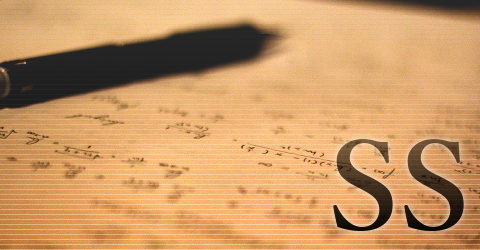
30日CPチャレンジなるものに挑戦したいと始めたはいいが単独カプで毎日とか無理なので暇を見て少しずつ。
ということでライレフで【01.手を繋ぐ】
通常進行でお送りします。
カリカリと紙の上をペンが滑る音が部屋に響く。もはや物置と化していた学習机の上は綺麗に片付けられ、教科書に参考書、ノートやプリント類が積まれていた。教科別にまとめられたそれらは、全て重ねればなかなかの高さになるだろう。
目の前の問題を解く合間、烈風刀は横目で隣に座る雷刀を見る。力強くペンを握ったその手は予想通り止まっており、赤い目は前に広げられたノートと参考書を往復していた。自力で解く気があるだけまだマシか、と烈風刀は諦めにも似た感情を抱く。いつものことだ。
月も幾度か変わり、そろそろ定期考査の時期が近づいてきた。毎度毎度成績表を赤く染め上げる雷刀だが、今回ばかりはそれを避けようと自ら烈風刀に教えを乞うてきた。どうも初等部の子らに本気で学力を心配されたのがきいたらしい。理由はなんであれ、自発的に勉強しようとする姿勢は評価すべきだろう。烈風刀は喜んで了承したのだった。
そうして、雷刀の部屋でテスト勉強をしているのだが。
「わっかんねー」
情けない声をあげ、雷刀は机に突っ伏した。集中力が切れてしまったようだ。まだもった方だな、と烈風刀は壁にかけられた時計を見て考える。彼にしてはもった方だが、常人のそれよりもずっと短い。はぁ、とわざとらしく嘆息し、烈風刀は手にしたシャープペンシルで俯せた赤い頭を軽く叩いた。
「まだ半分も解いていないでしょう。もう少し頑張ってください」
「だってわかんねーもん」
諌めるような烈風刀の声に雷刀はふて腐れたような声を上げる。どれが分からないのだ、とその頭を上げさせ彼が立ち向かっている問を見る。力強く記された文字は単純な計算式で導き出される箇所で途切れていた。そもそも、前提として求めるべき最初の式が間違っている。これではいつまでたっても正しい解に辿りつけないだろう。
「ここはこの公式を使えばいいのですよ。そもそも、最初の計算が間違っています。四則演算ぐらいはしっかりやってください」
「へーい」
やる気のない返事をして雷刀は消しゴムを動かす。シャープペンシルを持ち直し指摘された部分を修正するが、その手はすぐに止まってしまった。
「……れふとー」
「まずは教科書を読んでください」
雷刀は乞うような声と視線を烈風刀に向ける。しかし、返ってくるのは冷たい言葉だけだ。烈風刀自身もテストに向けて対策をしなければならないのだ。彼ばかりに構ってはいられない。教科書に載っている基本的な問題程度は自力で解いてもらわねば困る。
ガタン、と音をたてて雷刀が立ち上がった。一体なんだ、と目を眇め彼を見上げる。視線の先の彼の目は不自然に泳いでおり、口元は妙に引きつっていた。
「喉渇いたからコーヒー持ってくる!」
「ここにありますよ」
急いで部屋を出ようとする雷刀の前にダン、と音をたててコーヒーポットを置く。何かしら理由をつけて逃げようとするだろうと予測して、事前に用意しておいたのだ。その強い音故か、彼の身体がビクリと大袈裟に跳ねた。ギギギと音をたてそうな硬い動きでポットを見るその表情は、嘘が露見した時のような苦々しいものだ。
「もちろん、砂糖とミルクも用意してあります。お茶もありますからわざわざ持ってくる必要はありません」
「なんでそんなに用意がいいんだよ……」
「誰かさんが逃げようとするからです」
自分から頼んできたのですから終わるまで逃がしませんよ、と烈風刀は静かに告げる。有無を言わせぬ声音に、雷刀は諦めたようにのろのろと力無く椅子に座った。彼がペンを持ちノートに向かったところを見届け、烈風刀もテスト対策の課題を再開しようと問題文へと視線を向けた。
「そうだ!」
パン、と両手を打って雷刀が大きな声をあげる。今度は何だ、と眉間に皺を寄せ隣に座る彼を見る。ノートを押さえる自身の手の上に温かな何かが乗せられた。それが雷刀の手であると認識する間も無く、指を絡め手全体を包み込むようにぎゅっと握られる。熱いとすら思えるその温度にビクリと肩が跳ねた。
「これなら逃げれないな!」
彼はこちらを見て楽しげに笑みを浮かべる。指から伝わる熱と気恥ずかしさに思わずふいと視線を逸らし、その嬉しそうな笑みから逃げた。
「……これでは、まるで僕が逃げようとしているみたいではないですか」
「んじゃ烈風刀から繋いで?」
彼は笑顔でそう言うが、手を離す気配は全くない。その手を解いた瞬間、何かしら理由をつけて離れることが分かっているのだろう。眉をひそめ、烈風刀は誤魔化すように言葉を続ける。
「大体、これでは貴方が文字を書けないではないですか。意味がありません」
「こっちの手使えばいーじゃん」
雷刀はそう言って繋いでいない方の手をひらひらと振るが、彼の利き手はそちらではない。ただでさえ綺麗とは言い難い字だというのに、利き手でない方で文字を書くことなど不可能だろう。いけるいける、と意気込んで彼はシャープペンシルを握るがその手は覚束ない。のろのろとノートの上を走る線は手の震えに連動して歪み、漢字はもちろんひらがなですら何と書いてあるのか分からない状態だ。ミミズが這ったような字とはまさにこれを指すのだろう。
「やはり無理ではないですか」
「いや、もうちょい頑張ればいける。本気出せば書ける」
「そんなことで本気を出さないでください」
あまりに真剣な顔と声に呆れ、思わず苦笑する。この真剣さをほんの少しでも勉強に向けてくれればいいのだが、それは土台無理な話だろう。
雷刀が文字を書こうとする度、繋いだ手に力が込められる。きっと無意識の行動なのだろうが、ぴたりと隙間なく触れ合う手と手は否応にも意識してしまう。硬い指と指が擦れる度僅かに体が震え、その感覚に顔が熱くなるのが嫌でも分かった。
「分かりましたから」
ぐい、と強く手を引いて重なったそれをほどく。えー、と雷刀は不服そうな声を上げた。ほのかに色付いているであろう顔を見せぬよう、ノートに向かうふりをし少し俯いて烈風刀は言葉を続けた。
「早く続きをしましょう。逃げないのは、もう分かりましたから」
「えー。分かんねーよ? オレは気まぐれだし飽きっぽいからすぐ逃げるかもよ?」
「自覚しているなら直してください」
ニヤニヤとした笑みに冷え切った声をぶつけると、雷刀は反省したようにしゅんとした表情で俯いた。すぐに調子に乗ってふざけるからこうなるのだ。烈風刀は呆れるようにその姿を一瞥し、ペンを握り直しノートに向かった。
「手を繋ぐことぐらい、いつでもできるというのに」
無意識にそんな言葉がこぼれ落ちた。
しまった、と烈風刀は慌てて口を押さえる。しかしその小さな言葉はしっかり聞こえていたようで、雷刀は勢いよく顔を上げた。先程までの沈んだ色はすっかりと消え失せ、その瞳は喜びと期待にキラキラと輝いている。余計なことを言ってしまった、と烈風刀は苦々しく顔をしかめた。
「そうだな! いつでもできるな!」
「……はいはい、そうですね」
満面の笑みを浮かべる彼に投げやりに返事する。先に自ら肯定してしまったのだ、誤魔化して逃げることなどできない。後悔と諦めを色濃く滲ませ、烈風刀は深い溜め息を吐いた。
「ほら、早く続きをやりますよ。せめてこの単元だけでも終わらせましょう」
「えー」
「『教えてくれ』と泣きついてきたのは貴方でしょう。懲りずに赤点を取って、またニアたちを心配させるつもりですか?」
責めるような烈風刀の声に、雷刀は押し潰されたような声をあげた。無邪気で元気いっぱいな彼女らの姿と、ぶつけられた不安げな言葉を思い出したのだろう。
あの時、彼を見上げたニアとノアの表情は酷く不安げで、心の底から心配していることは傍から見ても分かった。そんな幼く純粋な心を無碍にするようなことなど、常日頃彼女らを可愛がっている雷刀にはできないはずだ。
ペンを握り、うー、と力なく呻く姿に苦笑する。先程までの姿を見るに、やる気はあるのだろう。ただ、一度切れた集中力を取り戻すきっかけがないのだ。
きっかけ、か。少し思案して、ノートを押さえていた手が迷うように揺れる。あぁ、やはり自分は甘いのだ。自嘲するように息を吐いて、机の上に放り出された彼の手に己のそれをそっと重ねた。温かなその手が驚いたようにピクリと跳ねた。
「分かるまで教えますから、頑張ってください」
そう言ってすぐに手を離し、参考書に目を移す。視界の端に、へにゃりと顔を綻ばせる彼の姿が見えた。
「ん、頑張る」
「また逃げないでくださいね」
「もう逃げねーって」
逃がしてくれないだろ、と雷刀は意地の悪い顔で問うてくる。当たり前です、と返す己の顔はまだ淡く色づいたままだろう。
白いノートの上をペンが踊る。二人分の軽やかな音が狭い部屋にゆっくりと積もっていった。
畳む
見上げた先の【咲霊】
見上げた先の【咲霊】
リハビリ咲霊。この子らは妙に書きやすい。
TLで見たラブコメチックな膝枕咲霊が可愛くて書き始めたはずなのにどうしてこうなった。
霊夢、と優しげな声が己の名を口にする。声の方へと目をやると、正座をした咲夜が手招きしていた。畳に手を付き、ぺたぺたと這って霊夢は彼女の下へ向かう。何の用だと言いたげに目の前の赤い瞳を見つめると、咲夜は微笑み己の太ももをとんとんと叩いた。誘われるがまま、そこに頭を乗せる。腹に背中を預けるように顔を横に向け頬を付けると、程よい弾力と心地よい熱がほのかに伝わってきた。細い指が頭を撫で、長い髪を優しく梳く。その心地よさに目を伏せた。
「足、痺れないの?」
こてんと仰向けになり、以前から疑問に思っていたことをぶつけた。咲夜の住まう館はテーブルと椅子ばかりで、正座しなければいけないような部屋はなかったはずだ。正座自体あまり慣れていないだろう。それに加え、人の頭を片足に乗せているのだ。足が痺れないわけがない。それでも彼女はいつも涼しげな顔をしているのだから、不思議でならない。
「もう慣れたわ」
こうやって何度もやってるもの、と咲夜は霊夢の前髪をかき上げる。日の当たらない額は僅かな汚れすら見つからないほど白く、黒い髪とは対照的でよく映えた。
「それに練習したのよ。休憩中は正座して過ごしたり、寝る前にベッドの上でやってみたり、すぐに立ち上がれるようにしたり」
「練習してまでやることじゃないでしょ」
指折り数える彼女にそんなに好きなの、と呆れた瞳で問うと、えぇ、と肯定の言葉と柔らかな笑みが返ってきた。物好きなやつだ、と霊夢はその優しい瞳をぼんやり見つめる。赤い目が弧を描き、慈しむような表情がこちらに向けられた。
そんなに楽しいのだろうか、と霊夢は内心首を傾げた。咲夜はよく膝枕をしたがる。彼女はどうも自分の髪を触るのを好むようで、よく自身を引き寄せ長いそれを撫で、時に結ってくれる。それだけなら隣りあって座った方はやりやすいはずだ。だというのに、彼女はこうやって自分を寝転ばせるのだ。一体何が楽しいのだろう。小さな疑問と好奇心が胸の内に湧き出で、どんどんと膨らんでいく。
霊夢が身を起こす。いきなりの行動に、咲夜は不思議そうにその赤い背を見た。そんな彼女を気にすることなく、向き合うように座る。すっと背筋の伸びた美しい姿勢で正座をし、無言で隣に座ったままの彼女を見つめぺしぺしと太ももを叩く。何を意味するのか理解できないのか、咲夜は頬に片手を当て首を傾げた。
「交代」
「え?」
「交代。たまにはやったげるわ」
早く、と急かすように霊夢は目を細める。不機嫌そうなその顔を見て、咲夜は畳に手を付き身を屈め、遠慮がちな様子で示された場所に頭を乗せ横を向いて寝転んだ。白くふわふわとした髪を持つ彼女の頭は存外重く、何故こんな重たいものを率先して乗せろと言ってくるのだろう、とますます疑問が深まる。
邪魔ね、と呟き、霊夢は咲夜のヘッドドレスを外す。動く気配すらなく、されるがままの彼女の頭をそっと撫でる。少し癖のついた髪はふわふわと柔らかな感触がして、触っていて心地よい。三つ編みが解けないように梳いてみる。少し跳ねた銀色は見た目よりずっとさらさらしていた。霊夢は楽しげに銀色の頭を優しく撫でる。咲夜は時折自分の髪を羨ましいというが、彼女の髪も十分に柔らかで滑らかだ。
柔らかな銀色を楽しんでいると、咲夜は仰向けになりこちらを見た。どこかきょとんと呆けたような顔をした彼女は、見上げた先の黒い瞳をじっと見つめた。なんだろう、と不思議に思いつつも、霊夢もじっと見返す。覗き込んだ赤色は井戸水のように澄み切っていた。主人が主人故に『血のようだ』と言われる彼女の瞳だが、どろりとしたあれよりもワインや紅茶といった底の見える透き通る赤だとぼんやり考える。白い髪と肌に浮かぶ赤いガラス玉は、はいつぞや見た赤い月よりも深いそれはとても綺麗で、揺らめいて輝くその色に触れてみたいという衝動に駆られた。
「……される側っていうのも、案外いいものね」
しみじみとした様子でそう呟き、咲夜はふわりと笑った。彼女はそのまま細い腕を伸ばし、霊夢の頬を優しく撫でる。陽の光にも似た柔らかい温かさとほんの少しのくすぐったさに、猫のように目を細めた。
「こうやって貴方を見上げるのも新鮮だわ」
「そういえばそうね」
この膝枕といい抱きかかえた時といい、たしかに彼女はいつも見下ろす側にいた。そう考えるとなんだか気に食わない。不服さが表情に出ていたのか、咲夜は困ったように眉を下げた。そっと頬を撫でる手つきはまるでぐずる子どもをあやすときのそれに似ていて、霊夢は小さくむくれた。
「でも、これだとなんだか遠くに感じるわね」
「そう?」
どこか寂しげな咲夜の声に、霊夢は不思議そうな顔をした。いつもされている時はそう感じない、むしろ近すぎるぐらいに思えた。身長の問題だろうか。いや、咲夜の方がほんの僅かに高いはずだ。何故なのだろう、と更に首を傾げていると、咲夜は苦笑した。
「私にも分からないけれど」
「なにそれ」
変なの、と呟くと、知ってるでしょ、と笑い交じりの声が返ってくる。そのまま、自然な動作で咲夜は立ち上がった。一体なんだ、と己の手から離れた銀色を見つめると、彼女はくるりと綺麗に振り返った。その口元は柔らかく弧を描いており、どこか楽しげだ。
「交代」
「へ?」
「やっぱり、されるよりする方が好きみたい」
さっと手早くスカートをさばき、咲夜は再び正座する。眉を下げ、困ったように笑う銀に誘われるがままに、霊夢も再び彼女に頭を預けた。ほんの少し離れていただけだというのに、布越しの温かさを長らく求めていたように錯覚する。
「……やっぱこっちのがしっくりくるわ」
「でしょ?」
しみじみと、少し悔しげに呟きじぃと天井の方を見る。見上げた先の彼女は楽しげに笑った。普通はされた方が嬉しいだろうに、何故こんなに楽しげなのだろうか。やっぱり変なやつだ、と霊夢は小さく息を吐いた。
「それに、こっちの方が貴方の顔がよく見えるわ」
うんうん、と一人頷いて、咲夜は霊夢の顔を覗き込む。だんだんと近付く赤い月に、霊夢は驚いたように目を見開いた。すぐさま眉間に深く皺を刻み、腕を伸ばし広げた手で彼女の顔を覆うようにしてぐいぐいと押し退けた。
「近い。調子に乗るな」
「あら、残念」
不機嫌そうな声を気にすることなく、咲夜は涼しい顔で姿勢を正す。調子のいいやつめ、と霊夢は目を眇め、ごろりと横を向いた。
「どうする? もうやめる?」
「…………もうちょい」
思案の末のふてくされたような声に、小さな笑い声と温かな手が降ってくる。さらさらと撫でられる感触は温かくて心地よく、安心する。思わず眠ってしまいそうだ。じわじわと姿を現し始めた睡魔に、霊夢は小さく欠伸をした。
「昼寝ばっかりしちゃだめよ」
咎めるような言葉とあやすような手つきは正反対だ。その裏に滲む『寂しい』という感情も、隠すように優しい声音とも正反対で、霊夢は呆れたように溜め息を吐いた。
こてん、と再度転がり、霊夢は咲夜の腹に顔を埋めるように向きを変える。
「寝ないしほっとかないわよ」
安心しなさい、と甘えるように頭を擦り付けると、撫でる手がぴたりと止まった。この体勢では顔を見ることはできないが、きっと彼女はくしゃりといつもの瀟洒な表情を崩し、子どものように笑っているだろう。勝てないわね、と苦笑交じりの声に、当たり前でしょ、と不遜に返した。
柔らかな手と、柔らかな体温と、ほのかに香る彼女の匂い。
やはり、こちらの方が安心できる。ぼんやりと考えて、霊夢は目を伏せた。
畳む
熱いものにはご注意を【咲霊】
熱いものにはご注意を【咲霊】
キスの日にリハビリにと書こうとして放置してた咲霊仕上げた。
二人でのんびりお茶飲んでるだけの話。
キス要素? そんなものほとんどないよ?
湯を注ぐとふわりと白い湯気と香りが宙を漂う。その瞬間は心地よいものだ。咲夜は小さく笑みを浮かべ、ティーポットの蓋を閉じた。白い指が陶器を撫でる様を霊夢はじぃと見つめていた。どうやら霊夢は自分の指にご執心らしい。貴方の指も綺麗よ、と以前言ったのだが、咲夜のじゃなきゃいや、と返された。可愛らしいものだ。
頃合いをみて、用意したカップの上にポットを傾ける。透き通った明るい琥珀色が白い陶器を満たしていく。色も香りも十分だ。ソーサーに乗せたそれを、隣でもそもそとマフィンを頬張る霊夢の前に差し出す。口の中のそれを飲み込み、彼女は礼を言ってカップに手を付けた。小さく息を吹きかけて冷ます様子はいつ見ても愛らしい。本当ならば飲みやすい温度まで冷ました状態で出したいのだが、やはりお茶はどの種類に置いても熱い方が美味しい。何より温ければ温いで彼女は怒るのだ。自分でちょうどいい温度にするのがいいらしい。難儀なものだ。
こくりと透き通ったそれを飲み、霊夢は満足気に小さく溜め息を吐いた。どうやらお気に召したらしい。
「紅茶、美味しいわね」
「あら、緑茶派ではないの?」
「緑茶派だけど過激派ではないもの。美味しいものにはちゃんと美味しいっていうべきよ」
すました顔でそう言って、霊夢はまた一口紅茶を飲む。緑茶のようにすすらずに飲むようになったのは何時頃だっただろうか。諦めずに注意し続けてよかった、と咲夜は小さく笑みを浮かべる。悪いことではないのだが、少し行儀が悪い。できれば両手でカップを持つ癖も直してほしいのだけれど、これはこれで可愛らしいので強く注意するつもりは今のところない。
そんな彼女の様子を眺め、咲夜も紅茶を飲む。色も香りもちょうどよいが、今日は少しばかり熱く感じる。どうやら湯の温度管理を少しばかり間違えたようだ。自分もまだまだだ、気を付けなければ、と考えてマフィンを口にする。こちらは問題ない甘さと焼き加減だ。
「あっ、つぅ……」
突然、驚いたように霊夢が小さく声を上げた。どうしたのだろうと彼女を見ると、先程の上機嫌な表情はどこへやら、どこぞの雨傘のように舌をべろりと出して顔をしかめていた。
「あら、火傷?」
「みたい」
うぅ、と霊夢は恨めしそうな声を上げる。両手で抱えてたカップを覗き込むと、少なくなっていたはずの中身は九分目あたりまで増えていた。どうやら自分で注いだらしい。時間も経ち既に程よく冷めていると思いそのまま飲んだ結果、うっかり火傷を負ったのだろう。
「貴方、いつも熱いお茶飲んでるのに火傷することなんてあるのねぇ」
「油断してたのよ」
「ごめんなさいね」
「……咲夜が悪いって言ってるわけじゃないわ」
それでも痛いものは痛いのか、霊夢はうーうーと不機嫌そうに呻く。自身の些細なミスへの怒りも含まれているのか、その表情は少し悔しそうにも見えた。
「口の中は治りが早いっていうし、少しの我慢よ」
「そんなこと言ったって痛いものは痛いのよ」
宥める咲夜を霊夢は恨めしそうに見る。べろりと外に出された舌は赤々としており健康的だ。火傷を負うと大抵その部位は赤くなるのだが、これでは分からないな、などと考えじぃとそれを見るめる。
「なによ」
見つめる視線に不機嫌な声が投げかけられる。自身の過失をじっと見られるのがお気に召さないらしい。痛みで動かし辛いのか、どこか舌足らずで可愛らしい。そんなことを言ったら問答無用で札なりなんなりが飛んでくるだろう。沈黙は金である。
「傷は舐めると治るというけど」
「こんなとこどうやって舐めるのよ」
思わずこぼれた言葉に霊夢はきょとんとした表情をする。反して咲夜はいたずらめいた笑みを浮かべた。すっと立てた指でその赤を指差す。ほんの少し動かせば触れてしまうような距離だ。
「人に舐めてもらえばいいのよ」
「ばっちい」
咲夜の言葉に霊夢は更に顔をしかめた。切り捨てる言葉に、今度は咲夜がきょとんと首を傾げる番だった。
「たまにしてるじゃない」
「あれは別よ」
ふざけてするようなことじゃないわ、と霊夢は言う。その声音は突っぱねるようであるが、しっかりと芯の通った真面目なものだ。
つまり、普段そのようなことをする時はおふざけではなく真面目に対してくれているということか。咲夜は嬉しそうに笑みを浮かべた。その笑みが気に入らないのか、霊夢は更に眉に皺を寄せた。そんなに皺を寄せたら痕が残っちゃうわよ、と眉間をつつく。彼女はむぅ、と不服そうに唸って咲夜を睨むが、飽きたのかぺたりと畳に手をつき追い払うかのように手をひらひらと動かした。
「あーもー、そんなこと言ってないで水持ってきてよ」
「はいはい」
子供らしい姿に咲夜は苦笑し、湯呑に水を汲んで彼女に手渡す。いきなり出てきたそれを気にすることなく、霊夢は湯呑を傾け口に含んだ。ようやく落ち着いたのか、はぁと疲れたように息を吐く。冷たいそれのお陰か、痛みは軽く引いたようだ。
「火傷したんじゃこういうお菓子は食べ辛いわね」
机の上に並べられた菓子はどれも水分が少なくぱさぱさとしている。舌を火傷した状態でも食べやすいとは言えないものばかりだ。咲夜の言葉に霊夢は残念そうに俯く。じっと菓子達を見つめる視線は寂しげだ。
「咲夜のお菓子が食べられないだなんて」
「食べやすいものを作るわ。最近暑くなってきたし、プリンなんてどうかしら」
「プリンって、あの黄色い水羊羹?」
「……まぁ、そんなところね」
洋菓子に疎い彼女の言葉に咲夜は諦めたように返事した。プリンと水羊羹は全く違うものだが、きっと違いを説明しても美味しいならそんなことはどうでもいい、と切り捨てられるだろう。実際、原材料や制作の過程を知らなくても美味しいものは味わえるのだから反論し辛い。
冷たい菓子に思いを馳せる霊夢にすっと片手を伸ばし、撫でるようにその頬に触れる。いきなりの行動に、彼女は驚いたように目を見開きこちらを見た。そんな表情にくすりと笑い、頬を撫でそのまま唇を指で撫でる。
「火傷したんじゃ、キスしにくいわね」
「……唇だけなら、痛くないし……大丈夫」
でしょ、と上目遣いで見つめられる。彼女らしい肯定の示し方にふわりと破顔し、その頬を両手で包む。手つきの柔らかさと優しい温度に霊夢は気持ちよさそうに目を細めた。
優しく触れた柔らかなそれからは、菓子のそれとは違う甘い香りがした。
畳む
空へと消える【ライ→レフ】
空へと消える【ライ→レフ】
これの原案というか最初に考えついた形。
なんでこうなった、とどうにか方向修正したけどこっちはこっちで書きたくなったのでさくっと書いたのそのまま載せる。片思いおいしいです。
キュッ、とペンが紙の上を走り終えた音。真っ赤な折り紙に黒がにじんでしまう前に、雷刀は油性ペンを片付けた。カタン、と机に硬いそれが当たる音がこぼれる。
「でーきた!」
力強い文字が駆けるそれを手にし、雷刀は得意げに声を上げた。うちわで扇ぐように鮮やかな赤色をぱたぱたと振る。既にインクは乾いているのだが、どうも癖でこうしてしまう。人の性というやつだろうか、と雷刀はぼんやり考えた。
七夕も近いから、とのことで、学園の玄関には数日前から大きな笹が設置されていた。空へと伸びるそれから少し離れた位置には、短冊を詰め込んだ箱と油性ペンが用意された机が複数設置されてた。ここで願い事を書いて吊るせ、ということなのだろう。こんなに大きな笹をどこから持ってきたのだろうか、という疑問はさておき、生徒たちはこぞって短冊に願い事を書き込んだ。己の願いをこめたそれをしなやかに揺れる緑の枝に括り付ける。最初は緑一色でどこか味気なかったそれは日に日に色を増し、今では賑やかしく華やかな色合いになっていた。
「ワタシもできマシタ!」
その隣で同じくペンを操っていたレイシスが顔を上げる。彼女は満足気な表情で、胸に抱えるように淡い桃色の短冊を両手で持つ。向こう側が透けて見えそうなほど薄い色紙の裏には黒いインクがにじんでいるが、鏡文字であることも相まってかはっきり読むのは難しかった。
「雷刀は何て書いたんデスカ?」
レイシスの問いに雷刀はにやりと不敵に笑い、手にした短冊をレイシスの目の前に掲げた。何と書いてあるのだろう、とレイシスは興味津々な様子で赤の上に散る黒を目で追いかけた。
「『頭がよくなりますように』だ!」
「その考え方が既に頭が悪いのですよ」
自信に満ち溢れた言葉は、冷たく鋭い声に切り裂かれる。雷刀が気まずそうな顔で声のした方を向くと、予想通り冷ややかな目でこちらを睨む烈風刀がいた。
「大体、願う前に自分で勉強しなさい。その方がずっと早いに決まっているでしょう」
呆れと怒りをにじませた言葉に、雷刀は逃げるように顔を反対側に向け視線を逸らした。反省する様子のないそれが気に入らないのか、烈風刀の目が更に細められる。ジトリとしたその目はどこか怖い。不穏な空気に、レイシスは慌てたように口を開いた。
「れっ、烈風刀はなんて書いたのデスカ?」
ひょこり、とレイシスは烈風刀の手元を覗き込む。彼女が見やすくなるよう、烈風刀は細い短冊を傾けた。幾許か遅れて、雷刀も浅い緑色のそれを覗き込む。若葉色の紙の上には、スラリとした細く美しい文字が四つ並んでいた。
「むびょー、いき……いき?」
「『むびょうそくさい』、デスネ」
「正解です」
流石ですね、と優しく微笑む烈風刀に、レイシスは嬉しそうに笑った。比較的簡単な四字熟語だが、正解したのが嬉しいようだ。反面、雷刀は拗ねたように口を尖らせた。ツッコミすらされず、放っておかれるのが気に入らないらしい。
「そういうのじゃなくてさー、もっと他にねぇの? こう、『野菜が美味しく育ちますように』とか、『料理が上手くなりますように』とか」
「自分個人のことを考えるよりも、皆のことを考える方が有益です。……個人的な願い事が思いつかなかった、ということもありますが」
「烈風刀らしいデス」
つまらなそうな雷刀の声を、烈風刀はバッサリと切り捨てる。しかし、その声はどこか自信なさ気だ。厳しくありながらも人を思いやる彼らしい、とレイシスは小さく笑った。
皆の事ねぇ、と雷刀は彼の言葉を反芻する。レイシスの言う通り彼らしい願いだが、もう少し自己を押し出してもいいのではないか、と考える。弟は他人のためなら簡単に自己を殺す性格をしている。雷刀はそれをあまり快く思っていなかった。
「レイシスは何と書いたのですか?」
「『みなサンにより良いサービスが提供できマスヨウニ』、デス!」
にこにこと笑うレイシスに二人は頬を緩めた。ナビゲートを一身に担う彼女にとって、それは心の底からの願いなのだろう。心優しい彼女らしい、と双子はくすりと笑った。
「さ、飾りましょうか」
烈風刀の声に、レイシスと雷刀は元気よく返事する。レイシスと烈風刀が手頃な高さの枝に結びつける中、雷刀はできる限り高い場所を目指して腕を伸ばす。つま先立ちになり、指に触れたしなやかな枝を掴み取る。
「そんなに上でなくともいいでしょう」
「いや、高いとこの方が願いが届く気がする。絶対そうだ。オレ知ってる」
雷刀の言葉に、烈風刀は呆れたように顔を渋くした。彼の思考は子供のそれそのものだと分かっていても、納得しがたい。反してレイシスはその手があったか、と言わんばかりの表情で雷刀を見つめていた。どこか天然な彼女はよく彼に影響されている。頼むからやめてほしい、と烈風刀は常々思っているが、言っても効果はないだろう。結局、彼女のふわふわとした雰囲気に負けてしまうのだ。
烈風刀の考えなど露知らず、雷刀は掴み取ったそれを離さぬよう注意しつつ、短冊を片手で器用に結びつけた。握った手を離すと、細い枝は勢いよくしなり空高くへと向かった。
「ほら、高いとこのが目立つ」
どうだ、と自慢げな表情で雷刀は天を指差す。鮮やかな緋色の色紙は、どの短冊よりも目立っていた。
「ワタシも高いところに結べばよかったデス……」
「レイシス、危ないからやめましょう? しなった枝が当たったらとても痛いのですよ? 葉で指を切ってしまうかもしれません」
心配げな烈風刀の言葉に、レイシスははわ、と短い悲鳴を上げる。想像しただけで怯えてしまったらしい。ハイ、と素直に頷く彼女を見て、烈風刀は安心し胸を撫で下ろした。
「そろそろ戻りましょうか」
「そうデスネ」
元々、ここには作業の休憩も兼ねて訪れたのだった。いくら運営に関わる大切な作業とはいえ、籠りっぱなしでは集中力も切れてしまう。外の空気を吸い、晴れ渡る空を見て、気分は大分よくなった。これならばこれからの仕事も上手くやれるだろう。
楽しかったデス、と笑うレイシスを見て、双子は嬉しそうに笑みを浮かべる。彼女が楽しめたのならば何よりだ。
ふと、雷刀が足を止めた。赤い瞳が見つめる先には、束になった短冊があった。この学園の生徒数は非常に多いが、全員が全員これに興味を示すわけではない。まだまだたくさん余っているのも当然だ。
すっと手を伸ばし、黄色の短冊を取り出す。隣に放置してあった油性ペンのキャップを開け、雷刀は薄いそれに文字を書き入れていく。ペンは先程のように勢いよく走らず、まるで書道をするようにゆっくりと動いていた。
「何をしているのですか」
耳慣れた声に雷刀が顔を上げると、隣に烈風刀がいた。兄がいなくなったのに気付き、戻ってきたようだ。なんかかんか甘いな、と雷刀は内心苦笑する。自分なんて放っておいて先に行けばいいものの、わざわざ迎えに来てくれたのだ。厳しい言動の割に、彼は根本がどこか甘い。
「んー? 一杯余ってるしもう一枚書こうかなって」
「欲張りな」
雷刀の言葉に、烈風刀は呆れたように溜め息を吐いた。いーじゃん、と雷刀は能天気に笑うが、烈風刀の表情は依然渋いものだ。
ふと、烈風刀の表情が変わる。眉間に皺を寄せた難しい表情は消え、代わりに不思議そうな色が浮かぶ。透き通った若草色の瞳は、雷刀の手元の短冊に吸い寄せられていた。
彼が手にした短冊には、『あの人と仲良くできますように』と書かれていた。その文字はいつもの走り書きのような乱れた文字ではなく、とても丁寧なものだ。普段ならばとにかく大きく書く彼だが、黄色い短冊に浮かぶ文字は小さい。まるで別人が書いたようだ、と烈風刀は首を傾げた。
「ん? なに? 気になる?」
「えぇ。貴方は皆と仲がいいでしょう? だというのにわざわざこうやって願うだなんて、さすがに気になります」
雷刀は明るく活発な性格をしており、かつ誰とでも分け隔てなく自ら関わりにいく人間だ。その元気さを疎ましく思う人間もいるが、最終的には彼の魅力の前に折れてしまう。そんな彼がわざわざ『仲良くなりたい』と願うだなんて、一体どんな人間なのだろう、と烈風刀は考え込む。
「知りたい?」
「えぇ」
にまりと楽しげに笑う雷刀に、烈風刀は真剣な表情で頷く。常に冷静に見える彼だが、その実兄と同じくらい好奇心が強い。加えて、疑問は全て解決してしまいたいという考えを持っていた。謎を謎のまま残しておくのはどこか気持ち悪く思えた。
「ひみつ」
「…………だったら、最初から聞かないでください」
いたずらめいた笑みを浮かべる雷刀に、烈風刀はジロリと鋭い視線を送る。視線に物理的な攻撃力があるとすれば、きっといとも簡単に身体を貫通させるような鋭さだ。しかし雷刀は気にかける様子もなく、笹の下へ歩き目の前の枝に吊るす。反動で枝が揺れ、黄色い短冊もつられてカサリと音を立てた。
「高いところに吊るさなくていいのですか?」
「いいの」
皮肉気な烈風刀の言葉に雷刀はすんなりと返す。一体何なのだ、と烈風刀は不可思議そうに顔を歪めた。
「――どうせ、叶わねぇし」
雷刀は寂しげな表情で呟く。その彼らしからぬ弱気な言葉は烈風刀に聞こえなかったようで、まだ難しそうに顔をしかめていた。
「ほら、さっさと行こーぜ。レイシス待たせてんだろ?」
「押さないでください。元はといえば貴方のせいでしょう」
ぐいぐいと背中を押し前へと進める雷刀に、烈風刀は抗議の声を上げる。まぁまぁ、と雷刀は悪びれずに笑う。仕方ない、といった風に烈風刀は溜め息を吐いた。結局、いつも折れるのは自分なのだ。
己の背を押す彼の表情を見れば、烈風刀はきっと驚くだろう。普段の明るさは消え、どこか暗く寂しげな表情を浮かべる雷刀など、双子の弟である烈風刀も滅多に見ることができない。そうやって顔に表れるほど、彼の思考は淀んでいた。
そうだ、己の願いは絶対に叶わないのだ。
実の弟と仲良く――より仲を深め、血縁という関係を超え、恋仲になりたいという願いなど、絶対に叶ってはいけないのだ。
そう自分に言い聞かせて、雷刀はぐ、と息を飲みこんだ。胸の奥に使える淀んだ思考をどうにかいに押しやる。こんな感情は、こんな劣情は、こんな恋情は、決して表に出してはならない。誰にも見せず、墓まで持っていかねばならないのだ。
それでも、わざわざ七夕なんてイベントに縋ってしまうのだから自分もまだまだ弱いなぁ、と雷刀は自嘲する。どこか変に天然の入った彼はきっと気付かないだろう。だからこそ、ああやって濁り汚れた言葉をしたためたのだ。女々しい。その一言に尽きた。
「さーさー早く行こうさっさと行こうどんどん行こう」
「だから押さないでくださいって」
ちゃんと歩けますよ、と烈風刀は不満げに声を漏らす。たん、と足を前に進め、烈風刀は背を押す手から逃れる。行きますよ、と彼は駆けだす。ん、と楽しげに答え、雷刀も走り出す。パタパタとコンクリートの床の上を駆ける音。二人分のそれは校舎へと吸い込まれていった。
細い笹の葉の中、秘めたる思いを込めた短冊が小さく揺れた。
畳む
届【ハレルヤ組】
届【ハレルヤ組】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
七夕のお話。初等部とか中等部とか高等部の皆がだらだら話してるだけ。
例により呼称は公式参考にしつつ捏造。
風の動きに合わせて細い緑の葉が揺れる。そこに吊るされた色とりどりの飾りもつられて揺れ、さらさらと軽やかな音を奏でた。
七夕も近いから、と数日前に学園の玄関に設置された笹の周りには、たくさんの生徒が集まっていた。少し離れた位置には短冊を詰め込んだ箱と油性ペンが用意された机が複数設置されており、皆ここで願い事を書いていた。己の願いをこめたそれを手にし、すっと上へ上へと葉を伸ばすしなやかな枝に括り付ける。始めは緑一色だったそれは日に日に色を増し、今ではとても賑やかで華やかな色合いになっていた。
「これでよし、っと」
キュッと油性ペンが軽やかな音を立てる。雷刀は手にしたそれを元の場所にしまい、顔を上げ真っ赤な短冊を手にしひらひらと振る。インクは既に乾いているのだが、そうやって振ってしまうのは人のサガというものだろう。
「ワタシもできマシタ!」
同じく隣でペンを滑らせていたレイシスも顔を上げた。彼女は胸に抱えるように淡い桃色の短冊を両手で持った。薄い折り紙でできた短冊の裏にはペンのインクがにじんでいるが、はっきりと読むのは難しい。
「雷刀は何をお願いしたんデスカ?」
レイシスの問いに雷刀はフフフ、と不敵に笑い、手にした短冊を彼女の目の前に掲げた。鮮やかな赤の上には力強い黒が勢いよく放たれていた。
「『成責がよくなりますように』だ!」
「『せき』の字が違いますよ」
切り捨てるような鋭い声がすぐ隣から飛んでくる。雷刀が気まずそうな顔でそちらを見ると、予想通り呆れを色濃く浮かべた翡翠の瞳でこちらを睨んでいた。
「成績の『せき』は糸偏です。大体、そんなことを願う前に居眠りせずに授業を聞きなさい」
怒りを露わにした指摘に雷刀は逃げるように視線を逸らした。毎度毎度のそれが気に入らないのか、烈風刀の目が更に細められる。ジトリとした暗いその瞳はどこか怖い。ゆるりと重くなった空気に、レイシスが慌てたように口を開く。
「れっ、烈風刀はなんて書いたのデスカ?」
ひょこり、とレイシスは烈風刀の手元を覗き込む。彼女が見やすくなるよう、烈風刀は短冊を傾けた。幾許か遅れて雷刀も浅い緑色のそれを覗き込む。若葉色の紙の上には、スラリとした美しい文字が四つ並んでいた。
「むびょー、いき……いき?」
「『むびょうそくさい』、デスネ」
「正解です」
流石ですね、と微笑む烈風刀に、レイシスは嬉しそうに笑った。反面、雷刀は拗ねたように口を尖らせた。ツッコミすらされず、放っておかれるのが気に入らないらしい。
「もっと他にないのかよ。こう、『野菜が美味しくできますように』とか」
「自分のことよりも皆のことを考える方が有益です。……個人的な願い事がいまいち思いつかなかった、というのもありますけど」
「でも、烈風刀らしいデス」
つまらなそうな雷刀の声に烈風刀はさらりと返すが、その声はどこか自信なさげだ。他人をよく観察し考えて行動する彼らしい、とレイシスは小さく笑った。その笑みが何だか恥ずかしくて、烈風刀は気まずげに視線を逸らす。
「レイシス姉ちゃんだー!」
パタパタとコンクリートの地面を駆ける音。レイシスが声の方へ身体を向けると、その胸にニアが飛び込んできた。少し遅れてノアもニアの背に抱き付くように止まる。三人はその胸の中できゃいきゃいと楽しげにはしゃぐ彼女たちを見た。
「ニアたちも短冊書きにきたのか?」
「うん!」
「さっき書いたから、飾りにきたの」
二人は手にした短冊を頭上に掲げ、雷刀に見せる。ひらひらと揺れるおそろいの青い短冊には、『みんなといっぱい遊べますように』と丸っこい可愛らしい文字で書かれていた。彼女らの純粋で真っ直ぐな願いに、微笑ましい、とレイシスたちは頬を緩める。明るく元気いっぱいの彼女たちならば必ず叶う願いだろう。
「きっと叶いますよ」
烈風刀は二人に笑いかける。彼女らは嬉しそうにえへへ、と笑った。ふと、二人がつけたカチューシャのリボンが兎の耳のようにぴんと立ち上がる。深海のように深くきらきらと光る二対の青は、レイシスたちの手元に目を奪われていた。
「レイシス姉ちゃんたちも書いたの?」
「はい。しっかり書きマシタ」
ニアの言葉に、レイシスは手に持った短冊を見せる。二人は桜色のそれを覗き込むが、漢字が読めないのか、うーん、と首を傾げていた。
「ねぇ、レイシス姉ちゃんたちのもノアたちと一緒に飾る?」
「はわ、いいのデスカ?」
うん、とニアとノアは元気よく頷く。むしろみんなと一緒に飾りたい、とのことだ。ありがとうございマス、と礼を言い、レイシスは三人分の短冊を彼女らに渡した。二人は手を繋ぎ、せーの、と声を合わせ、ぴょんと勢いよく飛び上がる。青い髪と緑がかった黄色のリボンが風を受けてふわりと揺れる。二人は空へと伸びる笹のてっぺんに近い位置に五人分の短冊を器用に結んだ。とん、と彼女らは同時に足を付き、体操選手のように両手を上に伸ばしポーズを決めた。繋いだ手を高く上げる姿は可愛らしい。
「これでよーし!」
「ありがとな」
「有難うございます」
「れふとたちのお願いも叶うといいね」
礼を言う烈風刀と雷刀に、ノアはそう言って笑った。だな、と雷刀も笑顔で返す。自分のものはともかく、烈風刀やニアたちのものはきっと叶うだろう。どちらも彼らならば努力し成し遂げることができることなのだ。
「あ、れふとおにーちゃんだ」
「れふとおにーちゃん、こんにちは」
「……こんにちは」
パタパタと三人分の小さな足音。名を呼ばれた彼が視線をやると、そこには短冊片手に駆けてくる雛、桃、蒼の三人がいた。三色の耳が、嬉しそうにぴょこんと立ち上がった。
「こんにちは。皆さんもお願い事をしにきたのですか?」
烈風刀の問いに、うん、と三人分の元気な声が答える。見て見て、と雛は己が持つ短冊を差し出す。淡い黄色のそれは『もっといっぱいあそべますように』とクレヨンで書かれていた。きっと教室で書いてきたのだろう。わたしも、と差し出した桃と蒼の短冊にも同じことが書いてある。仲がいいな、と烈風刀は微笑んだ。
「みんなのも高いとこに飾る?」
「ノアたちが飾ってくるよ」
二人の申し出に、雛たちは嬉しそうに声を上げる。ニアノアおねーちゃん、おねがいします、と三人は声を揃えて短冊を差し出した。しっかりと受け取ったニアたちは、地面を蹴り上げ空へと飛び上がる。青空に浮かぶ二人を見て、三人の子猫は楽しげに笑う。楽しそうでなによりだ、と烈風刀はその姿を見て顔を綻ばせた。隣にいる二人もきっと同じ表情をしているだろう。楽しげにはしゃぐ彼女らの姿は、愛らしいという言葉がよく似合う。
「あら、皆さんおそろいですの?」
よく通る高い声が後ろから上がる。はしゃぐ彼女らの後ろには、普段通り鴇色の着物に身を包んだ桜子がいた。その後ろには氷雪もいる。白い着物を身にまとった彼女は不思議そうな顔をしていた。
「これだけ人が集まっているのは珍しいですね」
「気付いたらみんな集まっていまシタ」
氷雪の声にレイシスは楽しげに答える。まだ多くの人と話すことに慣れていないのか、氷雪は桜子の後ろに隠れるように立っている。それでも自ら声をかけることができるようになったのだ、人との関わりをあまり持っていなかった彼女にとっては大きな進歩だろう。
「二人も短冊を飾りにきたのデスカ?」
「そうですの」
レイシスの問いに桜子は手にした短冊を彼女に示した。すぐハッとした表情になり、見ちゃだめですの、と慌てて己の背に濃い桃色の紙を隠した。大丈夫、見ていまセン、とレイシスはぱたぱたと手を横に振る。きっといつも通り『あの方』に関する願いなのだろう。彼女の想いは、きっと空の上、星の川の畔で夫のことを想う織姫にも負けない。
「そっ、そういえば、氷雪さんはなんて書いたのですの?」
くるりと振り返り、桜子は後ろにいた氷雪に問いかける。自分に振られるとは思っていなかったのか、氷雪はビクリと身体を震わせた。あわわ、と深い河の底のような美しい緑の瞳が辺りを泳いだ。
「えっと……、これ、です」
氷雪は恥ずかしげに俯き、そっと短冊を二人に差し出した。白にも似た水色のそれには、細く麗しい文字で『もっと皆さんとお話しできますように』と書かれていた。
「わたし、まだ皆さんと上手くお話しできなくて……。早く打ち解けて仲良くなりたいのですけれど、上手く言えなくて……」
「大丈夫デス!」
不安の色をにじませながら頬を赤く染める氷雪の手に、レイシスは己の手を重ねた。ひくり、と氷雪の肩が揺れる。驚く彼女を気にせず、レイシスは彼女の手をぎゅっと握った。冷たいですよ、と声を上げそうになる氷雪だが、レイシスの朗らかな笑みは己の冷たさを打ち消すような温かさをしていた。
「いつも頑張っているデショウ? だから大丈夫デス! きっと叶いマスヨ!」
ニコニコと笑い励ますレイシスに、少し強張っていた氷雪の表情が緩む。だといいですね、と困ったように笑う氷雪に、レイシスは再度大丈夫、と励ます。傍にいた桜子も二人の手に己のそれを重ね、大丈夫ですの、と声を上げた。二人分の温かさに、ツンと鼻の奥が痛む。ここは泣くところではない、ときゅっと口を引き結び、氷雪は小さな声でありがとうございます、と呟いた。その細い声は二人にちゃんと伝わったようで、桃と浅葱の瞳がふわりと弧を描いた。
「あれ、先輩たちどうしたんですか?」
不思議そうな声に雷刀と烈風刀は振り返る。赤と緑の二対の目の先には、深い青の髪で目元を隠した後輩がいた。いつもならば友人の魂や灯色がいるのだが、今日は珍しく一人で行動しているらしい。
「冷音も短冊飾りにきたのか?」
「いえ、これを飾りにきたんですけど……」
これ、と冷音が取り出したのはてるてる坊主だった。しかし、通常の物とは違い、天地が逆さまになっている。雨を降らせてくれ、というのが彼の願いなのだろう。短冊に書くより分かりやすい。これ自体の効果も期待もできる、というのも合理的だ。
「……止めといたほうがよさそうですね」
ハハ、と冷音は力なく笑う。さすがになぁ、と雷刀は苦笑した。三人の視線の先には、笹の下で楽しげに話すレイシスたちや、さらに飾り付けるニアや桃がいた。あれだけはしゃぐ彼女らの姿を見て、これを吊るすのは憚られた。
もったいないので屋上にでも吊るしてきます、と冷音は踵を返し校舎へと入っていった。吊るす事自体を止めてほしいが、既に遅い。普段は大人しい彼だが、雨に関する物事への執着は強くそう簡単に止めさせることはできないだろう。長い付き合いのある魂ですら勝率は五割なのだ。
子どもたちの声が響く中、レイシスはふと空を見上げた。雲一つなく晴れ渡る青空へと背を伸ばす笹は青々としており、育ち盛りの子どものように伸びやかだ。さらさらと揺れ心地よい音を立てる葉や飾り、そして多く吊るされた短冊は、皆の願いを受けて輝いているようにも見えた。
「……七夕が過ぎると、撤去しちゃうんデスヨネ」
寂しげなレイシスの声に、雷刀たちは目を伏せた。七夕は一日限りだ。そして、このような大きいものをいつまでも飾っておくことなどできない。回避することができない事実ではあるが、彼女のその言葉を肯定することは双子にはできなかった。
「レイシス姉ちゃん知らないの?」
きょとんとした顔でニアとノアがレイシスたちを見上げた。何の事だろうか、と三人は顔を見合わせる。その場にいた皆も不思議そうに口をつぐんだ。
「七夕の笹と飾りはね、終わったら燃やすんだよ」
「も、もやしちゃうのですか……?」
ニアの言葉に、後ろで話を聞いていた桃が怯えたような声を上げる。雛や蒼、桜子に氷雪も酷く驚いた顔をしていた。当たり前だ、いきなり『燃やす』だなんて物騒な言葉が小さな彼女の口から飛び出したのだ。
「だいじょうぶだよ」
不安げに震える桃の頭をノアが撫でる。その声は優しく、心配そうな色を浮かべた桃は少しばかり落ち着いた。それでも納得いかないのか、依然不思議そうな表情を浮かべている。彼女だけではない、どういうことなのだろう、とその場にいた全員が思っているようだ。
「笹を燃やして、煙が空に昇って彦星と織姫にお願い事を届けてくれるんだって。みんなのお願い事を、煙が運んでくれるんだよ」
だからだいじょーぶ、とニアとノアは空へと両手を広げ笑った。二人の言葉にレイシスと雛はキラキラと目を輝かせる。彼女らの話を聞いた烈風刀と雷刀はほぅ、と関心の声を上げた。
「そんなこと初めて聞いたな。すげー」
「どこかで聞いた覚えはありますが……、よく知っていましたね」
「すごいでしょー!」
「ニアちゃんと一緒に読んだ本に書いてあったんだ」
感心する二人の声に、ニアたちはえへんと胸を張る。すげー、と雷刀が両手を上げ喜ぶとニアとノアもぱたぱたと両手を空へと掲げ笑った。きゃっきゃとはしゃぐ三人を見てレイシスはふふ、と楽しげに笑った。その笑顔には先程の寂しそうな色など無く、いつもの柔らかな温かみに溢れていた。
「ちゃんと届くといいデスネ」
「えぇ」
大丈夫ですよ、と言う烈風刀の言葉に、レイシスは嬉しそうに顔を綻ばせた。
「そういえば、レイシスは何をお願いしたんだ?」
ニア達とじゃれていた雷刀がくるりと振り返り問うてきた。そう言えば、自分の願いは見せたが彼女のそれはまだ聞いていなかった、と双子はじっと見つめる。レイシスはにこりと笑い、空を見上げる。彼女の桃色の瞳の先には、先ほどニアたちが括り付けてくれた薄桃色の短冊があった。
「『みなサンにより良いサービスが提供できマスヨウニ』、デス!」
レイシスの言葉に、双子はくすりと笑う。心優しい彼女らしい、素敵な願いだ。
「レイシスも、自分の事ではないのですね」
「やさしーレイシスらしいけどな!」
「ハイ、みなサンの幸せが、ワタシの幸せですカラ」
だから叶ってほしいデス、とレイシスは再び空を仰ぐ。
真っ青な空には、若い緑と輝かしい願いが広がっていた。
畳む
雨音響く日常【後輩組】
雨音響く日常【後輩組】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
後輩組、というより魂と灯色がだらだら話してるだけ。後輩組はゆっるい付き合いをしているといい(私が)
照明など機能していない部屋の一角は青白い光で照らされている。光源であるモニタの前には、猫背になった魂がじっとそれを注視しキーボードを操っていた。暗い部屋で不健康な光を浴び続けるのは、学園のメインサーバーを管理する役目を担う彼の日常である。
その後ろ、少し離れた位置では灯色が硬い床の上に寝転びピクリとも動かず眠っていた。寝息すら聞こえないその姿は生きているかどうか不安になる者も多い。けれども、魂にとっては当たり前の日常の一コマでしかない。バグも現れない現在、起こす理由などないのだから、気にすることなくキーの上で指を踊らせた。
寝転がっていた灯色の指がピクリと小さく動いた。痙攣するように彼の身体が震え、小さな呻き声と共に酷く緩慢な動きで起き上がる。そのままゆるりと首を動かして暗い部屋を見回した。
「んー……魂、冷音は?」
「外走り回ってる」
八割方眠っている声に、魂はモニタから目を離すことなく答える。ふぅん、と答えにもならない声をあげて、灯色はつまらなそうにドアを見つめた。他の教室と違い、ガラス窓が無いその扉の向こうに何があるか見えることはない。ただ、魂の言葉から何が起きているかははっきりと理解できた。
二人の共通の友人である青雨冷音は普段は気弱で温厚な少年だが、雨の日は豹変する。口調も性格も強気で攻撃的なものに変わり、躁状態ではないかと疑うほどテンションが高くなる。雨の中外に飛び出し、ヒャーなどと叫び傘を振り回し走り回る姿は、最早学園名物の一つとなりつつあることを彼は知らないだろう。
本日の天気は雨。それも耳が痛くなるほど雨音がうるさくい土砂降りだ。朝から授業を放り出しそうなほどのテンションだった彼が放課後どうなっているかなど、火を見るより明らかだ。
「元気だね……何が楽しいんだろ……」
「さぁな。昔からあの調子だし」
やる気なく呟く灯色に、魂は同じくやる気なく答える。幼馴染で腐れ縁、長年共に過ごしてきた彼にすら分からないのなら他者が分かることなどないだろう。自然現象レベルだな、と灯色はぼんやり考え、窓のないドアをぼうと見る。雨の名を冠した彼はまだまだ帰ってこないように思えた。
「はしゃぐのはいいけど後のこと考えろよなー。毎度毎度ぐっちゃぐちゃのどっろどろになって帰ってきやがって……」
画面から目を離すことなく、魂はぶつぶつと愚痴をこぼす。放っておけばいいのに、と灯色は思うが、言っても意味はないだろう。二人ともなんだかんだ世話焼きのお人好しなのだ。
「……いいね」
「どこがだよ」
「ボクは、そういうの……覚えてないから……」
不律灯色には記憶がない。己の名前すら忘れた彼の今のそれは、学園に編入するために一時的に与えられたものだ。目的も忘れ、ただただ世界を彷徨う彼が過去にあったかもしれない光景、普通の未来に存在したかもしれない光景を羨ましがるのは当然ともいえるだろう。たとえ、それが意識することなく日常に存在するワンシーンだとしても、だ。
悪いことを言ってしまった、と魂は灯色の言葉に気まずそうに顔をしかめた。
「……まあ、どうでもいいけどね」
「いいのかよ」
つまらなそうにあくびをする灯色に、魂は思わず呆れたような声を上げる。先程までの寂しげな言葉は一体何だったのだ、と眉をひそめた。
「ていうか……魂はそういうの分からないの……? スーパーハッカーってやつなんでしょ……?」
「『スーパー』じゃねぇし。てか手がかり全くないのにできねーっての。その名前もマキシマ先生がつけたんだろ?」
「らしいね……」
「『らしい』って、お前当事者だろ……」
「半分寝てたから覚えてない……。ていうか、マキシマにボコボコにされて記憶飛んでる……気がする……」
先生、あんた一体何してんだ、と魂はげんなりとした表情を浮かべた。退治するにしてもやりすぎである。それほど灯色が強かったと考えるのが自然だろう。事実、灯色のバグ退治の腕は仕事を始めたばかりの頃から抜群に長けていた。記憶は消えてしまっても、身体はしっかりと覚えている。それが彼を探す手掛かりにならないか、と魂は幾度か考えたことがある。けれども、腕っ節の強い者などこの世界、それどころかこの狭い学園にすらある程度いる。それ以外の何も情報が無いのだから、そう簡単には見つからないだろう。下手をすればトライプルのように別世界から来たという可能性もある。手がかりがかけらもないのだから、どうしようもないのだ。
「……今は今で楽しいし」
魂たちもいるしね、と言って灯色はまた横になった。ヘッドホンが地面にぶつからぬよう器用に寝転がる姿は、まるでしなやかな猫のようだ。
「…………魂」
ガラガラとドアがゆっくりと開かれ、光が闇の深い部屋に注ぎ込まれる。二人の視線の先には冷音がいた。頭からつま先まで、全身余すところなくずぶ濡れになった彼は普段通りの落ち着いた様子だ。むしろ落ち込んで更にテンションが低くなっているようにも見える。
「雨、上がったのか?」
魂の問いに冷音は小さく頷いた。早すぎるよ、と酷く辛そうな、ほんの少しでも気を抜けば泣き出してしまいそうな声で彼は呟く。あんなに長く外にいたというのに、まだまだ足りないようだ。まだ入ってくんなよ、と魂は入口に佇む冷音に釘を刺す。機械だらけのこの部屋に水の塊と言っても差し支えないほど濡れた彼をそのまま入れるなどできない。魂は脇に置いてあった冷音のカバンからタオルを取りだし、持ち主に向かって投げた。自分でしっかりと用意していたらしい。案外理性的なのだな、と灯色はその光景を見て思う。
力なく頭を拭く冷音を見かねてか、魂は椅子から立ち上がりドアへと歩みを進める。部屋の境目に立ち尽くした手を伸ばして、無理矢理屈ませて乱暴にタオルを動かす。白いタオルが水を吸って重くなった頃には深い青色の髪はぼさぼさになっていた。冷音は急いで前髪を整え目元を隠す。雨が降っている時は隠すことなく行動するというのに、一体何が違うのだろう。それは皆の疑問だった。
「雨上がったなら帰るか。灯色はどうする?」
魂の問いに灯色はゆるゆると首を横に振った。もう日も暮れ、エスポワールと交代する時間が近い。一旦帰って休むには難しい時間だ。それを理解したのか、魂はそうか、と頷いた。
「んじゃ、また明日な」
いつの間にか二人分の鞄を手にした魂はひらひらと手を振り、そのまま冷音の背を押す。外に押しやられる冷音もじゃあね、と小さく手を振って廊下へと消えた。トン、と鉄でできた引き戸を閉めれば、元の闇が戻ってきた。
機械の低い唸り声が満ちる暗い部屋で灯色は寝転ぶ。薄く開かれた瞳で何もない暗闇をぼんやり見た。
記憶があれば、あのように友人らと帰ることができたのだろうか。
記憶があれば、このように寝て仕事をしてという日常を過ごすことはなかったのだろうか。
そんなくだらないことを考えて、灯色は寝返りを打つ。ヘッドホンが硬い床に触れ、カチンと小さな音を立てた。手を広げ、肉の薄い己の手を見つめる。
だらだらと友人らと話して、仕事が無い日は時折一緒に帰って、先生やエスポワールと他愛のない会話して、先輩方とバグ退治をして。今まで過ごしてきた日常を思い返して指を折る。
なんだ、今も変わらないじゃないか。
くぁ、と灯色は小さく欠伸をする。エスポワールが来るまでもう少しかかるだろう。時計は見えないが、なんとなく感覚で分かる。それほど、このような日常を過ごしてきたのだ。
重くなった瞼に逆らうことなく彼は目を閉じる。いつも隣にいる黄色と青が、暗い闇の中ぼんやりと見えた気がした。
畳む

ストレス解消法【ハレルヤ組】
ストレス解消法【ハレルヤ組】諸々言ってみたら諸々あってそんな感じのあれ。嬬武器弟が可哀想なだけ。
腐向けに腰まで突っ込んでる感あるが気にしない。
電子音の後、『データが保存されました』という一文がオレンジと黒で構成された画面に表示される。ゲームが終了した旨を示すそれを見て、烈風刀はトンとキーを叩いた。次はどうか、と彼は別の画面に切り替える。今の時間帯はプレーヤーが少なくマッチングを待つ者もあまりいないため、自身の仕事も普段のそれと比べて随分と少なかった。慌てずしっかりと作業を進められるのはいいことだ。彼はいつもより余裕のある表情で己のやるべきことをこなしていく。
「はわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ!」
「うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!」
突如、広い部屋に叫びにも似た大きな声が響く。いきなりのそれに烈風刀はビクリと肩を震わせた。一体何だ、と急いで辺りを見回す。はた、と止まった彼の視線の先には、両手を上げ大きく口を開けて声をあげるレイシスと雷刀がいた。無邪気でにこやかな笑顔を浮かべているので何か重大な問題が起きたわけではなさそうだ。
「二人とも! 叫ばない!」
鋭い声が重なる大声を切り裂く。怒りを露わにしたそれに、ぴたりと声が止んだ。発生源であるレイシスと雷刀の顔には、まずい、という三文字が浮かんでいた。
「誰も見ていないと思って遊ぶのはやめなさい。次の人が来たらどうするのですか」
「だって人少なくて暇だし……」
「やることがなさすぎて暇デス……」
口を尖らせ言い訳をする二人に、烈風刀は目を眇める。怒りを強く示したその視線に、二人は口をつぐみ目を逸らした。悪いと思っているようだが、そこに反省の色は全く見られない。雷刀はともかく、レイシスまでこんなことをするなんて。烈風刀は呆れたように溜め息を吐いた。
「そんなに暇なら別の作業をしてください。普段のことは僕が全てやりますから」
現在の人数ならば烈風刀一人でも十分に対処できる。ならば『暇』とのたまう彼らには溜まっている案件を消化させるのが合理的だ。キーを操り、烈風刀は二人に必要なデータを受け渡す。目の前の画面に表示されたファイルの量に、桃と赤の瞳が大きく開かれる。その顔は驚きと絶望に青く染まっていた。嘘だろう、あんまりではないか、と彼らは縋るように緑を見つめる。笑顔でこちらを向いた烈風刀の瞳は、暇なのだろう、文句を言うな、と物語っていた。はい、と諦めたような返事が二つ、のろのろとキーを叩くまばらな音が聞こえてきた。これでしばらくはふざけるようなこともないだろう。暗い顔で画面を見つめる二人を確認し、烈風刀は己の仕事に戻った。マッチング処理、楽曲・譜面データの確認、プレーヤーデータの管理といった細々とした仕事をこなしていく。どれもプレーヤーに快適に遊んでもらうための事だ。これのどこが暇なのだろうか、と彼は小さく首を傾げた。
しばらくして、レイシスが短く声を上げた。カタン、と椅子が動き、彼女が立ち上がる音がした。
「この案件、マキシマ先生に見ていただく必要があるみたいデスネ。ワタシ、ちょっと行ってきマス!」
「オレのも必要っぽいな。レイシス、一緒に行こうぜ!」
ハイ、と彼女はにこやかに返事する。一人が行けば十分だろう、という烈風刀の言葉は、走るように部屋を出ていった二人に届くことはなかった。単にサボりたいだけではないか、と烈風刀は眉間に皺を寄せ、深く溜め息を吐く。日頃からどうしようもなく不真面目な兄はともかく、何故普段は真面目に仕事をしているレイシスまでこんなことを。今日は一体どうしたのだ。彼は疲れ切った頭でぼんやりと考えた。
電子の文字が、音が、光が広々とした空間を包む。他者のいない部屋は痛いほど静かで、うるさいほど賑やかだ。画面を流れる情報が、液晶一枚隔てた向こうのプレーヤーが頑張る姿、楽しむ姿を伝えてくる。名も知らぬ彼らを思い浮かべ、烈風刀は小さく笑みをこぼした。己の努力が彼らを楽しませているのだ、と考えるとやはり嬉しい。もっと頑張ろうと更なるやる気が湧いてくるものだ。
一時的に人が途絶え、烈風刀は小さく息を吐く。最初は一人でも平気だと思ったが、存外忙しい。もう少し経てばプレーヤーも増えるだろう。二人が帰ってきたらその旨を伝え、手伝ってもらおう。そう考えて、烈風刀は画面の光で疲れた目を伏せた。
ふと、先ほどの光景がよみがえる。叫ぶ二人の表情はとても晴れやかで楽しそうだった。大声を出すのはストレス解消にいい、とどこかで聞いたことがある。その効果なのだろうか、と烈風刀は思案する。普段は真面目で頑張りやな彼女はともかく、ほわほわと何も考えず気ままに過ごす彼にストレスがあるとは全く思えないが。
ストレス、か。烈風刀は椅子にもたれかかり、宙を仰いだ。最近は小テストが重なり、加えて課題も少しばかり多い。どれも提出期限が長いため急いで片付ける必要はないのだが、何もせず後回しにすることを烈風刀は嫌っていた。故に、勉強量は増えるばかりだ。運営に関しても、ここひと月は様々なコラボレーションもあってか更新ペースが非常に早く、それに伴い仕事量もどんどんと増えていった。今はようやく落ち着いたが、昨年のことを考えるとまた更新ペースは早くなるだろう。それに疲れを感じているのは薄々気づいている。もしかして、先ほど怒鳴ってしまったのも八つ当たりではないか、と烈風刀は不安に駆られた。
自分こそ、溜まっているであろうストレスを解消すべきではないだろうか。烈風刀の思考はそこで止まった。
きょろきょろと辺りを見回す。人が来る様子もなければ、彼らが帰ってくる気配もない。つまり、今ここにいるのは烈風刀一人だけだ。誰かが見ている、ということもないだろう。
ふぅ、と息を吐く。なに、いつもよりほんの少し大きな声を出すだけだ。何も問題はない。大丈夫だ。そう己に言い聞かせ、烈風刀は口を開く。その唇はわずかに震えていた。
「あー……」
発せられた声は思ったより細く掠れていた。烈風刀は顔をしかめる。もう一度、震える唇を開き、喉を震わせる。
「ぁ、あー…………」
先ほどよりも大きいが、それでも普段の声とさほど変わらない程度のもので叫びというにはまだまだ小さい。
だんだんと羞恥心が姿を表してくる。ぶわ、と顔が赤くなるのがはっきりと分かった。あまりの恥ずかしさに耐えきれず、烈風刀は両手で顔を覆った。それでも、真っ赤に色づいた顔を全て隠すことはできていない。青にも似た柔らかな緑の髪からは、彼の兄の髪色のように染め上がった耳が覗いていた。
「無理、です……」
一体何をしているのだ。何を考えているのだ。こんなことをしてどうするのだ。二人のことを言えないではないか。己の中の何かが、自身を強く罵倒する。全て事実であり言い返せず、烈風刀は一人唸った。興味本位でやってみたことだが、今では後悔しかない。何故あの二人はこんなことができたのだ、と彼は羞恥に染まる頭で考えた。
ガタ、と大きな音が部屋に響いた。烈風刀は手を退け、急いでそちらの方を見る。翡翠の瞳には揺れる桜と紅が見えた。扉に半分隠れたその顔にはやってしまった、と気まずげな色が浮かんでいる。しかし、それ以上に好奇心やらなにやらで輝いていた。
見られていた。その事実に烈風刀の顔が更に赤くなる。茹で蛸のようだ、とはまさに今の彼のことを表すのだろう。
「い、いつから、そこに」
「……ちょっと前?」
「戻ってきたら、烈風刀がきょろきょろしてるのが見えたノデ……」
なんとなく入り辛かったんデス、と俯きレイシスはこぼす。雷刀はわざとじゃない、と主張するが、覗き見ていた事実に変わりはない。烈風刀は再度両手で顔を覆った。翡翠にも似た透き通る緑の瞳には、絶望の色が浮かんでいた。
「い、いや、でも烈風刀もそういうことするんだな!」
「そっ、そうデスネ! 意外デス!」
フォローするように二人は言葉を続けるが、全くの逆効果である。手で隠された烈風刀の口元がひくりと引きつる。もうどうにでもなってしまえ。彼の思考は自暴自棄な方向に傾きつつあった。
「まぁ、一回ぱーっとやってみてもいいんじゃね?」
「かもしれまセン。一回やってしまえば、それで満足すると思いマス!」
そんな烈風刀をよそに、二人は不穏な方向へと話を進める。その空気に気付き彼は顔を上げるが、二人の間では既に何かが決定してしまったようでもう止めることなどできなかった。
「大声出すのってとっても楽しいデスヨ? やってみまショウ!」
「誰も怒んねーからやってみようぜ。ほら」
「ぅ、え」
レイシスと雷刀は楽しげに笑みを浮かべ烈風刀に迫る。真正面からの圧力に、烈風刀は戸惑いの声を上げることしかできない。さぁさぁ、と二人はどんどんと距離を詰める。分かりましたから、と烈風刀は叫ぶように言い、彼らを押し退けた。羞恥に染まるその顔に、諦めと後悔の色が広がっていく。そんなことを気にする様子はかけらもなく、二人はにこにこと笑い彼を見つめる。明らかに面白がっているだけだ。
早く、と言わんばかりに華やかな桃色の瞳と燃えるような赤色の瞳が浅葱を見つめる。期待に染まった二色から目を逸らし、烈風刀は口を開いた。その頬は未だ赤く色づいていた。
「あ、あー…………」
「もうちょい大きくー」
どうにか音にしたそれは雷刀の声にかき消される。うるさい、と彼を睨み目で訴え、烈風刀は再度口を開いた。
「ぅ、う……あ、あー…………うぅ……」
「もうちょっとデス!」
先ほどよりも大きく開き喉から絞り出した音はレイシスの応援にかき消された。烈風刀は羞恥に俯き呻くが、彼女は笑顔で彼を見つめていた。その瞳には、純粋な励ましと溢れんばかりの好奇心が見える。彼女の期待に応えねばならない、そんな責任感が烈風刀を押し潰そうとしていた。
「ぁ……あ、ぅ、あっ…………ん、ぁ、あ…………」
声帯が震え音を発する度、彼の表情は強張り口元が引きつる。大きな声を出そうとしているというのに、烈風刀の喉はどんどんと細くなりひゅうと細い息が漏れるばかりだ。頬だけでなく目頭まで熱を帯び、視界がわずかにぼやけたように感じた。
「む、無理です! もう無理です! できません!」
耐えきれず、烈風刀は目元を腕で隠し二人から距離を取った。応援する、というよりも茶化すような声が止まる。まずい、と二人が悟った頃には、怒りの炎が宿った瞳が二人を睨んだ。その鋭さたるや、『視線がつき刺さる』という言葉はただの比喩ではないことが嫌でも実感できるほどのものだった。
「そもそも無理矢理叫ぶ必要性なんて全くありません! 何故こんなことをする必要があるのですか!」
羞恥だけでなく憤りの色が浮かぶ顔は般若の面にも似ていた。ふざけすぎたか、と雷刀は内心後悔するがもう遅い。こちらを睨む烈風刀の怒りが収まる様子は全く見られない。自分だけならまだしも、彼がレイシスまで怒ることなど滅多にないのだ。それほど、今回の彼の怒りは強いのだとはっきりと分かった。
「大体、元はといえば貴方たちがふざけていたせいですよ! 遊んでいないでちゃんと仕事してください!」
烈風刀はビシリと指を突きつける。ごめんなさい、と二人分の謝罪が重なった。それでも怒りはおさまらないのか、烈風刀は乱暴に椅子を回し元の位置へと戻る。逆ギレではないか、と喉までせり上がってきた言葉を雷刀は必死に呑み込んだ。そんなことを言ってしまえば、ただでは済まされない。
「人が増えてきましたよ。早く作業に戻ってください」
分かりましたか、と烈風刀は冷たい声と視線を向ける。はい、と殊勝な声が奏でられ、二人は自身の席へと急いで戻った。
烈風刀は様々な色が躍る画面を見つめ、重苦しい溜め息を吐いた。散々怒鳴ったことにより、更に疲れた気がする。けれども胸の内は不思議と軽くなっていたように思えた。何故だろう、と首を傾げる。はた、と先ほど己が考えたことが頭の中によみがえった。
大声を出すと、ストレスは解消できる。
なるほど、そういうことか、と烈風刀は一人頷いた。今回の場合、己の感情を思い切り外に出したのも更なる効果を発揮しているのだろう。それでも、怒りを伴うそれは心身的にあまりよいとは言えないはずだ。
今度はもっと健康的な方法でやろう。そう考えて、烈風刀は情報を目で追う。そんな無駄なことを考えている間に手を動かすべきである。彼の思考は既に仕事を行う時のそれに切り替えられていた。
いつも賑やかしいはずの部屋は、痛いほどに冷え切っていた。
畳む
#レイシス #嬬武器雷刀 #嬬武器烈風刀 #ハレルヤ組 #腐向け