SDVX[157件]
身支度はお家で済ませましょう【ライレフ】
身支度はお家で済ませましょう【ライレフ】
髪の毛いじる推しカプはどれだけあってもいいとされている。ということで髪をいじくり回す右左。
寝坊したオニイチャンときちんと起きた弟君の話。
しばし落ち着きを取り戻していた自動ドアが薄く音をたて開いていく。細っこい隙間に滑り込むように、人影が飛び込んでくる。ダン、と力強く地面を踏みしめる音が朝の教室に響いた。
「セーフ!」
大口開けて影は――嬬武器雷刀は叫ぶ。一瞬音が途切れた教室は、すぐさま元の賑やかしさを取り戻した。
「ギリギリセーフデスネ」
肩で息をしながら席に着く少年に、レイシスは時計を見て笑む。黒板の上に設置されたアナログ時計は、授業開始八分前を指し示していた。校門が開いているギリギリの時間だ。ほんの数分違いとはいえ予鈴もまだ鳴っていないのだから、彼の言う通りセーフはセーフである。
「何で起こしてくれなかったんだよー」
「二回は起こしましたよ。貴方が覚えていないだけでしょう」
背もたれに腕を預けて振り返り、兄は汗が一筋伸びる顔をしかめる。後ろの席の主――一緒に暮らす双子の弟である嬬武器烈風刀は、涼しい顔で返すだけだ。そんなことねぇって、と朱い少年は唇を尖らせる。糾弾される弟は、実の兄など一瞥もせず鞄からノートを取り出す始末である。
彼を何度も起こしたのは事実だ。揺さぶって、布団を引っ剥がして、遅刻すると言っても、片割れは身を捩るだけで起きる気配が無かった。そんなのに構っていては自分まで遅刻してしまう。そもそも、もう高校二年生なのに家族に起こされなければ目覚めないだなんて、いくらなんでも甘ったれている。自分にまで被害が及ばぬよう見捨てていくのは、烈風刀にとって当然の行動であった。いつもの行動でもあった。兄も分かっているだろうに。
はわ、と可愛らしい声が予鈴が鳴る教室に落ちる。鮮やかな桃のまあるい目が、不貞腐れたように頬を膨らませる横顔を見つめた。
「雷刀、寝癖すごいデスヨ……」
「え?」
レイシスの声に、雷刀は自身の頭へと手をやる。指摘通り、彼の髪はそこかしこが跳ねて乱れていた。普段はセットして跳ねさせている紅緋の髪の毛は、意図せず何カ所もぴょんと飛び出ていた。草刈り前で雑草がのびのびとしている芝生を彷彿とさせる有様だ。触れてやっと気付いたのか、髪の持ち主はうわぁ、と沈んだ声を漏らした。遅刻しかけたのだ、髪をセットする暇などなかったのだろう。当然であり、自業自得だ。
「寝坊するからこうなるんですよ」
「んなこと言っても仕方ねーだろ」
背を刺す弟の言葉に、兄は眇目で返す。理屈が通った反論ができないあたり、自身の非を理解しているのがよく分かる。うっわぁ、と朱は何度も跳ねた髪を押さえて引っ込めようと試みる。勝者は寝癖であった。
「ブラシでなんとかならナイデショウカ」
ポーチから小ぶりなブラシを取り出し、レイシスは席から身を乗り出す。頼んだー、と呑気な顔した当事者は声をあげて頭を少しだけ下げた。任せてクダサイ、と元気の良い声とたおやかな指が朱い髪へと伸びていく。触れるより先に、硬さの見える大きな手が白と朱の間に割って入って壁を作った。え、と声が二つ重なる。
「レイシス、必要ありません。寝坊した雷刀が悪いのですから」
きょとりと目を瞬かせるレイシスに、烈風刀は笑みを浮かべて穏やかに告げる。声の柔らかさに反して、手は惑う少女の手に合わせて動いて行く手を阻む。気配すら触れさせまいという気概に溢れた姿をしていた。
にこやかな横顔に、朱い視線が突き刺さる。少女へと向けられた碧い目が、一瞬だけ動いてそれに立ち向かう。視線の主は、つい数秒前のことなど忘れたかのように笑みを消していた。整った眉は寄せられ、まっさらだった眉間に小さく皺を刻んでいる。人より長い睫に縁取られた目は眇められ、鋭い光を宿していた。柔らかさを見せていたはずの頬はどこか強張り、八重歯がチャームポイントの口元はへの字に曲げられている。水を差すな、邪魔をするな、と言いたげな顔をしていた。よほどレイシスに手入れしてもらいたかったのだろう。弟にだって気持ちは痛いほど分かる。だからこそ、手を出し声を出したのだ。こんなことで兄だけが彼女の寵愛を受けるなどあってはならない。
「じゃあ、烈風刀やってくれよ」
「人の話聞いてました?」
もはや不貞腐れて頬杖を突く朱を、碧は一言で切り捨てる。会話をするつもりなど毛頭無いと言わんばかりだ。瞼の陰で深くなった夕暮れ空の瞳が、眠気など欠片も無い端正な横顔を睨みつける。昼空色の瞳が一度だけ鋭く返す。火花散るようなそれは、ブラシを持って首を傾げる少女には到底見せない、見せてはいけないような眼光をしていた。ハッ、と鼻を鳴らす短い音が少しずつ静かになってきた教室に落ちる。
「レイシス、ブラシ借りていい? 自分でやっからさ」
「いいデスヨ」
弟への険しい顔つきはどこへやら、ぱっと明るく表情を変えて雷刀は言葉を投げかける。まだ少しだけ不思議そうな顔をしたレイシスは、快諾の言葉と共にヘアブラシをその手に渡した。あんがと、と弾んだ声。
硬さが見える手がブラシを操り、少年は寝癖と闘う。根元から押さえ込んで梳かし、跳ねを内側に潜り込ませるように撫でつけ、いっそのこといつもの形になるように整え。様々な手を尽くしているようだが、自由な朱髪は抑圧をはねのけその身を気ままに弾ませた。少女が持って見せている鏡を道標に格闘するが、まともな形などほど遠い有様である。当然だ、整髪料はおろか水も無しでちゃんと整えられるはずがない。
ブラシの動きが止まる。角度を変えては活躍しようとしていた彼は机へと下ろされた。跳ね毛だらけの頭がゆっくりと動く。数秒前まで鏡が映し出していた真剣な目元は、眉も目尻も垂れ下がった情けないものとなっていた。
「れふとー……」
しょんぼりという表現がぴったりなぐらい沈んだ声で、兄は隣に座った弟の名を呼ぶ。目つきも声もしょげた哀れみすら感じさせるものだというのに、先ほどよりも胸の真ん中が痛みを覚えた。全ては自業自得だというのに。寝坊したのも、寝癖が付いたまま外に出たのも、寝癖を直せないのも全て兄が悪いのだと分かっているのに、良心というものは余計な勘違いをして勝手に痛み出すのだ。れふとぉ、ともう一度名を呼ばれる。追撃と言わんばかりだった。結ばれていた口から出たのは、重い溜め息一つだけ。
「……レイシス、借りてもいいですか」
どこか投げやりな調子な言葉と共に、烈風刀は手を差し出す。下がっていた眉も瞼も持ち上がり、ぱぁと効果音が聞こえてきそうなほど表情が明るくなった。おう、と打って変わった元気な声とブラシが手の中に飛び込んでくる。持ち主じゃないくせに、という言葉は面倒なので飲み込んだ。
鞄から小容量の整髪料を取り出し、少年は席を立つ。かしこまったつもりで背筋を伸ばす兄の後ろに立った。手で跳ねた毛を解し、ブラシで梳かし、指先に少量取った整髪料で形を作っていく。あっという間に自由人の跳ね毛は姿を消し、普段よりも落ち着いた朱い頭ができあがった。はわー、と可愛らしい歓声があがる。
「さんきゅー!」
鏡で一通り頭を眺めた少年は、振り返って片割れへと笑みを向ける。季節一足先に向日葵が咲いたかのようだった。感謝の言葉を投げかけられた烈風刀は、受け止めるのを躊躇うように渋い顔をする。表情筋を解してから、ありがとうございます、と少女にブラシを返す。すぐさま険しい顔に戻り、呑気な顔をした遅刻未遂へと冷えた視線を向けた。
「次からは自分でやってくださいよ」
「でも烈風刀がやるのが一番キレーじゃん」
突き放す言葉に、雷刀は悪びれる様子も無く言い放つ。それが唯一の真実だ、と言わんばかりの調子であった。反省の色など欠片も無い。浅葱の目がどんどんと冷たさを増していく。そんな目を向けられる兄はどこ吹く風といった様子だが。
「やっぱり烈風刀って器用デスヨネェ」
鏡とブラシを片付けたレイシスは、感心した様子で寝癖など影も形も無くなった頭を眺める。彼女もかなり癖の強い髪を持っている。きっと毎朝整えるのに苦労しているのだろう。だからこそ、その手腕に息を漏らしているのだ。
「まぁ、いっつもやってくれてっしな」
「そうなんデスカ?」
「そんなわけないでしょう。適当なこと言わないでください」
自分のことでもないのにどこか誇らしげに朱は言う。桃はぱちりと目を瞬かせた。すぐさま碧は否定する。袈裟斬りにするような勢いと強さがあった。漫画なら擬音でも付きそうなほど鋭く素早く、弟は呑気顔を睨みつける。察したのか、兄は一瞬口角を上げてからソーデスネ、ととぼけ声で言った。あまりにもわざとらしい、怪しさしかないしらばっくれた音色である。視線が鋭さを増す。逃げるように、整えられた頭がくるんと回ってそっぽを向いた。
いつもではない。ごくたまにだ。朝たまたま気付いて、たまたま時間があった時にやってやる程度だ。あんまりにも酷くて彼の手に負えない時だけ、乞われた時だけやってやる程度だ。それでも他人の頭に施すのが慣れるほどやっているという事実はこの指先が語っているのだから、たちが悪いったらない。
電子音が教室に響き渡る。時計を見ると、いつの間にか本鈴の時間になっていた。たかが寝癖一つに、しかも他人の寝癖にこんなに振り回されるだなんて。波打ち際のような目が眇められ、日に焼けていない眉間にはっきりと皺が寄る。ガタガタと椅子たちの鳴き声の中に、重苦しい息が落ちていった。
畳む
洗濯日和、二度寝日和【神十字】
洗濯日和、二度寝日和【神十字】
毎年恒例五月十日はGottの日!
ということで神十字。なんかごちゃごちゃ言ってるけど雰囲気で読んでください。
洗濯物をする神様と人間の話。
青を背に白が広がる。四角いそれは、まるで空の色をハサミで切り取ってしまったかのようだった。うっすらと熱をまとった風が世界を吹き抜ける。春に芽吹き育った草木とともに、広大な白は羽ばたきのようにひらひらと身を翻した。
眼前に広がる美しい白に、クロワは小さく頷く。空とはまた違う碧い目は普段よりも輝きを増し、口元は綻びつつも力が宿っている。洗濯物が入っていた大かごを前にした背中はどこか誇らしげだった。
今日は朝から良い天気だった。一足先に夏が来たかのような深い青広がる、雲一つ無い晴天が世界を包んでいたのだ。昇った太陽は美しいまでに輝き、風は晴れ模様にはしゃぐように駆け抜けている。絶好の洗濯日和だ。特に、シーツのような大物を洗うにはこれ以上ない条件が揃っている。
そうやって朝から洗濯に精を出し、まっさらに洗い上げ、まっすぐに干し終えた身体は満足感でいっぱいだった。それはそうだ、たとえ時間がかかっても綺麗に洗えた洗濯物がそよぐ様はこの上なく気持ちの良いものなのだから。
「くろわぁ……」
後ろから輪郭がどこかにいってしまったかのような声。ほぼ同時に、背中に小さな衝撃が加えられた。青年が振り返るより先に、その腹に腕が回される。袖がまくり上げられ剥き出しになった腕は、少し硬い腹をゆるく抱きしめた。寝惚けて蹴っ飛ばした毛布をたぐり寄せる時とよく似ていた。
「ねみぃ……」
「……珍しいですね」
「あんな早くに叩き起こされたらさすがにねみぃって……」
寝言のようにやわく言葉を紡ぐ青年――否、Gottに、クロワは穏やかに返す。戻ってきたのはやはり寝惚けたような声だった。本当に眠いのだろう。
確かに、シーツ洗濯したいがためだけに、不敬極まりなく早くに彼を起こしたのは事実である。その上、興味を示した崇める存在は二度寝することなく手を貸してくれたのだ。疲労も相まって尚更眠いのだろう。大物の洗濯は重労働なのだ。
しかし、こうも眠気を主張してくるのは本当に珍しい。何しろ、相手は神である。人間ではない、人の理など通用しない――睡眠を取る必要も、食事を摂る必要も無い、何もかもを超越した存在なのだ。人間のように『眠い』なんて言い出すようになったのはここ最近のことである。
人間のように寝て、人間のように起きて、人間のように食べて、人間のように働く。すぐに異物を排除しようとする人間たちに馴染むためには必要なことだ。けども、それは外で表面を取り繕っていればいいだけの話である。本当に人間のように腹を空かせたり、疲れたり、眠たげにする必要は無い――人間のように変化する必要などない。なのに。
弱っているのだろうか。満足げに輝いていた碧い目に、瞼の影が落ちる。陰った瞳の奥は、どんどんと暗さを増していく。沈みゆく色は、夜明けにはまだ遠い空を思わせる。
最近は子どもたちにも『お伽噺』は広まり、神の存在を認知し、信じる者は増えてきたはずだ。わずかながらとはいえ信仰は増したのだから力が戻ることはあっても、衰える可能性は低い。けれど、現実はヒトに近づきつつ――衰え、人間風情と同じ場所に立ってしまっていて。
己の信仰心が薄れているのか。否、そんなことはない。誰よりも彼を崇め、誰よりも彼に尽くしてきた。その力を取り戻さんと奔走してきた。強固になるならまだしも、薄れゆくはずなどない。けど、現実は。全てを示す彼の身体は。
「くろわぁ」
今にもとろけ落ちてしまいそうな声が自身を示す音をなぞる。首だけで振り返ると、茜空が広がった。活力に満ちた朱は瞼でわずかに姿を隠している。山の向こうに落ち行く夕陽のような光景だ。真ん丸でぱっちりとした、可愛さすら感じさせる目はどこか輪郭を失っているように見える。眠気が鮮やかな色をぼやけさせるように色を塗っていた。
「抱き心地悪い。硬い」
「それはそうでしょう」
「そーじゃねー」
むくれた声とともに、肩にぐりぐりと頭を擦り付けられる。全てお見通しなのだろう。分かりきった現実に、全てを見通す存在に、青年は密かに息を吐いた。無意識に身体が強張っていたことなど、触れる彼に隠せるはずがない。神が人間如きの思考をなぞることなど容易いに決まっている。
深呼吸するように息を吐き出し、強張っていたからだから力を抜いていく。吐き切るとほぼ同時に、腹に回った腕に力が込められた。袖をまくった腕が、剥き出しの腕が、薄布一枚隔てた腹に沈み込む。柔らかな肉の感触。うっすらと感じる骨の硬さ。生きている、穏やかなぬくもり。どれも手放したくない、失いたくないもの。
「こないだのシーツまだある?」
「あー……、切ってしまいましたね」
問う神に、クロワは眉を八の字にした。以前片付ける際に引っかけて盛大に破れてしまったシーツは、修繕を諦めて掃除に使ってしまったのだ。ベッドを覆うほどの布地は残っていない。無理をしてでも繕えばよかったか、と今更後悔が湧き上がってくる。そもそも、駄目になった時点で買い足すべきだったのだ。先延ばしにしたツケが崇める存在を蝕んでいる。こんなこと、あってはならないのに。
「じゃあ、タオルある?」
「ありますけど、ベッドを覆えるほどのものはありませんよ」
「何枚も敷きゃいいだろー」
朱い頭が硬い肩に擦り付けられる。少し痛むが、拒絶する権利など無い。全て己の不手際が招いたのだ。そもそも、崇め奉る存在にその身を委ねられて拒否する人間などこの世に存在するはずがないのだ。
「一緒に寝よ」
「台所の掃除が残っているので」
えー、とむくれた、今にも眠ってしまいそうな声があがる。腹を抱きしめる腕の輪が更に縮まった。それでも苦しさを覚えない程度なのだから明確に加減をしているのが分かる。じゃれる動きだ。脆い人間に合わせる、慈悲深い動きだ。
「用意しますから」
腹に回った手をノックするように軽く叩く。えー、とまた輪郭が柔らかな声があがった。渋々といった調子で、ゆっくりと腕が去って行く。確かに感じていた温もりが去っていく。肩に残る頭の重みが、彼がまだ存在している証明だった。
眠ってほしくない。そんなわがままを言うなどあり得ない。人間如きが神を動かそうとするなどあり得てはならない。けれど、聞き分けの悪い脳味噌は口から言葉を吐き出させようと回転する。残った理性が全てをもってして、その醜い動きを封じ込めた。
だって、また目覚めてくれる保証なんてないのに。
畳む
降りこめる本能【ライレフ/R18】
降りこめる本能【ライレフ/R18】
雨で薄暗い中暑いのも忘れて致す右左が見たかっただけ。
ぬかるみに足を突っ込んだような粘ついた音が鼓膜にへばりつく。現実は違う。そんな無邪気な子どものような動きによるものではない。粘膜と粘膜が擦れあい、潤滑油ではしたなく濡れそぼった穴がみっともない声をあげているのだ。身体が動く度、粘り気のある液体がこねくられる湿った音が、引き締まった肉と肉がぶつかりあう乾いた音が薄暗い部屋に響く。日常とはかけ離れた淫らな合奏が部屋を満たしていた。
業務も課題も無い休日で。テストは終わったばかりで急いで勉強する必要性も薄くて。有り体に言えば暇で。外は雨で。二人きりで長く過ごせるのは久しぶりで。
互いにごく普通の、年齢相応に健全な男子高校生だ。つがいを求める欲望など、つがいと触れあう欲望など、腹の底にずっと抱えている。見ないふりをしているだけで、いつだって燻っている。暇な土曜日の昼下がりにそれが燃え上がり爆発して発露することは必然的とも言えた。
そうやって時間も場所も常識も捨て去りソファに雪崩れ込んで、行儀が悪いと指摘するのも馬鹿らしく服を脱ぎ捨て、肌と肌とを直接触れあわせて、粘膜と粘膜で繋がる今に至る。
ぐじゅ、ぶちゅ、と濁った淫猥な音があがる。耳を塞ぎたくなるような響きが鼓膜を震わす度、凄まじい勢いで脊髄を電気信号が駆け抜けていく。快楽と命名されたそれは、脳味噌をぶん殴り烈風刀のまともな思考を奪っていった。ゴリゴリと常識ぶった部分が削れていく頭は、『きもちいい』の五音節を理解することで手一杯だ。
きもちよくて、きもちよすぎて、閉じる機能を忘れた口から声が漏れる。上擦ったそれは、少女のものだと勘違いされても仕方が無い響きをしていた。恥ずかしいと思う機能すら失われた頭は、我慢することを忘れた脳味噌は、本能が赴くままに甘い声を――今まさに繋がっている恋人の情欲を煽る音色を奏でた。
肉の悦びから逃れるようにぎゅっと閉じられていた目が薄く開いていく。涙をたたえた瞳は、大切に手入れされ澄み切った池を思い起こさせた。こんこんと湧いて出て溢れる水が、紅潮した肌に透明な線を引いていく。熱に浮かされとろけきった瞳は、本能に炙られて色付いた肌は、整ったかんばせを塗らす涙は、耳をも溶かすような嬌声をあげる口は、欲望の炎に薪をどんどんとくべていく。獣の本能に支配されつつ雷刀は、衝動がままに腰を打ちつけた。同じく獣欲に蝕まれる弟も、湧き出る衝動がままに甘ったるい声をあげた。
目の前の首に回した腕、汗ばんだ肌と肌がくっつきあって何とも言い難い感触を生み出す。雨で気温が下がって涼しいから、と今日は冷房を消していたのを頭のまともな部分がかろうじて思い出す。雲で隠れて日が差さないとはいえ、部屋は生ぬるい空気で満たされているだろう。その上激しく動いているのだから、汗を掻くのは必然であった。普段ならば暑いだなんだと文句を垂れる口は、意味を持たない音をこぼすだけだ。耐えられずリモコンを取るであろう手は、己の腰をがしりと掴んで離そうとしない。汗と体液で濡れた肌は、今は不快感を遙かに上回る快感と幸福感を生み出した。
涙でけぶった視界の中、ギラつく鮮やかな唐紅だけが浮き上がる。恋人の象徴である色。恋人が目の前に存在しているという事実。恋人が己だけを見つめているという証左。全てが馬鹿みたいに拍動する胸の奥に、愛する人を迎え入れた腹の底に更なる火を灯す。ぁッ、とソリッドな声が部屋に落ちた。
耳障りな水っぽい音が、赤みを増した耳に、淫悦でとかされた脳味噌に叩きつけられる。常ならば表現し難いほどの羞恥を覚えるはずのそれは、ひたすらに本能を煽って身体を昂ぶらせていく。悦びを謳い上げる口が、らいと、らいと、と愛する人の名をどうにか形作る。きもちよさに支配された脳味噌は、大好きな人を求める声を発せさせた。愛を抱えた心も飢えた身体も満たされているはずなのに、碧い少年は足りないとばかりに拙く音を紡いでいく。それがつがいにこれ以上無く効くことなど知らずに。
れふと、と吼えるような声。同時に、ごちゅん、と身体全てに響き渡るような衝撃。情欲を煽られた朱い少年は、丁寧に解され柔らかになった内部に一気に自身を突き入れる。閉じた肉を掻き分けられ、めいっぱいに刺激され、快楽信号がキャパシティオーバーになりそうなほど叩きつけられ、烈風刀は悲鳴めいた嬌声をあげた。それもまた、雷刀の腹に秘めたる獣欲を煽る。エナメル質が軋む高い音が卑猥な合奏の中に落ちた。
ぁ、あ、と突き上げられる度に掠れた細い声が開きっぱなしの口から吐き出される。まるでちゃちいおもちゃのようだ。おもちゃめいた単純な動作しかできないほど、少年の身体は快楽に支配されていた。ただひとつ、腹の中身を除いて。
ぐっ、と雄肉が這入ってくる。突き進むそれを逃すまいと、もっと奥へと誘わんと、ナカはぐねぐねとうねる。快楽を、子種をねだるようにまとわりついて絡みつく。まだ果てまいと、もっとつがいを貪らんと、更なる快楽を求めんと、剛直はそれを振り切り去っていく。まだ足りない、なんてわがままを通そうと、肉色の粘膜が蠢いてすがりつく。全ての動作がはしたないピンク色の悦びを生み出し、幾重にも重なった理性の皮を剥がして本能だけを剥き出しにしていく。雨天で陰った部屋に獣めいた声がどんどんと積もっていく。
腹の奥底を小突かれる度、身体から力が抜けていく。快楽ばかりを受容して言うことを聞かない脳味噌は、筋肉にもろくに指令を出さずにいた。汗ばんでうっすらと濡れた腕が、同じく汗ばんだ首をなぞるようにして解けて落ちる。上手く着地できなかった右腕が、だらりとソファの座面から垂れた。普段ならばすぐに上げて戻すが、今ばかりはそんな余裕がなど無い。腹の底から響き渡る法悦を味わうのに必死な身体は、ろくに動くことができなかった。
ハ、ぁっ、と呼吸なのか声なのか分からないものだけが口から漏れる。腕から伝わる温もりが無くなった分、腹が切なくてたまらない。欲しくて、触れたくて手を伸ばしたいのに、快楽に浸りきった脳味噌は能動的に筋肉へ電気信号を送ることなどとうに諦めていた。突かれる度、落ちて垂れた腕が揺れる。ソファの生地が擦れては心地良さなど覚えないはずだというのに、今ばかりはそれすらも快感を生んだ。腹の奥に突き込まれたものに全身を作り変えられてしまったようだ、なんて馬鹿げたことが頭の隅に浮かぶ。突かれた瞬間、それは弾け飛んで消えた。
ごちゅん、なんて漫画めいた音が聞こえるほど、行き止まりを強く穿たれる。瞬間、世界が止まった。
「――ァっ、あっ!」
一拍遅れて、凄まじい情報が――快楽が全身を駆け巡る。どうやら、許容量を超えたそれは脳味噌を焼け付かせたらしい。受容しきれぬそれを逃がすように、組み敷かれた身体が大きく跳ねる。喉仏が浮かぶ首がぐっとしなって、形の良い頭が固く作られているはずのソファの肘掛けに沈み込んだ。濃い布の上に鮮やかなが若葉が散る。額に張り付いていたそれも、衝撃のあまりに宙に浮かんでまた落ちた。
ままならない呼吸の合間、囀るように目の前の愛し人を呼ぶ。さいこうにきもちいいのに、おなかが寂しくて、腕が寂しくて、ぬくもりが足りなくて。けれども、快楽に融かされてろくに動かない身体は声を発するので精一杯だ。言葉だけでも兄を掴もうと、兄に縋りつこうと、弟は何度も名前を繰り返す。三度目を発するところで、ひぁ、という己自身の高い声が遮った。声も身体もどろどろに融けて、彼に融かされて、形を成さなくなっていく。それがきもちよくてたまらない。
腰の右側をひやりと空気が撫ぜる。代わりに、左頬に温かなものが訪れた。頬に触れられているのだと気付くより先に、唇に熱。口内に熱。触れる度に痺れるようなそれに、はしたない声が際限なく湧いて出てくる。全て、雷刀の口内に吸われてくぐもったものになってしまった。
「ァ、う……、ッ、ゥ……」
絡もうとする舌はどちらも溢れるほど唾液をたっぷりまとっていて、捕らえられることができない。それでも、ぬめる表面を熱いものが掠めていく感覚は腰を重くするには十分な刺激だった。痺れを切らしたように舌が離れていく。追いかけてだらしなく伸ばされた己のそれが、温かなものに包まれる。ぢゅう、と行儀の悪い音。同時に、凄まじい電気信号がシナプスを殴った。舌を吸われ扱かれる快楽が、その間も絶えずナカを穿たれる快楽が、脳味噌をダメにしていく。食らわれる碧にできることなど、もう甘ったるい――つがいを煽り、焚きつけ、昂ぶらせる声を漏らすぐらいだ。
張り出した傘がゴリゴリと内部を削るように去っていく。追いかけるように締め付ける内壁を、見事な先端が勢いよく突き進んだ。熱ときもちよさでとろけた肉は、張り裂けんばかりに法悦を叫んだ。連動するように、弟の口からも淫悦に染まりきった嬌声があがる。垂れ下がった目元から透明なものが流れて赤く染まった頬を静かに彩る。
ずるぅ、とされるがままだった己の舌が愛しい人の口から力無く抜ける。元の場所にしまわれるはずのそれは、喘ぎ声とともに突き出され天を向いた。興奮で湧いて出る唾液が口から溢れて、肌をしとどに濡らしていく。赤く熟れた粘膜が濡れてつやめくのはあまりにも刺激的な光景だ。食らう者が短く低く喘ぐぐらいには。
きもちよすぎて、もう口を動かすだけで精一杯だ。脳味噌は快楽を受け取るばかりで肉体を動かす信号を送ることなどとうに忘れていた。また愛しい人に触れたいのに、腕はもう指一本動かす余裕など無い。代わりと言わんばかりに、兄の腰に軽く回された足がしがみつくように、抱き締めるように絡みついた。本能に支配されているのだろう、振りほどかんばかりに突き出されるその身体に、烈風刀は鍛えられた足で縋りつく。汗ばんだ肌同士ではすぐに滑り落ちてしまうだろうに、外でも中でも恋人を抱き締めた。とうの昔に肉欲に溺れてダメになった脳味噌を本能が動かしてたのだ。
腰を掴まれる力が強くなる。ただでさえ激しかった腰つきが更に早まり、大胆な、重いものになる。上から降り注ぐ獣めいた吐息が唸りめいた嬌声へと変わっていく。何度も見てきた光景だ。何度も体験してきた動きだ。だからこそ、それが何を意味するかなどすぐさま分かる。この腹に精を吐き出し、種を植えつけようとしているのだ。は、ァッ、と艶めいた声が、どこか笑みを含んだ声が漏れる。だって、そんなの最高に決まっているではないか。期待が声に表れないわけがない。
れふと、と名を呼ばれる。ぼやけた視界の中に映るのは、険しげに眉を寄せ、目を細め、こわばったように口を開く恋人の顔だ。どれもが肉の悦びにとろけていて、どれもが己の欲望を焚きつけるものだった。視線に、声に、雄を迎え入れた腹が反応する。みっともなく大口開いて咥えこんだ場所が、きゅうと収縮するのが己でも分かった。あ、と濁った、熱で焼けた声が落ちてくる。彼がきもちよくなっている証拠だ。それが嬉しくて、また腹が勝手に蠢く。諫めるように一発ぶちこまれた。悲鳴めいた喘ぎが仰け反った喉から奏でられる。
暗い部屋のはずなのに、視界に白いものがちらつく。細かなパーティクルが何度も散る様は、己の限界を――頂点に上り詰めつつあることを示していた。腹に渦巻く熱を吐き出したくて、一番きもちいいところに行きたくて、内部は雄肉を煽るように細かに締めては撫でてを繰り返す。全くの無意識であるが、効果はてきめんだったようだ。腹を穿つ動きが更に重いものになった。
ぐ、ぁ、と降ってくる嬌声が数を増していく。ごちゅん、と耳に、骨に音が響く。掠れた短い音が聞こえた瞬間、腹の中で熱が爆発した。一番奥から熱いものが広がっていく。内臓全部を融かしてしまいそうな凄まじい温度に、目の前で、頭の中で、何かが弾けた。
「――ッ、ぅ、あっ!」
ビクン、と身体が跳ねて背が反る。頭が反る。盛大な、艶やかな、とろけた声がみっともなく開かれた口から跳ね出る。部屋に喜悦溢るる嬌声を響かせる。瞠られた目から涙が弾け飛んでソファの生地を濡らす。
腹の中も外も熱い。どちらも精によるものだ。どちらもきもちよくてたまらないものだ。ねだるように、達したばかりの内部がうねって硬度を失いつつある剛直を撫でて回る。うぁ、と上擦った声が聞こえた。更に腹の中に熱いものが――精が、種が、愛が注ぎこまれる。何もかもを焼きつくすその感覚に、横たわった身がまた大きく震えた。あ、ぁ、とはしたない、悦びに満ち満ちた声が開きっぱなしになったままの口から漏れる。熱に浮かされたそれは、腹を満たす欲望と同じほどどろりとしていた。
腹に、胸に、腕にぬくもり。耳の横を少し湿った柔らかなものが掠めていく。その感覚は分かれど、達したばかりの身体は反応する余裕すらなかった。あー、と少しだけ上擦った、満足げな声が耳朶を撫でる。兄が覆い被さってきたのだと気付くには随分と時間を要した――天上まで放り上げられた頭ですぐに状況を理解しろという方が無理なのだ。
短く、どこか甘さの残る呼吸が次第に落ち着いてく。やっとまともな量の酸素を取り入れた頭は、ゆっくりと現実の輪郭を辿り寄せていった。のしかかり触れる身体が重い。汗ばんで湿った肌が触れて気持ちが悪い。空調が効いていない部屋が暑い。貪るようにまぐわっていた間は快楽でしかなかったそれらは、今は不快感しか生み出さない。常人の思考回路を取り戻した脳味噌は快不快を正常に認識しだしたのだ。
パタパタ。軽い音が荒い呼吸の間を縫って部屋に落ちる。雨はまだ止んでいないようだ。朝から降っているのに。どれほど降り続くのだろう。明日には晴れるだろうか。洗濯物が。現実に足を付けた頭の中を所帯じみた考えが巡っていく。
そうだ、洗濯しなければいけないのだ。雨で部屋干しをするしかないのだから数は少ない方が良いに決まっているのに、何故わざわざ洗濯物を増やすようなことをしてしまったのだろう。しかもソファなんて後始末が大変なところで。冷静さを取り戻しつつある少年の頭の中に後悔ばかりが降り積もっていく。それほどまで溜まっていたのだ、なんて片割れが使いそうな言い訳がちょっとだけ動きの鈍い思考の底から湧いて出てくる。あまりにも稚拙すぎる言い様に、自己嫌悪は募っていくばかりだ。
「れふとー?」
頬に柔らかな、温かな感触。いつの間にか閉じていた目を開けると、そこにはこちらを覗き込むように見つめる兄の姿があった。涙というフィルターが消え失せた視界の中、朱い瞳がうっすらと部屋に差し込む光を映して輝く。つい数分前までは獣めいてギラついていたというのに、今はすっかりと穏やかな、けれどもまだ熱が残って輪郭がとろけたものになっていた。興奮で溢れた唾液でつやめく唇がゆっくりと動く。
「だいじょぶ?」
「だいじょうぶです」
同じほどの調子で弟は返す。声を出すことで、ようやく長く息を吐き出すことを思い出した。音が聞こえそうなほど深く呼吸を繰り返す。キックと同じほど重く響いていた鼓動はだんだんと速度を落とし、普段のものへと戻っていく。一気に押し寄せてきた疲労に、はぁ、と重く深い嘆息が漏れ出た。
互いに汗やらなんやらでどろどろだ。シャワーを浴びなければ。閉め切って運動したから身体も部屋も暑い。もう冷房を点けてしまった方がいいだろう。放り出した服をまとめておかねば。ソファの後処理も早い内にしないと。ほんの数秒考えただけでタスクがどんどんと積み上がっていく。どれも疲れ切った身体でこなすにはあまりにも重労働だった――全て自業自得なのは重々承知なのだけれど。
パタパタ。バタバタ。サァ。ザァ。窓ガラス一枚隔てて鈍くなった音が静かな部屋に転がっていく。雨の日の湿ったぬるい空気が二人を包んでいた。
畳む
雨と横顔【ライレフ】
雨と横顔【ライレフ】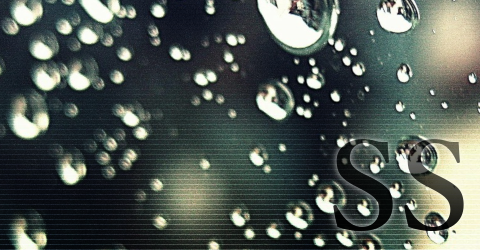
横顔に見とれるシチュが好きなんすよというヘキ。顔面と思考が一致してないのが好きなんすよというヘキ。
雨の日の右左の話。
窓が揺れる。強風を受けガタガタと震えつつもしかと立つ様は頼もしいものである。それでも、凄まじい音をたてる暴風を前にしては割れてしまうのではないか、倒れてしまうのではないか、とほんの少しの不安が残る。杞憂だと分かっていても、このゴウゴウとかビュウビュウとか激しく低い自然の呻り声を聞くと心の隅っこには暗いものが残るのだ。
健気に雨風を防ぐ窓ガラスの向こうを眺め、雷刀は小さく息を吐く。薄い板一つ隔てた外は、台風一歩手前の暴風雨が我が物顔で駆け回っていた。空は墨めいた黒で埋め尽くされ、太陽など陰すら無い。視界いっぱい、世界いっぱいに広がる様を見るに、今日一日中はこの調子だろう。
ただでさえ横殴りの酷い雨だというのに、子ども程度なら吹き飛ばしそうな勢いの風まであっては、せっかく咲いた桜は全て散ってしまうだろう。花見は先週して正解だったようだ。だけども、やはりあれだけの美しいものが蹴散らされてしまうのはわずかに心が痛む。綺麗なものは傷つけられぬままでいてほしいのだ。やだなぁ、と思わず沈んだ声が漏れた。
暗い世界から、淀む思考から視線を外し、弟を横目で見やる。同じように窓の向こうを眺める瓜二つの横顔は、普段と少し違った表情をしていた。
穏やかな曲線を描く整えられた眉は、今は少し鋭い角度になっている。寄せられたその間には、薄く皺が刻まれていた。いつだって目の前をはっきり見通す碧の目は、今は眠気に抗うように細められている。そこに宿る色は陰っていて、けれども普段よりもはっきりとしているように見えた。すっと通った鼻、その下に佇む口は直線を描くように結ばれている。まるで何かを堪えているかのようだ。普段はまろく柔らかな頬は、今はどこか強張っているように見える。固く閉じた口元がその印象を強めていた。
キレーだ。兄はぼんやりと考える。子どもたちやレイシスに接する時の柔らかな表情も綺麗で可愛らしいが、今のような険しさがよく見える表情も端正で美しい。惚れたフィルターもかかっているだろうが、やはりどんな表情でも恋人は素敵なのだ――たとえ何を考えていようとも。
「コインランドリー行けばいいじゃん」
「この暴風雨で外に出れるわけがないでしょう」
呆れた調子の朱の言葉に、碧は溜め息まじりに返す。腕の中に抱えられた洗濯物かごが彼の身体に食い込むのが見えた。山盛りの衣服がバランスを崩しかけるも、鍛えられた手によってすぐさま押し止められ中に押し込まれた。
「明日にすればいいだろー」
「バスタオルは早めに洗ってしまいたいんですよ」
じゃあバスタオルだけ洗えばいいのに、と出かけた言葉を飲み込む。ベランダが隔絶された今、バスタオルのような乾きにくいものを部屋干しにすれば臭いが付いてしまうのは交代制で家事を担当する己もよく分かっていた。除湿機とサーキュレーターがどれだけフル稼働しようも、最近の洗剤がどれだけ臭わないことを謳っていても、うっすらと湿った臭いが残ってしまうのだから面倒なものである。毎度ながら乾燥機、もしくはドラム式洗濯機が欲しくなる。置く場所も無ければ手が届かない値段の代物なのだから、永劫に叶うことはないが。
はぁ、と烈風刀はまた一つ溜め息をこぼす。どれだけ溜息を吐こうが天気は回復しないと分かっているだろうが、そうでもしなければやってられないことは痛いほど伝わってきた。己が同じ立場だったら同じかそれ以上にごちゃごちゃと言っていただろう。
険しげな、恨めしげな横顔から視線を外し、雷刀は携帯端末を取り出す。光る液晶を指で撫で、ニュースアプリを起動する。天気のタブ一面に表示されているのは傘のマークだけだ。どの時間帯にも鎮座しているそれの上には、八〇だとか九〇だとかの高い数字が書かれている。これでは今日中に洗濯するなど不可能だろう。つまり、洗濯物を余計に増やすような行動はできないのだ。
はぁ、と溜め息が二つ重なる。風を必死に受け止める窓の悲鳴が、小さなそれをかき消した。
畳む
もうちょっと季節ってものを考えなさいよ!【はるグレ】
もうちょっと季節ってものを考えなさいよ!【はるグレ】
最近春なのに暑すぎない????というあれ。京終始果絶対熱中症体験してるだろというIV当時からずっと見てる幻覚。
春の夏日に帰るはるグレの話。
世界に光が降り注ぐ。つい先月ならばもう茜に染まり始めていた空は、まだまだ昼の色を残している。傾きつつあるものの、冬の越えた太陽は元の調子を取り戻し暖かな陽光をあたりに振りまいていた。それはもう、元気が良すぎるぐらいに。
溜め息一つ吐き、グレイスは空を一瞥する。年が明けてから頭上を覆い尽くしていた厚い雲はさっぱりと消え、抜けるような青さを取り戻していた。太陽を遮るものなど一つも無い。おかげで強い日差しが目に刺さって痛いほどだ。焼き付いてちらつく目を瞬かせ、少女はまた息をこぼした。
「あっついわね……」
季節が一つ変わり、暖かな春が訪れた。しかし、最近はあまりにも暖かすぎる、というよりも暑い日々が続いていた。今日なんて、四月だというのに春から一足飛んで夏日である。桜はまだ華やかに咲いているというのにこの気温なのだから、季節感がごちゃまぜだ。四季のあるネメシスに来て日が浅い己にとっては尚更である。
うんざりといった調子で細められた躑躅の目が、音もなく動いて隣を見やる。視線の先に現れたのは、今日も今日とて隣やら後ろやらを付いて回る京終始果だ。黒く長い髪はいつも通り後ろで一つにまとめられ、身体はいつも通り萌葱の忍装束に包まれている。いつも通り、深い緑の長袖に黒い手甲、大ぶりな脚絆、丈の短い外套、とどめに長い襟巻きを巻いた姿だ。
「あんた、暑くないの……?」
懐疑をたっぷり乗せた声と視線で少女は問う。彼の格好は春の陽気にもあまりにも似つかわしくないものだ。寒がりだってもっと程度というものがあるだろう。加えて、今日のような夏めいた様相ならば輪を重ねて異常だ。こんなに着込んでいて、この気温を乗り越えられるものなのだろうか。忍といえど、中身はただの人間――肉体を持った存在である。暑さ寒さを感じるはずだ。けれども、彼は普段と変わらず顔色一つ変えないのだから外からでは何も分からないのだ。実態を知るには本人に訊ねるほか無い。
「特に……」
「ほんと? 喉渇くーとか、ふらふらするーとか、そういうの無い?」
首を傾げる始果に、グレイスもまた首を傾げて問う。繰り返しになるが、この少年は表情を変えるということを知らない。否、多少は変わるも、その度合いは微細である。気付けるのはこちらに来る前から付き合いある四人ぐらいだろう。喜怒哀楽はもちろん、快不快など一目で見抜くなど不可能である。何より、彼は人間らしい所作を知らない。己のように夏日に『暑い』と口に出したり、吹雪くさなかに『寒い』と着込んだりすることなど無かった。だからこそ、疑わしいのだ。こいつは自身の変化に気付いていない可能性の方が高いのだから。
あぁ、と襟巻きから覗く口が小さく音を発する。口元に指を当て、狐の少年はわずかに頷いた。
「少し頭がぐらぐらしますね……」
「そっ……それ、熱中症じゃない!」
事もなげに言う始果に、グレイスは悲鳴めいた声をあげる。こちらの夏はまだちゃんと味わっていないものの、暑い日に引き起こる『熱中症』というものについてはレイシスと烈風刀に聞いていた。ここ数年は春でも暑い日が増えてきているから、と事前に注意と対処法を教えられていたのだ。気温変化に慣れていないんですから気をつけてくだサイネ、と言われたのは記憶に新しい。まさしく『気温変化に慣れていない』彼が、式典以外では服装を変えるということを知らない彼が陥ってしまったのだろう。
「水! 水飲みなさい!」
鞄に慌てて手を突っ込み、躑躅は取り出したペットボトルのキャップを開ける。こぼす危険性など忘れ、手甲に包まれた手に勢いよく押しつけた。不思議そうに見つめた狐は、透明なそれに口を付ける。ちょっとずつよ、と急いで言い足す。蒲公英色の目が瞬き、言葉の通り一口ずつ小さく水を飲み下していった。
こういう時はたしか、水飲ませて、冷やして、冷たいもの食べさせて。冷やすってどの部分だっけ。たしか『首』の付く場所だったはず。凄まじい勢いで頭が回転し、脳内の引き出しを手当たり次第開けて対処法を探していく。とりあえず、冷やさねばならないのは確実だ。先ほどの水は常温である。もっと冷たいものを飲ませねば。何を。目が回りそうな勢いで思考が巡る。縋るようにビビッドピンクの瞳が辺りを見回す。端っこに引っかかったのは、青と白の看板だ。空に向けるよう高くそびえたつそれは、見慣れてきたコンビニエンスストアのロゴであった。
「歩ける? 大丈夫? 水飲んでるわよね?」
「大丈夫です……」
問い詰める少女に、少年は短く返す。常と変わらぬ声だというのに、今はなんだか弱っているように聞こえた。不安による錯覚か、それとも実際に衰弱しているのか。どちらでも変わりは無い。症状が出ている今、とにかく対処せねばならないのだ。
二人――常磐の袖をしかりと掴んだ少女と、言われた通りちびちびと水を飲む少年は看板の下目指して歩く。ついつい早足になってしまいそうなのをどうにかこらえ、グレイスはやけにしっかりした足取りの彼を引っ張っていった。
足取りが速くなるのを抑えられなかったのか、コンビニにはものの数分で辿り着いた。わずかに張り出た庇の陰に始果を押しやる。ここで待ってなさいよ、と指を差して告げ、少女は急いで店内へと駆けていった。開けたアイスケースの中から氷菓と氷を掴んでレジへと足早に向かう。慣れぬ会計をどうにか手早く済ませ、走る一歩手前の早さで外へと出た。
「これ食べて! あとマフラー取りなさい!」
「はい……」
スティックタイプのアイスを押しつけ、言葉より先にマフラーを引っ剥がす。されるがままの少年は、慣れない手つきで袋を開けて水色のそれを口に入れた。引き抜いた長い襟巻きを手早く畳み、ひとまず鞄に突っ込む。あらわになった首元を探り、短い外套もどうにか脱がせた。これで肌が出た。熱が放出できるはずだ。いや、出してよかったのだろうか。直接日光に晒されては熱くなるだけではないか。どうだったか。必死に記憶を引っ張り出した頭の中はぐちゃぐちゃで、何が正しいのか分からなくなる。苦しげに呻き声を上げながら、グレイスは始果の横に並ぶ。少しばかり背伸びをし、買ったばかりの袋入り氷を始果の首筋に当てた。薄い外套が剥ぎ取られた肩が小さく震える。ミモザの目が見開いたままこちらに向けられた。グレイス、とアイスを咥えていた口が疑問形で名前を紡ぐ。
「たしか首冷やさないといけないの。我慢しなさい」
「はい……」
切羽詰まった声に気圧されたのか、忍の少年は小さく首を傾げてながらも言われるがままに首筋をさらけ出したままでいた。シャリシャリとシャーベット状のアイスが囓られる音が二人の間に落ちていく。袋の中のロックアイスの角が取れてきた頃、少年の口から何もまとっていない薄い棒が引き抜かれた。刻印された『はずれ』の文字が青空の下に晒される。
「どう? 良くなった? まだダメ?」
「少し落ち着きました……」
「少しじゃダメなのよ! ほら、これ持って。首に当ててなさい」
ゴミを回収し、グレイスは空いた手を誘導して首筋に当てたままの氷を本人に持たせる。頑丈な防具に包まれた手は導かれるがままに忠実に動き、首の後ろを押さえる彼女の手とバトンタッチした。しばらくぶりに踵を地面につけ、少女は深く息を吐く。未だに状況を理解できていないこいつのことだ、まだまだ休む必要があるだろう。いつでもどこでも突然現れる――つまり、いつだってどこにいるか分からない彼が一人で倒れたら誰も看病できないのだから。
「それ、ちゃんと当てときなさいよ」
強い調子で言い捨て、少女はまた店内へと駆けていく。今度は二つセットのアイスと水のペットボトルを引っ掴み、レジへと駆けた。同じ足取りで外へ出、言われるがままに氷を押し当てた彼の下へと戻る。袋からアイスを取り出し、半分に分けてキャップを開けて空になっている方の手に握らせた。
「もうちょっと食べときなさい。あと水も」
熱中症の対処法はある程度分かっているものの、どれぐらい行えばいいかまでは分からない。けれども、冷やさないより冷やしすぎる方がマシなはずである。アイスを食べて、水を飲ませれば症状は改善するはずだ。考えながら、グレイスは己の分のアイスを開ける。ゴミをひとまとめにしてから、チューブ状のそれに口を付けた。コーヒーの味が、頭が痛くなるほどひやりとした感覚が、舌の上を流れていく。長らく感じていなかった涼に、自然と息が漏れる。ただの溜め息だというのに、先ほどよりも冷たく思えた。
また口を付け、隣を見やる。指示した通り、始果は言葉もなくアイスを食べていた。首に当てられた袋の中身はもうだいぶ溶けてしまったのか、水が張っているように見える。こちらももう一つ買った方がいいだろうか。考えながら、いつしかじぃと見つめながら、グレイスはシャーベット状の中身を吸い上げた。
「酷くなったら言いなさいよ」
「もう大丈夫ですけど……」
「あんたの『大丈夫』は信用なんないの!」
掴み所の無い声を鋭い声が切り捨てる。心配がうっすらと張ったマゼンタが、焦点が分からないイエローをまっすぐに射貫く。はぁ、と何も分かっていない調子の声が返ってきた。
風も無い中、少年と少女は黙ってアイスを口にする。蝉の鳴き声が聞こえてきそうなほど青い空は、依然太陽が燦々と輝いていた。
畳む
爪の先まで全部全部【ライレフ】
爪の先まで全部全部【ライレフ】
Domに尽くすタイプのSubって可愛いじゃないすか(ろくろ回し)
自分で自分をダメにする準備するの可愛いじゃないすか(ろくろ回し)
そんな感じでDom/Subユニバース右左。Dom/Sub要素はだいぶ薄いけど……。
爪切りする右左の話。
パチン。パチン。小気味良い音がいくつも部屋に落ちていく。目の前に並んだ硬い白に刃が宛がい、握ったテコに力を入れる。パチン、と気持ち良いほど軽快な音と共に白が分かたれた。細かに角度を変えながら繰り返し、伸びてしまった目の前の爪を切っていく。爪切りが仕事する音だけが空気を揺らしていた。
リズム良く動いていた手が止まる。眼前に持ち上げられた足をそっと支え直し、烈風刀は爪切りを閉じる。今度は傍らに置かれたヤスリを手に取った。切ったばかりの足の爪に添え、少年は細かい動きで柔らかな線になるよう削っていく。刃がどれだけ細かく丁寧に仕事しようとも、直線的に切る以上鋭利な部分はどうしても生じてしまう。そこが皮膚に引っかかって傷を付けてしまったら大変だ。きちんと丸く、美しくせねばならない。己に課された――己が己であるための使命だった。
かすかな音をたてて爪が削られていく。操る手は薄いガラスを扱うかのような繊細な動きをしていた。ヤスリが皮膚に当たって怪我をさせては本末転倒だ。当然である。丁重に動く手によって、少しばかり見えていた角はどんどんと消え去っていく。柔らかなカーブが足先に戻っていった。表面にも軽く掛けてツヤを出していく。足を人に見せる機会はなかなかないものの、やはり美しいに越したことはない。丁寧に、優しく、細やかに。剣胼胝がまだ残る手が道具を操っていく。
両足全てを処理し終え、碧は目の前、支えていた足をそっと離す。持ち上げられ続けていた足は優しく床に着地した。
「ありがと」
いいこ、と雷刀は目の前に座ったパートナーの頭を撫でる。大きな手が、まだ乾かしたばかりでふわふわとした浅葱の海を滑っていく。たったそれだけで、真剣な眼差しをしていた冷たい海色が一瞬でとろけて甘い色を灯した。ん、と鳴き声のような音が紅色で飾られた喉からあがった。
「まだ手が残っていますよ」
はっと瞠られた目が何度も瞬き、元の澄んだ色に戻っていく。道具一式を手に、烈風刀は床からソファへと移った。へーい、と気の抜けた声と共に目の前に手が差し出される。添えるように握る動きは、恭しさすら感じさせるものだった。
また爪切りで手の爪を切っていく。パチン、パチン、と軽い音が二人の間に積もっていく。できるだけアーチを描くように切り、時折破片を捨て、少年は伸びたそれを処理していった。
「短めにおねがいな」
「はいはい」
兄の言葉を、弟は軽くあしらう。毎回言われる、分かりきったことだ。言われずともこなしていた。深爪にならないよう気をつけながら、烈風刀は慣れた手つきで白い部分を切り取っていく。足に比べて薄いそれはすぐに整えられた。今度は足よりも時間を掛けてヤスリをかけていく。身振り手振りの大きな彼のことだ、少しでも尖っていては自分を、他人を引っ掻いてしまうかもしれない。入念に整えるべきであった。
それに、と碧は手を動かしながら考える。この指は、己のうちがわの柔らかな部分に触れるのだ。引っ掻けるほど長くては、内臓を傷付けてしまう。それは互いに避けたい事態であった。だからこそ毎回『短めに』と言うのだろう。何度も、必ず。
それだけ想ってくれているという現実に、それだけ身体を重ねているという事実に、少年の頬に色が宿っていく。顔が、腹の奥が熱を持ち始めたのが己でも分かった。小さく深呼吸し、少年は手元に意識を集中させる。邪念を振り払うように手を動かした。
全ての処理を終え、ようやくヤスリが手から離れていく。少し角張っていた爪は綺麗に整い、明かりを受けてぴかぴかと輝いてすら見えた。達成感と満足感に、知らず知らずの内に結ばれていた口元が綻ぶ。気付かれないよう軽く顔を伏せ、碧は使い捨てのそれと切った爪をティッシュでまとめる。包んだ手は中身がこぼれ落ちないように受け止めながら、白をゴミ箱に捨てた。これで爪切りは全て終わりだ。
「やっぱ烈風刀がやるとキレーだなー」
電灯に透かすように手を掲げ、雷刀ははしゃいだ様子で爪を見つめる。どうやらきちんと仕事をこなせたようだ。開いて、握って、朱は恋人によって綺麗に整えられた爪を眺める。夜だというのに茜色の瞳は輝いていた。
「烈風刀」
名を呼ぶ声。視線を向けると、そこにはこちらに向かって腕を大きく広げる兄の姿があった。ん、と機嫌の良い声と共に更に腕が広げられる。目元は穏やかに弧を描きながらも、その奥に光を宿している。どこか陰ったような、ギラつくような、鋭さすら見せる光が。
誘われるがままに、射貫かれるがままに、弟はソファに乗り上げる。普段ならば行儀が悪いと言ってやらない行動だ。けれども、今ばかりはこうするのが当然だ。求める人に呼ばれて最適解を選ばない理由など無い。
鍛えられた身体が傾き、広げられた腕の中に飛び込む。すぐさま手が動き、迎え入れたこの身をぎゅうと抱きしめてきた。抱き留めてくれたその身体に碧は腕を回し、少しだけ力を入れて抱き締める。焼けていない肌を飾る首輪が小さく音をたてた。
「いつもありがとな」
いいこ、いいこ。歌うように、唱えるように、まじなうように雷刀は言葉を繰り返す。あやすように背を叩く手が萌葱の頭に添えられ、なぞるように撫でた。頭を撫でられる感覚が、耳に注ぎ込まれる言葉が、身体を包み込む温度が、隅から隅まで染みこんで己というものを溶かしていく。ん、と鼻にかかった情けない声が漏れ出る。常ならば羞恥を覚えるところだが、今ばかりはどろどろにされるような喜びが勝った。与えられる全てが甘くて、心地よくて、きもちいい。シロップにでも漬け込まれたらこんな心地がするのだろうか、なんて馬鹿なことを考えた。
えらい。すごい。そんな言葉が耳から脳味噌を溶かしていく。透き通った藍晶石が炙られたようにとろけ、つややかに輝いた。どういたしまして、と烈風刀はなんとか言葉を返す。その声には普段のような芯など無く、やわくとろけた響きをしていた。当然だ、Domに褒められてまともな頭を保っていられるわけがない。
頭を撫でていた手が自然な動きでうなじへと下っていく。うっすらと水気が残る生え際を撫で、使い込まれてなお輝く首輪を撫で、広い背中を撫でていく。指先が何度も触れるも、爪が当たる痛みなどない。短く切り揃えたそれは誰も傷付けないのだ。だというのに、手が動く度に碧の身体は震える。背筋を電流が駆け上がっていく。だからこそ、雷刀、となんとか咎める音色で名前を呼んだ。
微細な快楽をもたらすそれが行き着く先がどこなのかなど分かっている。どこに触れて、暴いて、ぐちゃぐちゃにするかなど想像に容易い。けれども、それにはまだ早いのだ。まだテレビが愉快なドラマ番組を流すような時間である。深く触れあうにはまだまだ早い夜だ。そもそも、ここはリビングである。寝室以外で『そういうこと』をすると後が面倒くさいことは二人とも経験しつくしているのだ。時間と場所を限るのは、暗黙のルールのはずである。
想像に容易い。だからこそ、身体が、うちがわが熱を持つ。この切り揃えられたばかりの手が何をするのか、何をされるのか。いつだって、爪切りが終われば己の全てをつまびらかにされるのだ。知っているからこそ、この行為が好きでたまらない。尽くす喜びも褒められる喜びももちろんだが、頭からつま先まで愛を注がれ支配される未来を確約されるのがたまらなかった。
へーい、と拗ねた声が耳の真隣で聞こえる。抗議するように、兄は弟の背を何度か叩いた。先ほどまでの艶のある動きは消え、ただただ慈しみとじゃれる幼げだけがある。普段の彼らしい姿であった。
その手が己を全部開いて晒してめちゃくちゃにするのだと考えて、腹の奥底が疼いた。
畳む
日曜朝はテレビの前で【嬬武器兄弟】
日曜朝はテレビの前で【嬬武器兄弟】
公募アピカネタだけどオニイチャンタテレンジャー見てるんだよなぁと考えた結果がこちら。私が最近特撮見てる影響なのは内緒。
テレビの前に集まる嬬武器兄弟の話。
休日に似つかわない騒がしい足音が遠くで聞こえる。すぐさま乱暴にドアが開け放たれる音がリビングに飛び込んできた。
「寝坊した!」
おそらく寝起きであろう雷刀の叫びが聞こえる。うるさい足音と情けない声がどんどんと近づいてくる。パーカーに包まれた腕が、ローテーブルに置かれたままのリモコンを引ったくった。不必要なほど力強くボタンを押し、テレビの電源を入れるのが横目に見える。暗かった液晶画面に一瞬で光が宿り、静かだったスピーカーから派手な爆発音が鳴り響いた。
忙しない様子に眉をひそめることすらなく、烈風刀はコーヒーを一口飲む。淹れたばかりで熱いぐらいのそれが口内を満たしていく。苦みが舌の上に広がり、香ばしい香りが鼻を抜けた。
相変わらずドタドタと動いていた兄は、ようやくソファに腰を下ろす。勢い余ったそれは、己が座る座面まで跳ね上げた。カップの中の黒い湖面が波立つ。眉間に小さく皺が寄った。
またマグに口を付けながら、弟は密かに隣を見やる。寝起きはいつもぼやけた朱い瞳はぱっちりと開き、いつもの輝かしい光を灯している。視線はまっすぐ真ん前、テレビへ画面と向けられていた。拳を握って眺める様はまさに釘付け、首ったけと言うのが相応しい。
碧い目も液晶画面へと向けられる。二人暮らしには少しばかり不釣り合いな大画面には、今まさに変身ポーズを取るヒーローの姿が映っていた。偉丈夫がまばゆい光に包まれ、真っ赤なスーツ姿へと様変わりする。手を天に突き出しポーズを取った彼は、タテレンジャーレッド、と名乗り上げた。
ツマミ戦隊タテレンジャー。
今まさに放送されているのは、突如この夏から始まった特撮番組だ。きっと同時期に追加された楽曲の影響だろう。この世界はネメシスの影響で何でもかんでも起きる世界なのだ。楽曲の名を冠した特撮番組が始まるぐらい、エイプリルフールに一晩でマンションが生えてきた時よりずっとマシである。
そのヒーロー五人組に、兄である雷刀は虜になっていた。流れるように鮮やかな変身ポーズ、鬼気迫る迫力満点の肉弾戦、生身かCGが区別が付かないほど派手なアクション、そして豪快に怪人と戦う巨大ロボット。所謂『男の子』を魅了する要素ばかりが詰まっているのだ、同年代より幼げたっぷりな兄が虜になってもおかしくはない。
盛大な爆発音が値段以上に高品質なスピーカーから流れる。場面は巨大化した怪人と合体ロボットの対決へと移ったようだ。怪人の、ロボットの一挙手一投足で街が――架空の街を模したミニチュアだろうが――派手に壊されていく。本当にこれが正義のヒーローなのだろうか、と少年は眉をひそめた。隣で見入る子どもめいた高校二年生は、いけー、と拳を突き上げ応援しているが。
またマグの中身を飲む。少しばかりぬるくなったそれは、まだ薫り高い。ちびちびと口を付けながら、烈風刀もまた画面に視線を向ける。必殺技がハーモニーを奏でて叫ばれ、ロボットがエフェクトをまといながら派手なアクションを繰り広げる。怪人の叫び声と爆発音がリビングに響いた。また街が壊れる。
ロボットから降り変身を解いたヒーローたちは、口々に労りの言葉を投げかける。しかし、ブルーとブラックは不自然なほど互いを避けていた。前回の放送で二人の過去の確執が判明したのだ。深い深いその溝は、一話や二話で解決するはずがないだろう。されるとしても次週だ。下手をすれば今クールの最後まで引きずる可能性もある。
「面白かったー!」
エンディング楽曲が流れる中、雷刀が声をあげる。大きく伸びをしているのが視界の端に映った。タテレンジャーの放送はもう終わるが、テレビを消す様子はない。次の三十分も正義のヒーローが戦う特撮番組があるのだから当然だろう。タテレンジャーをきっかけに、兄は特撮番組にすっかりハマっていた。買い物帰り、変身アイテムが売られるおもちゃ売り場に吸い込まれていきそうになる彼を引き留める羽目になっている程度には。
烈風刀はマグを傾ける。ぐっと飲み干し、席を立った。同じく飲み干したのだろう、兄も後ろから付いてくる。湯を沸かしている横で、食パンをトースターに突っ込む彼が見えた。
「食べてから見た方がいいんじゃないんですか」
「今日は寝坊しちまったからしかたねーだろー」
ドリップコーヒーを用意しながら、弟は小さな棘が生えた言葉を投げる。少しむくれた声が返ってきた。オレの分も淹れといて、と都合のいい言葉と共にマグカップが隣に置かれた。自分でやってください、とコーヒーのパックを上に置く。カチン、と湯が沸いたとケトルが知らせてきた。トースターも一緒に高い鳴き声をあげる。
タテレンジャーの放送が開始してから、兄は休日でも午前中に起きるようになった。何年も何年も休日は昼過ぎまで寝ていたあの彼が、である。大きな進歩だ――その進歩に関わっているのが子どもがターゲット層の特撮番組というのが何とも言い難い気分になるが。
もう少し早く起きてくれれば、一緒に朝食を食べられるのだけど。碧い少年はあり得ない風景を夢想する。タテレンジャーの放送は午前が終わる少し前の時間だ。平日通り起きる己の起床時間とは、確実に被ることがない。過去は朝早くの時間に放映していたと聞いた時は、何だか惜しい気持ちになってしまったのは秘密にしておこう。
「烈風刀ー、はじまっぞー」
いつの間にかテレビの前へと移動した兄が呼ぶ。はいはい、とマグカップ二個手にしながら、弟はソファへと向かった。
ビビッドカラーで彩られた画面には、オープニング曲のサビと共に大技のキックを決めるヒーローの姿が映されていた。
畳む
本日の主役にはケーキを!【グレイス+烈風刀+つまぶき】
本日の主役にはケーキを!【グレイス+烈風刀+つまぶき】
誕生日おめでとう!!!!!!!!!!!!! お誕生日にはケーキだよねって話。
ケーキを作るグレイスちゃんと烈風刀と飛んできたつまぶきの話。
まだ少し固い赤をそっとつまむ。青や黄で彩られた真っ白な舞台に、慎重な手つきでつやめく果実を置いた。表面にたっぷり塗られたクリームが少しだけへこんでくっついて、小ぶりないちごを支える。少し斜めを向いてしまったが、崩れることなく盛り付けられた安堵にグレイスは小さく息を吐いた。
「もっと気楽でも大丈夫ですよ」
次のいちごをそぅっと手に取ると、笑みを含んだ声が飛んでくる。自然と半分下がった瞼のまま見やると、口元を綻ばせた烈風刀と目が合った。彼の胸元には銀の大きなボウルが抱えられている。泡立て器を持った左手は、心地よさを感じるほど一定のリズムで真っ白な中身を掻き回していた。
「大丈夫なわけないでしょう。誕生日ケーキなのよ」
ふん、と少女は鼻を鳴らす。そうですね、とやはりどこか笑みが浮かぶ声が返ってきた。
年も明けてしばらく経った今日は一月十八日。この世界が生まれた日。そして、レイシスたちの誕生日だ。
こんなめでたい日を祝わずにいられるわけがない。ネメシスは世界の祝福、そして世界のために日々尽くす少女たちの祝福に一丸となって動いていた。例えばお祝いの言葉だとか、ぬいぐるみ付きの電報だとか、誕生日プレゼントだとか、誕生日パーティーだとか。
週最後の平日である昨日は、放課後の教室で簡素なパーティーが行われた。クラスや学年の垣根を越えて人々がこぞって祝いに来たのだから、彼女たちの人望がよく分かる。四人をもってしても持ち帰られない数のプレゼントが積み重なったほどだ。保存がきくものは週末の間学校で過ごしてもらわねばならなくなってしまったぐらいには。
迎えた週末、誕生日当日。本日はレイシスたっての希望で、五人きりの小さなパーティーを行うことになっていた。グレイスと烈風刀は料理担当だ。ケーキ生地を焼き、生クリームを泡立て、果物を処理し。午後も早くから始めたというのに、丁寧に作業していた分随分と時間が経ってしまった気がする。パーティーはケーキだけではない、他にも料理を作らねばならない。冷蔵庫の中には醤油や塩だれに漬け込まれた大量の鶏肉が待っているのだ。長い時間キッチンを占領してはいけない。手早くしたい、でも綺麗に丁寧にやりたい。躑躅の心は逸るばかりだ。
そっと、そぅっと、崩れないように果物を配置していく。ブルーベリーにラズベリー、レモン汁を薄くまとったバナナ、薄切りにしたリンゴ、そしてツヤツヤのいちご。色とりどりの果実が白いスポンジケーキを彩っていった。
「いちご、もっと買ってくればよかったかしら」
ケーキ一周分載せたところで、グレイスは呟く。こぶりなプラスチックパックの中のいちごは残り三分の一ほどだ。あとは半分に切って載せるので問題はないが、やはりこれだけではどこか物足りない気がする。生クリームたっぷりのホールケーキといえば、大ぶりでツヤツヤで真っ赤ないちごだ。もっとたくさん載せるべきではないか。そんな疑問が、不安が胸をよぎるのだ。
「さすがにこれ以上は無理ですよ。今の時期は高すぎます」
「ちょっとぐらい私が追加で出すわよ」
パーティーで作る料理や買うジュースなどの費用は全員で平等に出し合っていた。旬を外れたいちごは店先で言葉を失い立ち尽くすほど高く、予算ではこの量が限界だったのだ。けれど、個人的に買えばもっと増やすことができた。何故早く思いつかなかったのだろう。もっと豪華なケーキを食べさせられたのに。今更になって後悔が押し寄せてくる。少しずつ沈んでいく少女の頭に、いえ、とはっきりとした声が降り注いだ。
「そういう部分をなぁなぁにすると雷刀が余計なことをしだすのでやめてください」
眉根を寄せて首を振る烈風刀に、そうね、とグレイスは一拍置いて頷き返す。雷刀のことだ、自費で肉を増やすとか、菓子を増やすとか、机の上が大変なことになるような買い物をしでかすだろう。レイシスもそうだ。たくさんあって困ることはない、とピザを三枚や四枚気軽に追加する姿が容易に想像できた。
「僕が提供できれば一番よかったのですが……」
「どこまで手広くやる気なのよ。もう農園に余ってるとこ無いでしょ」
烈風刀が営む農場で栽培されているのは、旬に合わせた野菜がほとんどだ。さすがにいちごを栽培するビニールハウス環境は整備していなかった。していても困るが、と少女はひそかに瞼を下ろす。知らぬ間に土地が増えていることが多いネメシスとはいえ、フルーツまで手を出すほど農園を広くするのは不可能だろう。何より、そんなに種類を増やしては世話をする彼の身体がもたない。
「おー! もうできてんじゃん!」
風を切る音と弾む声がキッチンに飛び込んでくる。思いもよらぬ声に、手元を見つめていた二人は顔を上げた。躑躅と浅葱の先には、銀色に光る小さな三角形があった。今日の主役の一人であるつまぶきだ。
「貴方、買い物についていったんじゃなかったの?」
「レイシスに留守番してろって言われた」
オレだって荷物持ちぐらいできんのにさ、とつまぶきは呆れた調子で首を振る。無理でしょ、と二つの声が綺麗に重なった。手のひらサイズの彼が持てるものなど、簡易包装のティッシュペーパー一パックぐらいだろう。ピザや菓子、ジュースに冷凍食品にと重い食品を買いに行った彼女らにとっては完全な戦力外だ。
スゲー、と感嘆の声を漏らしながら、つまみの精は制作途中のケーキの周りを飛んで回る。フルーツでデコレーションされつつある白を、三六〇度から素早く、忙しなく眺めた。ぴょこぴょこと宙で跳ねて揺れる動きは兎のようだ。
「ぶつかっちゃったらどうすんのよ。あっちいってなさい」
ぐるんぐるんと飛び回る彼を外に押しやるように、グレイスは手の甲を見せて大きく振る。扱いが虫と同レベルだ。あんまりな態度に、不満げな声が小さな口からあがった。
「そういや味見したのか? してねーならオレが――」
「つまぶき」
皿の端っこに着地した精を、たおやかな手がそっとつまむ。逃げられないようにがっちりとつまむ。動揺にきょろきょろと視線を泳がせる彼を眼前まで持ち上げ、少女はにっこりと笑った。不自然なほど目元を曲げ、口角を上げるそれは、『笑顔』と表現するにはあまりにも凶悪なものだった。びくん、と逃げられずにいる小さな身体が大きく跳ねる。
「食べたらナパージュぶっかけてケーキの上に飾るわよ」
「……ハイ。タベマセン」
たどたどしい調子で答えるつまぶきに、グレイスは白くなるほど力を入れていた指先を緩める。分かったならいいわ、と着信中の携帯端末のように震える銀に怒気がにじむ声をぶつけた。
解放された銀の精はぴゅんと飛ぶ。怒られた子どもが親の背中に隠れるように、烈風刀の肩に腰を落ち着けた。こえー、と怯えきった小さな声が少年の耳をくすぐる。
「生クリームにつっこまないでくださいよ」
「しねーって! 烈風刀までオレのこと信用してねーのかよ!」
「していますが、事故は起きるものです。注意して損はありませんよ」
ボウルを遠ざける烈風刀に、つまぶきはきゃんきゃんと子犬のように喚く。小さな身体が少年の肩の上でぴょんぴょんと跳んだ。説くように、いなすように、碧はさらりと言葉を紡ぐ。正論であるのは誰が聞いても明らかだ。
納得したのか、まだ腑に落ちないのか。小さな身体は動きを止めて、五分まで立てられた生クリームがたっぷり入ったボウルから少しだけ距離を取った。むくれた声が少年の後ろを漂っていく。
手を洗い、グレイスは再び飾り付けを再開する。変色することなく佇むバナナ、水気はないのにつやめくラスベリー、底が分からないほど濃い藍色を覗かせるブルーベリー、端っこがうっすら透けて見えるりんご、真っ赤に熟れたいちご。様々なフルーツを、事前に考えたバランスと相談しながら並べていく。丁寧な作業はようやく実を結び、やっとホールケーキが一つ完成した。安堵に、少女は思わず大きく息を吐く。すぐさまハッとして口元を手で押さえた。今の呼気で崩れてしまっては大変だ。揺れるラズベリルが白いキャンバスを見やる。華やいだフルーツたちは、ひとつも動くことなくケーキの上で咲き誇っていた。
「……これで足りるのかしら」
「二個ありますし大丈夫ですよ。今ロールケーキも焼いていますし」
へ、と強張っていた口から気の抜けた音が漏れる。急いで振り返ると、随分と前に使い終わったはずのオーブンには再びオレンジの灯りが宿っていた。ヒーターが唸る低い音が、彼が仕事の真っ最中であることを語っていた。
いつの間に、と驚愕を隠すことなく、グレイスは烈風刀を見やる。作り終わった生クリームをテキパキと処理し、揚げ物用の鍋を用意しながら、彼は小さく笑った。
「冷凍していた卵白がまだ残っていたので」
「卵白って冷凍できるものなの!?」
「できますよ。黄身を醤油漬けにしたりすると余りますから、いくらか冷凍して保存しています」
作りすぎる人がいるので、と少年は嘆息する。そうなの、と少女は呟くように答える。丸くなったペツォッタイトがぱちぱちと瞬いた。グレイスは寄宿舎暮らしだ。レイシスの部屋を訪れた際に料理をすることはあれど、毎日メニューを考えたり調理をすることはない。卵黄と卵白は必ずセットで使うものだと思っていたし、片方だけが余るだなんて想像ができないことだった。余ったそれを冷凍することは更に想像がつかない。凍ってもちゃんと泡立つのか。そもそもあのどろりとしたものが凍るのか。疑問は尽きないが、今問うのはやめておいた方がいいだろう。
疑問符を浮かべながらも、少女はナパージュを用意する。透明なそれを、シリコンの刷毛でフルーツに塗っていく。ただ飾っただけでも輝きを放っていた果物は、透明な衣をまとって更にキラキラと輝きだした。拙さの残る手作りのものだというのに、この一処理をしただけでまるで売り物のように様変わりしたのだから驚きだ。料理の奥深さに、手間暇を掛ける重要性に、アザレアの目が開いて閉じてを繰り返した。
ぶつからないように細心の注意を払いながら、透明な保存容器を逆さにして被せる。これまたぶつからないように慎重に慎重を重ねて冷蔵庫にしまった。これで一つ完成だ。すぐさま元の場所に戻って、新しく皿を用意し、ケーキクーラーに載せていたスポンジを載せる。切っただけだったはずのスポンジは、いつの間にかシロップが塗られ少ししっとりとしていた。きっと烈風刀が処理してくれたのだろう。本当に手際が良い。
一つ目と同じように、生クリームをたっぷり塗って処理し終えていたフルーツを丁寧に載せていく。先ほどのものはレイシス専用、今回のものは雷刀と烈風刀とつまぶき、そしてグレイスのものだ。貴方たちで全部食べなさいよ、と最初は遠慮したのだが、一人だけ仲間外れだとレイシスが悲しみますよ、と兄弟に押し切られてしまったのは記憶に新しい。本当に良いのだろうか、と未だに不安は残る。けれども、遠慮して食べずにいては、己にとことん甘いあの姉が眉を八の字にしてしょんぼりとするのは容易に想像できた。今日はレイシスの誕生日だ。誰一人として、彼女を悲しませてはならない。ならば己が取る選択は一つのみだ。
「僕らの分ですし適当でいいですよ」
「よくないわよ。何言ってんのよ」
焼けたばかりのロールケーキの生地を処理しながら、烈風刀は事も無げに言う。あんまりな言葉に、グレイスは頬を膨らませた。整えられた細い眉と、勝ち気な目元がいっぺんに吊り上がる。
「貴方たちも主役でしょ。適当でいいわけないじゃない」
「主役、ですか」
ケーキ生地からクッキングペーパーを剥がす烈風刀は、少したじろいだように呟く。少し高くなった声は、消しきれぬ疑問符が残った響きをしていた。あんまりにも理解していない様に、グレイスははぁと息を吐く。白い指が一本立って、少年をびしりと指差す。丸くなった翡翠の目が、指の勢いに押されたように揺れた。
「今日はレイシスと、雷刀と、烈風刀と、つまぶきの誕生日なのよ。レイシスだけじゃないの。貴方たちも主役なの!」
分かった、と語気強く問う少女に、少年は気圧されたようにはい、と返す。そーだそーだ、とここぞとばかりに肩の上で妖精が飛び跳ねた。
「主役のオレはぁー、いちごがいっぱい載ったケーキ食いてぇ!」
「言われなくてもいっぱい載せてるわよ。楽しみにしてなさい」
くるんと宙返りをして主張するつまぶきに、グレイスは不敵に笑んで返す。歓喜の声をあげ、妖精はまた器用に宙返りをした。落ちないでくださいよ、と大きな手が彼の前を素早く塞ぐ。落ちねーって、と上機嫌な声がキッチンに舞った。
「あと味見してぇ!」
「ダメって言ってんでしょ」
「後でロールケーキの切れ端上げますから、それまで待っててください」
忙しなく動いて主張する銀色を、躑躅色がバッサリと切り捨てる。露草色の眉がゆるく下がって困ったような笑顔を作り出した。また銀がくるりとひらめいて舞って、急かすように少年の肩をつついた。
いちごを半分に切りつつ、少女は時計を確認する。あと二十分もしないうちに二人は買い物から帰ってくるだろう。急がずゆっくり、何なら夕食に支障が出ない程度に買い食いでもして帰ってこいと言ってあるが、きっと彼らのことだからまっすぐに帰ってくるだろう。予約していたピザとポテトとチキンと、何リットルもあるジュースや器から溢れるほどの菓子を携えて。
フルーツを切る音と油が熱される音、ケーキ生地を扇ぐ音が三人を包む。生クリームを冷やす氷が、金属ボウルにぶつかって軽やかな音をたてた。
畳む
寄せあってぬくまって【ライレフ】
寄せあってぬくまって【ライレフ】
明けましておめでとうございますな正月の右左。やっぱこたつには並んで寝転びたいじゃないっすか。いちゃいちゃしてほしいじゃないっすか。
こたつでちょっと攻防する右左の話。
シンクを打ちつけていた流水が止まる。スポンジを握った手は淀みない動きで道具を所定の位置に戻していった。流れるように布巾を手に取り、水切りかごに伏せた食器たちを手慣れた動きで拭いていく。水気が消え失せ輝くそれらを棚に片付けたところで、烈風刀は小さく息を吐いた。
布巾を元の場所に掛け、少年は電気を消してキッチンを出る。十歩足らずで辿り着くリビングには、朱い頭があった。当然のように床の上に転がって、紅緋の髪を絨毯に散らせている。ゆったりと過ごすことを許された正月とはいえ、あまりにもだらしがない姿だ。冬に入って、正確にはこたつを出してからはずっとこの調子なのだから呆れ果てたものである。
「行儀が悪い」
一言諌めて、烈風刀はこたつに身体を滑り込ませる。いっそ暑いほどの温もりが下半身を包み込んだ。リビングと一続き、多少は暖房が流れ込むとはいえ、キッチンはいくらか肌寒い。夕飯の食器を洗うだけだったとはいえ、やはり足元は幾分か冷えてしまっていた。水風呂に浸したような感覚に陥っていた足先が温められていく。気付かぬ内に強張った身体がほぐされていくような心地がした。
「いいじゃん、正月なんだし」
寝返りを打ってこちらを向き、雷刀は言い訳めいた言葉を放つ。声はふにゃりとしたものであり、睡魔が彼の身体から力を奪っていっていることがよく分かった。このままでは眠ってしまうだろう。こたつで寝るなと言っても聞いた試しがないのだ、この兄は。
温められつつある足先を動かして、烈風刀はこたつの中にだらしなく伸ばされた足をちょいとつつく。震えるように小さく反応したそれは、器用な動きでこちらの足をつつき返してきた。眉をひそめて見やると、いたずらげに細められた緋色と視線がかちあう。行儀悪いぞ、と仕返しするように声が飛んできた。
「ほっといたら寝るでしょう、貴方は」
「寝ねーよ。全然眠くねーもん」
「……まぁ、昼過ぎまで寝ていましたものね」
大晦日から正月に移り変わる夜更けまで起きていたこともあってか、兄は初日の出が中天に昇るまで惰眠を貪っていた。半日近く眠っていれば、確かに夜でも眠気は薄いだろう。けれども、ふやけた声音で紡がれる言葉には説得力が全くと言っていいほど無かった。懲りることなく眠って起こされてを繰り返すこたつの中、という状況が合わさると尚更だ。信用しろという方が無茶である。
だろー、と雷刀はどこか得意げに返す。そんなだらしのない生活で得意になるものではないだろう。考えても、烈風刀は黙するのみだ。言ったところで効果がないのは何年もの時間をかけて保証されていた。
「烈風刀も寝てみろよ。こたつん中あったけーしきもちぃぞ」
「嫌ですよ」
上半身を起こし、兄は自身の隣に空いた絨毯を叩く。子をあやすような、信頼を置いた飼い犬を呼ぶような動きだ。弟は眉間に刻む皺を深くするばかりである。こたつに寝転ぶのが心地よいのは分かる。だからこそ、やりたくなかった。こたつに潜って寝転んで過ごすだなんて、どう考えても行儀も悪ければだらしもない。それに、そのまま眠るようなことがあっては示しがつかないではないか。どこまでも堕落させる魅惑の空間だからこそ、己を律しなくてはならないのだ。
「ちょっと寝っ転がるぐらいだらしくなくねーって。絨毯の上だぜ? その上布団があるこたつの中だし? 寝るのがトーゼンじゃね?」
誰にでも看破できる屁理屈をこねくり回しながら、朱はなおも絨毯の上を叩く。穏やかだったリズムは、いつの間にか機嫌の悪い猫が尻尾で地を叩くそれとよく似たものになっていた。つまりは、自論が通じないからと勢いで押そうとしている。いつものことだった。
烈風刀、と名を呼ばれる。昼に食べた汁粉よりもずっと甘ったるい響きだ。寂しがりの子犬が甘えるような響きだ。耳からたっぷり流し込んで思考を甘っちょろいものに冒していく響きだ。
一層険しい顔を作って、碧は寝転がった恋人を見やる。夕陽色の目はわずかに細められ、どこか伏し目がちだ。悲しげにも、眠たげにも見えた。彼岸花色の眉は端っこが下がっている。彼の内に渦巻く感情を、思惑をよく表していた。冬の茜空の髪は汗を掻いているのかどこか力を失って垂れている。悲しみに暮れる犬の耳とよく似ていた。
れふとぉ、ともう一度名を呼ばれる。息を飲み込もうとしたのに、喉がおかしな音をたてる。だらしのない言葉を跳ね除けようとしたのに、頭が上手く機能しない。言葉を紡ぐ頭はあの甘ったるい声にとっくの間に侵食されてしまっていた。
深く溜め息を吐き出す。ただのポーズであり言い訳だ。甘っちょろい己に対する自責だ。意味なんて成さないと分かっていながらも、こうでもしないと格好がつかない。年頃の心はいっちょまえに見栄を張った。
静かに立ち上がり、烈風刀は音もなく絨毯の上を歩んでいく。兄が叩いていた場所より少し離れたところ、それでも彼の隣である場所に身体を滑りこませた。座って逡巡。しばしして、姿勢良く伸びていた背が丸まり、横へと倒れて寝転がった。絨毯のやわい毛が頬をくすぐる。先ほどまで足だけに感じていたぬくもりが腹まで包み込んだ。
目の前、絨毯の上に髪を散らした朱が笑う。いたずらが成功した時のような、待ち焦がれたプレゼントをもらった時のような、テストで良い点を取った時のような笑みだ。つまりは幸いが彼の顔を染めていた。
「あったけーだろ?」
「当然でしょう」
まるで自分の手柄であるように雷刀は問う。そこにはもう眠りの膜は見えなかった。夜も更けてきたというのに、日が高い時間のようにケラケラと愉快そうに笑う。ただ己が隣に寄っただけで、何故こうも上機嫌になるのだろう。浮かんだ問いはすぐに解決して消えた。そんなの、己が寝転んだ理由と同じだ。
ぬくいこたつ布団の中、手にぬくもり。ヒーターが温めるそれとは明確に違う温度に、烈風刀は瞬き一つ落とす。眼前には眠る直前のように目を細め、口元を逆さ虹の形になぞった朱の姿があった。肌に直に触れる温度が緩やかに動いて、手を包んで引っ張る。ねだるように、乞うように。
むずがるように身動ぎ一つ、二つ。ようやく碧は動き出す。引く手に誘われて動き出す。ほんのちょっと身を寄せただけで、大きな手が背に回り引き寄せられた。暑いくらいのこたつ布団の中、体温が重なる。
「暑いんですけど」
「オレはちょうどいいけど?」
ウミウシのように動く弟の身体を、兄の腕ががっちりと捕らえる。とはいっても、軽くて緩いものだ。本気で動けば振り払えるだろう。だというのに、身動きがろくに取れなくなってしまうのだから、己は本当に甘いったらない。兄限定の甘さだけれど。
こたつ布団に朱い頭が埋もれる。ほぼ同時に、胸にやわい衝撃。紅色の頭は、匂いをつける猫のように己の胸に擦りついた。寝惚け声のような笑声が胸からあがる。幸せをそのまま音にしたような響きをしていた。
思案。思索。思慮。何十にも重ねた意味のない思考の末、碧は自由な手を動かす。少しごわついてきたこたつ布団の中で動いて、胸に飛び込んできた頭にそっと添えた。髪を梳くように頭を撫でていく。よく跳ねる赤色はほのかにしっとりとしていた。長時間こたつに入って寝転んでいた頭は、やはりうっすらと汗を掻いているようだ。
へへ、と胸の中から声があがる。甘えきったものだった。とろけきったものだった。心の中で生まれた幸せをめいっぱいに謳い上げたものだった。
また頭が擦りついてくる。その度に、胸の真ん中がぬくくなっていくような気がした。きっと、暖かなこたつのせいだろう。
畳む

涼しさは一緒に【ライレフ】
涼しさは一緒に【ライレフ】一緒に寝る右左が見たかっただけなどと供述しており。やっぱ夏は電気代節約しなきゃだからね(?)
クーラーを賭けた右左の話。
赤い唇が白い縁に寄せられる。薄く汗を掻いたマグカップは、持ち主によって大きく傾いた。薄く上気した喉が盛大に動く。しばしして、息を吐く音が部屋に響いた。共鳴するように、低い唸り声が部屋に落ちる。夏の生命線であるエアコンは、今日も元気に役目を果たしていた。シャワーを浴びて火照った身体に冷風と冷水。これ以上無い幸福が嬬武器雷刀の身体を満たしていく。
夏の間、己は昼も夜もリビングで過ごすことが多い。というのも、自室の冷房の動きが鈍く感じるからだ。日中熱しに熱された空気を冷やすのに時間を要するのは頭では理解できるものの、どうにももどかしい。ならば、既に涼しくなっているリビングで過ごすのが快適で合理的だ――こちらも眠る前には消さなければならないのだけど。
大きな手に携帯端末が握られる。ロックを外した液晶画面、端っこに鎮座するニュースサイトのウィジェットには『熱中症注意報』の文字が鮮やかに輝いていた。つまり、明日も暑くて湿っていて息苦しくて過ごしにくい。うへぇ、と情けない声とともに、赤い眉が小さく寄せられ八の字を描く。
インターネットでは『冷房は冷やす時に一番電気を食う』『つけっぱなしの方が電気代がかからない』なんてまことしやかに囁かれているが、どうにももったいない気持ちの方が強い。並外れた暑さの中帰ってきてすぐに涼しい空気に飛び込めるのはこれ以上無く魅力的であるが、やはり四六時中つけっぱなしというのは気が引ける。珍しく、兄弟で意見が一致した部分だ。
飲み干したカップを洗い、朱はエアコンの電源を消す。夏一番の功労者は音も無く口を閉じた。後ろ髪を引かれながらドアを開けた途端、熱気が正面からぶつかってくる。空調など存在しない暗い空間は、夜になっても随分と熱がこもってじっとりとしていた。眉が八の字を、口がへの字を描く。
早足で廊下を進み、自室に身を滑り込ませる。素早くクーラーを点けて、再び廊下へと戻った。そのまま、数歩進んで隣のドアを開く。途端、涼しい空気が身体を撫ぜた。険しげな表情が解け、普段の柔らかで朗らかなものへと戻る。
「何ですか、こんな時間に」
「涼ませて」
部屋の主――嬬武器烈風刀の声に、雷刀は軽い調子で返す。椅子の背もたれに腕を掛けて振り返った彼の顔は、就寝前には相応しくない険しいものとなっていた。健康的な色をした唇が一本の線を描き、解けて息を吐き出す。
「またですか」
呆れ、怒り、諦め。色んなものが混ざった声を正面から飛んでくる。気にすること無く、兄はベッドに腰を下ろした。だって、その声にはほのかな明るさがあったように思えたから。
「いいじゃん。あっつい部屋にいて熱中症になったらやばいじゃん?」
「そんな簡単にはなりませんよ」
ほんの数分でしょう、と弟は眉をひそめる。その数分が地獄なんだって、と兄は笑った。眉間に刻まれた皺が更に深みを増す。
「そんなに暑いならリビングで寝たらどうですか」
「さっき電源消しちゃったからもう暑くなってるって。死ぬ死ぬ」
あぐらを掻いて振り子のように揺れながら、冗談めかして返す。実は、既に考えた案だった。けれども、『みっともない』とかなんとかで弟に却下されるに間違いないと思い黙っていたのだ。けれど、今さっき彼の口からその提案が出た。言質を取れた。これで明日から涼しい空間ですぐに眠ることができるだろう。ふふん、と鼻歌めいた息が漏れ出た。
「それか、こっちで寝るとか」
「へ?」
ご機嫌に弧を描いていた口がぽかんと開く。八重歯が覗く赤いそこは、随分と間抜けな形をしていた。机に向かい直した背中から言葉が聞こえた言葉は、脳の処理を一時停止させるには十分なものなのだから仕方が無い。
「え? いいの?」
「本気にしないでくださいよ」
思わず上擦った声に、げんなりとした声が返される。再びこちらを向いた烈風刀の顔は、やはり釣り眉で眇目でへの字口だ。けれども、その頬にほんのりと紅が散っているのは部屋のライティングのせいではないだろう。もちろん、シャワーを浴びたせいでも。
「分かった! 枕取ってくる!」
「本気にしないでくださいよ! やめてください!」
ベッドの上に大人しく座っていた身体がすくりと立ち上がる。体育の徒競走もかくやという動きで、雷刀は駆け出した。背中に慌てきった声が飛んでくる。先に言ったのは烈風刀じゃん、と扉を開けると同時に叫んだ。
「――来客用の布団一式持ってきてください! 貴方寝相悪いんですから!」
開けっぱなしの扉から、深夜という事実を忘れた大声が飛んでくる。諦めきった、呆れきった、受け入れきった言葉に、分かった、とこれまた夜を忘れた声が返された。
畳む
#ライレフ#腐向け