No.72, No.71, No.70, No.69, No.68, No.67, No.66[7件]
+745【ジタ+サン】
+745【ジタ+サン】
息抜きに前から気になってたあれそれのネタ。ちょっとメタい。
タイトルでもう落ちてる感ある。
黒い雫が静かに黒の湖面を揺らす。抽出機の中身が空になったことを確認し、サンダルフォンは手にしたそれをシンクへと運ぶ。珈琲粉を処分し、使った器具を綺麗に洗い水切り籠に伏せた。人が来る前に拭いて片付けねばならないな、と考えて目をすがめる。珈琲一杯淹れるだけにいちいち共有部に来るのは手間であるが、ここでしか湯を沸かせないのだから仕方が無い。火の元素を扱える者は自室で淹れているらしいが、今の自分にそれができないということは彼自身が誰よりも理解していた。
冷める前にさっさと部屋に戻ろう、と青年はカップを手に踵を返す。廊下に繋がる扉まであと数歩というところで、厚い木の板越しにバタバタと騒がしい音が聞こえた。どんどんと近づいてくるそれに、サンダルフォンは眉をひそめた。この艇の人間は必要以上に人と関わろうとする。それをあまり好ましく思わないため常々人と会わぬよう避けて行動しているが、今回はどうにもタイミングが悪かったようだ。逃げようにも、台所の扉は目の前にある一つしかない。もう諦める他ない。
足音が止まると同時に、扉が開く音が響く。木製のそれの隙間から、ジータが顔を出した。
「あっ、サンダルフォン!」
どこか嬉しそうに青年の名を呼び、少女はそのまま小柄な身体を中に滑り込ませ静かに閉める。ただいまー、と呑気に言う彼女は、普段着ているワンピースではなく大きな襟が特徴的な魔道士風の衣装を身にまとっていた。依頼から帰ってきたばかりでまだ着替えていないのだろう。汚れが見当たらないのは外で軽く払ってきたのもあるだろうが、何より彼女の実力が確かなものであるという証だ。
「珈琲飲むの?」
夜空色の帽子を脱いだ少女が、サンダルフォンの手元を覗き込む。好きだねー、と感心にも問いにも似た音が小さな口からこぼれた。青年が珈琲を好んで飲んでいることは、彼が艇に乗ることになったその日から知っているはずだ。なのに、カップを持っているだけでいちいち反応するのだから煩わしい。赤き竜や蒼の少女といい、余計な世話ばかりかけてくる。青年の眉間にまた一つ皺が刻まれる。不機嫌であることが一目で分かる表情をしているというのに、少女は全く気にかけず返答を待つように深紅の目を見つめた。
「見れば分かるだろう」
「私の分はー?」
「無い。抽出機は既に片付けた。勝手に淹れればいい」
半ば無理矢理会話を切り上げ、青年が宛てがわれた部屋に戻ろうとする。足早に過ぎようとしたところで、ジータがあ、と何かひらめいたように声をあげた。この少女がろくなことを――少なくともサンダルフォンにとって、だ――思いついた試しがない。彼女が口を開く前に出ていこうと青年が一歩踏み出したところで、がしりと腕を掴まれた。見た目は幼く華奢な少女であるが、その力はそこらの大人よりもずっとある。数多の星晶獣と対峙し打ち勝ち、様々な属性と技を操る彼女は、この団の誰よりも強いのだ。顕現して日が浅く、まだ力が上手く扱えない青年を引き止めるぐらい、ジータにとっては至極簡単なことだ。
「あのね、サンダルフォンに食べてほしいものがあるんだ」
こっち、と少女は掴んだ腕を無理矢理引き、台所の奥へと足を動かす。こうなってしまってはもうどうしようもない。早々に諦め、青年は珈琲がこぼれぬよう大人しく彼女に引き連れられた。
ジータが足を止めたのは、共用の戸棚だった。その最下部、一番大きな開き戸を開けると、屈んで中を漁り始める。手を離された今逃げることは可能だが、あとが面倒くさいことは今までの経験ではっきりと知っている。大人しく従った方が早く済むだろう。緋色の瞳は屈んだ少女をぼんやりと映し出していた。
しばらくして、あったあったと嬉しそうな声があがり、少女は立ち上がる。そのままくるりと振り返り、サンダルフォンの目の前に大きな袋を差し出した。彼女が手にした透明な袋の中には、鮮やかな黄とオレンジが転がっていた。小さな丸いそれには、顔を模したような絵が描かれている。何だこれは、と紅の瞳が訝しげに細められる。これを見せることに一体何の意味があるのだろう。
「マカロンっていうんだ。甘くて珈琲に合うと思うの」
青年の声に出さぬ問いに答え、少女は片手で戸棚の皿を一枚取りだし傍らにある机に置いた。そのまま袋から菓子を取り出し次々と皿に並べていく。その量は茶請けにしては明らかに多い。彼女も共に食べるだろうとしても異常なものだ。白く大きな皿の上、山盛りになった菓子を見て、青年は顔をしかめる。鮮やかなそれが放つ甘い匂いで既に腹がいっぱいになりそうだった。
再び力強く腕を掴み、ジータはサンダルフォンを席に着かせる。未だ事態を理解していない様子をした彼の目の前に、どんと重い音をたてて皿が置かれた。少女が乱暴なのではない、純粋に皿が重いのだ。
「はい、召し上がれ」
向かいの席に座り、ジータは両肘をついて楽しげな表情で青年を見る。見つめるばかりで真っ白な手袋を外す様子はない。礼儀の正しい彼女は、食事をする際は必ず手袋といったものは外す。菓子に手を付ける気はないのだろう。
「……特異点は食べないのか?」
「うん。私が食べても意味ないもん」
「つまり、全て俺一人で食べろと?」
「そうだよ?」
ほら、と少女は青年の方へと皿を押しやる。早く食べろということだろう。その様子に、サンダルフォンは殊更強く眉を寄せた。勝手に呼ばれ、勝手に連れられ、勝手に差し出され、さぁ全て食えと無理矢理押しつけられる。特異点である彼女は度々無理を押しつけてくるが、今回はあまりにも勝手すぎる。不快感が胸の奥底からふつふつと湧き出てくるのが嫌でも分かった。
「何故俺がこんなに食わなければ――」
「食べて」
怒りを強くにじませた声を、はっきりとした声が切り捨てる。目の前に対峙した少女は相も変わらずニコニコと明るい笑みを浮かべているが、その声は冷え切ったものだ。こちらを見つめる鳶色は普段の温かみを完全に失っている。可愛らしい少女の姿にはあまりにも不釣り合いなそれに、黒鎧に包まれた背がぞくりと震えた。
「全部食べて。団長命令」
ね、とジータは小首を傾げる。有無を言わせぬ声音だった。戦いの最中、団長として仲間に指示を飛ばす時のそれと同じ音だ。あまりの気迫に――少なくとも、こんな場所で見るはずなどない様子に、青年は声を失った。
「……食べればいいんだろう」
「うん」
この様子では、少女が譲ることなどあり得ないだろう。恐怖で従うのではない、こんな少女に怯えることなどあり得ない、と言い聞かせ、サンダルフォンは山積みになった菓子へと手を伸ばした。さっさと食べきってしまおう、と小さなそれを丸々一個口に放り込む。途端口いっぱいに広がった味に、深紅の瞳が苦しそうに歪んだ。
甘い。あまりにも甘い。珈琲に入れる角砂糖をそのまま食べてしまったのではないかと錯覚するような甘さだ。少女は珈琲に合うと言っていたが、全く違う。珈琲に合うのでなく、珈琲で中和しなければ食べられない甘さだ。放つ香りから想像すべきだった。青年の顔からどんどんと色が失われていく。こんなものを、この皿いっぱい食べなければならないのか。
「六十九個、全部、残さず、ちゃーんと食べてね」
正面から送られる視線は、青年の様子を観察するものでなく、彼が言いつけ通り全て食べきるか監視するためのものだ。ただ菓子を食うだけのことではないか。たったそれだけだというのに、何故団長命令を下し、こんなにも強く迫ってくるのか。全く意味が分からない――そもそも、特異点の突飛な行動を理解できたことなど、ほぼ無いのだけれど。
一時的に身を置いているだけとはいえ、サンダルフォンはれっきとした団員だ。団長であるジータに、それこそ団長命令まで下されてしまっては逆らうことなどできない。彼に残された選択肢は、目の前の甘い菓子を胃に押し込むことだけだ。
「あ、珈琲のおかわり淹れる?」
「…………頼む」
問う声が楽しげに聞こえたのはきっと気のせいだろう。気のせいにしておこう。席を立ちぱたぱたと駆けていく少女の足音を背に、サンダルフォンはまた一つ菓子を口に放り込む。これ全て平らげるまでどれほどかかるのだろうか。考えるだけ無駄だ、と青年はカップの中身をあおり、口の中の甘ったるさを胃の腑に押し流した。
経験値を51405獲得!
Lvが15→45になった!
畳む
枕を二つ【グラ→ルリ】
枕を二つ【グラ→ルリ】
くっっっっっっそ寒いから推しカプは一つの布団で互いの体温を感じながら凍える事なくぬくぬくと温かく幸せに寝てくれと言う話。
諸々都合の良い捏造しかない。
あ、え、と意味を成さない音が、間抜けに開いた口からぽろぽろとこぼれる。室内は寒いというのに、顔は真夏の日差しを浴びたように熱い。きっと真っ赤になっているだろうな、と、脳のかろうじて冷静な部分が他人事のように判断を下した。
動揺で頭からつま先まで固まっている少年を見つめ、少女はこてんと小さく首を傾げる。丁寧に手入れされた長い蒼髪が、音もなくさらりと揺れた。
「グラン? どうかしましたか? ……もしかして、具合が悪いんですか?」
「あ、え、いっ、いや。何でもない。何でもないよ。大丈夫。大丈夫だから」
澄んだ丸い青に不安の色が滲んでいくのを見て、グランは異状はないと示すように慌てて手を振った。確かに身体に異常はない。けれど、ルリアが発した言葉は、少年の心と脳を揺さぶるようなものだった。
「えっと……、なん、だっけ?」
「はい。今日はとっても寒いですし、一緒に寝ませんか?」
腕に抱えた枕をぎゅっと抱きしめ、ルリアは今一度少年に問うた。奏でられた声は、たしかにルリア本人のものであり、聞き違いや己の脳が都合よく変換した言葉でないのだと確信する。本当なのか、とグランは胸中で頭を抱え蹲った。
これまで数多の戦いに身を投じてきたグランであるが、実情は無垢で純粋な子供だ。故郷であるザンクティンゼルには同い年の子供はあまりおらず、一緒に寝るなんてことは相棒である小竜のビィ、仲の良い男友達ぐらいとしかしたことがない。そんな彼に、近い年齢の――しかも、他者に向けるそれとは違う、名前の分からない特別な情を抱く少女が『一緒に寝よう』だなんて誘ってきたのだ。年頃の男の子が平静でいられるはずなどない。
「グラン?」
「あー……、そ、そうだ。カタリナさんとじゃなくていいの?」
ルリアはカタリナを家族のように慕っている。その様子は、グランが無意識に嫉妬してしまうほど睦まじいものだ。寒いというだけならば、グランよりもカタリナと一緒に眠る方がルリアも落ち着くだろう。
「その……、こういうこと言うと、カタリナは子供扱いしてくるから」
そう言って、少女は小さく頬を膨らませた。以前にそういう扱いをされて不満に思っているようだ。客観的に見てもルリアはまだ子供であるのだから仕方のないことだが、年頃の少女にとっては譲れないことなのだろう。同じく度々子供扱いされることのある――事実、彼もまだ子供であるが――グランにも、彼女の気持ちは分かった。
「グランは同じぐらいの歳ですし、私のこと子供だなんて言えませんよね!」
にこりと爛漫に笑う姿は、無邪気な子供そのものだ。指摘しては拗ねてしまうだろう、と少年は口を噤む。拗ねた姿も可愛らしいが、今はそんなことを考えている場合ではない。一番納得できるであろう案が否定されてしまったのだ。他に何か言い訳はないものか、と必死に頭を動かしていく。
「寒いなら毛布増やすのは……って、今予備のは無かったな……」
空を旅する中では、様々な気候の島を通ることとなる。寒冷地でも対応できるよう予備の毛布をいくらか用意しているが、つい最近団員が増えたので一時的にそちらに回したのだった。何ともタイミングが悪い。
「あっ、でも、僕よりビィと一緒のがいいんじゃないかな? 僕も冬場によくやってたけど、すごく温かいよ」
小さな相棒はトカゲと呼ばれることが多いが、変温動物ではない。成長した今こそ機会は減ったが、昔は冬場に彼を抱いて眠ることも多かった。小柄な彼は抱きしめるのにぴったりのサイズであり、子供のようにぽかぽかと温かいので、胸に収めればどんなに寒い日でもよく眠れた。その効果は今でも健在だろう。
「でも、ビィさんもう寝ちゃってますよ?」
蒼穹と同じ色の瞳が宙を見上げる。天井から吊るされた大きな籠――ビィがベッドとして利用しているものだ――からは穏やかな寝息が聞こえてくる。小竜は二人より一足先に夢の世界へと飛び立ったようだ。元気いっぱいの彼は日中によく動くためか、グラン達より早く眠ることが常であった。動揺のあまり完全に忘れていた、とグランは内心顔を覆う。
他に何か彼女を諦めさせる言い訳はないものか、と少年は小さな脳味噌をフルで働かせる。その苦悩を彼女に悟られぬよう必死に普段通りの表情を作っているつもりだが、素直な彼はどうしてもその心情が表情や声音に出てしまった。美点であり弱点である度々指摘されるそれを、グランはすっかり忘れていた。苦悩がにじむ少年の顔を見て、蒼の少女はその心を察してか表情を曇らせた。
「あ……、えっと……迷惑、でしたか……?」
「そんなことない!」
後悔に震える声を、大きな声が遮る。今が日の境に近い時間だということを思い出し、少年は慌てて口を手で塞いだ。普段声を荒げることのないグランがこうも強く主張したことに驚いたのか、ルリアはその澄んだ空色の瞳を大きく開いて固まっていた。
「迷惑なんかじゃないよ。迷惑じゃないんだけど……」
驚き固まったままの少女に戸惑いながら、少年は彼女の不安を吹き飛ばすべくどうにか言葉を紡いでいく。けれども、その本心をさらけ出すことは恥ずかしいのか、こぼれる音は淀むばかりだ。前述したとおり、彼は年頃の男の子である。一緒に寝ることを喜び、恥ずかしがっているだなどという格好の悪い事実を、特別な少女に隠そうとするのも仕方が無いことだろう。
「んー……? ぐらん……るりあ……?」
中空から寝ぼけた声が降ってくる。大きなあくびとともに、赤い耳が籠の縁から顔を出した。ごしごしと目元を擦り、ビィは縁に顎を乗せ、二人を見下ろす。起き抜けだからか、つぶらな目にはまだ眠気が膜を張っているようだ。
「どうしたんだぁ……?」
「ビィ、起きたのか」
「ごめんなさい、起こしちゃいましたね……」
助かったとばかりに相棒を見上げるグランと、起こしてしまった罪悪感に床を見るルリア。正反対な二人の様子を見て、ビィは一体何事だ、と首を傾げた。
「二人して何してんだ? もう夜も遅いだろ?」
「あー……いや……、ちょっと、な」
「今日は寒いから、グランと一緒に寝たいなって話してて」
枕を抱え俯く少女の言葉に、小竜は明後日の方向へ視線を逸らす相棒を見る。気まずそうに口を引き結ぶ少年の顔を見て、寝起きのそれとは全く違う半分閉じた目ではぁと溜め息を一つ吐いた。
「別にいいじゃねぇか。一緒に寝るくらい」
何が問題なんだよ、と胡桃色の瞳とともに少年の背に言葉を投げかける。今まで相棒と何度もともに夜を過ごした赤い竜にとって、一つのベッドで眠ることなど何らおかしなことではないのだろう。種族故か、歳故か、いつでも息がぴったりな相棒はその心情を理解できずにいるようだ。
「あっ、そうだ。ビィさんも一緒に寝ませんか?」
二人でも温かいですけど、三人一緒だともっと温かいと思うんです、と少女は言葉を続ける。先ほどグランが温かいと言っていたからか、それともビィも一緒ならば少年も了承してくれるのではないかと思ったのか。その顔には好奇心と期待と少しの不安が浮かんでいた。
「オイラは別にいいけどよぉ、お前はどうなんだ?」
「えっ? あー……、うん、いいと思うよ。三人だともっと温かいもんな、名案だ」
うん、うん、と少年は何度も深く頷く。二人きりでは抵抗感――というよりも羞恥が強いが、ビィと三人ならば胸中に渦巻くこの感情も少し薄まるだろう。少女が示してくれた絶好の逃げ道に喜ぶも、どこか落胆していることには彼は気付いていない。
賛同の言葉に、ビィは伸びをするように羽を広げふわりと籠から飛び立つ。そのままぽすりとグランの胸にその身を預けた。温かな相棒の瞼は半分降りており、今にも眠りの底へと落ちていきそうに見えた。
「さぁ、寝ましょう!」
弾む小さな声に振り向くと、そこにはぎゅうと枕を抱いたルリアの姿があった。その表情から憂いは消え、代わりに喜びがあった。楽しげな少女の姿に、少年はふわりと口元を緩める。あれほど否定し続けたことの罪悪感が胸をチクチクと刺すも、ルリアが笑ってくれることがとても嬉しかった。
自分の枕を置き、ぽすんと柔らかなベッドに飛び込むルリアに続いて、グランもビィを抱えたまま毛布に足を入れる。綺麗に整えられた寝具はひやりと冷たいが、直に三人分の体温でよく眠れる温度になるだろう。胸の中の相棒はそんな冷たさに気付くことなく、一足先にすぅすぅと安らかな寝息をたてていた。
ふふ、とかすかな笑い声。楽しげな音の方へ視線を移せば、そこには嬉しそうに弧を描いた空色があった。
「おやすみなさい、グラン。ビィさん」
「うん。おやすみ、ルリア」
ゆっくりと紡がれる穏やかな音に、少年も柔らかな音を返す。ゆっくりと降りていく瞼は、鮮やかな琥珀と瑠璃を優しく隠していった。
月が空を駆け、夜はどんどんと世界を広げていく。眠りの海に身を任せた子供達の表情は、とても穏やかで幸せそうなものだった。
畳む
#グラルリ
年を数える鐘の音【ライレフ】
年を数える鐘の音【ライレフ】
除夜の鐘の音って結構好きってのと年越しって何かわくわくするよねって感じの話。
一月は過ぎ去ったけれど、明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。
賑やかな笑い声がスピーカーを通して部屋に響く。煌々と光るテレビの液晶には、様々な芸能人が忙しなく動き回る姿が映っていた。ありきたりなバラエティ番組だが、一段と豪奢なセットや出演者のきらびやかな衣装、画面のそこかしこに現れる色とりどりのテロップも相まって普段以上に賑やかに見えた。
笑声の合間に、ごーん、と鈍い音が聞こえる。重く響くそれはかすかながらもはっきりとしており、音の主からずっと離れたこの部屋にもしっかりと届いた。
もう年が終わるのだな、と考えながら、烈風刀は籠に積み上げられたみかんを一つ手に取る。鮮やかな橙色の玉にそっと指を差し込み、曲線に沿うように薄い皮をゆっくりと剥いていく。柑橘の爽やかな香りが鼻をくすぐった。実を守るように走る白い筋を丁寧に取り去っていく。いくらかの時間をかけ、ようやく姿を表した赤味の強い橙を房に沿って外していく。小さな柔い半月を口に含むと、優しい甘みが舌を撫でた。
剥いた皮の上に置いた実に、節のある指が伸ばされる。手の持ち主、隣に座る朱は丁寧に処理された果実を一房口に放り込むと、甘い、と小さな声を漏らした。今日何度目かの言葉に碧は何も言う事はなく、また一つ小さな房に手を伸ばした。
一年の最後を飾る日の夜、兄弟はこたつに入りぼんやりとテレビを眺めていた。液晶に映る年末恒例の特別番組は騒がしいばかりで、高校生の好奇心をくすぐるには少し足りない。それでも音が無いのは何だが寂しく思えて、ただ点けているだけだ。二人で暮らし始めて幾年、言葉を交わさぬ静寂などすっかり慣れてしまったというのに寂しさを覚えるのは、冬の寒さ故だろうか。そんな取り留めのないことを考えながら、少年は甘酸っぱい橙色を口にした。
元々小ぶりなものを二人で分けたのだから、鮮やかな実はすぐに姿を消してしまった。残った柔い皮を小さく畳み、烈風刀は籠の傍らに置かれた屑入れに手を伸ばす。紙で作られた簡素なそれの中には、いくつもの橙色が積み重なっている。彼らがこの場に長い時間いるのだということを静かに表していた。
大掃除はどうにか日が暮れる前に終わり、夕飯時には例年通り年越し蕎麦を食べた。既に風呂も済ませたので、あとは歯を磨いて寝るだけだ。見たいテレビ番組や早く読んでしまいたい本、済まさねばならない課題があるわけでもないのだから、これ以上起きている理由や必要性は無い。むしろ、明日はレイシスたちと初詣に行く約束をしているのだから、早く寝るべきなのだ。なのに、何だか眠るのが惜しく思えるのは何故だろう。スピーカー越しの騒がしい音楽をどこか遠くに聞きつつ、碧はマグカップに手を伸ばす。中身は既に冷めてしまったようで、空色の磁器は無機物らしい冷たさを主張していた。淹れ直してくるか、と考えるも、足元から伝わる温もりに掻き消される。面倒だ、と彼にしては珍しく諦め、少年はその中身をぐっと胃の腑に押し流した。
飲み干したマグを机の中央に押しやり、烈風刀は両手をこたつの中に入れる。室内は決して寒いわけではないが、厚い布団の中に住まう温もりがおいでおいでと手招いてくるのだ。真冬という温度を全て奪い去っていく季節の中、その誘いを振り切るのは理性的な彼をもってしても難しいようだ。
雷刀とレイシスの強い要望により冬の始めに出したこの暖房器具は、すっかりと生活に馴染んでいた。日頃からソファやベッドに寝転がって過ごすことの多かった雷刀は言わずもがなであるが、意外なことに烈風刀も多くの時間をこの場所で過ごすようになっていた。エアコンとはまた違う、身体の内側まで染み入るような温かさはとても心地が良く、一度入ればつい長居してしまう。机としての役割も十二分に果たせるため、作業をするのに適しているのも一因だ。冬に限るならば、自室で過ごすよりも快適だった――というのはどれも確かな事実であるが、言い訳でもある。決して口にはしないが、兄と同じ空間、すぐ隣で過ごしたくて、烈風刀はここに訪れるのだ。
普段から兄弟二人でソファで隣り合って座り、共に過ごすことは少なくない。けれども、わざわざ単語帳や参考書を持ち込んで自室で済むようなことをするのは不自然ではないか、そうしてまで彼の隣にいようとするのはあまりにも幼いのではないか、自分ばかり求めるだなんて浅ましいのではないか。小さな羞恥と不安が、生真面目な少年の胸の隅に居座り、時折ぶわりと膨れ上がるのだ。
しかし、このこたつという暖房器具は座るのが当たり前であり、わざわざここで勉強なり作業なりをしていても不自然ではない代物である。この魔性とすら言える暖かさを知る者ならば、長居することを疑問に思うこともないだろう。冬限定とはいえ、この家具は隣にいたいというささやかな願いと小さな悩みに合理的な――あくまで彼にとって、である――答えを叩きつけ、解消してくれるものだった。
ごーん、とまた一つ鐘の音。ぺたりと机に伏した朱い頭を超し、烈風刀は窓へと視線を移した。何もかも吸い込んでしまうような黒に塗り潰された世界の中を、鈍い音が響いていく。秒針が進むのとはまた違う、残る時を数えていくようなそれは、寒空をゆっくりと歩んでいるかのようだった。ひとつ鳴るごとに、年が終わりに近づいていく。大晦日という言葉や日付よりも、この音が一番それを感じさせるもののように思えた。
スピーカーがわぁ、と大きな声をあげる。釣られて音の方へと目を向けると、液晶の中には仰々しい書体で六〇という文字が踊っていた。五九、五八と一つずつ減っていく様を見て、その数字が日付――そして新しい年へと移り変わることを示しているのだと気付いた。出演者皆で手を高く掲げ、指折りながらカウントダウンしていくのをぼぅと眺める。数字が小さくなるにつれ、声はどんどんと大きくなっていく。
一〇の二文字が一際大きく表示される。こたつ机にぺたりと頬をつけていた朱い頭がおもむろに持ち上がった。雷刀は顔を上げ、肘をつき己の手に頭を預ける。夕焼け空の瞳が煌々と光る画面を眺める。響く男女混合の笑声に、きゅー、はち、と耳慣れた声が重なった。呟くようなそれに耳を傾け、烈風刀も鮮やかな色を映す液晶を見つめた。
さん、にー、いち。
ぜろ、の声とともに豪奢に飾られた数字が画面いっぱいに広がった。新たな年を表すその数字とともに、大きな破裂音と色とりどりの紙吹雪がぶわりと舞う。明けたなー、と隣から少し弾んだ声が聞こえてくる。そうですね、と返して、少年は静かに背筋を伸ばした。
「れふと、れふと」
隣を向こうとしたところで、楽しげな声が碧の名を呼ぶ。何ですか、と問いながら横を向くと、そこには姿勢を正し、こちらに身体を向けた雷刀の姿があった。夜も深いというのに、まっすぐ向けられた茜の瞳はまるで昼間のようにきらきらと輝いていた。
「あけまして、おめでとーございます」
挨拶と同時に、ぺこりと朱い頭が下げられる。かしこまったその姿は、何だか子供が大人を真似して背伸びしているように見えた。どこか微笑ましく思えるその様子に、烈風刀は気付かれぬよう笑みをこぼす。今一度横――兄の方へと身体を向け、少年はすっと居住まいを正した。
「明けましておめでとうございます」
同じ言葉とともに、碧も礼をする。互いに深々と頭を下げる様は、家族に対しては物々しい立ち振る舞いに見えた。
年が明ける度行うこの挨拶は、二人にとっては恒例のこととなっていた。また今年も一緒に過ごしていこう。ともに助け合っていこう。そんな思いを、十五の音にのせる。そんな短い響きでも、互いにその思いが理解できた。それでも普段とは全く違う、仰々しいそれが何だかおかしく思えて、二人は顔を見合わせくすくすと笑った。
「今年もよろしくな!」
「はい、よろしくおねがいします」
全てを照らし出す太陽のように笑う雷刀に、烈風刀も穏やかな笑みを浮かべる。ともに過ごし、新たな年を一緒に歩み出す。当たり前のように感じるそれを改めて噛みしめ、翡翠に似た瞳が嬉しそうに細められた。
「さぁ、もう寝ましょう」
そう言って、烈風刀は机に置かれた屑入れに手を伸ばす。柑橘の爽やかさが香るそれを手早く畳んでいると、えーと不満げな声が飛んできた。
「もうちょっと起きてよーぜ?」
「駄目です。明日はレイシスたちと初詣に行く約束でしょう? 寝坊したらどうするのですか」
「……起こして?」
甘えるような声でこてんと首を傾げる兄に、弟は答えの代わりにじとりとした視線を返す。うぅ、と観念したかのような声が喉から絞り出されるのが見えた。ゴミを捨てに立ち上がろうとしたところで、くいと袖口を弱々しく引かれる。何だ、と目で問うと、朱はぽそぽそと小さな音をこぼしだした。
「だってー……、もうちょっと一緒にいたいし……一緒に初日の出見たいし……」
「貴方、今から起きていても絶対に途中で寝るでしょう。そのまま寝過ごすに決まっています」
朝から起きて、しかも大掃除で普段以上に身体を動かしたのだ。よく眠る彼が睡魔に打ち勝ち、これ以上起きていられるとは烈風刀には到底思えない。本人も自覚はあるのか、雷刀は気まずげに俯いた。でも、と反論を探して唸る様は拗ねているようにも見えた。はぁ、と小さく溜め息一つ。弟は今一度腰を下ろす。目線を合わせ、俯く兄の目を見つめた。
「今から寝て、日の出前にちゃんと起きればいいでしょう」
「絶対起きられな――」
「一緒に寝れば、僕と同じ時間に起きられますよね?」
一緒にいたい、という兄の気持ちは烈風刀にも十分理解できた。もう少しだけ、新たに刻み始めた時間をともに過ごしたい。これからまた三六五日ともに暮らしていくとは分かっていても、今を――年の始まり、二人きりでいられるこの時間を、誰にも邪魔されず彼を独り占めにできるこの夜を寄り添って過ごしたい。そんな甘えた願いが浮かぶのは、年が明けて無意識にはしゃいでいるからだろう。きっとそうだ、そういうことにしよう。そんな言い訳を胸中で繰り返し、烈風刀は訊ねるように小さく首を傾げ、わずかに伏せられた朱を見つめた。
言い聞かせるような問いに、雷刀はばっと顔をあげる。言葉をゆっくりと噛み砕いていく中、朱の瞳が大きく見開かれる。意味を飲み込んだところで、ぱぁと丸い瞳が輝いた。
「起きる! 絶対起きる!」
こくこくと大きく頷く様は、人懐っこい犬のようだった。その背後に勢いよく振られる尻尾すら見える。現金だな、ところころと変わる表情を見て、少年は密かに笑みをこぼした。
「まぁ、起こしてはあげませんけどね」
自力で起きてください、と告げ、烈風刀は屑入れを手にして立ち上がった。えー、と落胆したような音を背に、少年は応えることなく台所へと向かう。こたつに暖められた身体を冷やすような薄闇の中、折りたたまれた紙製の屑入れをゴミ箱に放り込む。朝焼け色の皮が、四角い暗闇に飲み込まれた。
さて、日の出の時間は何時だったろうか。晴れるだろうか。調べなければ、と考えたところで、ぱちりと瞬きをする。子供のように浮き足立った思考に、少年は小さく苦笑を漏らした。
朝日のように目を輝かせているであろう兄が待つ部屋へと、静かに歩みを進める。また一つ鐘の音が聞こえた気がした。
畳む
繋【ライレフ/R-18】
繋【ライレフ/R-18】
精神的な諸々がそこそこ回復してきたのでリハビリという名の書きたいところだけ手癖で書き殴った性癖の塊。
「……、っ、ぁ」
堪え噤んでいた口を開くと、声帯が細く掠れた音を奏でた。燃える情欲の炎に揺らめくそれが、背筋をそっとなぞる。駆けてゆく感覚に、熱を孕んだ吐息が漏れ出た。
羞恥を振り払うように頭を振り、一度頬をシーツに預ける。白の上を泳ぐ碧が視界の端に映る。日常でよくある風景だというのに、今はその二色が妙に艶かしく思えた。
「烈風刀」
甘い声が己の名を紡ぐ。汗ばんだ頬にわずかに張り付いた髪を退かす手つきは優しい。けれど、その指と声色には『目を逸らすな』と有無を言わせぬ命が乗せられていた。
「れふと」
甘い甘い声が、再度己を示す音を紡ぐ。柔らかなそれは思考を溶かしていくようだった。否、思考など、それどころか身体も既にぐずぐずに溶かされている。何もかもをとろけさせるようなそれは最早毒と大差ないのではないか、と益体のないことを考える。その甘ったるい毒が全身に回ってしまった自分は、もう救いようなどないのだけれど。
わずかばかりの抗いを乗せ、緩慢な動きで視線を正面に戻す。見上げた先の朱がどこか寂しそうに見えたのは気のせいか、それとも己の心情が反映されただけか。どちらにしろ、覗き込むその色がこちらを強く求めていることははっきりと見てとれた。
「らいと」
真似して、毒が回った甘い声で名を呼ぶ。それだけで嬉しそうに頬を緩めるというのだから、彼は単純だ。そして、その笑みを見て安心感を覚える自分も大概である。
額に口付け一つ。そんなかすかな触れあいだけで脳髄が痺れるのだから、この身体はもう彼に暴かれ、支配しつくされているのがよく分かる。熱に溺れた幼い声を漏らすと、紅玉が昏い光を宿したのが見えた。
ゆっくりと身体を揺り動かされる。肉と肉が直接擦れるだけで、何故ここまで気持ちが良いのだろうか。度々疑問に思うそれも、腹の奥底から迫り上がる感覚に掻き消される。泣く子を宥め背中を叩くような緩いリズムだというのに、背筋を走り神経を焼く快楽は酷く鋭い。ぴりぴりとしたそれが全身を駆け、体躯を震わせる。反射的に収縮する度、熱に浮かされた内部で抱きしめたそれを強く意識してしまう。
「んっ、…………ぅ、あ……」
ぐずぐずに溶けた脳味噌が、どろどろになった音をこぼす。己のはしたない声が耳すら犯していく。それは彼も同じなようで、息を呑むかすかな音が聞こえた気がした。抱えられた脚、その膝裏に差し入れられた手が薄い肉に食い込む。そんなわずかな反応でこの胸に喜びが広がるのだから、やはり自分は単純だ。
身体が動く度、下部から音が響く。深く繋がった場所は、入念に注がれた潤滑油に塗れていた。それはまるで女が悦楽に愛液を溢れさせる様と同じように思えて、背筋がぶるりと震える。びりびりと神経を焦がすそれは、嗜虐の光を灯していた。鋭さを増した刺激に、きゅう、と彼を抱え込む肉洞が狭くなる。突然のそれにか、歯が軋む音が聞こえた。
「ッ……、そんなにイイ?」
いたずらめいた視線と意地の悪い問いが降ってくる。ハ、とこぼした吐息は笑みにも似ているが、そこには愉快さや余裕など欠片も見えない。あるのは、獣欲に燃え盛る炎の輝きだけだ。
「……わ、るかった、ら……、こんなこと……っ、なる、わ、け……ぁ、ない…………で、しょう」
そう言って、覆い被さる彼の腰に空いていた片足を絡める。ほんの少し引き寄せただけで繋がりが深くなったように思え、襲う情欲に小さく息を吐いた。安っぽい挑発だが思いの外効いたらしい、光る瞳が苦しげに細められた。
「そーだよな……っ!」
仕返しと言わんばかりに、いきなり突き上げられる。内壁を勢いよく擦られ、頭を力いっぱい殴られたような快楽に思わず喉が仰け反った。だらしなく開いた口から、悲鳴になり損ねた嬌声があがる。見開いた目から大粒の雫が伝い落ちた。
「ッ……! ぁ、あっ…………、ぅ、あぁっ!」
快楽を示す信号が脳に叩きつけられ、衝撃に声帯が震える。言葉とは到底言えない音の集合体は、砂糖を煮詰めたように甘ったるい匂いを発していた。恋人を――雄を誘惑する香りだ。
涙で朧になる彼を求めるように、無意識に手を伸ばす。暗闇の中光を探るようなそれを、温もりが受け止める。手のひらがひたりと重なり合い、指と指とが自然に絡みあう。逃しはしないと言わんばかりに固く結ばれたそれに、心細さに冷えた心が満たされる。内に広がる幸福感に、ふわりと破顔した。
情欲にとろけきった瞳、閉じることができず端から唾液を漏らす口、溢れた涙がいくつもの道を作るこの顔が酷い有様であることは、鏡を見ずとも容易に分かる。そんな醜い顔を晒すなど普段ならば決してないが、今この場では別だ。目の前の揺らめく朱は『目を逸らすな』と言っているのだから、それに従わねばならない。何より、心より愛する彼が己のあられもない姿に背筋を震わせるその様を見ていたかった。正反対の色をした二対の瞳が交わる。欲望に燃えたそれは、己を見つめる色を切望していた。
「ぅ、あっ…………らい、と……らいと、らいとっ」
「れふと」
雛鳥が親鳥を呼ぶように愛し人の名を幾度も口にすると、熱を孕んだ声が己の名をなぞる。額に、瞼に、鼻に、頬に、唇に、柔らかな口づけが落とされた。焦がれていた感触に、心が満たされ、すぐさま渇きを覚える。奥底に秘めた獣の本能へと沈みゆくこの身体はどこまでも貪欲だった。より求め、白の海に放り出したままの片腕を彼の首に回す。首筋に顔を寄せ、甘えるように鼻先を擦りつけると、彼の香りと汗の香りが混じった匂いが鼻腔に満ちる。普段よりもずっと濃いそれが脳を揺らした。
「っ……、れ、ふと」
切羽詰ったような声が鼓膜を震わせる。己が発するのと同じ、求める音に応え、内も外も彼を強く抱きしめた。離れたくないとばかりにしがみつくそこに幾度も熱塊が突き立てられ、その度に喉がとろけきった声を奏でる。淫らな音が薄暗い部屋を満たしていった。
「あっ、ひ、ぅ…………、ぅ、あ……、ぁっ……」
呼吸と共に溢れる嬌声は、抱えた欲望の焔をはっきりと映し出していた。堪らえようにも、轟々と燃え上がるそれが許してくれない。閉じることなど忘れた口からは、本能がままに発する甘やかな音が漏れるばかりだ。
れふと、と掠れた声。数瞬の後、肩口に鋭い痛みが走った。痛覚によりわずかにクリアになった思考を、すぐさま強い快感が掻き消す。甘さに溺れた脳味噌は、牙を立てられたことすらきもちのいいことだと認識した。がぶがぶと牙が何度も襲う。甘噛みと言うにはいささか激しいそれは、肌にはっきりとした赤い痕を残していくだろう。後で困るのは自分だというのに、今はそれが嬉しくて堪らなかった。衝動に任せ噛み付くほど興奮している。淫らに乱れた己を見て欲情している。我を忘れるほど激しく求めている。情欲に溺れゆく胸の内に、陰を帯びた焔が灯ったように思えた。
「らいと、らいとっ……!」
首に回したままの腕を引き寄せる。頭を固定するようなそれは、もっと食らってくれと主張するようだった。獣めいた呻きが聞こえる。被虐を求めるようなそれに煽られたのか、それとも単に息苦しいのか。どちらか定かでないが、繋いだ手にぎゅうと力が込められたのが分かった。牙と共に、硬い欲望が内に突き立てられる。荒々しいそれに苦しさすら覚えるも、溢れ出るのは法悦に満ちた高い声ばかりだ。
獣欲の底へと沈みゆく意識の端に白が浮かぶ。淡いそれがどんどんと存在を主張し、思考を塗り潰していく。かろうじて明瞭だった部分すら染め上げ、快楽という強い色に上書きしていった。薄暗い部屋の中、視界に細かな星が舞う。水が跳ねるようにぱちぱちと音をたて不規則に明滅するその幻は、頂点が近いということを如実に表していた。
らいと、と必死に彼の名を呼ぶ。長く行為に及びとろけきった頭の中は、きもちのいいことと彼のことでいっぱいになっていた。
らいと。れふと。らいと。れふと。存在を確かめ合うように、互いに互いの名前を呼ぶ。たったそれだけで脳髄が痺れた。彼の声が己の名を模る度に、肉の洞は猛る欲望に絡みついた。
声と声とが重なり、呼吸が重なり、唇が重なる。動く度に溢れる声は、互いの口の中に飲み込まれた。くぐもったそれはシロップのように甘く思えて、ねだるように舌を伸ばした。ぐちぐちと交わった場所から淫猥な水音があがる。鼓膜を通り抜けた響きが、直接思考をぐちゃぐちゃに掻き乱していく。
ごつん、と鈍い音が聞こえた気がした。
好む一点を強く抉られた瞬間、目の前に激しく火花が散った。衝撃のあまり目を見開いたというのに、視界は真っ白に塗り潰され何も見えない。ただ、内部に咥え込んだそれの形だけははっきりと分かった。
ぴぃん、と強く張られた糸のように爪先までまっすぐに硬直する。唯一仰け反った喉から悲鳴になり損なった音が響いた。きゅうぅ、と熱塊を咥え込んだそこが強く締まる。激しく脈打つそれの存在を今一度認識し、受け入れた場所が悦びにきゅうきゅうと抱きついた。
腹の辺りに生温かいものが散っていることに気づく。果てたのだと理解して、は、と肺の奥底から深く息を吐いた。倦怠感がどっと押し寄せてくる。首に回していた手から力が抜け、ぱたりと皺だらけのシーツの上に落ちた。
「――ぅ、あッ!?」
落ちるはずだった。
足を掴んだ彼の手に力が込められる。そのままぐいと体重が掛けられ、押し潰すように腰が押しつけられる。焼けた刃が柔い秘肉を貫く感触に、大きく目を見開いた。一度凪が訪れた身体を暴風が襲う。普段ならばとうに過ぎ去るはずの快感が、絶える事無くどんどんと押し寄せてくる。熱を吐き出したことにより幾分かクリアになったとはいえ、まだ快楽の海に身を委ねた脳味噌では理解が追いつかなかった。
「れふとっ、ご、め……! も、ちょっと、だけ、だからぁ!」
荒い息の中、必死な音がこぼれ落ちてくる。果てたばかりの身体を今まで以上激しく揺り動かされ、喉が変な音をたてた。ひくつくナカを硬い欲が勢いよく擦り上げていく。柔い肉で必死に抱き止めるそれが、拘束を振り解くように一気に抜かれ、浅い部分から深い部分まで突き進む。好い部分までごりゅごりゅと音をたてて容赦なく擦られ、意識が飛びそうになる。消え行きそうなそれを、快感が無理矢理引き戻す。理解していた以上に凶暴なそれは、ひとりで逃げることなど許してくれなかった。
「あ、ッ……うぁ、あ! ひ、ぃ……やっ、ぁ…………!」
肉と肉がぶつかりあう度にあがる声は、嬌声と言うよりも悲鳴と表現した方が相応しく思えた。声と共に、先程欲を吐き出し終えたはずの場所からびゅくと雫が幾度も漏れる。押し出されたようなそれが更に腹を白で汚し、にちにちと卑猥な音をたてた。頂点まで登り詰めたはずなのに、情欲は猛るばかりで落ち着く様子は一切見られなかった。果てたはずなのに、果てが見えない。ずっと宙に吊られたままのような感覚に、ぞわりと心が粟立った。
快楽の荒波に揉まれる中見えた彼は、熱にとろけきった瞳でこちらを見つめていた。瓜二つと評されるそのかんばせは、まるで肉欲の溺れる己を映す鏡のようだった。彼も同じぐらいきもちよくなっているのだという喜びと、許容量を超えそうな快楽への恐怖がぐちゃぐちゃに混じり、胸の内を支配していく。それら全て、内部を我武者羅に突き上げられる衝撃と情動に搔き消された。
ごめん、と謝罪の言葉をひたすら繰り返すも、その身体は欲望がままに突き動いていた。抱き込むそこがめくれ上がりそうなほど勢いよく引き抜かれ、腹を突き破りそうなほど強く押し込まれる。配慮など全くない、本能に身を任せた――つがいを確実に孕ませんとする動きだった。
ならば、と首に回した手と腰に絡めた足に力を込める。絶対に離れまいと――注ぎ込まれるであろう子種すべてをこの腹で受け止めようと、覆い被さる彼にしがみついた。しっかりと手入れされた爪が彼の背に刺さる。痕がつく懸念よりも、離れてしまう不安が勝った。傷付けてでも離れない、離れたくないと身勝手な心が叫ぶ。諫める理性などとうに失った身体は、情動がままに動いた。
快楽を認識した神経が、その信号を脳味噌に叩きつける。受容限界を超えてなお送られるそれは、暴力と言っても差し支えないものだった。声帯がはしたない音を奏でる。みっともないほどぼろぼろと涙がこぼれる。それでも欲しくて、彼が欲する全てを捧げたくて、必死に繋いだ手に握り締めた。
「ぅ、あっ……、ぁ、れふとっ、れふとぉ……!」
ごん、と鈍い音が響くほど力強く突き上げられた後、腹の奥底に熱いものが勢いよく注ぎ込まれた。臓腑を焼き尽くすようなそれに、しがみついた身体がきゅうと丸く縮こまる。頭の中で膨れ上がった何かが音をたてて弾け、繋がった場所が今一度強く収縮する。幾度目かの絶頂を味わったのだと理解した頃には、腹の中は彼が吐き出した欲望で満たされていた。
ようやく高みに達した彼が、ゆっくりとのしかかってくる。脱力しきったその身体は重いが、気にする余裕など互いに持ち合わせていなかった。汗ばむ肌が重なるのは不快だろうに、今ばかりは心地良さすら覚えた。痛いほど駆動する心臓の音がふたつ合わさる。合奏のようなそれが安堵で胸を満たしていった。
れふと、れふと、と何度も呼ぶ声はとろけた甘いものだ。囀りのようなそれに応え、らいと、と名前を呼ぶ。己の声も酷く甘ったるいものだった。
少しばかり回復したのか、重なった彼が片肘をつき身を持ち上げる。わずかばかりの寒さを覚えるが、求め動こうにも倦怠感が邪魔をした。
「……ご、めん。また、噛んじまって」
まだ乱れた呼吸の中、眉を八の字に下げ謝る姿は、先程まで肉に食らいついていた様子からは想像できないものだ。うぅ、と呻き声一つ、再び肩口に顔を寄せた彼は、肌に浮かぶ赤を労るように舐めた。浅い傷口に唾液が染みるわずかな痛みと、行為を想起させるように肌を舌がなぞる感覚が、そわりと背筋を撫でる。まるで温和な犬のように思えるが、実態は猛る獣だ。またいつ噛み付くか――スイッチを切り替え、激しい行為に及ぶか分かったものではない。気怠い腕を持ち上げ、朱い頭を後方へと押しやる。抵抗と言うには弱々しいが、従順な彼はすぐに口を離した。うぅ、とまた後悔が色濃く滲んだ呻き声があがる。しゅんと項垂れる姿は、やはり人懐っこい犬のように見えた。
ちらりと痕に目をやり、仕方がないな、と言いように深く溜め息を吐く。責任の所在はそちらにある、と主張する稚拙な演技だ。責任など、強く抱き締め牙を求めた自分と半々なのに、そう言っては彼はまたもごもごと後悔の言葉を漏らすのだ。事後の甘さを掻き消すような無粋なそれは、面倒くさいの一言に尽きる。ならば、最初から押し付けておく方がいい。
いいですよ、と、肌に綺麗に並んだ赤をそろりと撫でる。酷くても皮膚が少し破れた程度だ、きちんと薬を塗ればすぐに治るだろう。寂しいなどと思ってしまうことは隠しておく。痕を残されることは嫌いではないが、調子に乗って量を増やされるのは日常生活に差し障る。今ぐらい――全てを知っている自分と彼には見えて、他人には悟られづらいぐらいがちょうどいい。
んー、と少ししょげた声を漏らし、彼は反対側の首筋に顔を埋めた。肌を呼気が撫でる感触がくすぐったい。仕返しするように、真似して彼の首筋に鼻先を擦り付ける。脳味噌を揺さぶったあの濃い匂いは、いくらか薄れているように感じた。
じゃれるように擦り付き合う内に、荒い呼吸が徐々に落ち着いていく。相手を求め、あれだけ高ぶり高鳴っていた心が凪いでいくようだった。
ぬるり、と楔が内部から抜かれる。刺激を与えまいとゆっくり動くそれが愛おしく思え、小さく息を漏らす。彼自身はどんどんと離れていっているというのに、腹の中にはまだその熱が残っていることがどこか不思議に思えた。
長い時間をかけ、ようやく繋がりが切れる。栓を失った後孔から温かなものがとろりとこぼれた。未だ悦びに浸った頭がもったいない、などと考える。浅ましい、と消え失せていたはずの理性が詰る。全て彼に与えられたものなのだ、失うことなどもったいないに決まっているではないか、と本能が声高に主張した。
そんなはしたない思考が表に出ていたのか、そっと額に口付けが降ってくる。ぐちゃぐちゃになった己を落ち着かせようとする度、彼は優しく唇で触れるのだ。柔らかな感触と温度に、胸の内に温かなものが広がった。
繋いだままの手を今一度ゆるく握る。離さないと言うように指と指が絡んでいることが酷く幸せに思え、ふわりと頬が緩むのが分かった。つられたように同じ笑みが返ってくる。目の前の穏やかな朱が愛しくて、浅く開いたままの口から音が二つこぼれ落ちた。
畳む
二匹の獣【陸海/R-18】
二匹の獣【陸海/R-18】
LegenD.赤AA乗りました。
お察しください。
ぶち犯すとか言ったけど普通に和姦。
夜の底に呻き声にも似た声がこぼれては消えていく。取り付けられた窓から差し込む明かりは、月がもたらす淡いものだ。ほっそりと空に浮かぶそれが雲に潜る度、埃臭い部屋は闇に侵される。それでも、二対の瞳は黒に埋もれることなくギラギラと輝いていた。
下半身から溢れる水音と、肉と肉がぶつかる鈍い音が耳を犯す。聞き飽きた音だというのに、身体は馬鹿正直に快感を拾い上げていくのだから腹立たしい、と烈風刀は心底不快そうに目を眇めた。歯を食いしばり、迫り上がっってくる声を喉に押し込める。人前でよがり声をあげるなど、何千、何万の兵の上に立つ者として――何よりも自身のプライドが許さない。たとえ相手が幾度も夜を共にした人間であっても、だ。
燃える瞳が交錯し、火花を散らす。暗闇すら焦がすようなそれを、空がまた陰らせた。
戦を終え、海軍大将である嬬武器烈風刀は今しがた王女が治める国へと足をつけた。帰るべき城を見上げると、忠誠を誓いこの身全てを捧げる王女の顔が思い浮かぶ――のが常であったが、今回は様子が違った。
先の戦は、わずかに刃を交えただけであっさりと終結してしまった。あまりにも呆気なさすぎて、わざわざ軍を動かす必要があったのかと疑問が残るほどだ。手応えなど皆無と言って差し支えのない戦は、彼の高ぶった気を抑えるにはあまりにも不十分だった。
闘いと血を求め燻る熱はなかなか消えない。臓腑を焼くそれは飢えにも似ていた。何もかもが満たされない苦しみ、苛立ち。足りない、と叫び暴れる本能は己が肉を食い散らかさんばかりの勢いで身体を駆け巡る。自身を食い尽くしたところで、その飢えが満たされるはずもないというのに。
こんなことではろくに行動できない。無理矢理押さえ込み必要なこと済ませるよりも、燻る胸の内を処理してしまった方がよほど合理的だ。
仕方がない、と烈風刀は外套を乱雑に脱ぎ捨て、近くにいた者に簡単なものだけでも処理しておくよう指示する。いきなりのそれに何か言いたげに顔を上げた兵は、彼の瞳を見て石のように固まった。海の底を彷彿とさせる蒼に、荒く蹴立てる波飛沫のような白が浮かぶそれは、不気味なほど煌々と輝いている。死を誘う鬼火のように冷たく、何もかもを焼き尽くしていくような焔がはっきりと見て取れた。
スゥと細められた目に、矮小なそれは弾かれたように返事をした。あの光に殺されては堪らない、と震える手で作業に取り掛かる。そんな塵芥など気にもかけず、烈風刀は部屋を出た。
壁にぽつりぽつりと取り付けられた灯が、暗闇に逆らおうとその命を燃やす。それでも夜を支配する黒に勝てるはずなどなく、長い廊下は仄暗い様相をしていた。足早にならぬよう意識し、静かに歩を進める。バタバタとうるさく走り回る兵らは、彼のことを一切気に留めることなく仕事をこなしていた。否、絶対に触れまいと皆一様に必要以上距離を取り行き交っているのだ。海を統べる彼が、どれほどその駒に畏怖の念を持たれているか如実に分かる。
揺らめく灯、愛しい王女のドレスのように鮮やか赤い絨毯を敷き詰めたその道を進むにつれ、向かう先の紅が脳裏にちらつく。何もかもを見下し、全てを征服せんばかりに口角を釣り上げるあの腹立たしい顔に、烈風刀は無意識に鋭く舌打ちをした。奴を利用するのは癪だが、合理性から考えるとそれが最適解だった。己の為に利用するだけだ、と言い聞かせ、どんどんと歩みを進める。奥へと向かうにつれ、騒がしい人影は宵闇に溶けていった。
角を曲がると同時に、烈風刀の視界に見知った色が飛び込んできた。
王女が纏うそれよりもずっと深い、凝固した血液のように濁った紅。見たくもない色――そして今、探し求めていた色だ。
あちらも気づいたのか、視線と視線がぶつかる。細められた二対の瞳はそれだけで容易く人を殺せるほどの鋭さがあった。それでも互いに臆することなく相対しているのは、二人が同格である証拠である。事実、目の前の紅は己と対を成すような陸地を征く兵を統べる大将であった。そんな大将様が、こんな時間に敵地と言っても過言ではない海軍管轄の施設ににいるなど、あまりにも不自然である。
陸軍も陸軍で、本日に戦を終え帰還したと聞き及んでいた。だから、予感はしていたのだ。
奴――双子の兄であり、陸軍大将を務める嬬武器雷刀も、この飢えを抱え込んでいるのではないか、と。
烈風刀の予感は的中したようだ。カッチリと着こなすべき軍服は外套を失い、ジャケットも袖を通さず羽織っている。首元には緩められたネクタイが所在なさげに揺れていた。その表情は不機嫌さを全く隠すことないもので、光る紅玉には轟々と燃え盛る昏い焔が沈んでいた。
ちらりと、烈風刀は長く続く壁を見やる。幸か不幸か、二人のちょうど間にはドアが一つぽつりと佇んでいた。たしか、戦には関係のない雑多な荷物を一時的に保管している倉庫のような部屋だったはずだ。機密に触れるような重要なものは別所に保管してあることもあり、誰でも整理できるよう鍵はかけず開けたままにしていたことは記憶している。
再び視線が交錯する。蒼瞳の意図を理解したのか、赤い口がわずかに釣り上がったのが見えた。
紅が足早に距離を詰め、ぐい、と烈風刀の腕を強く引く。掴んだそれを気遣う様子などまるでなく、雷刀はそのまま目的のドアへと向かっていった。引かれる蒼は、珍しく文句一つ言わずされるがままでいる。ここで抵抗するのも面倒だ、さっさと済ませてしまうことが先決である、と静かな瞳が語っていた。
乱暴な音をたてて扉が開かれ、二人の身体を飲み込んで閉まる。カチ、と内鍵がかかる音が耳に届いた。手際のいいことだ、と烈風刀は侮蔑するように白い手袋に包まれたその手を眺める。
人の出入りはそこまで多くないのか、埃の匂いがわずかに鼻をつく。その割には片付けられており、床や棚には綺麗なものだ。申し訳程度には取り付けられた窓は嵌め殺しの簡素なもので、カーテンなどはかけられていない。明かりを灯す器具もないこの部屋唯一の光源だ。
力任せに腕を引かれ、月明かりなど掻き消してしまいそうな暗闇を進む。数歩進んだ部屋の奥には、人一人が何とか寝転がれる程度の空間があった。なんともまあ都合の良いことだ、と考えていると、がくんと首に衝撃が走る。ネクタイを掴まれ、手綱のように引かれたのだ。首が締まる息苦しさとともに、唇が塞がれる。噛みつくようなそれは、烈風刀の薄い唇を食い千切ってしまいそうな勢いだった。余裕のないことだな、と内心嘲り、与えられる熱に集中する。甘噛みするように幾度も降り注ぐそれを享受し、反撃だと言わんばかりに離れようとする唇を食む。逃げ追いかけを繰り返す様子は幼い子供がじゃれあう姿のようだ――ただし、二対の瞳はどちらも鋭く眇められ、射殺さんばかりの気迫に満ちているが。
擬似的な捕食の応酬が落ち着くと、ネクタイを引く手が離される。そのままトン、と軽く押され、烈風刀は重力に身を任せ倒れた。容易に予測できた行動に、受け身を取りそのまま床に背を預ける。ほんのりと埃のむず痒い匂いが鼻をくすぐった。深いこの青が汚れた灰にけぶることに思わず眉をひそめるが、この後の行為を思うとその程度の汚れは些事でしかない。
バサリ、とジャケットが地に落ちる音とともに、すぐさま紅が覆い被さり再び唇を食らう。いくらかの殺伐としたじゃれあいの後、合わさったそこからぬめる塊が遠慮なく這入ってくる。厚く熱いそれが擦れる度、腹の奥に熱が蓄積されていく。燻る炎にいくつもの薪がくべられ、高らかに燃え上がり勢いを増していく。それは相手も同じようで、口と口が離れる度に漏れる吐息は酷く熱い。互いに燃え盛る炎に思考を焼かれ始めていた。
あぁ、満たされる。
燃え上がる欲に反し、蒼い心は凪いでいくようにすら思えた。あれだけ内を食い破らんばかりに暴れていた飢えが満たされていく――けれども、猛る炎はまだまだ足りないと勢いを増すばかりだった。
兄は随分と『人気』があるようだが、それでも弟を『利用』しているあたり、飢えを満たしてくれるほどの『餌』は見つかっていないようだ。当たり前だ、こんな猛獣を満足させるほどの『餌』がそこらに転がっているわけがない。屑肉が何十、何百とあろうが、この獣を満足させ、飼い慣らすことなどできないに決まっている。そして、それは弟も同じだ。そこらに転がる餌で飢えが満たされるはずがない。簡単に飼い慣らせるほど、安い存在ではないことなど、よっぽどの節穴でもなければ一目で理解できる。
だからこそ、兄弟は互いを『利用』する。己すら食い散らかさんばかりの凶悪な飢えを満たせるのはこいつしかいない、と双方理解していた。そんな屈辱的な事実を口に出すことは一生無いけれど。
唾液に濡れた赤と赤が絡みあう。擦り寄り、離れ、食み、潜り、自在に動く様は、まるで踊っているかのようだった。即興なれど息の合った美しいダンスは、月明かりに照らされてらてらと輝いていた。口内に溢れる唾液は掻き混ざり、もはやどちらのものかなど分からない。飲み下す度、欲が満たされ、更に渇きを覚える。燃えたぎる炎は快楽という名の安寧を求め、貪欲に相手を食らおうと、黒に包まれた手が乱れたシャツの襟元を引き掴む。そのまま自ら距離を詰め、噛みつくように口を寄せた。荒い呼吸はどちらのものか、それとも互いのものか。そんな瑣末なことを考える。とうの昔に放り出された理性が思考を動かすことはない。脳味噌の中身など、既に本能によって支配されていた。
手袋に包まれた指先が、するすると深い海色の布を滑っていく。汚れの見当たらない白は慣れた手つきで装飾を乱雑に解き、分厚い布を剥いでいく。肌を撫でる夜の冷たい空気にそわりと粟立つ。それもすぐに交わる熱に上書きされた。
踊るように戯れていた舌と舌が離れる。睨みつけた先の紅は、情欲に煮え滾っていた。そうでなくては、と掴んでいた布から手を離し、蒼は口角を釣り上げる。この程度で満足するような獣に、凶暴で気高い獣の相手が務まるはずもない。
そう、獣だ。本能に身を任せ暗く薄汚れた空間で盛りまぐわうのは、大将の地位に就く人間でなく、ただの飢えた獣だった。人間の尊厳を捨て去り、貪欲に快楽を求め互いを食らいあう姿は、理性など持ち合わせていない動物と同じだ。
日が沈みきる直前の空のように赤々とした口に、白い指が這入り込む。鋭い牙を使い、雷刀は力任せに手袋を脱ぎ捨てた。剥き出しになった指は節くれだち、硬い印象を焼き付ける。剣を振るい闘う者の手だ。
咥えた白を頭の動きのみで適当に放り、開いた口に硬い指が潜り込む。先程まで絡めあっていた舌が、まとめて差し入れられた指の隙間を割っていく。根本まで唾液に塗れ、窓から差し込む月明かりでてらてらと輝く様は淫靡の一言に尽きた。
指の腹を舐め上げるような動きで舌が離れる。空いていた片手が深い蒼を纏った膝裏に差し入れられ、ぐいと足を持ち上げられる。薄暗い部屋の中、日常生活では決して人に見せることのない奥に秘めたる箇所が月明かりに照らされた。本当に必要最低限、肉と肉が繋がりあうために要する部位のみ露出された様子は淫猥である。これも、飢えた獣の欲を煽り満たすための演出だ。もちろん、実用性も十二分にある。いちいち厳かなこの衣装を全て脱ぎ、行為により体力を消費しきった身体でのろのろと着直すのは酷く面倒である。この程度ならば容易に終わるのだから効率的だ。どうせ戦場を駆け抜けた後の衣服は洗うのだから、汚れを気にする必要もない。それでも、目の前の紅は分厚いジャケットを解き、白で染まるであろう腹部を包む箇所も剥ぎ、律儀に捲りあげるのだ。この関係は既に周囲に――流石に愛おしき王女には気づかれないよう徹底的に情報を排除している――暗黙の了解として共有されているのだから、汚してしまっても何ら問題はないというのに、と蒼は常々疑問に思う。その真意を尋ねるつもりなどは無い。
そろそろと過剰なほど慎重な手つきで濡れた指が後孔に添えられる。雷刀のそれが、ゆっくりとその表面を撫でる。皺を伸ばすような動きに、烈風刀は強く眉を寄せた。互いに飢えを満たすためだけに『利用』しているというのに、この男は必要以上に優しく『準備』を行う。愛撫という言葉がよく当てはまるそれは、海色の神経を搔き乱す。腹立たしさに、ギリ、と歯噛みした。
その感情を察したのか――この男のことだ、今までの行動は意図的なものだった可能性が高い――ゆるゆると円を描くように淵をなぞっていた指が、窄まったそこにひたりと宛てがわれる。そのまま、節のある硬い指が洞の中へと潜った。第一関節まで進み、爪の根元まで戻る。緩慢な動きで繰り返されるそれに、肉が悦ぶように痙攣した。理性ではコントロールできないそれに気を良くしたのか、雷刀は少しずつ指を埋めていく。第一関節から第二関節、第二関節から根本まで、段階を踏んで挿し込んでいくその動きは壊れ物を扱うかのようなものだった。烈風刀にとっては不愉快でしかない。荒立つ海のような瞳が苛立ちに眇められた。
侵入した指の腹が内壁をなぞる。細かな動きで擦られ、ぞわりと背筋を快感が走っていく。浅い抽挿を繰り返し、ずるずると深く抜き、またゆっくりと全体を使ってうねる壁を擦る。動く度に、内に宿した炎がどんどんと勢いを増し、轟々と高く昇っていく。音を漏らすまいと引き結んだ口から、焔に焼かれた吐息がわずかにこぼれた。好む場所を柔く突かれ、反射的に身体をよじる。しかし、中途半端に脱いだ服は枷として機能し、それを許してくれなかった。そういう点は不便である。否、兄から見れば利点なのかもしれない、と弟は快楽が押し寄せる脳味噌で考える。いちいち動かれるのも手間だ、拘束しておいた方が楽である。
唾液を追加しつつ、紅の硬い指がぴっちりと閉じたそこを解していく。二色のみ存在する閉鎖空間に小さな水音が響き積もる。欲で燃え盛る炎にどんどんと薪をくべるようだった。それが発する熱が出口を探し、雄としての器官に集中する。一切の刺激も与えられていないというのに、そこは反り返るほど血液で膨張していた。己がこぼした蜜で濡れ、快楽を求め時折震えるそれは淫らで蠱惑的だ。それでも、そちらの肉へと手が伸ばされることはない。雷刀が欲を満たすために必要なのは後孔のみである。そちらに触れ相手を満たす必要性など、彼は持ち合わせていなかった。烈風刀も同様である。たしかに肉体はそこへの刺激も強く求めているが、今この場、兄がこちらを注視している時に自らそこに触れ、一人慰める姿など死んでも見せるわけにはいかない。それに、幾度も行為を繰り返したこの身体は、秘所を暴かれることばかりを好むようになってしまった。とんだ変態、汚らしい淫乱である、と己を罵倒する。けれども、事実が変わることはない。心の底から飢えを満たすためには、硬く熱されたあの楔を解れ潤んだ己の鞘に納めるしかなかった。
何度も月が雲の影に身を隠すほどひたすらに時間をかけ、ようやく二本目を根本まで咥え込んだ頃には、そこは既に剛直を受け入れる場所としての役割を思い出していた。それでも、内を暴く指は止まらない。身体的な機能として残された硬さすらも解し溶かそうとするようなそれは、蒼の中に燻る熱と苛立ちを強く刺激する。視線の先、相手の髪よりもずっと深い紅の衣装の一部は、痛々しいほど膨れ上がっていた。早く済ませれば良いものの、何故ここまで時間をかけるのか。理解するつもりも、わざわざ問う予定も持ち合わせていない。
肘をつき、烈風刀は身を起こす。入念に『準備』をするそこから顔を上げた紅と視線が交わった。交錯したそれはそのまま、空いた手を膨れ上がった箇所へと伸ばす。硬度を増したそれに、黒い薄布に包まれた細い指を一本宛てがった。
「さっさとしたらどうなのですか」
根本から頂点へと、焦らすようにゆっくりとなぞっていく。たったそれだけで、覆い被さった身体が大袈裟なほど震えた。ハッ、と侮蔑と挑発を込め嘲笑う。行為の意味も手段も知らぬ無垢な子供のような反応は、肉欲に飢えぎらつく瞳とは正反対で酷く愉快に思えた。
交わった先、情欲に燃え上がる赤目が愉快そうに細められる。とん、と先端を軽く突いた黒を絡め取り、雷刀はそれを床へと縫い止めた。指と指を絡めあいぎゅうと強く握るそれは、恋人同士が行うそれに似ている。もちろん、そんな甘さなど欠片も含んでいない。余裕を装いきれず、急かすそれに応えただけだろう。
ニィ、と牙の覗く口が醜く釣り上がる。赤々とした唇は、溢れ出る愉快さと、浅ましさへの嘲りと、抑えきれぬ情欲とが混ざりあった色で彩られていた。
ズルリと内部を占領していた指が性急に引き抜かれる。勢いよくうねる壁を擦り上げられ、快感が脊椎を直接駆けていく。制御しきれず跳ねた蒼の身体を見てか、短い嘲笑が漏れたのが聞こえた。
金属と布が擦れる音の後、唾液で濡れそぼった孔に硬いものが宛てがわれる。指とは全く違う硬度と質量を持ったそれに、ひくひくと淫らな肉が期待に震えた。
「痛いからって泣くなよ? 大将サン」
何を、と海の将は嘲笑に嘲笑で返す。数多の戦場を駆け、この身で闘う人間に言う言葉ではない。そして、その手で過剰なほど丁寧に解した癖に、痛みを感じるなどとよく宣えたものだ。
焦らすような緩慢な動きで、熱塊が洞の中へと進んでいく。ゆっくりと内部を焼かれる感触は未だに慣れることができない。処女であるまいに、と呆れるも、細い道を質量が増した器官でみちみちと音をたてて割り広げられると、どうしても苦しさが迫り上がってくるのだった。闘いで味わう、外から強く与えられるそれではなく、うちがわからじわじわと染めていくそれは、日常生活では到底得ることのできない、まず味わうことのないものである。
熟れた先端が先陣を切り、続いて浅黒い幹がひくつく肉を割っていく。空白が埋め尽くされていく感覚に、脳髄に鋭い電気信号が叩き込まれた。ぐ、と、烈風刀は喉奥から迫り上がってくる嬌声を歯を食いしばり殺す。互いに本能をさらけだし身体を貪る関係を持っているとはいえ、相手は実の兄かつ敵対していると言っても過言ではない集団の頂点に立つ者である。そんな人間に、女があげるような高い声を聞かせるわけにはいかなかった。
長い時間をかけ、ようやく欲望の塊が柔らかな内部に納められる。渇き喘ぎ叫ぶ飢えがゆっくりと治まっていくのが分かった。唇を合わせ、舌を擦り合わせた程度では決して得ることのない充足感に、心の底から悦びが湧き出る。歓喜に満ちゆく情意を、落ち着いたはずの飢渇が食らっていく。隙間無くぎゅうぎゅうに埋め尽くされているというのに、快楽に貪欲な孔はもっと欲しいと訴えるようにはくはくとうごめいた。強く締め付けるそれにか、欲に潤む赤い瞳が苦しげに細められる。初めて行為を経験する若人のような反応に、青い瞳が愉快そうに細められた。
暗闇の中、紅と蒼の視線が再びぶつかりあう。どちらの色も、欲望に満ちた光で煌々と輝いていた。両者とも、床の上で交えた手を固く握る。互いを強く抱き締めあう白と黒の姿は、獲物を逃すまいと乗り上げ押さえつける獣のそれだった。
溶けて接合してしまうのではないかと錯覚するほど長い停滞の後、ようやく埋め込まれた楔が動き出す。ゆっくりと退き、また同じ速度で奥へと進む。緩慢な刺激に、包み込む鞘が乞うようにうごめいた。熱いそれが動く度、強く抱き締める度に快楽がちりちりと心を焼いていく。飢えを満たすはずのそれは、燻る炎に燃料を与え更に燃え上がらせようとするものだった。与えられる自分ですらこの調子なのだ、相手もこの程度では渇くばかりだろう。本能に身を任せ動けば良かろうに、と寒さを孕む瞳が憎しげに細められた。
烈風刀は空いた手を伸ばし、覆い被さる雷刀の頬に触れる。意識がこちらに向いたことを確認してから、抱え込んだそれを搾り取るように締め付けた。ぐ、と息を呑む鈍い音とともに、内を広げる欲望がびくりと震える。さっさとしろ、という無言の要求に、陸の将は牙を見せ笑みを浮かべる。愉快さではなく嗜虐の色に染め上がったそれは、まさしく獣の容貌をしていた。
壁全体を擦るように時間をかけて抜かれた熱塊が、柔い洞を一気に突き進んでいく。望んだ通り衝動に身を任せた動きに、強い快感が全身を駆け抜けた。迫り上がる声を殺すと、喉が醜い音をたてる。痛みをこらえるような響きをしているが、実際は真逆、悦びを隠すものだ。とうの昔に理解している紅は、それを引き出そうと動く。先程までの無駄な遠慮や配慮は既に消え失せていた。それでいい、と蒼は密かに口角を上げる。求めているのは欲望を満たす衝動なのだ。それ以外のものなど不必要、排除すべき障害でしかない。
結び交わった箇所から粘ついた水音が漏れる。本能に染め上げられた思考は、鼓膜を震わすそれすらも快感と判断して拾っていく。内だけでなく、外からも犯されるようだった。駆け巡るそれが発する声を必死に殺すも、身体はそうはいかない。快感を伝える電気信号が、そのまま筋肉に命令を下す。身体が震え、跳ね、しなり、ひくひくと物欲しげに獣欲を抱き締める。拠り所を求めるかのように、烈風刀は繋いだ手を強く握る。子供のような仕草にか、上空から嘲りが含まれた吐息が降ってきた。余裕など欠片もない、床に縫い付けんばかりにこの手を握る人間がする反応ではない。非難に満ちた視線に、何を勘違いしたのか、雷刀は牙を見せ酷く愉快そうに笑った。
暗闇を走る細い月明かりに、獣が獣を食らう姿が照らし出される。
獣欲に猛る剣と情動に潤む鞘が擦れる度、ぐちゅぐちゅと淫猥な水音が響く。時折、熱と欲に浮かされた息を吐き出す音が混ざる。合奏のようなそれが闇夜に溶けていく。
入念に解され、涎をこぼす欲望の象徴を何度も受け入れた細い道は、はちきれんばかりに膨れ上がったそれを難なく飲み込めるほど柔らかくなっていた。うねる壁で侵入者をきゅうきゅうと抱き締める。甘えるようなそれに、這入り込んだ塊が応えるように好む場所を幾度も穿つ。全身に走る鋭い快感に、海をたたえた目が大きく開かれた。唇を噛み、烈風刀は必死に声を殺す。その姿が気に入らないのか、それとも嗜虐を煽る様子を気に入ったのか、雷刀は細やかな動きでそこを刺激する。びりびりと頭の奥が痺れた。数え切れないほどの悦びの信号が、脳髄を焼き切らんばかりに叩きつけられた。ギリ、と鈍い音が引き結ばれた口から漏れ、薄い唇が歪む。耐えるように力いっぱい噛んだそこからは、冷たい青を見つめる瞳よりもずっと明るい赤が滴り落ちた。
闇夜に浮かび上がる鮮烈な紅が眇められる。何を思ってか、雷刀はぐいと身を乗り出した。その拍子に肉と肉とが重なりあう面積が増え、びくりと蒼に浮かぶ白い身体が跳ねる。近付いてきた兄が、べろりと血で化粧された唇を舌でなぞる。溢れ出る鮮血を止めんと幾度も舐めとるそれは、犬が水を飲むようだった。人の血液を食らうなど、悪趣味極まりない。冷気すら感じる海色が侮蔑に歪んだ。飢えに喘ぐ茜空は、口を開けと言うように歪なそれを見つめ、依然血がこぼれ染められた唇を舐める。時折軽く吸われ、背筋に寒気が走る。血を吸われるなど、流石に嫌悪感が勝る。それが己の欲求に無理矢理従わせようとする稚拙な策略ならば尚更だ。拙い策により抗議の声すらあげることができず、烈風刀は射殺さんばかりに鋭い視線を兄へと向ける。弟のそんな姿など露も気にせず、雷刀はひたすらに唇を寄せ、悪趣味な愛撫を続けた。
血液が止まらない様子に諦めたのか、それとも単純に飽きたのか、唇が離れていく。どれほど経ったか認識できないほど長く舐め尽くされたそこが、わずかな寒さを覚えた。べろり、と目の前の赤の舌が、唾液に濡れた自身の唇を舐める。そこに残った血液を全て舐めとるような、獣が馳走を前に目を輝かせるような動きだった
突然、止まっていた抽挿が再開される。いきなり内をごりごりと擦り上げられ、目の前に火花が散った。身体が法悦の声をあげる度、白い光がいくつも瞬く。闇に染め上げられたこの部屋が星空に変わったようだった。実際はそんなロマンチックで可愛らしいものではない。思考全てを消し飛ばすような衝撃だ。
血液で彩られた唇から、歯が砕けてしまいそうなほど強い音が響き渡る。流石というべきか、不意打ちのようなそれでも烈風刀が声を漏らすことはなかった。チッ、と小さな舌打ちが快楽の海に落ちるのが聞こえる。それもすぐに互いの身体が生み出す音に掻き消された。
律動に合わせ、肌と肌、肉と肉が鈍い音を奏でる。熱に浮かされた吐息が交ざりあい、埃舞う空気に溶け込んでいく。設備も何もない、ただ闇に包まれた冷たい空気が満ちているはずなのに、どちらの身体も心も熱に溺れていた。薄暗い部屋の中、二対の瞳は相対するそれを貫かんばかりに睨み合う。欲望の炎が轟々と燃え盛るそれは、夜が支配する中でもまるで恒星のように力強く光っていた。満たされ渇きを繰り返す内なる獣と同じ輝きをしていた。
ぼたぼたと溢れる唾液が床を、服を、身体を汚していく。烈風刀の胸元は激しい行為による汗と、雷刀がこぼす唾液でじっとりと湿っていた。際限なく漏れ出るそれは、彼の興奮の度合いを如実に表していた――そんなものを見なくとも、依然睨み合っている兄弟は互いのことなど全て理解しているのだけれど。
痛いほど張り詰めた自身が、鍛え上げられた筋肉に包まれた腹を汚す。突き上げられるとともに己の肌に擦られるそこは、淫欲の印で濡れていた。それでも決定的な刺激を与えられず、絶頂を求めるそこはただただ粘つく液をにじませるだけだ。内部が隙間無く満たされる悦びと、欲望の頂点が全く見えない苦しみに、青の心は凪と暴を繰り返す。
覆い被さる赤の手に、更に強い力が込められる。腰に回されたそれも、薄い肉を引きちぎり骨を砕かんばかりに強く掴んだ。打ち付ける衝撃がより大きくなる。乱雑なその動きは、欲望の果てが差し迫っていることを表していた。指では到底届かない深い場所を幾度も突かれ、反射的に白い身体が跳ね、勢いを増していく快楽に震える。数え切れないほど脳髄に送り込まれる電気信号は、刃物のような鋭さをしていた。鋭利なそれが思考を切り裂いていく。その後ににじむのは、身体があげる悦びに満ちた声だ。
荒々しく暴かれる秘所が、深くまで咥え込んだそれを締め付ける。はくはくと淫らにひくつき剛直を愛おしげに抱き締める姿は、まるでまだ足りないとねだるようなものだった。当たり前だ、まだ内なる獣は飢えに酷く喘ぎ、欲望に猛る炎は消える気配すら見せないのだ。満たされるまで食らいつくに決まっている。
その望みを叶えるように、己が抱えた獣を満たすために、熱せられた欲望が勢いよくうちがわを擦り上げる。硬いそれが好む箇所を容赦なく抉り、烈風刀の背が弓のようにしなった。過ぎた快楽が身体中を殴りつける。逃げようにも、掴み押さえつけ縫い止める手が許してくれない。声を殺し続ける喉がおかしな音を漏らした。そんなこと欠片も気にすることなく、雷刀はひたすらに欲望を打ち当てる。どちらも既に人間らしさなど消え失せた、本能に従い行動する獣の姿をしていた。
再び目の前にいくつもの火花が散る。不規則な明滅を繰り返すそれは、果てが近いことを示していた。内部の感覚ばかりが鮮明になる。熟れきった柔らかな内壁は、突き立てられる楔の形を覚えようと――否、もう覚えきってしまっているというのに必死に絡みついた。
互いに重なった箇所は、間に何も入れることなどできないほど密着し、交わり奏でられる音が身体を直接伝わってくる。その凄まじい感覚に、今まで相手から逸らすことなどなかった海色の目がぎゅうと固く伏せられた。これ以上にないほど眉間に皺を寄せ歯を食いしばる姿は、その凶悪さとは正反対の怯える子供のようなものに見えた。
熱塊が肉洞の最奥に到達する。剛直が奥の奥に秘めた襞を突き破った刹那、視界全てが白に染まった。稲妻が落ちたような衝撃と快感が身体を、思考を、意識を強制的に塗り潰していく。恐怖すら覚えるそれに見開かれた海色の瞳とは正反対に、潤み甘え絡みつく内部は食い千切らんばかりに獣欲の象徴を締め付けた。
熱い、という言葉では到底表現しきれないほどの迸りが、快楽に震え高らかに法悦の声をあげる身体に直接注ぎ込まれる。腹の奥底まで焼かれ溶かされるような感覚。その強烈な温度に、頂点に至る刺激を求め涙を流していた己自身も、溜め込み膨れ上がった欲望を吐き出したのを頭の片隅で認識した。内部を蹂躙されただけで達した浅ましい身体が、襲い来る様々な情で断続的に震える。後孔がひくひくと悦びに喘ぐ度、上空から痛苦と快楽の混ざった音が降ってきた。もう一つの繋がった場所、絡みあい縫い付けられた手は、離すまい――離れまいと互いを抱き締めていた。手袋の薄い布越し、必死に相手を掴むその姿は、孤独を恐れ他者に縋り付くようだった。
うちがわを埋め尽くさんばかりの欲の奔流がようやく止まる。唇に突き立てていた牙を外し、烈風刀は口を開く。快感に加減なく殴られた身体は、酸素を貪欲に求めていた。は、とようやく吐き出した息は酷く重く、普段の彼からは想像できないほどの甘さで潤んでいた。それは覆い被さる雷刀も同じである。肉食獣めいた鋭い牙が覗く口からは、快楽のあまり塞き止めきれずにいる唾液と甘やかな呼気が流れ出ていた。
じわり、と胸の奥に充足感が広がっていく。吐き出された欲望が身体中に染み渡り、渇きと飢えを癒やしていくようだった。天すら貫かんばかりに燃え上がっていた焔がゆっくりと勢いを失っていく。ようやく、凶暴な獣を抱えた心にわずかながら凪が訪れた。
押し倒し押し倒され向かい合わせ、荒く甘やかな吐息が絡みあい、闇夜に踊り消えていく。見上げた頬を伝う汗が、わずかばかりに差し込む月明かりに照らされ光るのが見えた。
再び赤い視線が降ってくる。その瞳と同じほど赤々とした舌が依然流れる血をべろりと舐め、啄むように唇を重ねる。吐き気がするほど甘ったるいそれに顔をしかめながらも、烈風刀は同じく舌を差し出した。奥深くまで潜るそれからは仄かに己の血の味がした。求めあい寄せ合う赤が、湧き上がる唾液を纏いぬるりと表面を滑る。望む刺激が得られず、紅と蒼は更に身を寄せた。粘膜が触れ合う度、弱々しくなった炎にどんどんと薪がくべられていく。放り込まれた燃料に、煌々と輝くそれが勢いを増していくのが分かった。
先程満たされたのはたしかに事実だ。渇きに荒れた心が凪いだのも、紛れもない事実である。
けれど、この程度で抱え込んだ飢えが完全に満たされるわけがない。
腹は十全に満たされていない。目の前にはまだまだ餌が転がっている。ならば、十二分に満足するまで食らいつくのは必然的だ。飢えた獣はどこまでも貪欲なのだから。
黒い手袋に包まれた指が、雷刀の頬にそっと添えられる。緩慢な動きで肌をなぞるその仕草は、愛撫とよく似た形をしていた。這入り込んだ赤色がより動きを強める。対抗するように、口腔を蹂躙せんと忍び込ませた己のそれを更に奥へと伸ばした。
数え切れないほどの応酬の末、ようやくじゃれあい絡んだ赤が身を離す。舌先から繋がりを求める銀が姿を現すが、すぐに闇に掻き消された。荒い呼気、溢れ出る唾液、そして、熱を増していく肉。粘膜の触れ合いを終えた二色の中には、既に恐ろしいほど音をあげ燃え盛る炎が宿っていた。
歪な赤い三日月が闇夜に浮かぶ。心底愉快そうな、しかし余裕など欠片も存在していない一対の紅玉髄を眺め、同じ様子を浮かべた水宝玉も三日月を作った。
かちあう視線が火花を散らす。再び目を醒ました獣が、高らかに遠吠えをあげたのがはっきりと分かった。
畳む
おひさまのいろ【ライレフ】
おひさまのいろ【ライレフ】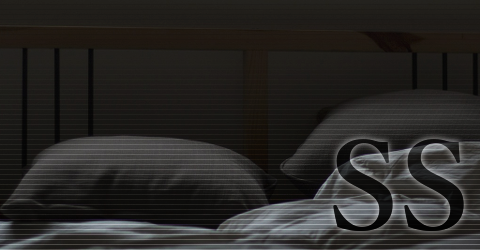
Pawooで書いてたいかがわしいようないかがわしくないようなちょっといかがわしい話。判断のつかないものは支部に投げられないのでこっちに投げておけという精神。
お腹を触るのが好きという話。あと飯食えって話。
シーツの上に散らばる髪よりもずっと深い、海の底のような青に触れる。その裾をつまみ、雷刀はなだらかな身体を撫でるように薄いそれをめくっていく。すぐ下から現れた肌は、冬の冷たい陽光を浴びた雪のように白く、薄暗い部屋の中ほのかに輝いていた。元より色が薄いのもあるが、その身を包んでいたシャツの色と己の手との対比で更に色を失っているように見えた。
胸のすぐ下、中途半端に押しやった薄布から手を離し、少年は晒されたそこに直接触れる。見た目よりもずっと硬く、血の通った温度をしたそこは、指一つつけただけで反射のように震えた。そのまま恐る恐るといった調子で肌の上を滑っていく。見た目通りなめらかな白は触り心地の良いものだ。
「くすぐったいですよ」
ふふ、と小さな笑い声が耳をくすぐる。手を伝ったずっと先、烈風刀は寝転がったままで腹部を撫でるその手を眺めていた。言葉に反して、抵抗する様子は一切ない。好きにしてくれ、と言わんばかりに、その腕はシーツの上に投げ出されていた。
「ほんと、烈風刀の肌ってしっろいなぁ」
「貴方が日に焼けただけでしょう」
証明するように、烈風刀は腕を伸ばし兄のそれを掴む。触れた手とその甲、すらりと伸びゆくそれは、すっかりと日に焼けた雷刀のそれより少し薄く色づいているが、肘を過ぎた二の腕のあたりは腹部と同じ白を保っていた。何も着ない上に日焼け止めを塗らないからこうなるのですよ、と弟はどこか愉快そうに笑う。
つい先日、何年ものすれ違いの末、ようやく愛しいレイシスと海に行く事が叶った少年二人ははしゃぎにはしゃいだ。夏の強い日差しの下、同じく約束づけた友人らと日が暮れるまで様々な遊びに興じた彼らの肌が健康的に色付いたのはごく自然なことである。ただ、烈風刀は日焼け止めを塗り、パーカーを着ていたので多少その被害が抑えられていた。露出していた部分は健康的な色で染まり、薄い布地で保護されていた箇所は元のままだ。そのはっきりと分かれた二色の対比はどこか艶めかしい。そう感じるのはオレだけかもしれない、と雷刀は眺めてぼんやりと考える。否、そもそも潔癖で鉄壁で純粋で純潔な烈風刀のこんなところを見ることができるのは、自分ぐらいだ。ならばどう思っても全く問題はあるまい。弟のこんな姿を見るのは自分一人だけでいい。
しっかりとした筋肉のついた硬い腹を撫でていく。へその下から撫で上げ、そのまま脇へと向かうと、また笑い声があがった。くすぐったそうにもぞもぞと動く様は、常は大人びた雰囲気をまとう彼にしては珍しく幼く見えた。
「……ちゃんと飯食ってるよな?」
「食べていますよ。何ですか、いきなり」
「いや、細くね? 大丈夫か?」
脇腹からわずかな曲線を描く腹を超え、反対の脇へ。なぞったそこの距離は酷く短く思え、雷刀は少しの焦りを覚える。下手をすればレイシスよりも細いのでは、と不穏な疑問がよぎった。
「そうですか?」
疑問符を浮かべた様子で、烈風刀は兄と同じように己の腹部を撫でる。示されたルートを辿り首を傾げる姿は、投げかけられた疑問が全く理解できないと言った調子に見えた。
「なぁ、明日から飯増やそ?」
「だから食べていますってば。体質によるものではないのですか?」
「だってオレはふつーだし」
ほら、と腹部に置かれた手を取り、雷刀は自身の腹にそれを引き寄せた。烈風刀は肘をついて少し起き上がり、示された硬いそこをぺたぺたと触る。細い指が先程と同じ動きで肌を撫ぜる。他者に触れる故か慎重なその手つきに、むずむずとこそばゆさを覚えた。思わず小さな笑いを漏らすと、ほら、といった風に碧の目がいたずらげに訴える。なるほど、確かにこれは笑ってしまうのも無理はない。
「やはり変わらないと思いますが」
「そーか?」
「メジャーがあったはずですし、あとで測ってみますか?」
あとで、の部分がどこかゆっくりと聞こえたのは気のせいか。そーだな、と手早く切り上げ、雷刀は再び白い肌に手を伸ばす。先程と同じ道を辿り、今度はたくし上げた服の下へ。ひくりとその身体が震えたのは、気のせいではないはずだ。
「……脱がさないの、好きですよね」
へんたいみたい、と罵る弟の声はその語に反して柔らかい。じゃれつくようなそれに、兄はにぃと口角を吊り上げ返答する。肯定も否定もし難い問いだった。衣服を中途半端に着たままにするのが特段好きなわけではないが、今日は白い肌と暗い色とのコントラストが酷く妖艶に思え、脱がさなかっただけだ。確かに、くしゃくしゃになった衣服と、着ているとは到底言い難いほどたくし上げて肌を露出した姿は非日常を演出しているようで扇情的だという事実に変わりはないが、そちらは口に出さないでおくことにした。
「烈風刀だって、着たままなの嫌いじゃないだろ?」
「洗濯が面倒ですけれど」
はいやいいえではない、曖昧な答え。仔細に問い質してやりたくもあるが、今はやめておこう、とその目を見つめたまま組み敷いた白をなぞる。もぞりと動いた拍子に、たくしあげていた裾がわずかにずれ落ち、肌を隠すという役目を果たそうとしているのが見えた。再びその端を摘み、今度は喉元まで勢いよくめくりあげる。次いでこぼれた声は、先程のくすぐったさによるそれとは随分と違うように思えた。
ほんと、まっしろ。
今一度呟き、温かな雪原を撫でる。色を失ったようなそこがもう少しで別の色を宿すことを考えて、雷刀は小さな笑みをこぼした。
畳む

雁字搦め【ライレフ/R-18】
雁字搦め【ライレフ/R-18】解釈違いの自分を捩じ伏せて書いた趣味の塊でしかない文章。
つまぶきらいとくんがつまぶきれふとくんにひどいことするだけのはなし。
ぴちゃ、くちゅ、と日常ではあまり聞かない音が、静かな部屋に落ちては積もっていく。それに比例するように腹の奥に熱が生まれ広がっていく感覚に、寝転んだ背がふるりと震えた。わずかな恐怖と多大な渇求を乗せて、烈風刀は覆い被さる兄の袖に手を伸ばす。普段ならば皺になると気が咎めるが、今はそんなことを考える余裕などない。非日常めいた水音と粘膜から直に感じる他者の体温に、理性がガリガリと削れ失せていく。代わりに、獣めいた本能が冷静だと評される少年の頭を染めていった。
そっと忍び込み口内を蹂躙していった赤が、同じように静かに去っていく。追いかけ無意識に舌を伸ばすと、再び熱と熱が逢瀬を果たす。待ち望んだ刺激に、細い指が白いシャツをぎゅうと握った。ねだるように腕を引き寄せられ、雷刀もまた相手を求めるように唇を寄せる。触れ合い繋がった部分がより密着し、互いに更に奥深くへと潜り込んだ。
ぬめる赤たちが口内で踊る間に、硬さが目立ち始めた手が器用にネクタイを緩めシャツのボタンを外していく。はだけられたそこから覗く肌に、朱は恐々と触れた。重なるそこから伝わる温度に、烈風刀は小さく声を漏らす。体温は同じぐらいだというのに、今触れる彼のそれはずっと高いもののように思えた。火傷してしまいそうだ、と益体のないことを考える。そんなことはあり得ないと分かっているのに、どこかそれを望む己がいるように思えた。
直に伝わった音に気を良くしたのか、雷刀も小さく笑声をこぼす。潜り込ませた熱をざらりと擦り合わせ、歯の一本一本を確かめるようにゆっくりと沿っていき、上顎を愛しそうに突く。同じように、腹に乗った手がゆっくりと肌を伝っていく。脇腹をくすぐり、肋を超え、筋肉でわずかに盛り上がった胸へと手のひらで撫でゆく。そのまま、朱はその頂にそっと指を伸ばした。柔らかなそこに直に触れられ、烈風刀の身体がびくりと跳ねる。弟の様子などお構いなしに、兄はふにふにとしたそこに指を押しつけ、擦るように撫でる。先程までの壊れ物を扱うような手つきが嘘のような動きだ。捏ねるように擦り、くすぐるように円を描き、時折いたずらするかのように爪で掻く。じわじわと与えられる刺激に、柔らかだった粒はどんどんと硬さを増していった。主張し始めたそこを咎めるようにわずかに爪が立てられる。背筋を走る得も言われぬ感覚に、碧の背が大きくしなった。
胸部から広がる快楽と、口を塞がれ続ける酸素不足で頭の中がぐらぐらと揺れ始める。危機感を持った脳味噌が司令を出し、助けを求めるように掴んだシャツをぐいぐいと引いた。察したのか、朱はゆっくりと唇を離す。名残惜しそうに伸ばされたままの舌と舌が細い糸を紡いだ。
「っ、あっ、ぅあ、っ……」
酸素を取り込もうとした口が、意思に反して声をあげる。久しぶりに発した音は、己でも驚くほど甘ったるいものだった。快楽を如実に表したそれに、目の前の紅玉が嬉しそうに細められる。常ならば陽の光の下澄んできらめく紅の中には、どこか仄暗い明かりが灯っていた。あてられたかのように、潤む蒼の中にも炎が灯る。どちらも、内で盛る熱でとろりととろけていた。
指が離れ、今度は手のひらが心臓の真上の肌を包み込む。鍛えられた筋肉の上、健康的についた肉を、包み込んだそれが捏ねるようにやわやわと揉む。優しくも淫らな手つきに、烈風刀はまた小さな嬌声を漏らした。男のくせに女のような声を出すなんて。悦び媚びるような音を漏らすなんて。削れたはずの理性が咎め、羞恥を呼び起こす。苦しくなるほどのそれに従い、少年は咄嗟に空いている手の甲を口に押し付けた。声帯が震え奏でるいやらしい音を漏らすまいと、ぎゅうと目をつむり必死に押し当て塞ぐ。ガリ、と薄い肉に噛みついたところで、胸部に奉仕していた手が止まった。胸部を焼く熱が去り、ギシ、と男子高校生二人分の体重を受け止めたシングルベッドが悲鳴をあげる。頭の横のマットレスが沈む感覚に、碧が瞼の下からおそるおそる姿を現した。
「声、我慢すんなって言ってるだろ」
不服そうな声と共に、雷刀は口に押し当てた弟の腕を掴む。指が食い込みそうなほど手首をしっかりと握られている光景を見て、今の自分では振りほどくことなどできないと悟る。己の声を殺す手段を失い、烈風刀は不安そうに眉尻を下げた。
「だって、みっとも、ない、ですし」
「そんなことねーって」
逃げるように視線を逸らす碧の姿に、朱はむくれたように頬を膨らます。彼が口にした評価は、烈風刀の理性が評したものと正反対だ。この場で自身の判断を捨て相手の主張を信じられるほど、少年の中の羞恥心は薄いものではない。ちがう、と抗議する声はあまりにもかすかで、朱色の髪に隠れた形の良い耳に届かぬまま消えた。
「あぁもう、噛んじゃってるし。傷つくからダメだって言ってるだろー」
あーあ、と呆れたように雷刀は声を漏らす。そのまま掴んだ手首を引き寄せ、甲に浮かぶ赤い歯型をべろりと舐めた。肌を這うぬめった感触に、小さな口がまた媚びる音色を発する。聞かせたくないと反射的に口を塞ごうとするが、やはり掴まれた腕が動くことはなかった。
不機嫌さを表すように眇められた柘榴石が突然パチリと開く。弟の腕を強く掴んだ手から力が抜ける。そのまま捕らえていたそれを解放し、兄は目の前の首へと手を伸ばした。ひくりと動く喉の真横、先程解いた学園指定の青いネクタイを掴む。しゅるりとかすかな衣擦れの音の後、雷刀は引き抜いたそれを皺を伸ばすようにピンと張った。
一体何だ、と熱に潤む水宝玉が訝しげに紅玉髄を睨む。にぃと口端が歪に持ち上がる様を見て、欲に沈みつつあった頭が警鐘を鳴らす。逃げようと烈風刀が身を捩るより先に、つい先程までネクタイを握っていたはずの雷刀の手が素早く伸びる。どこか華奢にすら見える手首を片手でまとめて掴み、蒼髪の真上のシーツに押し付けた。そのままもう片方に握っていた青い布で、手首から腕の中頃までぐるぐるに巻き上げる。食い込みそうなほど強く締めたそれの真ん中に、いくつも固結びを作っていく。一体何だ、と碧は混乱に身じろぐが、がっちりとまとめ縛られた腕は動かすことすら困難だった。
「オニイチャンの言うことぜーんぜん聞かない悪い烈風刀にはー」
おしおき、ってやつ?
楽しげな声と共に、兄は可愛らしく小首を傾げる。発した言葉の凶悪さとの酷い落差に、弟の頭は思考することを一時的に停止した。困惑に開いたままの口から、間の抜けた声が漏れた。
たっぷり十数秒の沈黙。ようやく己が置かれた状況を理解したのか、組み敷かれた少年の顔がその頭髪よろしく真っ青に染まる。あまりの事態に、白い喉がおかしな音をあげた。
「なっ、何を馬鹿なことを言っているのですか! 早く外しなさい!」
「ダーメ。言っただろ? おしおき、って」
細められた緋の瞳は、声や表情とはまた別種の愉快さに輝いていた。こんなこといつの間に覚えたのだ。漫画の読みすぎだ。誰だそんな内容のもの貸したのは。強い危機感を覚えるこの状況から逃避するように、少年の頭の中には些末な疑問ばかりが浮かぶ。全ては再び腹に添えられた熱に霧散した。ひゃ、と驚きの声があがる。咄嗟に口を塞ごうとするが、でたらめに縛られた腕はびくともしなかった。
「ちょ、っと、雷刀!」
予想される行為に、烈風刀は静止を望む声をあげる。焦りが強く滲むそれを無視して、雷刀は再び白い肌に手を這わせた。
腹筋が薄く浮かぶ腹を撫で、柔らかな脇腹をなぞり、浮かぶ肋の段差をくすぐり、熱の塊のような手がまた心臓の真上に辿りつく。ゆっくりと曲げられた人差し指の腹が、芯を失った頂に乗せられる。そのまま、ぐにりと力任せに潰した。
「ッ――ひ、あっ、ぁ!」
直接的な鋭い刺激に、烈風刀は目を見開き声をあげた。組み敷かれた身体が跳ねる度、ギシギシとスプリングが抗議の音をたてる。そんなことなど露程も気にせず、胸部に乗り上げた手は覆ったそこを好き放題に弄くる。粘土でも弄ぶようにぐにぐにと押し潰し、勃ち上げるように二本の指で挟んで捏ね、きゅうと引っ張る。だんだんと強く主張しだしたそこを、今度は爪でかりかりと引っかき、痕を残さんばかりに強く突き立てる。痛みすら覚えるそれに、碧は困惑と焦燥の混じった嬌声をあげた。浅ましいそれを抑えようとするも、自由を奪われた手は込み上げる羞恥心を救うことなどできなかった。
「ぁ、あっ、やっ……嫌、だ、雷刀っ、外して――」
「おしおきって言っただろ」
懇願を切り捨てる声は、普段よりもずっと低い。ぞわり、と恐怖とよく分からない何かが混じったものが胸中を撫で、弟の身体が硬直する。その間に、兄の両の手が眼下の薄い胸に這わされた。
「ひッ……、あ、ぁっ、や、ぁっ…………ぅ、あ」
硬い筋が浮かぶ手が、薄くついた柔肉を揉む。指と指の間に粒を挟まれ、そのまま肉全体をぎゅうと掴まれると、理解したくない感覚が腹の底に火を灯した。どんどんと勢いを増していくそれに比例して、漏れる声も甘さを増していく。漏らすまいと唇を噛んで抑えようとするも、与えられる快楽が抵抗する力を全て奪っていった。口の端からだらだらと唾液が垂れていくのが分かる。肌を生温かい液体が伝っていくのは不快でしかないが、拭う術など今の彼は持ち合わせていなかった。
恥ずかしい。みっともない。はしたない。浅ましい。愚かだ。消え行きつつある理性が最後の叫びをあげる。それを押しのけて、本能がきもちいいと声高に主張した。こんな、こんな胸を揉まれるなんて、腕を縛り上げられるなんて、あまりにもおかしいことなのに、常識から逸脱した行為なのに、脳味噌は法悦の声をあげる。神経器官に叩きつけられる快楽を処理できず、烈風刀は喉はただただ艶めいた声を奏でた。
本能に従いつつある弟を愉快そうに見やり、兄はその胸部から手を離した。とろけた蒼玉がわずかに光を取り戻す。困惑と失望が交じるその色を一瞥し、雷刀は再び薄い腹に手を当てる。今度は逆方向、太腿の方へと焦らすようにゆっくりと這わせた。予測される行動に、碧は我に返り引きつった悲鳴を漏らした。嫌だと駄々をこねる子供のように幾度も呟くも、朱は手を止めることなどしない。そのまま、制服の青い下衣が寛げられた。太ももを合わせ必死に抗おうとするが、両足の間には既に兄の身体が座している。目的とは正反対、離れまいとするように腰に絡めるような形になってしまった。
ずるり、と、雷刀は下着ごと弟の下衣を全て剥ぎ取る。役目を放棄したそれを乱雑に投げ捨て、兄は胸につくほど腿を押し上げる。顕になった雄の証は既にゆるく勃ち上がっていた。己の身体の反応に、烈風刀は信じられないとばかりに首を横に振る。うそ、と呟いた言葉は彼の口の中で消えた。
「ぁ、あッ!?」
突如、己自身が異常なまでに熱を持つ。違う、これは内から発するものではない、と脳が否定する。いきなりの感覚に戸惑いつつ、烈風刀は己の下肢へと視線を下ろしていく。そこに見えたのは、鮮やかな赤だけだった。薄暗闇の中、ただ燃えるような緋色がふわりと揺れるばかりで、顔も何も見えない。理解が追いつかないまま呆然とそれを眺めていると、頭が動くのと同時に下半身に強い快楽が叩き込まれた。口で愛撫されているのだ、とようやく理解し、碧は普段ならば決して聞かせることのない高い悲鳴をあげた。
「やだっ、やだ、らいとっ! やめっ、ぅ……ぁ……っ、ゃ、だ!」
熱い口内から逃れようと必死に腰をひねるが、押し上げられた足ごとがしりと押さえつけられては動くことすら難しかった。普段ならばその頭を力いっぱい押し引き剥がすが、両腕を縛り上げられたこの状況ではそれが叶うはずなどなかった。やだ、とひたすらに抗議の声をあげるが、朱が動きを止めることはない。むしろ、じゅぷじゅぷとわざとらしくはしたない音をたてて行為を続けた。
少し前に互いに擦り合わせたあの赤が、今度は己自身を擦り上げている。そう考えて、腹の底に灯った炎が音をたてて燃え上がったのが分かった。熱くぬめったものが幹を撫で上げ、張り出した境目をぐるりとなぞる。裏筋を舌全体で舐め上げられ、脳味噌が感電したかのようにびりびりと痺れた。
「らいとっ、はなれ、……ぅ、あっ、ァ!」
意思に反して腰が跳ねる度、兄の喉奥へと自身を突き入れる形となってしまう。突き上げるタイミングに合わせてじゅうと強く吸われ、白い喉がのけ反る。細いそこから、快楽に溺れた音が奏でられた。
健康的に色付いた唇が、硬度を増していく竿を撫であげる。引き抜けそうなほど扱きあげ、喉奥限界まで呑み込み戻っていく。また先端まで吸い上げ、奥深くへと潜り込む。ゆっくりとした動きのはずなのに、伝達される快感は神経を焼き切ってしまいそうなほど鋭い。少年の口から漏れるのは、最早意味を成さない単音と飲み込みきれない唾液ばかりだ。
膨れ上がった頭を磨くように舐め回され、窪んだ箇所を尖らせた舌で抉られる。次々と叩き込まれる快感に、翡翠の目から大粒の涙がいくつも零れ落ちた。水が膜張る視界はぼやけ、映すものを歪ませる。滲む視界の中でも、朱は相変わらず頭を動かしていることは分かった。
腹の奥が熱い。内に燃え盛る炎が限界を主張し始めたのが、靄がかる意識の中でも分かる。奥底から昇ってくる何かに、断続的に怯えた高い声があがる。融けた翡翠が、逃げるように固く瞑られた。
途端、下肢から送られ続けた強い感覚が止まる。突然のそれに、唾液でしとどに濡れた唇からぇ、と困惑の音が零れた。吐き出そうとした熱が、来た道を戻りまた奥底でぐずぐずと燻る。何で、と物欲しげな問いが漏れ出るより先に、鋭い快感が髄を駆け上った。
「えっ、あッ、なっ……なに…………ぃ、ぁッ」
再び自身を這う舌の感覚に、烈風刀の声帯が戸惑いと悦びの混じった音を奏でる。高みに上り詰めかける度に兄は動きを止め、少し落ち着くと口淫を再開する。弟の好む場所を熟知した動きと、わざと気をやらせないよう焦らす行為に、拘束された少年は涙し嬌声をあげることしかできなかった。泣いて喚いて懇願しても終わることのないこの状態は、烈風刀にとって地獄と形容するのが相応しいものだ。
「ぅ…………あ、ぁ……?」
容赦なく絞り上げていた口の動きが少しばかり緩む。やっと終わったのか、という碧のわずかな希望は、内腿を這う手に粉々に砕かれた。つつ、と見た目よりも柔らかな腿を辿り、奥の奥、決して暴かれることなどないはずの秘めた場所に指がそっと添えられる。溢れた唾液と先走りでぬめる秘所を、節が浮き始めたそれが縁をなぞるように円を描く。まるで行為の始まり、熱塊が媚肉を割り開くべく狙いを定めるようなその動きに、少年の身体が端から端、爪先までぴぃんと硬直した。
「え、ァ……、ま、まって……、まって、くだ、さ……」
雄の場所を好き放題にされただけで狂ってしまいそうなほどきもちがいいのに、雌の役割を与えられつつある場所まで弄られるだなんて。それも、きっと二つ同時に容赦なく蹂躙されるだなんて。容易に想像できる未来に、引きつった口元から慄く音が零れる。多大な快楽を期待する色と過剰な快楽に恐怖する色が混ぜごぜになったそれは、兄の胸に潜む何かを煽るのに十分だったようだ。怯えぎこちなく首を横に振る弟など視界にすら入れず、朱は奥まったそこを暴くべく、押さえた片足を横に押し退けた。
「ひ、ぃ…………ぃ、あ、あ……ッ」
形を確かめるように外周をなぞっていた指が止まる。少しばかり太いそれがようやく狙いを定め、浅く沈んだ部分に宛てがわれた。二人の体液でたっぷりと濡れた孔穴に、つぷり、と淫らな音をたてて指が這入っていく。慣らし始め、ほんの浅い場所を擦られただけだというのに、烈風刀の背が弓のようにしなる。喉が奏でる音はもう意味など欠片も持たず、意思伝達に使うはずのその役割は、受容限界を超える快楽を逃がすためのものに塗り替えられつつあった。
秘めたる孔が、食いちぎらんばかりに侵入者を締めつける。脳味噌は快楽に恐怖しているというのに、淫肉は奥へと誘うようにひくついた。ぎゅうと拳を握る。怯えから逃れるため何かに縋ろうにも、頭の真上に縛られた手に届くものなど何も無い。心細さが胸を蝕む。縋るものがないだけで、こんなにも恐ろしいだなんて知りたくなかった。浅海色の瞳からぼろぼろと涙が零れては紅潮した肌を濡らした。
浅く挿し込まれた指がそっと引いていく。爪の中頃まで抜かれ、また奥へと進み第一関節まで埋め込む。指の腹が内壁を優しく撫でる度、甘い声が涙と同じくぽろぽろと零れる。抑え込む理性はとうの昔に消え失せ、残るのは肉欲に溺れつつある本能だけだ。己と同じ場所まで沈みつつある弟の姿に、兄は密かに笑みを漏らした。埋め込んだものはそのまま、未だ口腔に迎え入れられた昂ぶりを強く吸い上げられる。嬌声と涙が乱れたシーツの上に零れ落ちた。
ゆるゆると抜き差しされる指が、奥を目指してどんどんと歩みを進める。節の部分が、熱に潤む肉を耕すように侵入する。硬いものが内部を擦る感覚に、窄まりがきゅうと縮こまった。早く去ってくれと必死に願うも、身体は意思に反して侵入者を強く抱きしめる。その度に這入ったそれの形を意識してしまい、日に焼けていない体躯がびくびくと震えた。
「っ、ぅ、ぁ……ご、ごめ、な、さい…………ごめんな、さ、ぁっ……」
ごめんなさい、ごめんなさい、と、烈風刀はひたすらに謝罪の言葉を繰り返す。恥も外聞もなく涙を流し、必死に許しを乞うその表情はどこか幼く、反面嗜虐心を煽るような淫猥さがあった。
いいつけをまもらなかったぼくがわるい。らいとがおこるのはあたりまえだ。わるいことをしたのだからあやまらなければならない。快楽で朦朧とする頭が、理不尽な罰を受け入れる。ごめんなさい、と幾度も繰り返す声はとろけきっており、雄を誘うような音色に移り変わっていた。
舐め上げるかのように唇がゆっくりと幹を辿り、ちゅぽんとわざとらしく音をたてて欲の塊が口腔から抜け落ちる。ようやく熱から解放された安堵に、碧は浅い息を吐いた。許容限度を超える快楽を叩き込まれた身体が弛緩する。瞬間、内部に埋め込まれたものの存在を思い出し、肉洞が食むように収縮した。きゅうきゅうと甘え抱きしめる内部から、指が逃れ戻っていく。ずるりと引き抜かれ、甘美な痺れが腹の底を刺激した。
足を押しつけ割り開いていた手が離れる。しばしして、涙の跡がいくつも走る頬にそっと汗ばんだ手が触れる。水が張りぼやける視界の中、紅玉が藍玉を覗き込んでいるのが見えた。
「もう噛んだりしない?」
雷刀の問いに、烈風刀はこくこくと首肯する。ごめんなさい、と今一度謝る声に、兄は困ったように眉端を下げた。澄んだ雫が零れ続ける眦を、親指が優しく拭う。早く外してくれ、と強い訴えを乗せ、翠玉は覆い被さる朱を見上げる。浮かべる表情は穏やかだが、その瞳には未だ燃え盛る炎が宿っていた。
肉付きの薄い内腿を濡れた手が再び辿る。戸惑いの声があがるより先に、ぐにゅと柔らかな音をたてて隘路が割り開かれた。
「えっ、え、ゃ……、やっ、な、で」
「だから、おしおき」
混乱に陥る碧を見下ろし、朱は唇を舐める。心底愉快そうに口端を吊り上げる様は、肉食獣が獲物を見定めたそれに似ていた。
許す気など欠片も無いのだと悟り、組み敷かれた身体が恐怖に大きく震えた。どうにか逃れようと、烈風刀は必死に身を捩る。知らぬ間に更に奥へと潜り込んだ指が、宥めるように腹側の壁を押した。弱い箇所を直に刺激され、海に似た瞳が目いっぱいに見開かれる。悲鳴にも似た嬌声が薄暗い部屋に響いた。
「あッ、あっ! だっ、だ、め……、らいと、そこ、だめ、でっ……ぅ、ぁッ!」
神経を焼き切るような鋭い快感に、烈風刀はいやいやと首を横に振る。浅葱の髪が白いシーツの上に踊る様子はどこか淫らなものだ。脊髄を走り抜ける快楽から逃れようにも、既に足は取り押さえられており動くことは困難だった。何より、肉洞は奥深くを暴く侵入者を逃すまいというように強く締め付けていた。あまりにも浅ましい己の身体に、藍玉の埋まる目元から溢れる水量が増す。だめ、やだ、とほんのわずかに残った思考がうわ言のように否定の言葉を並べ立てる。聞き入れられることのないそれは、内壁を擦り上げる指に掻き消された。
「ぅあ、ッ……ら、いと…………ァ、らいと、らいとっ……!」
縋るように兄の名前を呼ぶ度、ぞくぞくと背筋を何かが撫でていく。彼こそが全ての元凶だというのに、暴力的なまでの快楽に翻弄され朦朧とした頭は愛する者に泣き縋ることしか選択できなかった。
もーちょい待って、と宥める声がぼやける意識に降ってくる。余裕ぶってはいるが、明らかに切羽詰った響きをしていた。己の欲望を押さえつける理性から獣の欲がにじむそれに、心のやわらかな部分がふるりと震える。らいと、らいと、と雛鳥のように囀る度、褒美とばかりに好む場所をとんとんと柔く突かれる。許容量以上に伝わる法悦を示す電気信号に、脳髄が痛いほど痺れる。思考力をガリガリと削り落としていくそれに、烈風刀は最早涙を流し喘ぐことしかできなかった。
浅い場所まで退いた指が増援を呼び、再び潤む肉を拓いていく。ばらばらに動くそれが、柔らかなうちがわを擦り耕す度、奥底に燻る熱が薪をくべた炎のように盛っていく。何かを求めて、腹の底がきゅうきゅうと甘い声をあげた。根本まで咥え込み、指では届かないほど奥へ誘うようにひくひくとうごめく。もっととねだるように食む様は、淫らの一言に尽きた。
ちゅぷり、と淫靡な音をたて、二人の侵入者が狭い洞から抜け出す。浅ましい肉孔が寂しげにはくはくと収縮するのが己でも分かった。羞恥する余裕もなく、はぁはぁと細く甘い吐息を漏らす碧を眺め、紅の目が苦しげに細められる。暗い色の奥に灯る火は、轟々と音をたてて燃え盛っていた。
小さな金属音の後、かすかな衣擦れの音が情欲の海に揺蕩う浅葱の意識を現実へと引き戻す。未だひくつく孔口に、熱く硬いものが触れた。疲弊し弛緩しきった烈風刀の身体が、いっそわざとらしいほど大きく跳ねる。ばくばくと懸命に動く心臓が、苦しさを覚えるほど一際大きく鼓動した。
本能がが待ちわびていた熱に、無意識に腰が揺れる。早く早く、と丁寧に耕されぷくりとした孔穴が、先走りで濡れた赤黒い先端に擦りつくように動く。その姿は淫乱と評するのが相応しいものだ。ぐぅ、と苦しげな唸りが聞こえる。食いしばる朱の口から漏れた音は、獣欲の支配に抗うものだ。淫情に濡れた藍晶が、ひとを保とうとする雄を見上げる。獣としての本能で濁る意識が、愛し人を示す響きを舌足らずに奏でる。幾度もつがいを求める声に、炎瑪瑙の中にかろうじて残るひととしての意識が消し飛ぶのが見えた。獣の唸りをあげ、雷刀は膝裏に挿し込んだ手に指の痕がつくほど力を込める。
ずちゅん、と重く粘ついた音をたて、熱塊が解れきった肉洞に突き立てられる。容赦なく内壁を擦り上げられる感覚に、少年の背が限界までしなった。
「――――ァ、ッあ、ぁッ!!」
本能が求め続けていた感覚に、烈風刀は高い法悦の声をあげた。感電したかのように目の前にバチバチと強い光が輝く。衝撃と共に、奥底に渦巻いていた熱が一気に迫り上がる。刹那、二人分の体液でてらてらとした肉茎から勢いよく欲望が吐き出された。熱杭が突き入れられる度びゅくびゅくと溢れ出るそれが、色情で薄く色付いた肌に濁った白を塗り重ねる。
雄の象徴が力任せに隘路を突き進む。ごりゅごりゅと加減無しに擦り上げられ、声帯が悦びの音を奏でた。うちがわから脊髄を砕くような快楽が際限なく与えられる。薄い肉に硬い腰骨がごつんと鈍い音をたてて打ち付けられる。腕を縛り上げるネクタイがギチギチと抗議の音をたてた。痛覚はとっくに麻痺し、その衝撃すら甘美なものとして脳に電気信号を送った。スプリングが軋む音、肉が打ちつける音、粘液が泡立つ音、欲に溺れきった悲鳴。淫らな重奏が薄暗い部屋に響く。
熟れた硬い先端が、烈風刀が好む箇所を幾度も抉る。弱点を容赦なく穿たれ、薄い身体が痙攣するように跳ねた。開きっぱなしの口から溢れる唾液と際限なく湧く涙が、上気した少年の顔を彩る。ぐちゃぐちゃと言って差し支えない面様は、この場においては酷く扇情的なものだった。頭の上に縛り上げられた腕が非日常感を演出し、組み敷く獣に眠る本能を煽る。
濃い妖艶な香りに誘われ、雷刀は艶めくその唇を覆うように噛みつく。ぬめる赤との邂逅に、海の底に似た青が愛おしそうに細められた。息をするのもやっとだというのに、再びの逢瀬に悦び、彼は舌を伸ばして相手を求める。普段ならば、つい先程まで己を咥えていたそれと再び合わさることはあまり好まないというのに、今ばかりは違った。溢れ送られてくる唾液は甘露のように美味で、もっとと求めるように自ら奥深くへと進む。口腔での邂逅の間も腰使いは止まらない。力任せに揺さぶられ、粘膜が擦れる度、合わさった箇所から甘ったるい音が漏れる。わずかなそれすら逃すまいと、朱は唇を殊更強く押しつけた。飲み込みきれない二人分の唾液がぐぷぐぷと淫猥な音をたてる。
酸素を補給せよと脳が司令を下したのか、ようやく唇が離れる。名残惜しげに繋がる糸は、下から突き上げる衝撃にすぐさま失せた。生きるために必要なものを取り込みたいのに、揺さぶられる身体は悦楽を拾うことを優先する。開かれたままの口から細かな甘奏が溢れた。
奥の奥まで潜り込んだ剛直が、こつこつと腹の底を突く。子宮を持つ女ならまだしも、男である己の内部に行き止まりなど存在しないはずだ。だというのに、熟れきった硬い先端が存在し得ない壁を突き破ろうと一心不乱に突き上げる。勢い良く奥まで突きこみ、抜け落ちてしまいそうなほど戻っていく。柔らかな洞を焼けた楔で耕す度に内壁が蹂躙され、快楽が脳を殴る。いっとう好む場所を強く擦り上げられ、悲鳴とほぼ同義の嬌声があがった。
不規則に明滅する小さな光が面積を増し、少年の思考が無彩色に塗り潰されていく。欲に溺れギラつく紅玉、獣めいた吐息、足に食い込む爪の感触、内部を抉る雄の形。果てが近い意識が、兄のことばかり認識する。熱い迸りを求め、情欲が燃え盛る腹の奥が疼いた。
「ぃっ、ぁ……あっ、あッ、ア――――」
あるはずのない最奥を熱杭が穿つ。腹を突き破られるような衝撃に、丸い翡翠が限界まで見開かれた。脳髄がバチと激しい音をたてる。神経全てを焼き切る悦びが身体中を駆け巡る感覚は、暴力と言って差し支えないものだった。欲望の証を咥え込んだ場所が、痙攣するように収縮する。意思でコントロールできないそれは、内部を蹂躙する兄自身を食いちぎらんばかりに抱き締めた。高みに昇り詰めたはずなのに、勃ち上がりきった雄は涙をこぼすことなく、ただびくびくと震えるばかり。代わりに、疼いていた腹の底が恭悦を叫んだ。
必死に抱きつく柔肉から逃れるように、雷刀は勢いよく腰を引き、抜け落ちる直前でまた突き上げナカを満たす。身体全てを揺さぶる衝撃に、碧の宝玉からぼろぼろと涙が溢れる。腕を厳重に拘束され、足を掴まれ固定され、何一つ抵抗できない獲物を獣が食らっていく。当初覚えた恐怖は既に消え失せ、どこか悦ぶ声が頭の片隅から聞こえた。芽生え始めたマゾヒスティックな快楽に、烈風刀は甘い鳴き声を何度もあげた。
ごつん、と骨と骨とがぶつかる音。一際大きく打ち付けられ、繋がった部分が限界まで密着する。肉が肉を叩く高い音に紛れ、ぁ、と朱のか細い声が部屋に落ちた。数拍の後、絶頂で未だ攣縮する内部に獣欲の迸りが勢いよく注ぎ込まれた。劣情で煮え滾った濁流が、指では届かない奥深くを舐めていく。身体の内から焼き尽くされるような感覚に、碧の背がぴぃんとまっすぐに伸びる。固結びにされたネクタイの悲鳴と、悲鳴になり損ねた歓喜の声が薄闇に溶けた。
おなかがあつい。うでがいたい。きもちいい。きもちいい。身体の奥深くまで埋める熱と悦が、痛覚が訴える信号を好むべきものだと塗り替えていく。異常でしかないというのに、快楽に支配された脳はそれを簡単に条件付けした。
ぜぇはぁと疲労が濃く浮かぶ息遣いの中、ひとのものとは思えない低い唸りが落ちる。溜まった涙が流れ落ち少しばかりクリアになった視界に、燃える赤が浮かぶ。荒い呼吸の中、組み敷いた深碧の瞳を紅緋が射抜く。眇められた赤の中、淫情が業火のように燃え盛るのが見えた。恐怖すら覚えるそれに碧は大きく震える。先程条件付けを終えたばかりの身体は、恐ろしさでなくこれから与えられる愉楽への期待で揺らめいた。
熱をたっぷりと受け止めた肉鞘が、さらなる糧を求めてひくひくとうごめく。淫欲の海へ誘う動きに、埋められた刃がびくりと反応した。大きな脈動と共に、己を貫く肉槍が更に肥大する。欲望を欲する場所が満たされる感覚に、烈風刀は無意識に笑みを浮かべた。涙を湛えた浅葱の瞳はとろりととろけ、同じ色の細い髪が汗ばむ肌に散り、浅く開いた口から真っ赤に熟れた舌が覗く。雄を惑わす蠱惑的な姿だった。
ギシリとスプリングが音をたてる。いくつもの染みができたシーツの海に、幸福に満ちた嬌声が落ちた。
そろりと手を伸ばし、雷刀は白の布越しに烈風刀の腹に触れる。布が肌に擦れる感覚にか、上から小さな笑い声が聞こえた。可愛らしい声がもっと聞きたくて、いたずらするように服の上から撫でる。くすぐったいです、と咎める楽しげな声が飛んできた。
音の方へ笑みを向け、そのままそろそろと手を下ろしていく。すぐに辿り着いたシャツの裾から、中へと潜り込んだ。撫であげるのと同期して、指定の制服も身体に沿って胸の方へと進んでいく。直接触られる感覚に、今度は堪えるような声が耳をくすぐった。
するすると衣擦れの音と共に、日に焼けていない白い肌が顕になる。肉の薄い腹、浅く小さな臍、淡く浮かぶ肋骨、そして平坦に見えて筋肉でわずかに盛り上がった胸。健康的、けれどどこか艶めかしい身体つきに、雷刀は赤い唇を舐める。組み敷いた弟がふるりと震えたのが手の平越しに分かった。
なだらかな丘を、壊れ物を扱うかのようにそっと撫でていく。節の見える指が頂に辿り着いた瞬間、怯えるように息を呑む音が聞こえた。鼻にかかった響きには、この先にあるものへの期待がはっきりと見てとれた。応えるように、触れたそこを指の腹で優しく撫でる。擦るように細かく動かすと、柔らかな粒がすぐに芯を持ち始める。その存在を持ち主に知らしめるように外周をなぞる。スプーンでコーヒーをかき混ぜるようにくるくると指を動かすと、薄い胸が小さく震えた。
赤い瞳が捲れ上がった白を辿り、上へと視線を移していく。いつも目にする綺麗な碧は瞼の下に身を潜めていた。ふ、と溢れ出そうな感情を堪える音が、懸命に閉じようとする唇から漏れる。我慢しなくてもいいと常々言っているが、意外と強情な彼はこうやっていつも湧き出る声を殺すのだ。見下ろす紅玉が不服そうに細められる。その口を開かせるべく、ぷくりと膨れた頂点を爪で軽く引っ掻いた。いきなりの強い刺激に、ひ、と甘さを含んだ小さな悲鳴が響く。期待通りの反応に、朱の唇がゆるく弧を描く。日頃見せる明るく朗らかなものとは正反対、暗く意地の悪い笑みだ。
ばっ、とシーツに投げ出されていた烈風刀の左手が素早く持ち上がる。そのまま、彼は手の甲で己の口を塞いだ。こうやって組み敷かれた時点で艶めいた声を漏らしてしまうことは分かっていただろうに、往生際の悪いことだ、と雷刀は内心嘆息する。けれども、この強情な弟の心を暴き、徹底的に乱すことを彼は無意識に楽しんでいた。
優しく引っ掻いていた尖りを、今度はぐにりと押し潰す。そのまま円を描くように捏ねると、薄い身体が幾度も跳ねた。塞がれた口元から熱い吐息が漏れ出すのが聞こえる。指先のそれを楽しげに弄んでいると、ガリ、と何かをかじるような音が鼓膜を震わせた。痛々しい響きに、朱の眉がピクリと動く。胸部に置いた手を離し、雷刀は持ち主の口を必死に塞ぐ腕を掴んだ。
「だーかーらー、噛むなって何回も言ってるだろー?」
不満げな声と共に、掴んだ腕を弟の口元から取り払う。くるりと裏返し当てていた甲の方を見ると、そこには並びのいい歯型が薄く浮かんでいた。はぁ、と呆れたように息を吐く。苛立ちの浮かぶ嘆息に怯えてか、瞼の下から丸い碧がおそるおそる姿を現した。紅玉髄が咎めるように孔雀石を見つめる。兄の鋭い視線に、烈風刀はぅ、と気まずげな声を漏らした。再び覗いた碧の目が不安げに泳ぐ。幾度も朱を見上げては逸らすその様子に、少年は小さく首をひねった。何か言いたげに見えるが、彼がここまで言い淀むことはあまりない。一体どうしたのだろうか、と眺めていると、ようやく翡翠が柘榴石を見据える。常ならば澄んで涼やかな色をしたそれは、既に熱で柔くとろけていた。
「あ、の」
小さく開いた口から響く声はか細い。あの、えっと、とつっかえるように何度も繰り返し、決心したように烈風刀は己の首元に手を伸ばす。綺麗に結ばれたネクタイを自ら解き、その片端をゆるく握った。
「あの、えっと…………く、癖とはいえ、また、悪い事をしてしまいましたし……」
おしおき、しますか?
甘さの漂う声が怯えるように問う。わずかに震える声音とは裏腹に、上目遣いに見上げ手にした青を差し出す姿は期待で満ちていた。
予想外の問いかけに、雷刀は目を見開く。あまりの驚愕に、覆い被さった身体がビシリと硬直した。投げかけられた言葉を頭の中で何度も何度も噛み砕き、飲み込み、反芻する。長い時間をかけて言葉の意図をしっかりと理解し、驚きに真一文字に結ばれていた口の端がにぃと醜く釣り上がった。一対の紅玉が鈍く光る。そこには、暗い欲望が姿を現し始めていた。
そーだなー、と間延びした声で悩むような言葉を紡ぐ。装った音は明らかな偽りで、心は既に決まっていた。うーん、とわざとらしく呟いた後、朱は多大な期待に揺れる碧にニコリと笑いかけた。非常に楽しそうなその表情は、普段の彼を知る者が見れば目を疑うであろうほど歪んでいた。
「そーだよなー。烈風刀はオニイチャンの言う事聞かない悪い子だもんなー。じゃあ、おしおきしないとな」
おしおき、の部分を殊更ゆっくり言うと、碧の瞳が嬉しそうに輝く。淡い願いが叶い歓喜するその頬はすっかりと上気していた。
差し出されたネクタイをしゅるりと取り上げ、雷刀は投げ出された弟の両腕を片手でまとめる。いつぞやは抵抗されたが、今回はあっさりと捕まった。協力的にすら見えたのはきっと気のせいではないだろう。そのまま海色の頭の上に軽く縫い付け、掴んだ両手首を深青の布でぐるぐると巻き上げる。幾重にも重なる青を彩るように、最後に固結びを一つ作る。ぎゅっと縛る音に、熱を孕んだ吐息がこぼれたのが聞こえた。自ら進んで罰を望み、被虐を期待する姿は淫らとしか表現できない。
早くと言わんばかりに身を捩る烈風刀の姿に、雷刀の胸の内に暗い欲求が湧き上がる。可愛い。虐めたい。愛しい。泣かせたい。愛でたい。抱き潰したい。正反対に見えて表裏一体の感情がぐらぐらと腹の底に煮える。被虐を望む碧に、朱の加虐心が強く刺激された。
は、と艶めいた吐息を漏らす口を見やる。薄闇の中、ちらつき輝く淫靡な赤に誘われ、朱は噛みつくように愛し人の唇に己のそれを合わせた。
畳む
#ライレフ #腐向け #R18