No.51, No.50, No.49, No.48, No.47, No.46, No.45[7件]
まどろみと熱【ライレフ】
まどろみと熱【ライレフ】
今書いてる諸々が上手くいかないので息抜きにりりかるほも。
いつぞやTLで見たライレフが可愛かったので。
温かなものがそっと触れ、熱を味わう間もなく離れる。また柔らかなものが触れ、その感触を求める暇もなく離れる。幾度も繰り返されるそれに、烈風刀はゆっくりと目を開けた。その表情は眠たげで、酷く不機嫌そうに見える。
「雷刀、やめてください」
「んー?」
眠気を孕む声は低く、彼の機嫌の悪さをよく表している。しかし、その原因を作り出す雷刀はとぼけるばかりだ。眠気と恥じらいと苛立ちに、若葉色の瞳がすぃと細められる。宥めるように、言葉を紡ぐそこに熱が触れた。すぐ目の前に輝く紅葉色の瞳は妙に上機嫌で、眠気などかけらも感じられない。終わる気配のないそれに、烈風刀は眉間に深く皺を刻んだ。
寒いから、といきなり押しかけてきた雷刀を拒むのを諦め、大人しく布団に招き入れた結果がこれだ。眠りたいというのに、彼は睡魔の仕事を邪魔するようにこうやって幾度も唇を寄せてくるのだ。与えられる感覚は、普段彼が求めるそれとは違うじゃれるような軽いものだ。それ自体は恥ずかしさを覚えるものの受け入れることはできる。しかし、こう何度も何度も繰り返されるとさすがに嫌気が差すものだ。眠い。恥ずかしい。寝たい。気恥ずかしさと睡眠欲が混ざり、胸の内は表現しがたい感情がぐるぐると渦巻いていた。
顔を合わせているからこうなるのではないか。眠気で鈍る頭が当たり前の事実にやっと気がつく。ならば、と烈風刀は寝返りをうち、雷刀に背を向けた。これならもう何もないだろう。やっと眠れる。小さく息を吐き、彼は静かに瞼を下ろした。忍び寄る睡魔に身を全て委ね、あとは深い無意識の底まで静かに沈んでゆくだけだ。
首筋に何かが触れる感覚。わざと鳴らされた音に、また口づけをされたのだと分かった。
驚きとくすぐったさに、烈風刀は小さく声をあげる。それに気をよくしたのか、雷刀はまたその首筋に唇で触れた。ちゅ、ちゅ、と小さな音と共に少しかさついた唇が首筋をたどる。鼻先で髪を掻き分け生え際に、回り込むように喉元近くに、埋めるように潜り込んで肩口に。熱を孕む彼の唇が、日に焼けていない箇所を滑っていく。時折吐息が肌を撫でてこそばゆい。与えられる感覚に、烈風刀は小さく身じろぎをした。
気がつけば、腹に手が回され後ろから抱きすくめられていた。服越しに触れる手も、うなじをたどる唇も、ほのかにかかる息も、彼の全てが熱い。融かされてしまいそうだ、などと眠気と熱でぼやける頭で考えた。
ん、とかすかに声を上げ、己を包む熱から逃れる。そのままこてんと寝返りを打ち、烈風刀は再度兄と向き合う。その顔は先程と違い、眠気だけでなく恥じらいの色が強く浮かんでいた。あれほど熱っぽく行為を繰り返されれば、さすがに眠気よりも気恥ずかしさの方が勝る。翡翠の瞳は、眠たさだけでなくじわじわと湧き上がる熱に潤んでいた。
「雷刀」
「なに?」
返事の代わりとばかりに、雷刀の唇が己のそれを撫でる。ゆるりと開いた目のすぐ先、紅玉の瞳にも熱が宿りつつある。くすぐったさと気恥ずかしさに、烈風刀は逃げるように俯いた。つっぱねるように彼の胸元に手を添える。その姿は縋り付いているようにも見えた。
「眠いのです。寝かせてください」
「えー」
どこか幼い音へと変わるその声に、雷刀は不満げな声を漏らす。逃がさないと言わんばかりに、その背中に手を回された。唯一無二の片割を抱くその腕は優しいもので、なにもかもじわじわと融かされてしまうような温かさと心地よさに包まれた。
「キスぐらいいいじゃん」
そう言ってまた一つ口づけが降ってくる。浅葱の髪に落ちたそれは、淡雪のようにすぐ溶けて消えた。明確な感覚のないそれを寂しいと思ってしまうことは言わないでおこう、と烈風刀は心地よさに包まれたまま考える。
「さすがにやりすぎですよ」
「ちょっとだけだし」
「『ちょっと』という数ではないでしょう」
このわずかな時間で何度触れ合ったのかなど分からない。確かに言えるのは、二人分の両手でも数えきれないということだけだ。触れては消え、与えられては失う熱は知らぬ間に己が内に蓄積されていく。燻るそれが心を掻き乱す。
「……起きたら、してあげますから」
好きなだけさせてあげますから、寝させてください、と投げやりな声が雷刀の耳をくすぐる。予想だにしない言葉に、彼の動きがぴたりと止まった。その顔には、喜びと戸惑いと猜疑が混じった、形容しがたい色が浮かんでいた。
行為自体が嫌なわけではない。言葉と行動で示さないが、烈風刀自身もその熱を欲しているのだ。好いているものに触れたい、当たり前の欲求である。
そう、求めていることは互いに同じなのだ。ただ、タイミングが悪いだけで。
「……そっか」
じゃあちゃんと寝なきゃな、と雷刀は頬を緩める。とんとんと腕の中の弟の背を優しく叩く姿は保護者のそれで、烈風刀は不服そうに目を細めた。しかし悔しいかな、それがとても心地よい。安心感が身体を包み、とろりと意識が緩やかに溶けていく。
おやすみ、とまた口づけ一つ。最後の温かみとともに、烈風刀は緩やかな眠りの闇に沈んだ。
畳む
夏模様【ハレルヤ組】
夏模様【ハレルヤ組】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:理想的なつるつる
即興二次小説で書いたのを加筆修正。昨年夏のエンドシーンネタ。ハレルヤ組かわいいってだけの話。
実際に書いたのは秋というのは内緒。
太陽は空の頂点に立ち、憎らしいまでに陽の光を降り注がせる。強いそれにより気温は上昇の一途を辿り、全国各地で新記録を叩き出していた。季節が巡り、夏がやってきたのだ。
『暑い』という感覚を身をもって体験せねばならないこの季節を苦手とする者は多い。日々ゲームの運営に駆けずり回る三人も、もちろん例外ではない。むしろ、日頃寒く思うほど冷房の効いた部屋で運営業務に励む彼女らにとって、陽の光で何もかも熱せられた外は他者よりも辛く感じるものだ。
けれども、そんな暑さの真っ只中、三人が浮かべている表情は涼しげで穏やかなものだ。
「冷たい飲み物、幸せデス」
「クーラー涼しい、幸せだ」
ほぅ、と幸せそうに息を吐いて、レイシスと雷刀は呟いた。手足を伸ばしだらしなくソファに倒れこむ雷刀に、背筋をしっかりと伸ばし姿勢よく座りお茶を飲むレイシス、烈風刀の二人。どんなに強い日差しが窓から差し込み彼女らを照らしても、それは文明の利器によりすぐさま熱を失う。真夏の暑い日にクーラーの効いた涼しい部屋で過ごす時間は、まさに幸せの一言に尽きた。
「そうだ、五月に植えたスイカが食べ頃です。冷蔵庫で冷やしてあるのでみんなで食べましょうか」
「スイカ!?」
「スイカデスカ!」
烈風刀の言葉に、雷刀は素早く身を起こしレイシスは茶を飲む手を止める。カラン、と氷がグラスにぶつかる涼やかな音が冷えた部屋に響いた。夏といえばスイカだ。けれども、店頭でよく見かける、けれども少しばかり高く手が出し辛いそれを食べる機会などないだろう、と二人とも半ば諦めていたのだ。それだけに喜びは大きい。好奇心と喜びで輝く二色二対の瞳は、烈風刀をまっすぐ見つめた。
「つーか、いつの間にそんなの作ってたんだ」
「貴方が作ろうと言ったのではないですか」
二人ともTAMA猫と間違えていましたけれど、と烈風刀は苦々しい顔をする。雷刀の表現力が壊滅的だったということもあるが、さすがに生き物と間違えるのはどうなのだ、と彼は内心呆れたものだ。純粋でどこか天然なレイシスと思ったことをすぐ口にする雷刀が組むと、ツッコミが追いつかないほどのボケを生み出すのだから大変だ。
「見ていいか? いいよな? いいよなっ!」
「ワタシも見たいデス!」
返事も待たずにソファから飛び起きキッチンへ駆ける雷刀に、レイシスも楽しげな表情で続く。子どもようにはしゃぐ二人の姿を見て、烈風刀は小さく苦笑し同じくキッチンへと足を向けた。
パタパタと響く二つの足音はキッチンの隅に置かれた冷蔵庫の前でぴたりと止まる。期待を色濃く浮かべた桜と茜は、その扉を勢いよく開けた。蛍光灯で白く照らされた箱の中には、小ぶりなスイカが静かに佇んでいた。おぉー、とレイシスと雷刀は揃って感嘆の声を上げる。人工的な光に照らされたそれを見つめる二人の背後に、追いついた烈風刀が険しげな表情で立った。
「冷蔵庫を開けっ放しにするのはやめなさい」
「はわわ、ごめんなサイ」
「いえ、全ては雷刀が悪いのです」
「いくらなんでもそれはひどくないか?」
眉を八の字に下げ申し訳なさそうに謝るレイシスに、烈風刀は優しく声をかける。理不尽な言葉に対する兄の抗議は、彼女を一心に見つめる弟には届かないようだ。いつも通りである。
一旦二人を冷蔵庫の前から退け、烈風刀は冷えたそこからスイカを取り出しまな板の上に置く。雷刀とレイシスは、その脇から丸くつややかなそれを見つめた。
「個人で作ることができる程度なので、あまり大きくないのですけれど」
「すごいデス!」
「烈風刀スゲー!」
少し申し訳なさそうな様子で言う烈風刀に、二人は澄んだ瞳を向ける。その表情は心底嬉しそうで、楽しそうで、太陽のように明るく輝いていた。これほど喜んでくれるとは、と烈風刀もなんだか嬉しくなる。
「TAMA猫みたいデスネ。すべすべデス」
「だなー。つるつるだ、つるつる」
感心するように声を漏らし、二人はスイカを撫でる。その姿はTAMA猫に対するそれと同じだ。つるつるとしたその表面の触り心地は彼女らを魅了したらしい。冷蔵庫から取り出したばかりで冷たくて気持ちいいということもあるのだろう。
そうだ、と何かひらめいたような顔をして、雷刀は走ってキッチンを出ていく。その様子を烈風刀とレイシスは不思議そうに眺めた。また何かおかしなことを考えているのでは、と烈風刀の顔には懐疑の色も浮かんでいる。日頃兄の思い付きに振り回されている彼には、すっかり警戒する癖がついてしまったようだ。
ほどなくして、楽しげな笑みを浮かべた雷刀が戻ってきた。その手にはごく普通の油性マジックが握られている。二人をスイカの前から退け、勢いよくキャップを外し彼は何かを始めた。キュッキュッとペンが滑る音がキッチンに響く。険しげな表情でその背を見る烈風刀に、一体何なのだろうと興味津々な様子で赤髪を見つめるレイシス。二つの正反対な視線を気にすることなく、彼は手を動かした。
「――これでよし、っと」
「ワァ!」
小さく呟き、雷刀は満足げな表情で顔を上げた。その手元を覗き込んだレイシスは感激の声を上げる。まな板の上に座る黒と緑の縞々には、歪ながらも顔と小さな手のようなものが書かれており、見知った真ん丸へと姿を変えていた。
「TAMA猫デス!」
「こうしたら尚更似てるだろ?」
「はい、可愛いデス!」
ニコニコと笑ってレイシスはTAMA猫、もといスイカを撫でる。レイシスの方が可愛いですよ、と烈風刀は彼女に聞こえないように呟く。だな、と隣にいる雷刀がすぐさま返した。真逆と言われることの多い双子だが、彼女に関してはいっそ美しいほど意見が一致する。
「しかし、これでは食べるときに手にインクがつくのではないですか?」
「あ……」
「そうデスネ……」
烈風刀の言葉に雷刀とレイシスは固まり、しゅんとしょげたような顔をする。怒られるのでは、という不安も窺えた。
「……まぁ、あとで手を洗えばいいでしょう。さぁ、切りますよ」
フォローするような烈風刀の言葉に、二人の表情がぱぁっと明るくなる。やったー、と両手を上げる桃と赤を見て、緑は笑った。ころころと表情が変わる彼女らは見ているだけで楽しい。
スイカに包丁を当て、力を込め割れ目を作る。そこにぐっぐっと刃を押し当てていくと、真ん丸だったそれはだんだんと形を崩し、半円へと姿を変えた。それを更に半分に切り、皮目を下にしてとんとんと切り分けてるといくつもの三角形が出来上がった。その姿を見て二人はおぉー、と声を上げる。丸いそれが変化する度に、二人の表情は期待に輝いていった。
「切れましたよ。食べましょう」
烈風刀は切り終えたそれを盆に載せ、リビングへと向かった。ハイ、おう、と元気に返事をして、雷刀とレイシスは先を行く彼の背に続く。その姿は仲のいい家族のそれと同じだ。
手を拭くためのタオルと種を入れるためのボウルを用意し、三人はソファに座る。綺麗に切り分けられたスイカを手に取る。いただきます、と声を揃えて言い、赤と白と緑の三角形にかぶりついた。
「んめー!」
「はわー、甘いデス! 美味しいデス!」
「それは良かった」
雷刀とレイシスは幸せそうな表情でスイカを頬張る。見ている者が幸せになるような、明るく可愛らしい笑顔だ。頑張って作った甲斐があったものだ、と烈風刀は小さく微笑んだ。趣味で作ったものとはいえ、これだけ喜んでくれるのはやはり嬉しいものだ、と考えて彼も赤いそれを口にする。程よい甘みが口の中に広がった。
「烈風刀、ありがとな!」
「ありがとうございマス!」
「へ?」
両隣に座る二人から向けられた笑顔と感謝の言葉に、烈風刀はきょとんとした顔をする。なんのことだろう、と不思議そうに二人を見る彼に、彼女らはニコニコと満面の笑みを向けた。
「だってオレらが言ったから作ってくれたんだろ? すっげーうまいし、ほんとにありがとな!」
「そうデス! 烈風刀のおかげでこんなに美味しいスイカが食べれたんですカラ。烈風刀、本当にありがとうございマス!」
嬉しそうな彼らの笑みと言葉に、烈風刀は頬を少し染めた。こちらこそ、とはにかむ彼に、二人は嬉しげに笑った。
明るい陽光が差し込む涼しい部屋に、三人の賑やかしい声がこぼれた。
畳む
足並み揃えて【ハレルヤ組】
足並み揃えて【ハレルヤ組】
弟君PURおめでとーやっとだねーとかそういう感じでうわーってネタが湧いてきて書き始めたら朝になったでござるの巻。とりあえずtumblrに投げ。
ハレルヤ組可愛いってだけのあれ。
失礼しました、と一礼し、烈風刀は静かに引き戸を閉める。済ませるべき用事を一つ終わらせ、彼は普段の仕事に戻るため廊下を歩み始めた。さて、今日はアップデートについて何かあると聞いていたはずだ。先月から楽曲追加だけでなく様々なイベントやアイテムを用意しているが、今回はその類のことはあるのだろうか。先日はバグが忍び込み多大な被害を受けたが、次はどう対策しようか。そんなことをぼんやりと考えながら、彼は己が戻るべき部屋へと足を動かす。
パタパタと軽やかな足音が空間に響く。背後から聞こえるそれはだんだんと近付き、そこに聞き覚えのある声が混ざる。普段行動を共にする二人を思い浮かべ、烈風刀はくるりと振り返った。
「烈風刀! やりマシタ! やりマシタヨー!」
「やったぞ烈風刀ー! やったー!」
彼の予想通り、そこにはレイシスと雷刀がいた。二人は上げた手をぶんぶんと振り、満面の笑みで己の名を叫びこちらへと走ってくる。元から元気のいい二人だが、今日はあまりにも元気がよすぎる。あまりのテンションの高さに、烈風刀はビクリと身体を震わせた。どうしたのだろう、と考えている内に、二人は彼の目の前でぴたりと足を止めた。息の揃った動きだった。
「烈風刀! これ見てくだサイ!」
レイシスは興奮した様子で烈風刀に端末を差し出した。彼女の勢いに押されるも、彼はそれを受け取り液晶画面に沈む文章を目で追う。どうやら、次回のアップデート内容を記したものらしい。楽曲の追加、曲数、難易度、解禁手順、必要ブロック数などが書かれている、普段のそれと何ら変わりないものだ。だというのに、彼女は何故ここまで興奮しているのだろう。烈風刀は小さく首を傾げた。
「ここだよ! ここ!」
横から覗き見ていた雷刀がペタペタと画面を指差した。邪魔だとその手を退けさせ、示した部分をじっくりと読む。『PUR』『ネメシスクルー』と並ぶ文字を見るに、ジェネシスカードに追加があるようだ。目玉であるPURとネメシスクルーは先月も実装したはずだが、またなにか新しいものがあるらしい。次は誰だろうか、と続く文字を緑の瞳が追っていく。ある単語を認識し、烈風刀の動きが止まった。その個所には、『嬬武器烈風刀』と彼自身の名が書かれていた。
「烈風刀のPURがとうとう実装されマス!」
「ネメシスクルーもな! おめでとー!」
両手を上にあげニコニコと笑う二人は祝いの言葉を幾度も述べた。まるで己の事のように喜ぶレイシスと雷刀だが、反して当人である烈風刀の表情はどこか呆けた、心ここにあらずといったようなものだ。どうしたのデスカ、とレイシスは不思議そうな表情で彼を見る。緑を見つめる桃の瞳には、騒がしすぎたのだろうか、と少しの不安の色が浮かんでいた。あぁ、いえ、と、烈風刀は慌てて顔を上げる。しかしその表情は依然晴れず、思案するかのように口元に手を当てた。
「なんだか実感が湧かなくて……」
PUR。ネメシスクルー。どちらも追加アップデートの際にいつも関わっていたし、レイシスたちがその任に就いたときは心の底から祝った。けれども、自分がそうなるというのは全く想像が出来ない。己がそのような立場になることを考えたことが無いわけではない。しかし、いざ現実となるとまるで自分の事ではないように感じた。不思議な感覚だ、と烈風刀は目の前の二人をぼんやりと見つめた。彼らしからぬ、ふわふわと気の抜けた声に、二人は本当なのだと訴えかける。
「本当デス! ちゃんと現実デスヨ!」
「そーそー現実現実! 最後になっちゃったけど、やっとだな!」
「……この前のイベントも、僕は最後でしたしね」
雷刀の言葉に、烈風刀はぽつりと呟いた。小さな声には寂しさにも似たなにかがにじんでいるように聞こえた。
以前イベントでとある機種と楽曲を交換した際も、烈風刀がジャケットを担当した楽曲のみかなり後になってからの配信となった。開催期間が不定期なのだから、そういう順番だから仕方ない、とは思うが、また最後なのか、という気持ちもたしかにある。不満とは違う何かが胸の中に陰を作った。
「あ……、なんか、ごめん……」
「ごめんなサイ……」
その色に気付いた二人はしゅんと表情を曇らせる。責めているわけではないのだ、と烈風刀は慌てて手と首を横に振った。彼女らを悲しませたいわけではないのに、何故あのようなことを言ってしまったのだろう。己の考えのなさを悔やむ。
「なにはともアレ! 烈風刀、改めておめでとうございマス!」
切り替えるように明るい声で祝いの言葉を述べぱっと顔を上げたレイシスは、烈風刀の手を己の両手でぎゅっと包み込んだ。彼を見上げる彼女の瞳は虹のように美しい弧を描いており、はしゃぎ上気した頬は健康的な紅が浮かんでいる。晴れやかで華やかなその笑みに、烈風刀の顔はどんどんと赤く染まっていった。好いている女性に手を握られ、笑顔で見上げられたのだ。奥手な彼にとっては非常に強い刺激であった。その柔らかく温かな手を意識するだけで、烈風刀の心臓は破裂してしまいそうなほど強く脈を打つ。手を伝って、それどころか大きすぎる己の心音がそのまま彼女の耳に届いてしまうのではないかという不安に駆られた。その不安も、先程胸の内にできた陰も、湧き上がってくる様々な感情にすぐ上書きされたのだが。
「あ、えっ、はっ、はい、あ、ありがとう、ございます」
驚きと喜びと恥ずかしさに、烈風刀の声は自然と固くなる。いつもはなめらかに言葉を紡ぐ唇も、今ではカクカクと一世代前のロボットのように軋んでいた。つかえつかえ出す声もどこか上ずっている。普段はクールで落ち着いた弟のそんな年相応に可愛らしい姿を見て、雷刀は密かに笑みを浮かべた。
「オレもオレも! おめでとー!」
負けじと言わんばかりに雷刀が横から抱き付く。すっかり固まってしまった烈風刀が勢いづいたそれを止められるはずもなく、彼の身体がぐらりと斜めに傾く。その手を握っていたレイシスもバランスを崩し、三人まとめて床に倒れた。かシャン、と端末が硬い床に落ちる音が遠くで聞こえた。
「はわわっ、大丈夫デスカ?」
「え、あ、はい。大丈夫です。ら、雷刀っ、重いです! どいてください!」
ごめんごめん、と謝る雷刀だが、その手を離す気配はない。むしろ、より腕を伸ばし烈風刀の身体を包もうとしているように見えた。その顔は心底嬉しそうな笑みで溢れていた。巻き込まれて倒れたレイシスも心配そうな声を上げるが、その表情には不安の色など全くなく、澄んだ晴れやかな笑みで彩られている。何故自分の事でもないのにこれほど笑えるのだろうか、と烈風刀は冷たい床に転がったまま考えた。
「ほら、そろそろ準備をしましょう。アップデートに遅れが出たら大変ですよ」
ようやく心が落ち着き、烈風刀は普段通りの冷静な声で元気のいい二人を諭す。その耳は未だに赤く染まっていることに彼は気付いていない。言わないでおこう、とレイシスたちは密かに視線を交わし決めた。
ハイ、わかった、と二つの素直な声が重なり、烈風刀の身に追加された重みが消える。依然床に倒れ込んだままの烈風刀に、先に立ち上がった二人は手を差し出していた。きょとんとした顔の彼に、さぁ、とふたつの笑顔と声がかけられる。緑色の目がゆっくりと柔らかな弧を描き、半分ずつの手を取った。
「さ、行こうぜ」
「いきまショウ」
「えぇ」
二人は取ったその手を握ったまま廊下を駆ける。いきなり強く手を引かれ烈風刀は驚いた顔をしたが、どうにか体勢を立て直し前を行く桜と赤についていく。二色の髪が風を受けてふわふわと揺れた。
PUR。ネメシスクルー。どちらに関しても未だに実感は湧かない。
けれども、二人がこうやって自分のことのように喜んでくれるのが、嬉しくてたまらなかった。
ようやく自覚した喜びが胸から溢れ、烈風刀はくしゃりと笑った。年相応の、少年らしいその笑みは、振り返ることなく走り続ける二人には見えない。
足取りを速め、翡翠は先を行く撫子と茜空に並ぶ。自ら隣まで歩んできてくれた彼を見て、レイシスと雷刀の二人も嬉しそうに笑った。
三人分の賑やかな声が放課後の廊下に響き渡った。
畳む
ストレス解消法【ハレルヤ組】
ストレス解消法【ハレルヤ組】
諸々言ってみたら諸々あってそんな感じのあれ。嬬武器弟が可哀想なだけ。
腐向けに腰まで突っ込んでる感あるが気にしない。
電子音の後、『データが保存されました』という一文がオレンジと黒で構成された画面に表示される。ゲームが終了した旨を示すそれを見て、烈風刀はトンとキーを叩いた。次はどうか、と彼は別の画面に切り替える。今の時間帯はプレーヤーが少なくマッチングを待つ者もあまりいないため、自身の仕事も普段のそれと比べて随分と少なかった。慌てずしっかりと作業を進められるのはいいことだ。彼はいつもより余裕のある表情で己のやるべきことをこなしていく。
「はわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ!」
「うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!」
突如、広い部屋に叫びにも似た大きな声が響く。いきなりのそれに烈風刀はビクリと肩を震わせた。一体何だ、と急いで辺りを見回す。はた、と止まった彼の視線の先には、両手を上げ大きく口を開けて声をあげるレイシスと雷刀がいた。無邪気でにこやかな笑顔を浮かべているので何か重大な問題が起きたわけではなさそうだ。
「二人とも! 叫ばない!」
鋭い声が重なる大声を切り裂く。怒りを露わにしたそれに、ぴたりと声が止んだ。発生源であるレイシスと雷刀の顔には、まずい、という三文字が浮かんでいた。
「誰も見ていないと思って遊ぶのはやめなさい。次の人が来たらどうするのですか」
「だって人少なくて暇だし……」
「やることがなさすぎて暇デス……」
口を尖らせ言い訳をする二人に、烈風刀は目を眇める。怒りを強く示したその視線に、二人は口をつぐみ目を逸らした。悪いと思っているようだが、そこに反省の色は全く見られない。雷刀はともかく、レイシスまでこんなことをするなんて。烈風刀は呆れたように溜め息を吐いた。
「そんなに暇なら別の作業をしてください。普段のことは僕が全てやりますから」
現在の人数ならば烈風刀一人でも十分に対処できる。ならば『暇』とのたまう彼らには溜まっている案件を消化させるのが合理的だ。キーを操り、烈風刀は二人に必要なデータを受け渡す。目の前の画面に表示されたファイルの量に、桃と赤の瞳が大きく開かれる。その顔は驚きと絶望に青く染まっていた。嘘だろう、あんまりではないか、と彼らは縋るように緑を見つめる。笑顔でこちらを向いた烈風刀の瞳は、暇なのだろう、文句を言うな、と物語っていた。はい、と諦めたような返事が二つ、のろのろとキーを叩くまばらな音が聞こえてきた。これでしばらくはふざけるようなこともないだろう。暗い顔で画面を見つめる二人を確認し、烈風刀は己の仕事に戻った。マッチング処理、楽曲・譜面データの確認、プレーヤーデータの管理といった細々とした仕事をこなしていく。どれもプレーヤーに快適に遊んでもらうための事だ。これのどこが暇なのだろうか、と彼は小さく首を傾げた。
しばらくして、レイシスが短く声を上げた。カタン、と椅子が動き、彼女が立ち上がる音がした。
「この案件、マキシマ先生に見ていただく必要があるみたいデスネ。ワタシ、ちょっと行ってきマス!」
「オレのも必要っぽいな。レイシス、一緒に行こうぜ!」
ハイ、と彼女はにこやかに返事する。一人が行けば十分だろう、という烈風刀の言葉は、走るように部屋を出ていった二人に届くことはなかった。単にサボりたいだけではないか、と烈風刀は眉間に皺を寄せ、深く溜め息を吐く。日頃からどうしようもなく不真面目な兄はともかく、何故普段は真面目に仕事をしているレイシスまでこんなことを。今日は一体どうしたのだ。彼は疲れ切った頭でぼんやりと考えた。
電子の文字が、音が、光が広々とした空間を包む。他者のいない部屋は痛いほど静かで、うるさいほど賑やかだ。画面を流れる情報が、液晶一枚隔てた向こうのプレーヤーが頑張る姿、楽しむ姿を伝えてくる。名も知らぬ彼らを思い浮かべ、烈風刀は小さく笑みをこぼした。己の努力が彼らを楽しませているのだ、と考えるとやはり嬉しい。もっと頑張ろうと更なるやる気が湧いてくるものだ。
一時的に人が途絶え、烈風刀は小さく息を吐く。最初は一人でも平気だと思ったが、存外忙しい。もう少し経てばプレーヤーも増えるだろう。二人が帰ってきたらその旨を伝え、手伝ってもらおう。そう考えて、烈風刀は画面の光で疲れた目を伏せた。
ふと、先ほどの光景がよみがえる。叫ぶ二人の表情はとても晴れやかで楽しそうだった。大声を出すのはストレス解消にいい、とどこかで聞いたことがある。その効果なのだろうか、と烈風刀は思案する。普段は真面目で頑張りやな彼女はともかく、ほわほわと何も考えず気ままに過ごす彼にストレスがあるとは全く思えないが。
ストレス、か。烈風刀は椅子にもたれかかり、宙を仰いだ。最近は小テストが重なり、加えて課題も少しばかり多い。どれも提出期限が長いため急いで片付ける必要はないのだが、何もせず後回しにすることを烈風刀は嫌っていた。故に、勉強量は増えるばかりだ。運営に関しても、ここひと月は様々なコラボレーションもあってか更新ペースが非常に早く、それに伴い仕事量もどんどんと増えていった。今はようやく落ち着いたが、昨年のことを考えるとまた更新ペースは早くなるだろう。それに疲れを感じているのは薄々気づいている。もしかして、先ほど怒鳴ってしまったのも八つ当たりではないか、と烈風刀は不安に駆られた。
自分こそ、溜まっているであろうストレスを解消すべきではないだろうか。烈風刀の思考はそこで止まった。
きょろきょろと辺りを見回す。人が来る様子もなければ、彼らが帰ってくる気配もない。つまり、今ここにいるのは烈風刀一人だけだ。誰かが見ている、ということもないだろう。
ふぅ、と息を吐く。なに、いつもよりほんの少し大きな声を出すだけだ。何も問題はない。大丈夫だ。そう己に言い聞かせ、烈風刀は口を開く。その唇はわずかに震えていた。
「あー……」
発せられた声は思ったより細く掠れていた。烈風刀は顔をしかめる。もう一度、震える唇を開き、喉を震わせる。
「ぁ、あー…………」
先ほどよりも大きいが、それでも普段の声とさほど変わらない程度のもので叫びというにはまだまだ小さい。
だんだんと羞恥心が姿を表してくる。ぶわ、と顔が赤くなるのがはっきりと分かった。あまりの恥ずかしさに耐えきれず、烈風刀は両手で顔を覆った。それでも、真っ赤に色づいた顔を全て隠すことはできていない。青にも似た柔らかな緑の髪からは、彼の兄の髪色のように染め上がった耳が覗いていた。
「無理、です……」
一体何をしているのだ。何を考えているのだ。こんなことをしてどうするのだ。二人のことを言えないではないか。己の中の何かが、自身を強く罵倒する。全て事実であり言い返せず、烈風刀は一人唸った。興味本位でやってみたことだが、今では後悔しかない。何故あの二人はこんなことができたのだ、と彼は羞恥に染まる頭で考えた。
ガタ、と大きな音が部屋に響いた。烈風刀は手を退け、急いでそちらの方を見る。翡翠の瞳には揺れる桜と紅が見えた。扉に半分隠れたその顔にはやってしまった、と気まずげな色が浮かんでいる。しかし、それ以上に好奇心やらなにやらで輝いていた。
見られていた。その事実に烈風刀の顔が更に赤くなる。茹で蛸のようだ、とはまさに今の彼のことを表すのだろう。
「い、いつから、そこに」
「……ちょっと前?」
「戻ってきたら、烈風刀がきょろきょろしてるのが見えたノデ……」
なんとなく入り辛かったんデス、と俯きレイシスはこぼす。雷刀はわざとじゃない、と主張するが、覗き見ていた事実に変わりはない。烈風刀は再度両手で顔を覆った。翡翠にも似た透き通る緑の瞳には、絶望の色が浮かんでいた。
「い、いや、でも烈風刀もそういうことするんだな!」
「そっ、そうデスネ! 意外デス!」
フォローするように二人は言葉を続けるが、全くの逆効果である。手で隠された烈風刀の口元がひくりと引きつる。もうどうにでもなってしまえ。彼の思考は自暴自棄な方向に傾きつつあった。
「まぁ、一回ぱーっとやってみてもいいんじゃね?」
「かもしれまセン。一回やってしまえば、それで満足すると思いマス!」
そんな烈風刀をよそに、二人は不穏な方向へと話を進める。その空気に気付き彼は顔を上げるが、二人の間では既に何かが決定してしまったようでもう止めることなどできなかった。
「大声出すのってとっても楽しいデスヨ? やってみまショウ!」
「誰も怒んねーからやってみようぜ。ほら」
「ぅ、え」
レイシスと雷刀は楽しげに笑みを浮かべ烈風刀に迫る。真正面からの圧力に、烈風刀は戸惑いの声を上げることしかできない。さぁさぁ、と二人はどんどんと距離を詰める。分かりましたから、と烈風刀は叫ぶように言い、彼らを押し退けた。羞恥に染まるその顔に、諦めと後悔の色が広がっていく。そんなことを気にする様子はかけらもなく、二人はにこにこと笑い彼を見つめる。明らかに面白がっているだけだ。
早く、と言わんばかりに華やかな桃色の瞳と燃えるような赤色の瞳が浅葱を見つめる。期待に染まった二色から目を逸らし、烈風刀は口を開いた。その頬は未だ赤く色づいていた。
「あ、あー…………」
「もうちょい大きくー」
どうにか音にしたそれは雷刀の声にかき消される。うるさい、と彼を睨み目で訴え、烈風刀は再度口を開いた。
「ぅ、う……あ、あー…………うぅ……」
「もうちょっとデス!」
先ほどよりも大きく開き喉から絞り出した音はレイシスの応援にかき消された。烈風刀は羞恥に俯き呻くが、彼女は笑顔で彼を見つめていた。その瞳には、純粋な励ましと溢れんばかりの好奇心が見える。彼女の期待に応えねばならない、そんな責任感が烈風刀を押し潰そうとしていた。
「ぁ……あ、ぅ、あっ…………ん、ぁ、あ…………」
声帯が震え音を発する度、彼の表情は強張り口元が引きつる。大きな声を出そうとしているというのに、烈風刀の喉はどんどんと細くなりひゅうと細い息が漏れるばかりだ。頬だけでなく目頭まで熱を帯び、視界がわずかにぼやけたように感じた。
「む、無理です! もう無理です! できません!」
耐えきれず、烈風刀は目元を腕で隠し二人から距離を取った。応援する、というよりも茶化すような声が止まる。まずい、と二人が悟った頃には、怒りの炎が宿った瞳が二人を睨んだ。その鋭さたるや、『視線がつき刺さる』という言葉はただの比喩ではないことが嫌でも実感できるほどのものだった。
「そもそも無理矢理叫ぶ必要性なんて全くありません! 何故こんなことをする必要があるのですか!」
羞恥だけでなく憤りの色が浮かぶ顔は般若の面にも似ていた。ふざけすぎたか、と雷刀は内心後悔するがもう遅い。こちらを睨む烈風刀の怒りが収まる様子は全く見られない。自分だけならまだしも、彼がレイシスまで怒ることなど滅多にないのだ。それほど、今回の彼の怒りは強いのだとはっきりと分かった。
「大体、元はといえば貴方たちがふざけていたせいですよ! 遊んでいないでちゃんと仕事してください!」
烈風刀はビシリと指を突きつける。ごめんなさい、と二人分の謝罪が重なった。それでも怒りはおさまらないのか、烈風刀は乱暴に椅子を回し元の位置へと戻る。逆ギレではないか、と喉までせり上がってきた言葉を雷刀は必死に呑み込んだ。そんなことを言ってしまえば、ただでは済まされない。
「人が増えてきましたよ。早く作業に戻ってください」
分かりましたか、と烈風刀は冷たい声と視線を向ける。はい、と殊勝な声が奏でられ、二人は自身の席へと急いで戻った。
烈風刀は様々な色が躍る画面を見つめ、重苦しい溜め息を吐いた。散々怒鳴ったことにより、更に疲れた気がする。けれども胸の内は不思議と軽くなっていたように思えた。何故だろう、と首を傾げる。はた、と先ほど己が考えたことが頭の中によみがえった。
大声を出すと、ストレスは解消できる。
なるほど、そういうことか、と烈風刀は一人頷いた。今回の場合、己の感情を思い切り外に出したのも更なる効果を発揮しているのだろう。それでも、怒りを伴うそれは心身的にあまりよいとは言えないはずだ。
今度はもっと健康的な方法でやろう。そう考えて、烈風刀は情報を目で追う。そんな無駄なことを考えている間に手を動かすべきである。彼の思考は既に仕事を行う時のそれに切り替えられていた。
いつも賑やかしいはずの部屋は、痛いほどに冷え切っていた。
畳む
積み重なる温度【ライレフ】
積み重なる温度【ライレフ】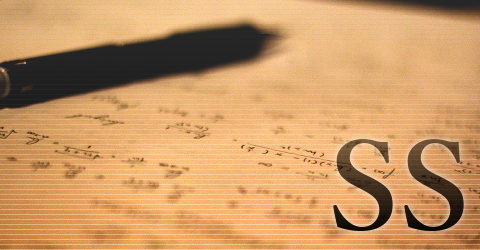
30日CPチャレンジなるものに挑戦したいと始めたはいいが単独カプで毎日とか無理なので暇を見て少しずつ。
ということでライレフで【01.手を繋ぐ】
通常進行でお送りします。
カリカリと紙の上をペンが滑る音が部屋に響く。もはや物置と化していた学習机の上は綺麗に片付けられ、教科書に参考書、ノートやプリント類が積まれていた。教科別にまとめられたそれらは、全て重ねればなかなかの高さになるだろう。
目の前の問題を解く合間、烈風刀は横目で隣に座る雷刀を見る。力強くペンを握ったその手は予想通り止まっており、赤い目は前に広げられたノートと参考書を往復していた。自力で解く気があるだけまだマシか、と烈風刀は諦めにも似た感情を抱く。いつものことだ。
月も幾度か変わり、そろそろ定期考査の時期が近づいてきた。毎度毎度成績表を赤く染め上げる雷刀だが、今回ばかりはそれを避けようと自ら烈風刀に教えを乞うてきた。どうも初等部の子らに本気で学力を心配されたのがきいたらしい。理由はなんであれ、自発的に勉強しようとする姿勢は評価すべきだろう。烈風刀は喜んで了承したのだった。
そうして、雷刀の部屋でテスト勉強をしているのだが。
「わっかんねー」
情けない声をあげ、雷刀は机に突っ伏した。集中力が切れてしまったようだ。まだもった方だな、と烈風刀は壁にかけられた時計を見て考える。彼にしてはもった方だが、常人のそれよりもずっと短い。はぁ、とわざとらしく嘆息し、烈風刀は手にしたシャープペンシルで俯せた赤い頭を軽く叩いた。
「まだ半分も解いていないでしょう。もう少し頑張ってください」
「だってわかんねーもん」
諌めるような烈風刀の声に雷刀はふて腐れたような声を上げる。どれが分からないのだ、とその頭を上げさせ彼が立ち向かっている問を見る。力強く記された文字は単純な計算式で導き出される箇所で途切れていた。そもそも、前提として求めるべき最初の式が間違っている。これではいつまでたっても正しい解に辿りつけないだろう。
「ここはこの公式を使えばいいのですよ。そもそも、最初の計算が間違っています。四則演算ぐらいはしっかりやってください」
「へーい」
やる気のない返事をして雷刀は消しゴムを動かす。シャープペンシルを持ち直し指摘された部分を修正するが、その手はすぐに止まってしまった。
「……れふとー」
「まずは教科書を読んでください」
雷刀は乞うような声と視線を烈風刀に向ける。しかし、返ってくるのは冷たい言葉だけだ。烈風刀自身もテストに向けて対策をしなければならないのだ。彼ばかりに構ってはいられない。教科書に載っている基本的な問題程度は自力で解いてもらわねば困る。
ガタン、と音をたてて雷刀が立ち上がった。一体なんだ、と目を眇め彼を見上げる。視線の先の彼の目は不自然に泳いでおり、口元は妙に引きつっていた。
「喉渇いたからコーヒー持ってくる!」
「ここにありますよ」
急いで部屋を出ようとする雷刀の前にダン、と音をたててコーヒーポットを置く。何かしら理由をつけて逃げようとするだろうと予測して、事前に用意しておいたのだ。その強い音故か、彼の身体がビクリと大袈裟に跳ねた。ギギギと音をたてそうな硬い動きでポットを見るその表情は、嘘が露見した時のような苦々しいものだ。
「もちろん、砂糖とミルクも用意してあります。お茶もありますからわざわざ持ってくる必要はありません」
「なんでそんなに用意がいいんだよ……」
「誰かさんが逃げようとするからです」
自分から頼んできたのですから終わるまで逃がしませんよ、と烈風刀は静かに告げる。有無を言わせぬ声音に、雷刀は諦めたようにのろのろと力無く椅子に座った。彼がペンを持ちノートに向かったところを見届け、烈風刀もテスト対策の課題を再開しようと問題文へと視線を向けた。
「そうだ!」
パン、と両手を打って雷刀が大きな声をあげる。今度は何だ、と眉間に皺を寄せ隣に座る彼を見る。ノートを押さえる自身の手の上に温かな何かが乗せられた。それが雷刀の手であると認識する間も無く、指を絡め手全体を包み込むようにぎゅっと握られる。熱いとすら思えるその温度にビクリと肩が跳ねた。
「これなら逃げれないな!」
彼はこちらを見て楽しげに笑みを浮かべる。指から伝わる熱と気恥ずかしさに思わずふいと視線を逸らし、その嬉しそうな笑みから逃げた。
「……これでは、まるで僕が逃げようとしているみたいではないですか」
「んじゃ烈風刀から繋いで?」
彼は笑顔でそう言うが、手を離す気配は全くない。その手を解いた瞬間、何かしら理由をつけて離れることが分かっているのだろう。眉をひそめ、烈風刀は誤魔化すように言葉を続ける。
「大体、これでは貴方が文字を書けないではないですか。意味がありません」
「こっちの手使えばいーじゃん」
雷刀はそう言って繋いでいない方の手をひらひらと振るが、彼の利き手はそちらではない。ただでさえ綺麗とは言い難い字だというのに、利き手でない方で文字を書くことなど不可能だろう。いけるいける、と意気込んで彼はシャープペンシルを握るがその手は覚束ない。のろのろとノートの上を走る線は手の震えに連動して歪み、漢字はもちろんひらがなですら何と書いてあるのか分からない状態だ。ミミズが這ったような字とはまさにこれを指すのだろう。
「やはり無理ではないですか」
「いや、もうちょい頑張ればいける。本気出せば書ける」
「そんなことで本気を出さないでください」
あまりに真剣な顔と声に呆れ、思わず苦笑する。この真剣さをほんの少しでも勉強に向けてくれればいいのだが、それは土台無理な話だろう。
雷刀が文字を書こうとする度、繋いだ手に力が込められる。きっと無意識の行動なのだろうが、ぴたりと隙間なく触れ合う手と手は否応にも意識してしまう。硬い指と指が擦れる度僅かに体が震え、その感覚に顔が熱くなるのが嫌でも分かった。
「分かりましたから」
ぐい、と強く手を引いて重なったそれをほどく。えー、と雷刀は不服そうな声を上げた。ほのかに色付いているであろう顔を見せぬよう、ノートに向かうふりをし少し俯いて烈風刀は言葉を続けた。
「早く続きをしましょう。逃げないのは、もう分かりましたから」
「えー。分かんねーよ? オレは気まぐれだし飽きっぽいからすぐ逃げるかもよ?」
「自覚しているなら直してください」
ニヤニヤとした笑みに冷え切った声をぶつけると、雷刀は反省したようにしゅんとした表情で俯いた。すぐに調子に乗ってふざけるからこうなるのだ。烈風刀は呆れるようにその姿を一瞥し、ペンを握り直しノートに向かった。
「手を繋ぐことぐらい、いつでもできるというのに」
無意識にそんな言葉がこぼれ落ちた。
しまった、と烈風刀は慌てて口を押さえる。しかしその小さな言葉はしっかり聞こえていたようで、雷刀は勢いよく顔を上げた。先程までの沈んだ色はすっかりと消え失せ、その瞳は喜びと期待にキラキラと輝いている。余計なことを言ってしまった、と烈風刀は苦々しく顔をしかめた。
「そうだな! いつでもできるな!」
「……はいはい、そうですね」
満面の笑みを浮かべる彼に投げやりに返事する。先に自ら肯定してしまったのだ、誤魔化して逃げることなどできない。後悔と諦めを色濃く滲ませ、烈風刀は深い溜め息を吐いた。
「ほら、早く続きをやりますよ。せめてこの単元だけでも終わらせましょう」
「えー」
「『教えてくれ』と泣きついてきたのは貴方でしょう。懲りずに赤点を取って、またニアたちを心配させるつもりですか?」
責めるような烈風刀の声に、雷刀は押し潰されたような声をあげた。無邪気で元気いっぱいな彼女らの姿と、ぶつけられた不安げな言葉を思い出したのだろう。
あの時、彼を見上げたニアとノアの表情は酷く不安げで、心の底から心配していることは傍から見ても分かった。そんな幼く純粋な心を無碍にするようなことなど、常日頃彼女らを可愛がっている雷刀にはできないはずだ。
ペンを握り、うー、と力なく呻く姿に苦笑する。先程までの姿を見るに、やる気はあるのだろう。ただ、一度切れた集中力を取り戻すきっかけがないのだ。
きっかけ、か。少し思案して、ノートを押さえていた手が迷うように揺れる。あぁ、やはり自分は甘いのだ。自嘲するように息を吐いて、机の上に放り出された彼の手に己のそれをそっと重ねた。温かなその手が驚いたようにピクリと跳ねた。
「分かるまで教えますから、頑張ってください」
そう言ってすぐに手を離し、参考書に目を移す。視界の端に、へにゃりと顔を綻ばせる彼の姿が見えた。
「ん、頑張る」
「また逃げないでくださいね」
「もう逃げねーって」
逃がしてくれないだろ、と雷刀は意地の悪い顔で問うてくる。当たり前です、と返す己の顔はまだ淡く色づいたままだろう。
白いノートの上をペンが踊る。二人分の軽やかな音が狭い部屋にゆっくりと積もっていった。
畳む
見上げた先の【咲霊】
見上げた先の【咲霊】
リハビリ咲霊。この子らは妙に書きやすい。
TLで見たラブコメチックな膝枕咲霊が可愛くて書き始めたはずなのにどうしてこうなった。
霊夢、と優しげな声が己の名を口にする。声の方へと目をやると、正座をした咲夜が手招きしていた。畳に手を付き、ぺたぺたと這って霊夢は彼女の下へ向かう。何の用だと言いたげに目の前の赤い瞳を見つめると、咲夜は微笑み己の太ももをとんとんと叩いた。誘われるがまま、そこに頭を乗せる。腹に背中を預けるように顔を横に向け頬を付けると、程よい弾力と心地よい熱がほのかに伝わってきた。細い指が頭を撫で、長い髪を優しく梳く。その心地よさに目を伏せた。
「足、痺れないの?」
こてんと仰向けになり、以前から疑問に思っていたことをぶつけた。咲夜の住まう館はテーブルと椅子ばかりで、正座しなければいけないような部屋はなかったはずだ。正座自体あまり慣れていないだろう。それに加え、人の頭を片足に乗せているのだ。足が痺れないわけがない。それでも彼女はいつも涼しげな顔をしているのだから、不思議でならない。
「もう慣れたわ」
こうやって何度もやってるもの、と咲夜は霊夢の前髪をかき上げる。日の当たらない額は僅かな汚れすら見つからないほど白く、黒い髪とは対照的でよく映えた。
「それに練習したのよ。休憩中は正座して過ごしたり、寝る前にベッドの上でやってみたり、すぐに立ち上がれるようにしたり」
「練習してまでやることじゃないでしょ」
指折り数える彼女にそんなに好きなの、と呆れた瞳で問うと、えぇ、と肯定の言葉と柔らかな笑みが返ってきた。物好きなやつだ、と霊夢はその優しい瞳をぼんやり見つめる。赤い目が弧を描き、慈しむような表情がこちらに向けられた。
そんなに楽しいのだろうか、と霊夢は内心首を傾げた。咲夜はよく膝枕をしたがる。彼女はどうも自分の髪を触るのを好むようで、よく自身を引き寄せ長いそれを撫で、時に結ってくれる。それだけなら隣りあって座った方はやりやすいはずだ。だというのに、彼女はこうやって自分を寝転ばせるのだ。一体何が楽しいのだろう。小さな疑問と好奇心が胸の内に湧き出で、どんどんと膨らんでいく。
霊夢が身を起こす。いきなりの行動に、咲夜は不思議そうにその赤い背を見た。そんな彼女を気にすることなく、向き合うように座る。すっと背筋の伸びた美しい姿勢で正座をし、無言で隣に座ったままの彼女を見つめぺしぺしと太ももを叩く。何を意味するのか理解できないのか、咲夜は頬に片手を当て首を傾げた。
「交代」
「え?」
「交代。たまにはやったげるわ」
早く、と急かすように霊夢は目を細める。不機嫌そうなその顔を見て、咲夜は畳に手を付き身を屈め、遠慮がちな様子で示された場所に頭を乗せ横を向いて寝転んだ。白くふわふわとした髪を持つ彼女の頭は存外重く、何故こんな重たいものを率先して乗せろと言ってくるのだろう、とますます疑問が深まる。
邪魔ね、と呟き、霊夢は咲夜のヘッドドレスを外す。動く気配すらなく、されるがままの彼女の頭をそっと撫でる。少し癖のついた髪はふわふわと柔らかな感触がして、触っていて心地よい。三つ編みが解けないように梳いてみる。少し跳ねた銀色は見た目よりずっとさらさらしていた。霊夢は楽しげに銀色の頭を優しく撫でる。咲夜は時折自分の髪を羨ましいというが、彼女の髪も十分に柔らかで滑らかだ。
柔らかな銀色を楽しんでいると、咲夜は仰向けになりこちらを見た。どこかきょとんと呆けたような顔をした彼女は、見上げた先の黒い瞳をじっと見つめた。なんだろう、と不思議に思いつつも、霊夢もじっと見返す。覗き込んだ赤色は井戸水のように澄み切っていた。主人が主人故に『血のようだ』と言われる彼女の瞳だが、どろりとしたあれよりもワインや紅茶といった底の見える透き通る赤だとぼんやり考える。白い髪と肌に浮かぶ赤いガラス玉は、はいつぞや見た赤い月よりも深いそれはとても綺麗で、揺らめいて輝くその色に触れてみたいという衝動に駆られた。
「……される側っていうのも、案外いいものね」
しみじみとした様子でそう呟き、咲夜はふわりと笑った。彼女はそのまま細い腕を伸ばし、霊夢の頬を優しく撫でる。陽の光にも似た柔らかい温かさとほんの少しのくすぐったさに、猫のように目を細めた。
「こうやって貴方を見上げるのも新鮮だわ」
「そういえばそうね」
この膝枕といい抱きかかえた時といい、たしかに彼女はいつも見下ろす側にいた。そう考えるとなんだか気に食わない。不服さが表情に出ていたのか、咲夜は困ったように眉を下げた。そっと頬を撫でる手つきはまるでぐずる子どもをあやすときのそれに似ていて、霊夢は小さくむくれた。
「でも、これだとなんだか遠くに感じるわね」
「そう?」
どこか寂しげな咲夜の声に、霊夢は不思議そうな顔をした。いつもされている時はそう感じない、むしろ近すぎるぐらいに思えた。身長の問題だろうか。いや、咲夜の方がほんの僅かに高いはずだ。何故なのだろう、と更に首を傾げていると、咲夜は苦笑した。
「私にも分からないけれど」
「なにそれ」
変なの、と呟くと、知ってるでしょ、と笑い交じりの声が返ってくる。そのまま、自然な動作で咲夜は立ち上がった。一体なんだ、と己の手から離れた銀色を見つめると、彼女はくるりと綺麗に振り返った。その口元は柔らかく弧を描いており、どこか楽しげだ。
「交代」
「へ?」
「やっぱり、されるよりする方が好きみたい」
さっと手早くスカートをさばき、咲夜は再び正座する。眉を下げ、困ったように笑う銀に誘われるがままに、霊夢も再び彼女に頭を預けた。ほんの少し離れていただけだというのに、布越しの温かさを長らく求めていたように錯覚する。
「……やっぱこっちのがしっくりくるわ」
「でしょ?」
しみじみと、少し悔しげに呟きじぃと天井の方を見る。見上げた先の彼女は楽しげに笑った。普通はされた方が嬉しいだろうに、何故こんなに楽しげなのだろうか。やっぱり変なやつだ、と霊夢は小さく息を吐いた。
「それに、こっちの方が貴方の顔がよく見えるわ」
うんうん、と一人頷いて、咲夜は霊夢の顔を覗き込む。だんだんと近付く赤い月に、霊夢は驚いたように目を見開いた。すぐさま眉間に深く皺を刻み、腕を伸ばし広げた手で彼女の顔を覆うようにしてぐいぐいと押し退けた。
「近い。調子に乗るな」
「あら、残念」
不機嫌そうな声を気にすることなく、咲夜は涼しい顔で姿勢を正す。調子のいいやつめ、と霊夢は目を眇め、ごろりと横を向いた。
「どうする? もうやめる?」
「…………もうちょい」
思案の末のふてくされたような声に、小さな笑い声と温かな手が降ってくる。さらさらと撫でられる感触は温かくて心地よく、安心する。思わず眠ってしまいそうだ。じわじわと姿を現し始めた睡魔に、霊夢は小さく欠伸をした。
「昼寝ばっかりしちゃだめよ」
咎めるような言葉とあやすような手つきは正反対だ。その裏に滲む『寂しい』という感情も、隠すように優しい声音とも正反対で、霊夢は呆れたように溜め息を吐いた。
こてん、と再度転がり、霊夢は咲夜の腹に顔を埋めるように向きを変える。
「寝ないしほっとかないわよ」
安心しなさい、と甘えるように頭を擦り付けると、撫でる手がぴたりと止まった。この体勢では顔を見ることはできないが、きっと彼女はくしゃりといつもの瀟洒な表情を崩し、子どものように笑っているだろう。勝てないわね、と苦笑交じりの声に、当たり前でしょ、と不遜に返した。
柔らかな手と、柔らかな体温と、ほのかに香る彼女の匂い。
やはり、こちらの方が安心できる。ぼんやりと考えて、霊夢は目を伏せた。
畳む

隠し色【ライレフ】
隠し色【ライレフ】設定も説明もクソも訳が分からない、ただただ自分が書いてて楽しいだけの文章。貧乏性なので投げる。
ちょっとだけ頼りないオニイチャンとちょっとだけかっこいい弟君が書きたかっただけ。
「れーふーとー」
シャワーを終えキッチンで茶を飲んでいると、間延びした声がリビングの方から飛んできた。コップを手にしたまま、烈風刀は声の方へと頭を動かす。視線を移した先には、ソファに座りニコニコと笑みを浮かべた雷刀がいた。彼は広げた足の間に手を付き、片手でそこをぺしぺしと叩いている。ここに座れ、と言っているのだろう。
コップの中身を飲み干し、烈風刀は大人しく兄の下へと向かう。少しばかり躊躇いつつも、その手が示す場所に浅く腰掛けた。後ろからごく自然な動きで腕が回される。ゆっくりと抱きしめられ、否応なしに二人の距離が縮まる。熱と熱とが重なり合う。普段ならば文句の一つや二つ飛ぶのだが、今日の彼は借りてきた猫のように大人しくしていた。抱き寄せたその背に、雷刀はこつんと額をつけた。
「烈風刀、あったけー」
「お風呂あがりなのだから当たり前でしょう」
それに加え、兄弟の平熱は人よりも少しばかり高い。それでも肌を触れ合わせると、熱さよりも心地よさや安心感が胸の中にじわりと広がっていくのから不思議だ。背から伝わる熱に、烈風刀は小さく息を吐いた。身じろぎもせず、ただただ抱きしめ抱きしめられたまま時計の針は進んでいく。カチ、カチ、と秒針が時の道を歩く音が静かな部屋に響いた。
抱きしめる雷刀の腕にゆっくりと力がこめられる。骨で守られていない柔らかな箇所を圧迫され、少しの息苦しさと鈍い痛みがじわじわと広がっていく。その感覚に、烈風刀は小さく顔をしかめた。
「ちょっと雷刀、苦しい――」
「んー、もうちょい」
彼は苦しさを訴えるが、雷刀が手を離す様子はない。むしろ逃がさんと言わんばかりに更に強く抱きしめられ、二人の身体がひたりと密着する。内臓を潰されるような感覚は決してよいものではない。どうにか引きはがし腕から逃れようと、烈風刀は腹に回された手に己のそれを重ねる。掴んだそれは想像していたよりもずっと冷たく、烈風刀は悔しげに顔を歪めた。
思い切り力を入れ、烈風刀は抱き寄せる腕を無理矢理引きはがす。そのままくるりと身体を反転させる。透き通った緑青の瞳の先には、疲れを誤魔化すような、深い傷を隠すような表情をした兄がいた。彼への、そしてなにより自分への強い苛立ちに烈風刀は眉間に深い皺を刻む。そのまま鮮やかな深緋に彩られた頭を思い切り胸に寄せ、抱きつくように抱きしめた。
「烈風刀?」
「疲れてるなら――辛いなら、ちゃんと言ってください」
先程のお返しだと言わんばかりに、烈風刀はふつふつと湧いてくる怒りを込めて強く抱きしめる。少し跳ねた真っ赤な髪がくしゃりと崩れた。
「……バレた?」
「分かりますよ」
どこかバツが悪そうな雷刀の声に、烈風刀は怒りを色濃くにじませた声を返した。胸に顔を埋めたままでは息苦しいだろうに、腕の中の赤色は何も言わず大人しく抱かれたままだ。彼らしくないその様子に、抵抗する力すらないのではないかいう不安が烈風刀の胸をじわじわと侵蝕していく。
ここ最近はアップデートの頻度が高く、楽曲データの生成や管理および照合、プレーヤーデータへの反映など普段以上の業務が要求され、運営に関わる者は文字通り忙殺される日々を過ごしていた。あまりにも膨大な量に、細かいことを不得手とするため普段は別作業を担当している雷刀まで駆り出されるほどだ。しかも、その忙しさを突いてきたバグの侵入を許してしまい、退治のために彼は学園中を何度も何度も駆け回っている。慣れない作業で頭と精神をすり減らし、加えてバグ退治で肉体まで酷使しているのだ。いくら体力に自信がある雷刀でも、疲れ果てるのは当たり前である。
しかし、彼はそれをひた隠そうとしていた。心配をかけるのが嫌なのだろう、疲れていないかと問われれば、普段通りの笑顔で大丈夫だと答えていた。けれども、その瞳に沈む疲れの色はを風刀には隠し通すことなどできない。十数年も離れることなく隣にいるのだ、些細な嘘など互いに通じるわけなどなかった。
無理に行動させていたこと。いつも自分に『隠すな』という癖に、己のそれを隠そうとしたこと。一人だけで解決しようとしていたこと。そして何より、一切頼られなかったこと。様々な怒りと悔しさが烈風刀の中で渦巻いていた。
「貴方は僕のことをよく分かっているのでしょう? だったら、僕だって同じです。貴方のことぐらい、全部知っています」
当たり前でしょう、と烈風刀が言うと、くすりと小さな笑みが聞こえた。そのまま、その背にわずかばかり温度を取り戻した手が回される。今度は添える程度の優しい手つきだった。
「大体、僕に無理するなと言う癖に、何故貴方は溜め込むのですか」
「あー……うん……」
責める声に、雷刀は気まずそうに言葉を濁す。弱々しいその音に、烈風刀は目を伏せ抱きしめた頭を優しく撫でた。ふわふわとした柔らかな髪を指で梳くと、落ち着いた呼吸が彼の耳に届いた。
「もっと頼ってください。僕もレイシスも、迷惑だなんて思ってませんから。むしろ、本当に大丈夫なのか心配しているのですよ? だから、一人で無理をするのはやめてください」
いつも雷刀が自分に言い聞かせる言葉を、烈風刀は口にする。その声には強い熱が宿っていた。
彼もこんな気持ちで言っていたのだろうか、と烈風刀はぼんやりと考えた。たしかに、こうやって無理をしている姿を見るのは心臓にも精神にもあまりよろしくない。今度からもっと上手く隠さねば、とその思考は間違った方向へと捻じれた。
無理をして倒れられた方が迷惑です、と照れたように付け加えると、はは、と気の抜けた笑い声が聞こえた。腹に息がかかって少しくすぐったい。
「ん、分かった」
とんとん、と、雷刀は己を抱きかかえる弟の背中を優しく叩く。これではまるで自分があやされているようだ、と烈風刀は少し拗ねたように顔をしかめた。くすり、とまた笑う声。腕の中に納まる兄からは己の顔など見えるはずがないというのに、全て見透かされているように思えた。これも双子故だろうか、と考えて、ふわふわとした赤を優しく撫でる。
「なぁ、烈風刀」
「なんですか」
「オニイチャン、さっきの体勢のがいいなー。烈風刀あったかいし、抱きしめてると落ち着く」
「嫌です」
おどけたような声をきっぱりとした声が否定する。えー、と不服そうな声が上がるが、烈風刀は黙ったままだ。幾許かして、小さく息を飲む音が雷刀の耳に落ちてくる。薄い唇が開かれ、紅梅を抱きしめた若草は、その胸の内を音へと変えていく。
「……先程の体勢では、『僕が』抱きしめられないでしょう」
たまには黙って抱きしめられていてください、と少し拗ねたような音がぽつりとこぼれた。
思えば、烈風刀はいつも雷刀に抱きしめられてばかりで己から動くことは少ない。だからこそ、今日ばかりは自分から抱きつきたい。抱きしめ、肌を触れ合わせ、体温を共有することは心地よく、安心する。その安心感を、今度は自分が彼に与えたいのだ。
「そっか」
じゃあ仕方ないな、と機嫌のよさそうな兄の声に、そうですよ、と開き直って返す。すり、と雷刀は目の前の胸に額を擦り付けた。可愛らしい姿と少しのくすぐったさに、烈風刀は小さく笑みを浮かべる。応えるように、燃える緋色をゆっくりと撫でた。
あぁ、温かい。
体温を取り戻した手から伝わる熱が、腕の中で優しく笑むその熱が、この上なく心地よかった。
畳む
#ライレフ #腐向け