No.8, No.7, No.6, No.5, No.4, No.3, No.2[7件]
例えばのお話【ライレフ】
例えばのお話【ライレフ】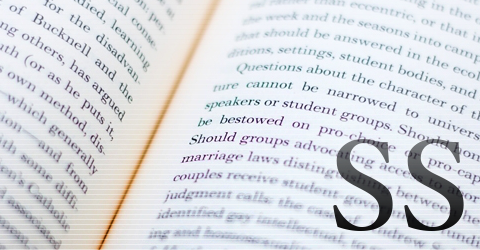
そろそろなんか書かないとなーということで診断メーカーからお題拝借。140字SSのだけど気にしない。
30mで終わらせるつもりが足りず。追加10mで合計40mSS。
貴方はライレフで『たとえばの話』をお題にして140文字SSを書いてください。 http://shindanmaker.com/375517
「例えば、さ」
背もたれによしかかり、椅子の足を浮かせギコギコと揺らしていた雷刀が口を開く。烈風刀は作業する手を止める様子はない。どうせろくでもない話だ、真面目に聞いても仕方がない。
「オレが頭良かったらどうする?」
「どうもしないでしょう」
ありもしないことを、と烈風刀は続ける。冷たい言葉に雷刀はやる気なく声を上げた。酷くつまらなそうだ。
「例えばだって」
「ありえないことを例えてどうするのです」
「あり得ないことだから例えるんだよ。夢がないなー」
笑う雷刀を不機嫌そうに見る烈風刀。雷刀は気にする様子なく、そのまま天井を指すように指を立てた。
「例えば、冷音がずっと雨降った時の性格だったら」
「……赤志君が苦労しそうですね」
「灯色がキレそうだな。『眠れない』って」
「彼ならどれだけうるさくても眠れるでしょう」
授業中はもちろん、野外でもどこでも眠っている灯色だ。確かに睡眠の邪魔をされた時の彼は酷く不機嫌だが、その程度で起きるほど彼の眠りは浅くない。
「例えば」
「例えば?」
「レイシスが妹だったら」
雷刀の言葉に烈風刀の手がぴたりと止まる。どうしたのだろうと顔を窺うと真剣な表情で自身の指先を見つめていた。声をかけるのもはばかられ、彼が口を開くまで待つことになる。
「…………今も、妹みたいなものでしょう。変わりませんよ」
ようやく答えた声は妙に平坦だ。先ほどの表情と相まって本気で考え導き出した答え――いや、その上でぼかしたような答えにしか聞こえない。それがなんだか面白くなくて、雷刀はからかうように問うた。
「そんなに真剣に考える事か?」
「真剣になんて考えていませんよ。ただ想像してみただけです」
「やらしー」
「何がですか」
烈風刀の声に怒りの色が混じる。少し潔癖症の気がある彼をからかうにはどうも悪かったようだ。ごめんごめん、と謝って雷刀は言葉を続ける。
「例えば」
「……例えば」
「オレたちが双子じゃなかったら」
再び烈風刀の手が止まった。どういう意味だ、と訝しげに雷刀を見るが、彼は普段通りの表情でこちらを見ていた。しばらく彼を見つめた後、烈風刀は机の上の書類に目を戻り言葉を紡ぐ。
「きっと、関わることはなかったでしょうね」
「そうか?」
「貴方と私は成績も性格も真逆でしょう。話す機会はあまりないと思いますし、進路も違っていたでしょう」
雷刀の学力と烈風刀の学力には随分と差がある。この学園は雷刀の学力では難しい部類だったが、兄弟である烈風刀と同じ進学先にしたいと努力した結果入学することができた。もし烈風刀がいなければ、雷刀が自身の学力に見合わないこの学園を選ぶことはなかっただろう。
烈風刀の答えに雷刀は首を傾げ、彼の顔を見る。
「そうか? なんかかんか出会ってそうだけど」
「出会っても、こうやってずっと一緒にいるなんてことはありませんよ」
ただのクラスメイトで終わりです、と烈風刀は言う。雷刀は相変わらず不思議そうな表情でいたが、すぐにいつもの明るい表情に切り替わった。
「双子じゃなけりゃこんなことなってなかったと」
「……こんなことって」
どんなことですか、と問おうとして烈風刀は口を閉ざした。きっと茶化すような答えしか返ってこないだろう――もし行動で示されれば、困るのは自分だ。幸い、雷刀は楽しげに笑うばかりで追及する様子はない。
「やっぱ双子でよかったな」
「そうですね」
補色のように正反対の二人。それを繋ぐのは血縁という名の硬い糸。
その他に彼らを繋げるものはあったのだろうかなんて考えても仕方ないのだ。そう結論付けて雷刀は天井を仰いだ。
ふと、ペンを動かす烈風刀の手が止まった。教室に響いていた音がぱたりと止まり、どうしたのだろうとそちらに目をやると積み重ねられた書類を揃える烈風刀姿があった。
「終わりました。早く提出して帰りましょう」
「おう」
雷刀は反動をつけて椅子から立ち上がる。危ないですよ、と諌める烈風刀の声は聞こえていないようだ。
教室を出ようとする烈風刀の手を雷刀が握る。びくりと烈風刀の体が小さく震えた。
「いこうぜ」
雷刀は楽しげに笑って、握った手を引き廊下を駆けだす。突然のことに烈風刀は声を上げる暇もない。ただただ、彼の速度に合わせて足を動かすばかりだ。
こんなことも、双子でなければやることはなかったのだろうな。そもそも、手を握るなんてこともなかったのだろう。
双子だから。兄弟だから。こうやって繋がっているのだ。
そんなことを考えて烈風刀は小さく笑った。
夕暮れ茜色に染まる廊下に繋がった影が走っていく。
畳む
感情論【ライ→レフ→レイ】
感情論【ライ→レフ→レイ】
ぐわっとライ→レフ書きたいのとレフレイ熱が来たのとが合わさった結果。
オニイチャンしか出てこない。
烈風刀がレイシスを好いていること――恋していることを、雷刀は知っている。
彼女に対する弟の態度は明らかに恋をしているそれで、言葉の端々にもよく表れている。何時でも冷静で顔色一つ変えない彼故に他者は気付かないかもしれないが、兄である雷刀にはすぐに分かった。そんな弟の姿を、幼い頃から何度も何度も見ていたのだから嫌でも気付く。
そんな彼が彼女に想いを伝えることはないだろう、と雷刀は確信している。
彼はああ見えて臆病で、きっと関係を壊すのを恐れている。堅実な彼が大きな賭けに出ることはまず無い。だから、ずっとこのままだ。
諦めればいいのに、と雷刀は常々考えている。
恋い焦がれながらも現状維持を望む弟のいじらしい姿は見ていられない、というのもある。けれども、そんなものはただの建前だ。本音は『烈風刀とレイシスが恋仲になること』を恐れているのだ。三人の関係が変わると言うこともあるが、何より烈風刀が好きなのだ。烈風刀がレイシスを好いているように、雷刀も烈風刀を好いていた――もちろん、恋愛感情として、だ。
彼と同じように、自分がこの想いを伝えることはない。血の繋がった弟にそんな感情を抱く兄なんて、気持ち悪くて堪らないだろう。現在の関係も壊れ、彼との繋がりもなくなってしまう。そんなことになるぐらいなら、この想いなど殺してしまえばいい。なのに、殺しきれない。一度芽生えた感情は、そう簡単に消すことなど出来なかった。
自分も大概臆病だ、と雷刀は自嘲した。何て女々しいのだろう。自分らしくもない。
彼が自分とそういう仲になることは絶対にない。けれども、他者に彼を奪われるのは嫌だ。弟が叶える気のない恋をすることすら嫌だった。なんて我が儘なんだろう。
けれども、この醜い考えが消えることはないのだろう。きっと彼が恋をする度こいつは顔を覗かせる。愛する人の不幸を願う、醜く汚ならしい感情が。
『恋』なんてものがなければ。そう考えても仕方がないのに、頭にはそんなことばかり浮かぶ。彼が恋をしなければ。自分が恋をしなければ。
はぁ、と誰にも気づかれぬよう雷刀は嘆息する。
実らない想いは募るばかりで、胸を苛む。
彼がいる限り、この痛みが消えることなどない。
畳む
色づく春【SDVX】
色づく春【SDVX】
新年早々エンドシーンに滾ったので。プロ+氷+桜。
はぁ、とゆっくり吐いた息は白に染まってすぐに消えた。寒さの度合は違えど故郷と同じだ、と氷雪は薄く笑う。
彼女は同じ学園に通う桜子と初詣に来ていた。これだけ人がいればあの方にお会いできるかもしれませんの、と言う桜子に誘われたのだ。
がやがやとうるさいくらい賑やかな人混みの中を歩くのは少し怖い。隣を行く桜子はそんなことは気にしていないようだ。自分より小柄ながらも元気に歩みを進める彼女に続いて人混みを掻き分けていく。
「あ。桜子ちゃん、氷雪ちゃん」
喧噪の中に響いた聞き覚えのある声に二人は振り返る。見上げた先にはひらひらと手を振る識苑がいた。身長の高い彼は人混みの中でも見つけやすい。むしろ、何故小柄な自分達を見つけられたのか不思議だ。
「識苑先生、明けましておめでとうございますですの」
「明けましておめでとうございます」
「明けましておめでとう」
ぺこりと頭を下げ挨拶をする彼女らに識苑は笑みを返し、真似するように頭を下げて挨拶する。そのまま彼女らと視線を合わすように彼は身を屈めた。普段は白衣姿の識苑だが、流石に寒いからかコートを着ていた。学内での彼しか見たことのない二人にその姿は新鮮に映った。
「二人とも初詣?」
「そうですの。新しいお着物で来たのですの」
「先生も初詣ですか?」
「そうだよ。暇だから行こうと思って」
作業中なんだけどねー、と識苑は笑った。よく見ればコートの裾から白いものが覗いている。何故白衣を脱いでこないのだろうと二人は不思議に思うが、触れないでおこう。
「氷雪さんも新しいお着物なんですの!」
「とっておきの晴れ着を出してもらいました……。ど、どうでしょうか……?」
桜子の紅や山吹の鮮やかな色合いとは反対に、氷雪のものは白を基調とした涼やかなものだった。桜子はすぐさま見抜いたが、普段と同じ物に見られるのではないか、と氷雪は不安に思っていた。
「う~ん、いいねぇ! とってもいいと思うよ!」
そんな氷雪の不安を吹き飛ばすように識苑は嬉しそうに笑った。事実、晴れ着姿の彼女らは非常に可愛らしかった。それこそ、人混みの中でも分かるくらいに鮮やかだ。
「ありがとうございますの!」
「あ、ありがとうございます」
満足げに笑い礼を言う桜子に続き、氷雪も一礼する。微笑ましい姿をにこにこと眺めた識苑だが、少し悩むように顎に手を当てた。
「でも先生はピンクがいいなー。氷雪ちゃんはピンクも似合うと思うよ」
「ピンク、ですか……」
氷雪はちらりと隣の桜子を見やる。元気で温かで可愛らしい彼女を体現するようなその色は、冷淡と言われることもある自分にも似合うのだろうか。
氷雪は何においても白を選ぶことが多い。故郷の雪の色が好きだからというのもあるが、それよりも『雪女』という自分の体質に縛られているようにも思えた。『雪女』だから白。それが自分の意識に根付いてしまっているのだ、と氷雪は度々考えていた。
「白とか青みたいな涼しくて綺麗な色もいいけど、ピンクみたいな暖かい色も似合うと思うよー」
識苑の言葉に氷雪は顔を伏せた。そうしなければ、紅潮した顔を彼に見られてしまうからだ。
『暖かい色が似合う』。そう言われたのは初めてだった。寒く冷たい『雪女』というコンプレックスに縛られた彼女に、その言葉は嬉しくてたまらなかった。
「ワタシはどうですの?」
「桜子ちゃんは黄色みたいな淡い色も似合そうだね。あとあれ、ピンクに紺色の袴とか可愛いよね。尻尾の色が映えそうだな」
「本当ですの?」
「本当だよ」
キラキラと目を輝かす桜子に識苑は優しく返す。その姿はまるで歳の離れた兄妹のようだ。
「そうだ、先生も一緒についていっていいかな? 男一人じゃちょっと寂しいや」
「は、はい!」
「もちろんですの!」
識苑の言葉に氷雪も桜子も喜んで返事する。ありがとう、と礼を言う識苑に、それくらいなんてことありませんの、と桜子はニコニコ笑った。
「じゃあ、早くいきますの!」
そう言って桜子は氷雪の手を握った。冷たくないのだろうか、と氷雪は不安げな表情をするが、桜子は何も気にしていないように彼女の手を引き人混みを掻き分けていく。
先生は、と振り返る氷雪の手を誰かが握る。彼女の小さな手を包むのは識苑の大きな手だ。先生も混ぜて、と彼は笑った。はい、と氷雪も笑う。ふわりと空から舞う雪のように柔らかな笑みだ。
賑やかな人混みの中、ピンクと白が駆けていく。冬の空は冷たくも綺麗に晴れ渡っていた。
畳む
消夜【ゆかれいむ】
消夜【ゆかれいむ】
即興二次小説で気になるお題があったので第二弾。今回は時間制限なし。
ジャンル:東方Project お題:1000の交わり 文字数:952字
眠りの底から意識が現実へと浮上する。長い睫毛で縁取られた目がふわりとゆっくり開く、まだ頭が働かない。眠気を消すようにごしごしと目をこすり、幾度か瞬きをしてやっと焦点が合い周りを見回すことができた。
寝転んだ隣を見る。昨晩共に過ごした彼女の姿も、その見た目よりも高い体温も残っておらず、ただ綺麗に整えられた白いシーツがあるばかりだ。いつもと変わらぬその風景を霊夢は冷めた目で見つめた。
夜を共にした日、紫は自分が眠っている間に必ず消える。何の跡も残さず、夢だったのではないかと錯覚しそうなほど綺麗に姿を消す。いっそ怒りが湧いてくるほどだ。
紫にとって、自身はただの代替品であることを霊夢は知っている。どんなに優しくされても、どんなに甘い言葉を与えられても、幾度も肌を重ねても、彼女の瞳には霊夢ではない別の誰かが映っている。それが書き換えられることなどないのだろう。それほど瞳の奥の『誰か』の存在は強く見えた。
きっと彼女はこうやって数々の代替品と夜を過ごしたのだろう。妖怪の生は人のそれとは比較できないほど長い。『誰か』がどれほど前に出会ったものかは知らない。自身と同じ『代替品』が何人いたのかなど想像できない。けれど、自身に与えられてきたそれを他者に与えていないはずがないことぐらいは分かる。同列の存在なのだから当たり前だ。
知らない『誰か』や『代替品』に嫉妬しているわけではない。紫の瞳に自身ではない『誰か』しか映っていなくとも、八雲紫が博麗霊夢を愛しているという形に変わりはない。形だけのそれでも、霊夢にとっては確かな事実だった。
ほっそりとした白い指が赤々と下唇をなぞる。そこに彼女の温度はない。けれども、忘れることなどできない数えきれないほど与えられた感覚が霊夢の中にはしっかりと残っている。
「……さむ」
ふるり、と小さな身体が震える。温かな布団の中にいるのに、どこか寒い。風邪でも引いたのだろうか。あいつ心配するだろうなぁ、と考えて目を伏せる。優しくされるのは嬉しいが、心配されるのは少しうっとおしい。『代替品』なのに、本物の『誰か』のように接するのだから性質が悪い。
足を折りたたみ、胎児のように身体を丸める。肌をなぞる彼女の感覚が揺らめく意識の中にしっかりと残っていた。
畳む
かみさま【SDVX】
かみさま【SDVX】
即興二次小説で気になるお題があったので、同じ設定で挑戦。
ジャンル:SOUND VOLTEX お題:神の経験 制限時間:15分 文字数:695字
「そういやさー」
雷刀は机に肘をつき、窓の外を見て口を開く。向かいに座った烈風刀は眉に皺を寄せる。二人は――正確には雷刀は抱えた課題を解いて、烈風刀がそれを見張っている。
「こないだ、魂が『神様に会った』っつってたんだよ」
「神様?」
「神様」
赤志らしくない、と雷刀と烈風刀は顔を見合わせる。甘党で現実主義な彼が、『神様』なんてファンタジーなことを言うなんて、どんな風の吹き回しだろう。
確かにこの学園には人間以外にも様々な種族がいる。妖精やロボットがいるのだから、神ぐらいいてもおかしくはないかもしれない。けれども『神』という存在があまりに不確かなものに思えて、信じがたい。
「あぁ、そういえば冷音も同じようなことを言ってましたね」
魂と俺と神様とで並んで歩いたんですよ、と言っていた彼を思い出す。普通なら嘘だと切り捨てるところだが、真面目な青雨がそんな荒唐無稽な嘘を言うとは考えられない。
神様ねぇ、と雷刀は呟いて溜め息を吐く。窓の外は鼠色の雲で覆われていて薄暗い。雨でも降りそうだ。そう考えて、『神に会った』という彼を思い出す。表情は前髪で隠れてよく見えなかったが、話す口調は穏やかで嘘をついているようには思えなかった。
「お願いしたら叶えてくれるのかな」
「そんな流れ星じゃあるまいし」
神に願う。信仰心などないが、切迫した状態の時にはいるかいないか分からないあの存在に願ってしまう。都合のいい話だ。
「神様がいるならこの課題を今すぐ消してほしい」
「馬鹿げたことを言っていないで解きなさい」
烈風刀は近くにあった参考書で雷刀の頭を叩く。パァンと教室内に音が響いた。
畳む
祝う日【わグルま!】
祝う日【わグルま!】
ワンドロやりたいけど1時間で絵なんて描けねーよちくしょーってことでSS書いた。突発的なあれなので30m。
リリムと鬼神族がだらだら喋ってるだけの話。
「祝日ムード」ってあったけど祝日って解釈していいのかどうか。解釈して書いたけど。
穏やかな午後を流れる時間は普段の物よりずっとゆっくりで、皆好き好きに行動している。武器を振るい己の技を磨く者もいれば、柔らかな絨毯に寝転がりだらだらと漫画を読む者、落ち着いた色合いの調度で白く美しい食器を用い茶会を開く者もいる。
本日は勤労魔王の日。祝日である。ただ一人、魔王を除いて。
「祝日ってもやることねーしなぁ」
「私達も探索しに行かなくていいだけで何にも変わりませんね」
トンカンと工具をいじる転生悪魔――鬼神族の隣には、リリムが一人。初期から連れ添っている彼女は、時々マスターの隣で行動する。鍛え上げられた肉体と大きな角を持つ鬼神族と、小さな角と羽を持つ小柄なリリムが並ぶ姿はさながら親子のようだ。
「つーか魔王『だけ』働くってのも意味分かんねーな。魔王ってなんだっけ」
「さあ? でも、マスターは働くんですね」
本日は事実上の祝日ということで、普段探索に出かけて忙しい彼女達にも休みを与えることにした。しかし、マスターである鬼神族の行動はいつも通りのものだ。
「そりゃあ、休みなんだから好きなことするだろ」
「いつも通りじゃないですか」
「やることねーしな。家具作ってるのがいい」
互いにやる気のない様子で会話する間にも、彼の手は動く。その手にあった木材は様々な道具によって形を変え、家具らしい姿へと変わっていく。その様子を見るのがリリムは好きだった。
「そういや飯どうする? 今日、休みの店多いんだろ?」
祝日なので休みを取る店も多い。大きな店は開いているだろうが、そこまではかなり距離があった。
「材料は残ってますけど、何にしましょうか」
「もうカップ麺でよくないか。面倒くさいし」
「あー……、ストック足りるか分かりませんね。人数増えましたし」
確かにカップ麺はいくらか買ってあったはずだが、先日の『衝動買い』で、この家は随分と賑やかしくなったこの家には足りないだろう。
「そういやそうだな」
「どこかの誰かさんのせいで」
「それ、マスターに言う言葉か?」
「どうでしょ」
彼が魔界に来た時から一緒にいるリリムとの会話は主従関係から離れたようなものも多い。けれども、それは二人にとっての日常であり何ら問題のないことだ。
「まぁ、どれもこれも魔王様様だな」
魔王という存在があったからこそ、彼はここに存在し、そして彼女もこの暮らしを手に入れた。そして、多くの『家族』と出会えることができた。全ては真っ黒で正体が分からない『魔王』という王の存在があるからこそ、この安らかな日常を過ごすことができるのだ。
「なんか労う方法はねーのかな」
「毎朝おにぎりを持ってきてくださいますし、ポストに手紙でも入れておくとかどうでしょう」
「サンタクロースみたいだな」
ハハ、と彼は笑う。リリムも穏やかに笑った。
そんな穏やかな、祝日の午後。
畳む

菓子と貴方【神十字】
菓子と貴方【神十字】夜中にTL見てぶわっと熱がきたので、朝45mで書いた神十字。投稿ついでに少し修正。
見切り発車なんで設定とか色々ふわっとしてていつも以上にやまもおちもいみもない感じ。
がさがさと草をかき分け道なき道を進む。草原をかき分けて進むのは最初は抵抗があったが、今では慣れてしまった。慣れてしまうほどここに通っているという事実は受け入れがたいが、諦めるしかない。
ほどなくして一つの建物が目に入る。崩れかけといった言葉がとても似合うこの教会が目的の場所だ。こんな古びて朽ち果て機能を果たさなくなった教会がまだ壊されずに残っているのだと常々疑問に思うが答えは見えない。おそらく、彼がなにかをしているのだろう。それくらいのことなど造作なくできる男なのだ。
壊れて役目を放棄したドアが散らばる玄関を潜り抜ける。かつん、と固い音が壊れた長椅子ばかりが並ぶ広い空間に響く。最前列、まだ椅子と判断がつくそこから起き上がる影があった。赤い髪がふわりと舞い、真紅の瞳がこちらを捉え弧を描いた。
「おかえり」
「……また寝ていたのですか」
「だってやることねーし」
けだるげにに答え、ぐっと背伸びする男を見つめる。
『神』と名乗ったこの男と出会ったのはどれほど昔だろうか。最初はそんな馬鹿げた言葉は信じられなかったのだが、時折見せる『力』とやらは彼が人ならぬ高位の存在であることを如実に示していた。疑わしいが、信じざるを得ないのだ。
「んで、今日は何持ってきてくれた?」
「クッキーですよ。子供達に配る為に焼いたものです」
「ふぅん」
長椅子の背もたれから身を乗り出した彼はつまらなそうに目を細めた。どうも自身をついで扱いされたのが気に食わないらしい。見慣れたその姿に呆れながらも言葉を続ける。
「貴方の分は別に焼きましたよ。子供達と同じような動物型のものでは嫌でしょう?」
「別に? お前のなら何でも美味しいし、見た目とかどうでもいい」
ストレートなその言葉に思わず息が詰まる。彼に褒められるのは嬉しいのだけれど、どうもこそばゆい。焦る気持ちを抑えようと鞄からクッキーが詰められた袋を取り出し、彼に手渡した。しかし、いつもならばすぐに食べ始める彼が動く様子がない。どうしたのだろうか、と顔を覗き込むと、にぃといたずらめいた笑みが返ってきた。
「食べさせて」
「は?」
なんでそんなことを、と問うとなんとなく、とやる気のない声が返ってきた。しかしいつもならば明るく透き通った赤い瞳はどこか暗い血のような色に移り変わっており、彼の機嫌の悪さを明確に表している。やはり、先ほどの言葉が気に入らなかったらしい。このまま放置して妙なことをされては自分が困る。はぁ、とわざとらしくため息をつき、彼の手にある袋を開ける。丸いクッキーを一つ取り出し、彼の口元に運んだ。茶色のそれが赤い口内へと消えていく。嬉しそうに咀嚼しごくりと飲み込むと、彼はまた口を開いた。一枚だけでは済まさないつもりらしい。気が済むまで付き合うしかないようだ。
彼の手から袋を取り、クッキーを次々と食べさせていく。まるで親鳥が雛に餌をやっているようだ、と考えて小さく笑みが漏れた。閉じられていた瞳がふわりと開き、一対の赤が不思議そうな色でこちらを見つめた。
「どした?」
「なんでもありませんよ」
はい、と誤魔化すようにまた一枚。促されるまま彼はクッキーを頬張る。子供のようだ、といつも思う。こうやって美味そうに食べてもらえるのだから、作り甲斐があるというものだ。そんな彼だからこそ、長年ここに通い『神への供え物』と称した食べ物を持ってくるようになってしまったのかもしれない。一人で作ってただ食べるよりは、他者のために作って喜んでもらいたい。彼のために見えるこの行為だが、自身のためであるのも事実だ。
そんなことを考えていると、指先に違和感を感じる。驚いて彼の方を見ると、自身の白い指に彼の赤い舌が這わされていた。赤くぬめったそれが自身の白い指を這う。その生暖かい感触と味わったことのない感覚にぞくりと背が震えた。
「な、に、してるんですか!」
急いで手を引く。反応の意味がよく分からないのか、彼はこちらを見て不思議そうに首を傾げた。
「なにって、手に粉いっぱいついててもったいないなーって」
だから舐めた、と言う彼の表情は普段と変わらないものだ。本当にそれだけらしい。付き合いは長い部類に入るが、未だに彼の行動はよく分からない。
「……みっともないからやめてください。ほら、まだありますから」
先ほどの失態を誤魔化すように溜め息をついて、そのまま彼に袋を手渡す。渡されたそれをガサガサと音を立てて開け、食事を続ける。いくらか頬張ったところでこちらを見上げ、嬉しそうに笑った。その顔は子供のそれと一緒だ。
「ん、やっぱ美味い」
「そうですか」
その屈託のない表情にこちらも笑みが零れる。彼が食事をしているときの顔はとても幸せそうで、それを見るのが好きだった。相手がどうであれ――人であれ、神であれ、喜んでもらえるのはやはり嬉しい。
「食べるか?」
ほら、と彼は一枚差し出した。少し悩んだ末、彼と同じく口で受け取る。ふわりと砂糖の甘さが口の中に広がった。
「美味しい?」
「貴方が美味しいというなら、美味しいのでしょう?」
そうだな、と彼は笑う。
壊れた屋根や窓の隙間から差し込む光は柔らかく、二人だけの広い教会を照らしていた。
畳む
#ライレフ #腐向け