No.29, No.28, No.27, No.26, No.25, No.24, No.23[7件]
辿る幻【早苗】
辿る幻【早苗】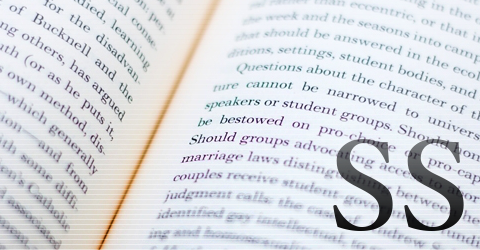
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:100の幻想[30m]
小さい頃は本を読むのが好きだった。
小説はもちろんだが、図鑑を読むのが好きだった。現実でありながら未知の世界が広がっている光景は圧巻で、幼い知識欲が刺激された。動物、花、昆虫、鳥、どんなものでも読んで、それらが存在する世界に思いを馳せた。
図鑑は実在しないものも教えてくれた。妖怪もその一つだ。雪女、のっぺらぼう、小豆研ぎ、猫叉。何百もの幻想の生き物をそこで見ることができた。小説の中で出てきたそれを調べたことも多々ある。
様々な本の中で活躍する彼らは非常に楽しそうだった。人間を驚かせ、時には悪に立ち向かい、何物にも縛られず思うがままに日々を自由に過ごしている。それはルールでガチガチに縛られた人間から見れば羨ましいものだった。
同時に彼らは苦しそうでもあった。人間に存在を否定され、姿を現せば疎まれ退治される。彼らは常に人間とともにあり、人間に虐げられていた。それを可哀想だと零したのは何時だっただろう。
幻想は幻想である。そう簡単に認め受け入れられるものではない。
そんなことを、同じく幻想の存在とされる神は語った。その表情はどこか寂しそうで、幼いながらも胸が苦しくなった。今思えば、彼女らは幼子を宥める為に自身で自身を否定したのだ。幼い子供が感じた程度では済まされないであろう辛さがあったはずだ。
幻想の存在。見たことのない彼らは本当に存在するのだろうか。
図鑑は何も答えてくれない。
パタリ、と床に広げていた本を閉じる。フルカラー印刷に耐えうるしっかりした分厚い紙で作られた本は重く、成長した今でも閉じるのには力が必要だった。これを毎日開いて読んでいたのだから、子供の集中力と探求心は凄い。
固い表紙を撫でる。大きく書かれた『妖怪大図鑑』という文字はどこか色褪せていて、時間の経過を物語っていた。
押し入れの中のダンボールに眠っていたそれらを見つけ黙々と読んでいたが、どれも懐かしいものばかりだ。動物、花、昆虫、鳥、そして妖怪。幻想の存在。見たことのなかった者たち。それらは変わらずそこにいた。
開け放たれた障子の外、鮮やかな青の空を見上げる。遠くにぽつりと浮かぶ黒い点は同じ山に住む天狗だろう。境内で神奈子と話している青い服の少女はおそらく河童だ。最近付き合いができた彼女らは度々ここを訪れ神――神奈子と話していた。
図鑑の中の幻想の存在だった妖怪達。
それが今ここにある。目の前で生きている。
「否定なんて、できませんよね」
だって、この目で見ちゃいましたもの。
そう考えて、くすりと笑みが漏れる。
畳の上では色褪せた図鑑がいくつも寝転んでいた。
畳む
時と夢の比例【魔理沙】
時と夢の比例【魔理沙】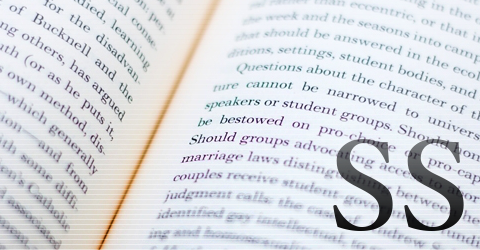
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:大人の夢[15m]
ぐ、と息を詰め足先に力を籠め腕を目一杯伸ばす。そうしても棚の上に積み上げられた本に指先すら届かない。
何故届きもしないこんなところに片づけたのだ、と呆れたように溜め息を吐き、大人しく諦めて椅子を運ぶ。あれほど遠い位置にあったそれはすぐに手の内に収まった。なんだか負けたようで腑に落ちない。
もっと身長が高ければ。そう思うことは多々あるが、身長が伸びる気配はない。徹夜する以外は健康的な生活を送っているというのに何故なのだ、とむくれる。見た目が小さいというのは生きる上で不便なのだ。
もっと成長すればどんなところにも手が届くだろうか。
もっと時が経てば今以上に魔法に近づけるだろうか。
大人になれば。
そう考えることはあるが、結局は机上の空論だ。たらればは物事のきっかけにはなれど、ただ囚われるだけではろくなことにならない。
そもそも、だ。大人になれば身長が高くなるなんて保障はない。大人なんて夢に憧れて悪戯に時を過ごすだけで心身共に成長できるはずがない。大人になるということは、有限である時間が着実に減っていることを意味する。今ですら足りないというのに、これ以上減るなんてごめんだ。
大きな夢を追うために、大人になるのはまだ早い。
抱えた本を机の上に載せる。重いそれは音を立てて着地した。
戻した椅子に座りその内の一冊を開く。遠い昔の大人達が残した知識を、夢を、願いを吸収し、幼い魔法使いは成長を遂げるのだ。
畳む
あまやどり【神奈子+早苗】
あまやどり【神奈子+早苗】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:神の経験[15m]
「神様でもやったことないことってあるのでしょうか?」
「あるよ。いっぱいある」
外は雨。神社の賽銭箱の前、雨宿りをするように座っている早苗が小さく呟く。隣に座った神奈子は同じく呟くように答えた。
「神様なのにですか?」
「神様だからだよ」
神奈子の言葉に早苗は首をかしげる。何でもできる神奈子様にもできないことなんてあるのだろうか。小さな早苗には分からなかった。
「早苗みたいに学校に通ったことはないね」
「そうなのですか?」
早苗は目を丸くする。こんなになんでもできる神奈子様が、学校に行ったことがないだなんて。
「だから、早苗が羨ましいよ」
「そんなこと、ないです」
遊ぶのは楽しいけど勉強は嫌です、と早苗は口をとがらせる。子供らしいその姿に微笑んで、神奈子は彼女の頭を撫でた。
「勉強も楽しくなるさ」
「楽しくなりません」
「なるさ。興味があることが出てきたら、楽しくなる」
「……学校の勉強では、神様のことは出てくるのでしょうか?」
小さな瞳が神奈子を見上げる。神と日々を過ごす彼女にとって、神は最大の関心事だった。彼女らが出てくる話はないかと図書館で本を読み漁った日々もあった。神奈子たちの話に耳を傾けることは日常と化している。彼女にとって神は別格の存在なのだ。それが学べるなら、どんなに楽しいのだろう。気になって仕方ないのだ。
「あー……、あるんじゃないかね」
「あるんですか?」
「学校に行ったことないから分からないや」
「ずるいです!」
逃げるような神奈子の言葉に早苗は頬を膨らます。神奈子は申し訳なさそうに笑った。
「まぁ、頑張りなさいな」
「うー……」
小さく唸る彼女の頭を優しく撫で、緑色の細い髪を梳く。少しだけ雨に濡れたその髪は、いつもより少し濃いように見える。
雨はまだ止みそうにない。
畳む
四月の始まり【後輩組】
四月の始まり【後輩組】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
前々から腐れ縁、というより後輩組を書きたいなと思っていたらネタが降ってきたので。後輩組だけど灯色君の出番は少ない。
扉を開き薄暗い部屋の中へと身を滑り込ませる。音を立てぬようそっと扉を閉め、冷音は室内で一際強く光を放っている場所へと歩みを進める。そこには一人の少年が座っていた。色の違う両の目で画面を食い入るように見つめ、人間離れした速度でガチャガチャとキーボードを叩く姿は小さな身体に不釣合いのように見えた。
「魂」
「ん、冷音か」
幼馴染の声に短く応える魂の瞳は画面に吸い寄せられたままだ。いつもならばほんの一瞬でも相手の顔を見るというのに、今日はその素振りすらない。それほどまでに状況が悪かった。
以前から度々悪さをしていた者達――現在判明しているのはハルト=カプサイシン=スチプチサットと弐拾四階段の道化師の二名だ――が徒党を組んで攻め込んできた。お陰で学園のサーバーを管理をしている魂は忙しいなどという言葉で済まされないほどの状態だ。大の甘党である彼の脇に山のように積み上げられた菓子は全く減っておらず、食べ物を口にする暇すらないほどの状況だということを冷音は悟った。いつもなら床で静かに眠っている灯色も今日はいない。どうしたのだと冷音が尋ねると、あまりにもやっかいなので直接始末しに行ってもらったと魂は答えた。そういえば彼はバグ退治をするのが仕事だったな、と冷音は常に眠たげな顔をした友人を思い浮かべる。
「ったく、四月に入ったばっかだってのになんでこんなことやらなきゃならねーんだよ」
画面を見つめる魂の表情は真剣そのもので、吐き出された言葉には苛立ちが滲み出ていた。自身が組み上げたプログラムが好き放題に荒らされているのだ。気分が良い訳がない。
いつもならば簡単な作業を手伝う冷音だが、今回ばかりは全く戦力にならないことは彼も自覚していた。ズノーロードーする上で必須だと語る菓子を食べる余裕すらないのだから、冷音にできることなど全くない。彼はただただ熾烈な攻防を繰り返す幼馴染の姿を眺めるしかなかった。
「まだまだかかるし先に帰っといた方がいいぞ」
そう言う魂の目が画面から離れることはない。人工的な青白い光とキーボードを叩く音ばかりが部屋を満たす。
「……じゃ、帰るよ」
「ん」
魂が最後まで冷音の姿を――どこか寂しげに、どこか悔しげに見つめるその姿を見ることはなかった。
「――――――終わったー……」
肺の中にある酸素を全て吐き出すかののように力なく呟き、魂は勢いに任せばたりと後ろに倒れこむ。重みに耐えかねた背もたれがギィと不快な音を立てた。
灯色とエスポワール、そして業務を早く切り上げた識苑の助けにより彼らを一時的に退治することに成功した。また復活する前に更に強化せねば考えるが、疲れ果てた今、すぐに実行することなど不可能だ。明日から識苑やレイシスを交えつつ案を出そう、と魂は身を起こした。
画面の隅に表示された数字を見る。四桁の数字は現在夜であることを示していた。想像より早く終わったらしい。喜ばしい限りだと立ち上がり大きく伸びをして、片付けを済ませ部屋を出る。窓から見える空は光を全て吸収するような黒で染まっていた。グラウンドのライトも既に消されており、見えるのは街灯が発する白い光ばかりだ。
ふと視界に黒以外の色が映る。その色には見覚えがある、というよりも毎日見る――いつも隣で見上げている色だった。
「冷音?」
腐れ縁である友人が壁にもたれかかっていた。思わず名を呼ぶと彼は手に持った端末から顔を上げる。相変わらずその目は長い髪に覆われていて表情は見えない。
「帰ったんじゃなかったのか?」
「課題忘れたから取りに戻ってきた」
休み明けに提出だったよね、と言う冷音の姿に魂は首を傾げた。確かに休暇中の課題は出ていたが、春休みももう終盤だというのに真面目な彼が今の今まで課題を忘れていたことに小さな違和感を覚える。
不思議に思っていると、ずいと目の前に袋を差し出された。なんだ、と目の前の友人を見るが、長い髪に阻まれて彼の目を見ることは叶わない。
「お茶買うついでに買ってきた。あげる」
更に強く差し出され、反射的に受け取る。コンビニのロゴが書かれた小さな袋の中にはチョコレートや飴といった小さな菓子が沢山詰め込まれていた。よく見ると、それはどれも魂の好物だった。
冷音の言葉はどれも明らかに嘘だ。きっとわざわざ買いに行って、わざわざ待っていてくれたのだろう。しかし何故そんなことを、と魂はますます首を傾げた。確かに今までこのようなことは何度もあったが、今日のように彼が行動することはなかったはずだ。なのに、何故今日は。疲れ切った頭でぐるぐると考えていると、ふと先ほど見た数字が浮かんだ。
今日は四月が始まる日、四月一日。――世間ではエイプリルフールと騒がれている日だ。
なるほど、と魂は内心笑う。有難いことに、腐れ縁な彼は何かとこちらを気にかけてくれる。きっと今日の惨状を見て行動に移したのだろう。『嘘をついていい日』だから、嘘をついてまで待っていてくれたのだ。申し訳なさと共に喜びが湧き上がる。
彼の不器用で優しい嘘は指摘しないでおこう。なんといったって、エイプリルフールなのだから。
「帰ろ。もう真っ暗だよ」
「おう」
漏れ出そうになる笑みを隠し、一歩先を行く冷音の背を追い廊下を歩きだそうとすると向こうから誰か歩いてきた。近くまで寄って、やっと灯色だということに気付く。
「んー……冷音……と、魂……?」
灯色は不思議そうな顔をするが、それはすぐに眠そうな表情に変わる。その足取りはいつも以上にふらふらとしていて見ているこちらが心配になるほどだ。先ほどの作業で灯色は普段以上の仕事量をこなしたのだ、疲れて眠いに決まっている。
「お疲れ」
「お疲れ。助かったわ、さんきゅー」
「あぁ……魂もお疲れ」
手を上げ礼を告げると彼もそれを真似しようとしたが、その腕はほんの少ししか動かない。表情も最早寝ていると判断されてもおかしくないようなものだ。このままでは廊下で眠ってしまいかねない。
「灯色ー? 寝るなら宿直室行けよ?」
主に夜間活動する灯色は宿直室の使用を許可されていた。無理に帰宅するよりもこちらで休んだ方が彼にとっても、学内を歩く人間にとっても安全だ。
「んー……うん……?」
応える灯色の声は力なく、瞼は八割方下ろされていた。ダメだこりゃ、と呟くとあぁ、と灯色は言葉を続けた。
「いや、大丈夫……帰るよ。今日は仕事免除されたしゆっくり寝たい……」
くぁ、と大きなあくびを一つ。いつも以上に眠そうだが、帰宅する意思がある程度には大丈夫なようだ。それでも危なっかしいことには変わりないので目を離すことはできない。もし倒れても、非力な自分と冷音では見た目よりもしっかりとした体つきの彼を起こすことは難しいのだ。
「じゃ、一緒に帰ろうか」
「ん……分かった……」
いつ倒れても大丈夫なようにと二人で灯色を挟み、廊下を進む。灯色の『大丈夫』は嘘じゃないだろうな、なんて少しだけ不安に思いながら。
畳む
慣れないこと【ライレフ】
慣れないこと【ライレフ】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
エイプリルフールだしってこととべったべたな話が書きたかっただけ。糖分が足りない。
ギィ、と後ろで扉が開く音がする。音の主は容易に想像がつく。烈風刀は振り返ることなく手元の本に目を落とす。紙がめくられる小さな音が静かな部屋に落ちた。
「何読んでんの?」
すぐ後ろから問いかけられ、直後肩に重みを感じる。雷刀が後ろから覗き込んでいるのだろう。身を乗り出したのか赤い髪がすぐ近くに見えた。
「ミステリですよ」
「犯人分かった?」
「まだ推理の途中です」
彼の方を向かぬままページをめくる。話は容疑者のアリバイが判明し、個々の身辺を洗い直しているところだ。もう少し材料が必要だ、と烈風刀は二段に並ぶ文字を追いかける。雷刀もそれを眺めているようだが読書をあまり好まない彼のことだ、しっかりと読むつもりは更々ないのだろう。
静寂が部屋を満たす。珍しいと烈風刀は内心首を傾げた。いつもなら作業に集中し辛くなるほど騒ぐというのに、今日は不気味なほど静かだ。何かあったのだろうか、と問いかける前に雷刀は口を開く。
「烈風刀」
「なんですか」
「――――嫌い」
心臓を力一杯握られたような心地だった。全身の骨を粉々に砕かれたような衝撃だった。腹を裂かれ臓腑が全て押し潰されたような痛みだった。
雷刀が烈風刀のことを明確に『嫌い』と言ったのはこれが初めてではないだろうか。子供めいた言葉で文句を言うことは普段からあるが、その三文字が自分に向けられたことはなかった、などと烈風刀は思考する。そんな彼がその言葉を口にしたのだ、自分はよほど酷いことをしたのだろう。普段から想いを口に出さないのが悪かったか。構ってくるのを冷たくあしらい続けたのが悪かったか。彼の為などと称して厳しくしすぎたのが悪かったか。心当たりは沢山あった。それほど沢山、彼に不満を抱かせていたのだろう。
身体が冷えていく。もう春は近く暖かいというのに、指先は氷のように冷たくなっていた。
そうですか、と努めて冷静に返そうとするが、渇いた喉はひゅうと細い音をたてるだけだ。惨めだ、と烈風刀は俯く。視界に入った自分の手は震えていた。
「…………ごめん、嘘。エイプリルフールだからって調子乗った」
ぎゅ、と後ろから強く抱きしめられる。首に回された雷刀の腕も小さく震えている。自分で言って自分でダメージを受けたようだ。何故そうなってしまうような嘘をつくのだ。怒りと共に呆れが湧き上がる。
「エイプリルフールだしなんか嘘言おうと思ってさ。こないだ読んだ漫画にそんなのあったからやってみようって」
言い訳する声は泣き出しそうなほどだった。泣きたいのはこちらだ、などと考えながら、烈風刀は震えを抑え口を開く。
「嘘で言うようなことじゃないでしょう」
「ごめん。驚かせようと思っただけなんだ」
交わす声はどちらも小さい。ごめん、と雷刀は再度謝る。
烈風刀はギリと歯を噛みしめた。このようなことで振り回されたのが腹立たしい。そして、嘘だということに心の底から安堵している自分も腹立たしい。複雑な感情が彼の腹の中に渦巻いていた。
「――――雷刀」
「はい」
「好きです」
どこか冷えた声にビクリと雷刀の身体が大きく跳ねる。視界に映る彼の耳がどんどんと赤色に染まる。そして瞬時に血の気を失い真っ白になる。
そのようなことをほとんど口にしない烈風刀がさらりとその言葉を発したのだ、驚きながらも喜んだのだろう。しかし、すぐさま先ほどの自分をなぞらえているのだと気付き青ざめた、というところだろうか。そんなことは欠片も気にかけず烈風刀は言葉を続ける。
「好きです。大好きですよ」
そう言う烈風刀の表情は珍しく意地の悪いものだ。先ほどのこと、ひいては普段世話をかけられている分意趣返しだ。頬が熱い。きっと自分も雷刀に負けず劣らず真っ赤に染まっているのだろう。たとえ『嘘』の言葉でも、その二文字をスラリと言えるほど、烈風刀はこのような行為に慣れていない。
「……それ、嘘?」
「勝手に判断してください」
冷たく言い放ち烈風刀は本に視線を戻す。反応を返してやるつもりはないということを示すためだ。
ほんとごめん、と謝り倒す雷刀を解放するつもりは今のところない。
畳む
年の初めの運試し【バタキャ+烈風刀】
年の初めの運試し【バタキャ+烈風刀】
pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
2/22で猫の日なので手帳に眠っていたバタキャ+烈風刀の話をば。1月頃のおみくじ云々エンドシーンのお話。季節感など知らん。
呼称は例によって公式参考にしつつ捏造。
烈風刀が特別教室棟に続く渡り廊下を歩いていると、ふと視界の端に鮮やかな三色が映った。そちらに目をやると、初等部の桃、雛、蒼の三人組が吹きさらしの渡り廊下の一角に集まっていた。午前の授業も無事終わり、今は昼休みだ。昼食を終え教室を飛び出している者も少なくはない。元気盛りの彼女達だ、いつもの学内探検だろうかとそちらに足を向ける。
三人が見つめる先には小さな機械があった。筐体を模したそれは誰が設置したのか、いつ現れたのかは誰も――学内を預かるエスポワールや灯色、こういうことに長けた識苑、魂ですら知らない。冬休み明けに登校してきた時にはもうここに鎮座していた、と皆は口を揃えて言っている。一体誰が何の目的で、と疑問に思う者も多いが、おみくじが引けるだけなのだから害はほぼないだろうということでそのまま放置されている。好奇心旺盛な彼女達は初めて見たのであろうそれに心惹かれているようだ。
「こんにちは」
彼女らの横に屈みこみ、目線を合わせてから声をかける。同じ高さにある三色の瞳がこちらに向けられた。
「れふとおにいちゃん」
「こんにちは」
「……こんにちは」
彼を認識した三人は嬉しそうな顔で挨拶を返す。しかし目の前の機械がよほど気になるのか、意識は烈風刀よりもそちらに向かっているようだ。
『突然現れた謎の機械』ということでこれの知名度は学内でもそれなりのものだ。彼女達も噂を聞きつけてきたのだろうか、と烈風刀は会話を続ける。
「おみくじを引くのですか?」
「おみくじ?」
彼の言葉にきょとんとした顔で雛が言葉を繰り返す。桃と蒼もよく分からないようで、皆首を傾げて互いに顔を見合わせていた。この筐体を模した機械と、神社や寺で引くおみくじがいまいち結びつかないのだろう。
「これで今年一年の運を占うのですよ」
機械を指差し説明する烈風刀の言葉に、三人は興味を引かれたようにピンとその大きな猫の耳を立てる。その瞳は好奇心でキラキラと輝いていた。
「おみくじ」
「うらないですか」
「うらない……きになる……」
やはり女の子だからか『占い』が気になるようだ。やろうやろう、と機械を触る彼女らに手順を教える。烈風刀の説明を聞き終えた三人は、せーの、と意気込んでつまみに手をかけ思い切り回す。ガチャン、と大きな音がして下部に設けられた取り出し口から小さく折りたたまれた紙が三つ出てきた。桃がその内の一つを手に取り、丸まったそれを開き三人で覗き込む。広げられたそれには『大吉』という赤い文字が大きく描かれていた。
「だい……きち、ですか?」
「だいきちっていいの?」
「だいきち……」
「よかったですね。大吉は一番良いものですよ」
『一番良い』という言葉に三人は顔を綻ばせる。楽しげにきゃいきゃいとはしゃぐ彼女達だが、互いにその紙を得ようと引っ張っていることに気付くと表情を歪めた。皆、自分が貰うものだと思っていたようだ。
「雛がだいきちもらうの!」
「桃もだいきちがほしいです……」
「蒼も……だいきち……ちょうだい」
三人とも泣きそうな顔でうーうーと唸りながら主張する。譲る気は欠片もないようで、おみくじを手放そうとする様子はない。微笑ましいその光景を眺めていた烈風刀だが、様子がおかしいことに気付き慌てて残っていた二つを広げ顔をつきあわせる三人に見せた。
「大丈夫、三人とも大吉ですよ!」
ほら、と烈風刀が示したそれを見て不機嫌そうな声がぱたりと止まる。三色三対の瞳がぱちくりと幾度か瞬きして彼が広げたそれを見つめた。それでも誰一人として手にしたおみくじを放そうとしないのだから、よほど『一番良い』それが欲しいのだろう。言い方が悪かったか、と烈風刀は小さく後悔する。
「ほらほら、みんな泣かないで」
烈風刀は少し困った顔でハンカチを取り出し、透明な雫を湛えた桃の目元を拭った。
迷惑をかけてしまったと思っているのか、桃は申し訳なさそうにごめんなさい、と呟いて紙から手を放す。はい、と烈風刀は桃の分だと言って手に持ったおみくじを差し出すと、彼女は両手で受け取りそっと胸に抱き柔らかく笑った。同様に蒼にも差し出すと、ありがとうと小さく礼を言い彼女も受け取る。ひっこみがつかないのか、くしゃくしゃになったおみくじを抱え一人唸っている雛の頭を烈風刀は優しく撫で、よかったですねと笑いかける。彼女は少し申し訳なさそうな顔で頷いた。
「そうだ、お年玉をあげましょうね」
そう言って烈風刀は制服の内ポケットから小さな袋を三つ取り出した。彼女らに渡そうと用意していたものだ。
「おとしだま?」
「おとしだま……なの?」
「いいのですか……?」
『お年玉』という言葉に子供らしくキラキラと瞳を輝かせる雛と蒼、反して桃はどこか申し訳なさそうにこちらを見上げた。親族でもない、日頃面倒を見てもらっているお兄さんという立ち位置の烈風刀からお年玉、つまりお金をもらうということがあまり受け入れられないようだ。
「いいのですよ。もらってください」
あまり多くはありませんが、と烈風刀は苦笑する。高校生の経済事情では大人のような大きな金額を渡すのは難しい。精々、いつもより少しだけ多くお菓子が買える程度のものだ。それでも彼女たちが喜んでくれれば、と用意したのだった。
「れふとおにいちゃん、ありがとう!」
「ありがとう……おにいちゃん」
「れふとおにいちゃん、ありがとうございます」
受け取った三人は嬉しそうに満面の笑みを浮かべ、先ほどの涙を感じさせないほど弾んだ声で口々に礼を言う。普段通りの明るい彼女達の笑顔にこちらまで嬉しくなる。
はた、と何か思いついたのか雛が烈風刀を見てその小さな口を開いた。
「れふとおにいちゃんはおみくじひいたの?」
「えぇ、レイシス達と引きました」
「なにがでましたか?」
「だいきち……?」
「吉でした」
当たり障りのない結果だ、と烈風刀は考えている。兄と同じなのが少し気になるが過度に悪いものでもないし、と気にかけていなかったが、レイシスや雷刀に言われ神社や寺のそれと同じく近くにあった紐に括り付けたのでもう手元にない。
彼の言葉に三人はじっとその顔を見つめ、今度は手元の紙を見つめる。おみくじと自身の顔交互に見やるその姿に、一体どうしたのだろう、と首を傾げると、桃が手に持ったそれをずいと差し出した。
「桃のだいきちあげます」
「雛のだいきちもあげる!」
「蒼のも……だいきちあげる……」
皆手に持ったそれをぐいぐいと烈風刀に差し出す。その様子に彼は驚いたようにぱちぱちと瞬きし、すぐに嬉しそうに破顔した。あれだけ自分が自分がと主張していた彼女らがあげる、と言うのだ。その姿は可愛らしく、心遣いが嬉しくてたまらない。
「いいのですよ。それは三人のものです」
「いいの?」
不思議そうに問う雛にえぇ、と返す。三人の顔を見回し、にこりと笑いかけた。
「三人の笑顔が、私にとっては大吉と同じぐらい嬉しいものなのですよ」
その言葉に桃は恥ずかしそうに頬を赤らめる。雛はとても嬉しそうに笑い、蒼は小さく笑みを浮かべ照れ臭そうに俯いた。
三者三様の反応を示す彼女らを眺め、烈風刀はすくりと立ち上がる。彼よりもずっと背の低い彼女らは自然と彼を見上げることとなる。
「さ、授業が始まりますよ。教室に行きましょう」
「うん!」
三人は元気よく声を揃えて返事をし、烈風刀の周りを囲むように歩き出す。
昼休みの賑やかしい廊下、その隅に機械は静かに佇んでいた。
畳む

信【霊夢】
信【霊夢】pixivで非公開にしていたものをサルベージ。キャプションとか諸々全部当時のままです。
お題:大きな信仰[30m]
博麗神社の巫女といえば博麗霊夢だが、彼女自身は何故巫女をやっているのか、そもそも何故ここで暮らしているのかは全く知らない。
ずるずると記憶の糸をたぐってみても、思い出せる一番古い記憶は『ここに居た』ということだけだ。生んでくれた両親の顔など思い浮かばないし、こんな辺鄙な神社で暮らすことになった経緯も覚えていない。妖怪やら里の者に世話になった覚えはあるが、何故このような状態にいることは誰も教えてくれなかった。自ら尋ねたことがないのだから当たり前かもしれない。一体何故なのだろうと不思議に思ってはいるが、そんなこと気にしても仕方のないことだと彼女は現状を受け入れていた。諦めていたともいえるかもしれない。
そんな彼女は信仰心なんてものは持ち合わせていない。神がいることは自ら実証し知覚しているが、彼らを強く信じ敬っているわけではない。ただそこにいるということだけを認識し、その事実を否定しないだけだ。無論、ここ博麗神社におわすという神も例外ではない。巫女なんて役割を貰っているが、霊夢には神を信仰するなどという考えはなかった。
信じる者は救われるなんて言うけれども、救われなかった者を霊夢は沢山見てきていた。彼らはその願いが叶えば神に感謝するが、叶わなくとも神を本気で恨んだりしない。『救われる』のは本人の気の持ちようでしかないというのが、この辺鄙な場所で願掛けをしていく者の行く末を見てきた霊夢の考えだ。
そんなことを考え実質上蔑ろにしているのだから、自分は救われることはないだろう。そもそも救ってもらいたいと強く思うほどの状況に陥った覚えがないのだけれど。都合よく祈っても思いなど届かず、ただただ自分の無力さを痛感するばかりに決まっている。人にしろ神にしろ、いざというときだけ頼られても困るのは明白だ。自分だってそんな奴見捨てるに決まっている。
けれど。
けれど、もし本当に神様とやらが人を救う気があるのならば。
「……空っぽよねぇ」
上の木枠を外し中を見る。大きな木の箱の中には枯葉すら入っておらず、すっからかんという表現がとても似合う状態だ。予想通りの光景に霊夢は深く溜め息を吐いた。
神様。やる気があるならこのいっそ清々しいほど中身のない賽銭箱を満たしてください。
畳む
#博麗霊夢